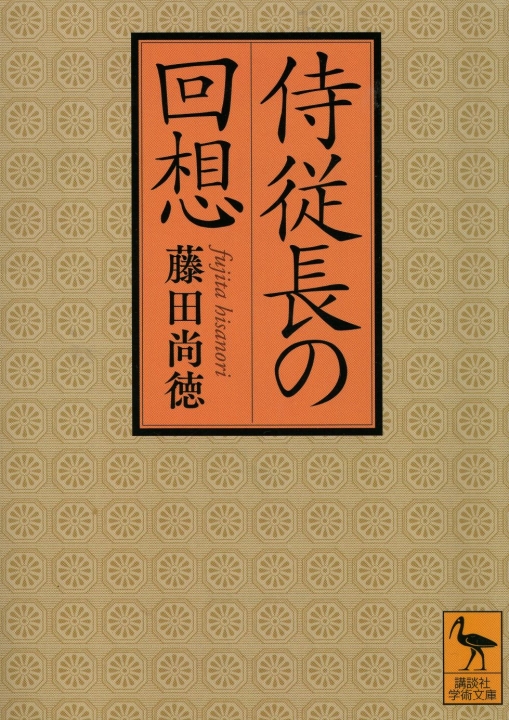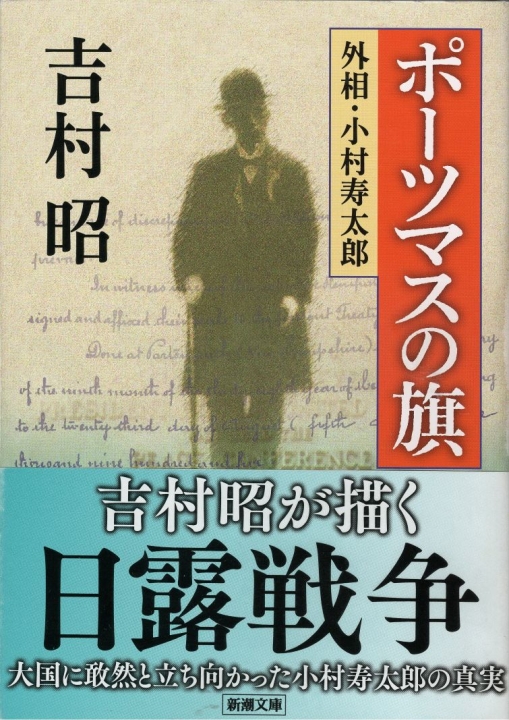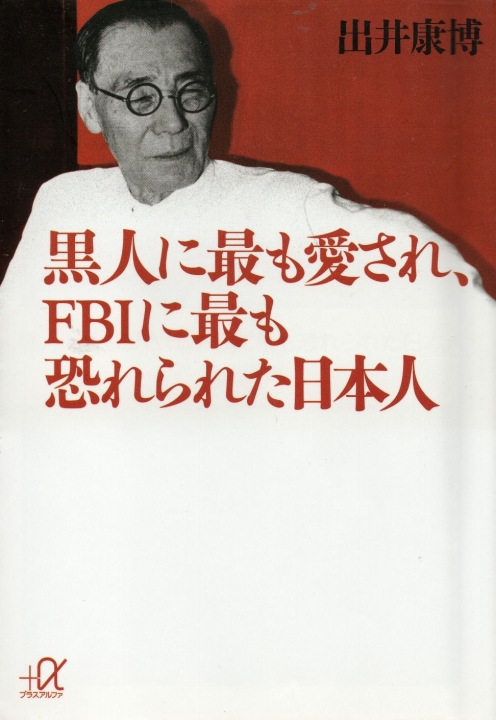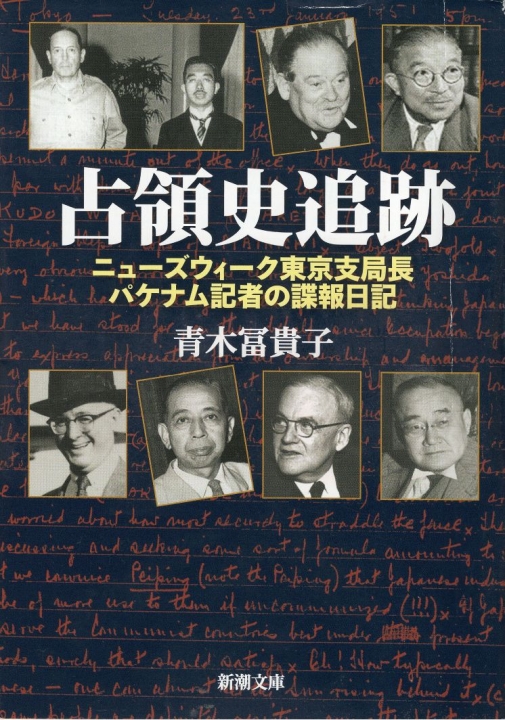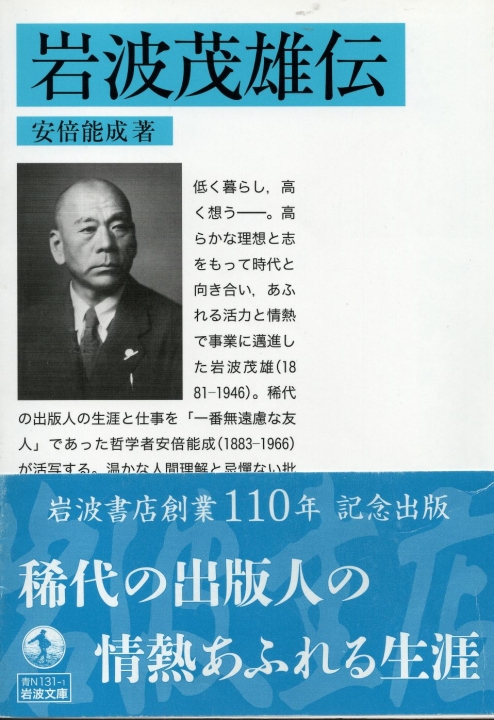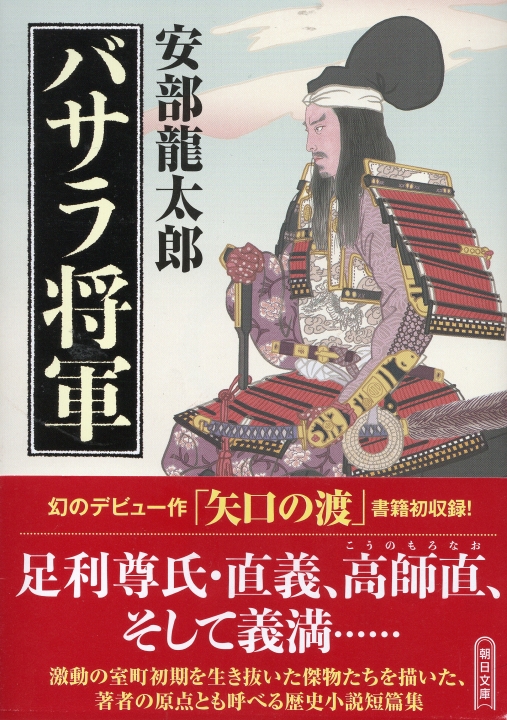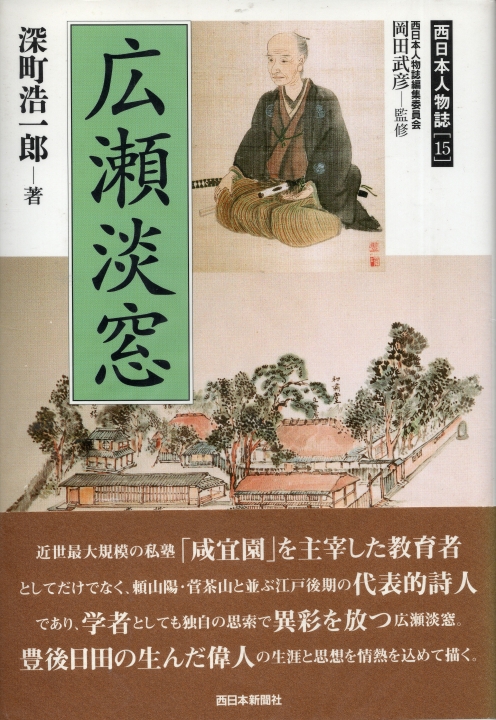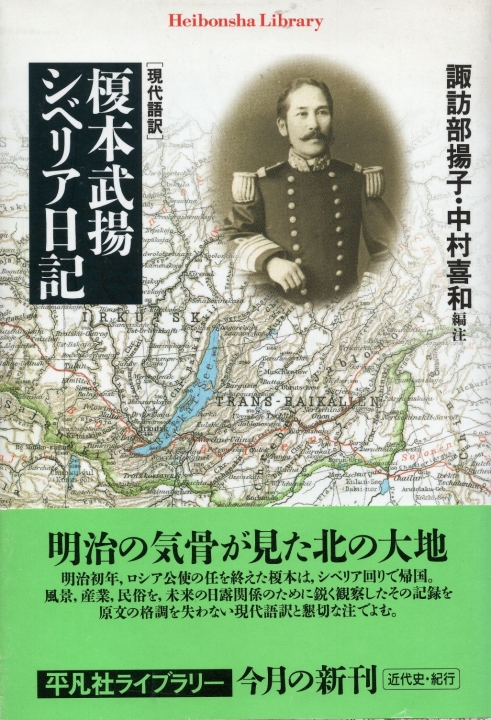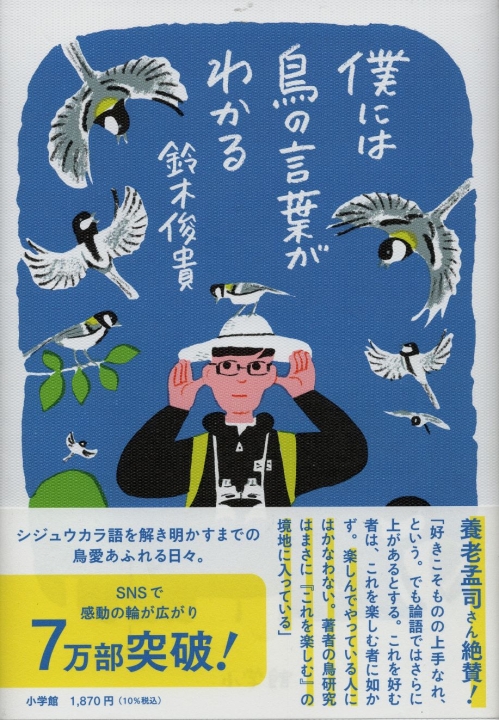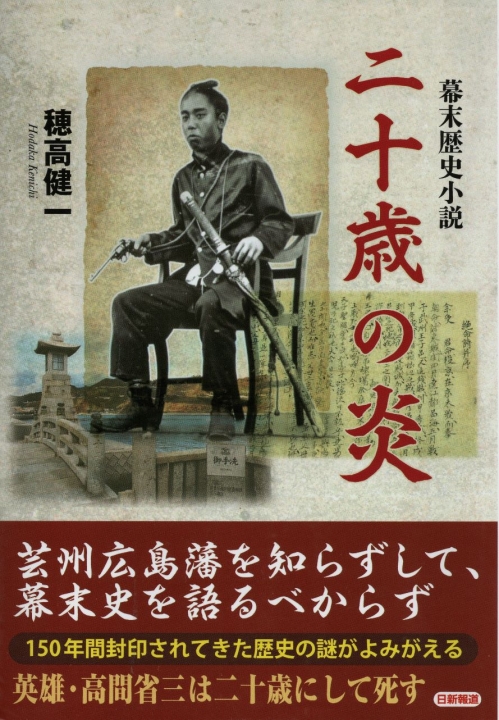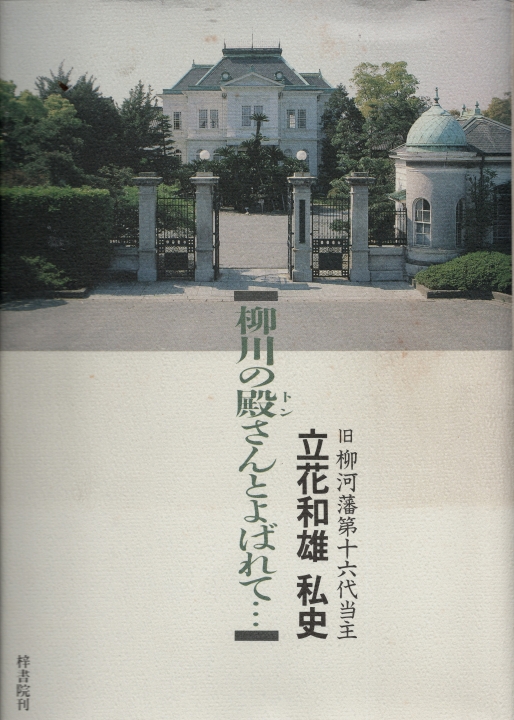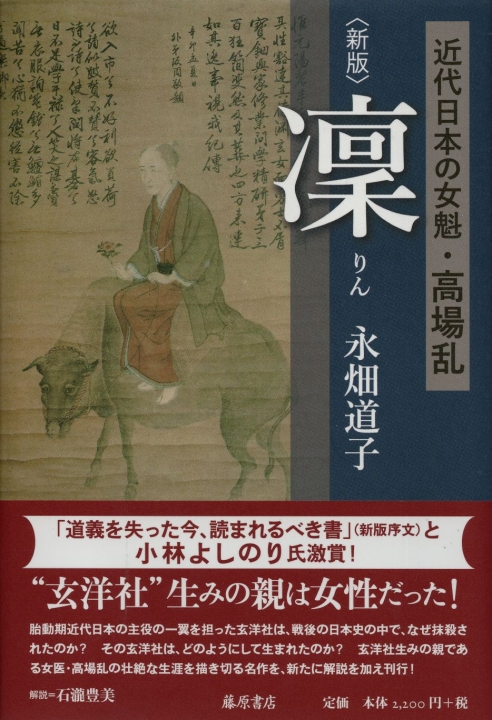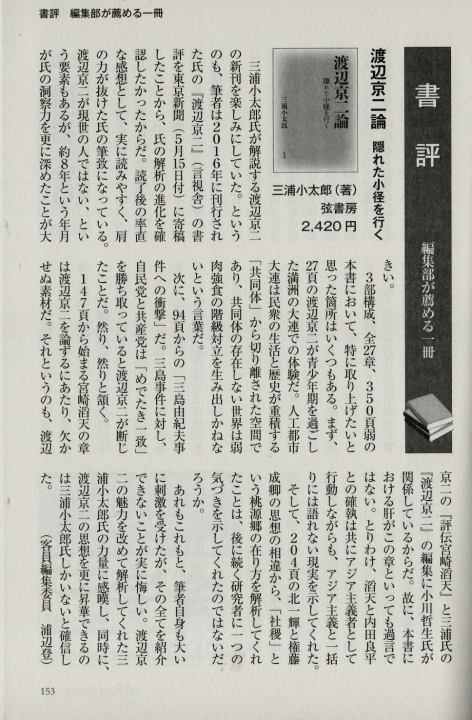・戦後80年、まだまだ見えない史実が隠れているのではないだろうか
本書は、昭和19年(1944)8月29日から昭和21年5月3日まで、昭和天皇の侍従長を務めた藤田尚徳の回想録だ。いわば、昭和天皇にとっても日本にとっても、終戦という最も苦難の時代を送った侍従長の記録だけに、その一文字、一言が実に重要な意味を含んでいる。藤田は海軍大将まで務めた軍人だったが、退役後は明治神宮の宮司だった。しかし、乞われて昭和天皇の侍従長に就任した。
米英を主軸とする連合国軍との戦争について、自存自衛の開戦決定は昭和16年9月6日と記されている。そして、同年12月8日未明、日本海軍機動部隊がアメリカ海軍の根拠地であるハワイを急襲した。ここで大戦果を挙げたが、その後の戦局についてはジリ貧であり、ついにポツダム宣言受諾、敗戦となった。藤田は、この敗戦にいたるまでの回想を淡々と述べるが、時に昭和天皇と側近とのユーモア溢れる様子も記述していることから、意外な面白さを感じることができる。
しかし、終戦に至る経過の中では、言葉は控えめながら木戸幸一を「貴族」と揶揄し、時に木戸が昭和天皇側近でありながら天皇を侮蔑しているのではとも疑念を抱く。この疑念は藤田だけではなく、占領軍の高官も同じ感想を述べた。ふと、この件で長州閥による明治天皇すり替え説を想起してしまった。
更に、「貴族」といえば近衛文麿も木戸と近い印象を藤田は書き記す。近衛の場合、明治維新での成り上がり「貴族」ではなく、本家本元の貴族だが、やはり、戦争責任を回避するための自身を優雅に見せる風が見えてくる。
この回想録を読み進みながら、皇太子時代から昭和天皇を神格化していく向きが政権中枢にあったことが見える。その神格化することで天皇を形骸化したのが、やはり木戸幸一であったと藤田は柔らかな言葉で評する。これは近衛文麿が昭和天皇に奏上する際、侍従長に代わって城戸幸一が側にいたことに端を発していると考えられる。それも、ウソをついて藤田を控えさせたことが55頁に記されている。
本書には終戦工作、昭和天皇とマッカーサー元帥との会談などが出ているが、127頁には原爆投下、及びその威力の凄まじさを昭和天皇が知っていたことだ。それも奏上する外相の東郷茂徳より早く、詳しく、だった。これは、皇室において海外の短波放送を受信していたからといわれる。この事実は『占領史追跡』(青木冨貴子著)を併読すれば、「ナルホド!」と合点がいく。内務秘書官長の松平康昌は敗戦後、ニューズィーク東京支局長のペケナム記者を介して、アメリカ本国の意向を昭和天皇に伝える役目を担っていた。この松平が昭和天皇側近のキーマンではなかろうか。
東條英機の戦局の見通しの甘さは有名だが、この東條を首相にと内奏したのは木戸幸一である。もしかして、木戸は「敗戦革命」を主導していたのではとさえ思えてならなかった。終戦80年を経て、まだまだ多角的に見なければならない史実があるのではと思った。
浦辺登の読書館(書評)
- Home
- 浦辺登の読書館(書評)
『侍従長の回想』藤田尚徳著、講談社学術文庫、2021年
『ポーツマスの旗』吉村昭著、新潮文庫、令和6年(2024)
日露戦争の講和会議において、その全権となった小村寿太郎(安政2~明治44、1855~1911)を描いた作品。読了したのは、これで二回目となる。最初に読んだのは今から二昔ほど前のことだった。ゆえに、内容については全て忘れていた。それだけに、新鮮な感覚と軽い興奮を覚えながら読み進むことができた。
ただ、忘れていたとはいえ、小村の私的な生活においては不幸な人であったというのは覚えている。実父の借金の債権者に追われまくる。結婚しても生活臭の無い女性であったことから、心安まる家庭生活を送ったことがない。別居生活が長かったために、実の子供達とも和やかな団らんを経験したことがない。
官吏として勤めた外務省でも、ハーバード大学留学経験者でありながら、出世街道をばく進するという風でもない。それが、偶然にも二流内閣と称される桂太郎内閣の外務大臣となり、全権大使としてロシアのウィッテと交渉を進め、講和を成し遂げた。しかし、そのギリギリの妥結である講和も日本国民の歓迎するところではなく、逆に暴徒に自宅を襲撃されもした。
小村は「ネズミ公使」と揶揄されていた。それは小村の身長が1メートル50センチに満たない体格だったからだ。一応、パスポートには1メートル56センチと記されていたという。欧米の外交官のみならず、アジアの外交官の間に立っても小さかった。それでいて、負けん気の強さ、情報収集に余念の無いところから、すばしっこい「ネズミ」に例えられたのだ。そして、忍耐強さは債権者に追いまくられた体験からのものだろうか。
この作品を読みながら思い返すのは、大東亜戦争(太平洋戦争)である。すでに、日露戦争後に日米の一戦が予見されていた。それだけに、連合国軍との戦いにおいても講和の機会を日本側が逸したことは残念である。始めたからには、終わらせなければならない。その見極めは難しいが、それだからこそ、日露戦争での教訓は大事だったのだ。
近年、大東亜共栄圏構想の魁として小村寿太郎を取り上げた研究者がいた。その小村の構想を受け継いだ一人に小村の嫡男である小村欣一を挙げていた。家庭において、親子関係において、円滑であったとは断定できないだけに、果たして小村の構想を欣一が受け継げたのだろうかと疑問を抱いたのだった。むしろ、講和会議の随員の一人であり外務省政務局長の山座圓次郎の方が小村の考えを十分に理解していたのではと思えてならない。
いずれにしても、講和会議の全権という大任を果たした小村寿太郎の交渉力は高く評価されなければならない。外交交渉とは、こうあるべきという事例の一つとして記憶にとどめておきたい作品であるのは確かだ。
『黒人に最も愛され、FBIに最も恐れられた日本人』出井康博著、講談社α+文庫、2008年
・まだ解明されていない戦中、戦後史がある
本書は中根中(なかねなか)という日本人が、日米の戦争前、アメリカで黒人に民族自決を煽動した記録である。中根中は大分県杵築の出身で、旧制大分中学に進み、そこでアメリカ人英語教師であり宣教師のサミュエル・ウェンライトの影響から洗礼を受けた。ウェンライトの支援を受け関西学院に進学し、地元大分杵築中学の英語教師を務めていた。その中根は紆余曲折の末、北米大陸に渡り人種差別に苦しむ黒人を煽動する工作を始める。中根は「自称」黒龍会員、元海軍少佐と身分を偽って工作活動を進めていた。
黒龍会は福岡発祥の自由民権運動団体玄洋社から派生した満洲シベリアを対象とする経済シンクタンクだが、その黒龍会の名前が北米大陸にまで及んでいることに大きな関心を抱いた。黒龍会は日本語、中国語、英語などの会報誌を発行していたが、実数は不明ながら、北米大陸でも黒龍会の会報誌が読まれていた。当然、日系移民などが購読者と思われるが、それにしても、北米にまで及んでいたことは驚きの何物でも無い。
この黒龍会だが、「エチオピア問題懇談会」という組織を玄洋社とともに昭和10年(1935)6月4日に立ち上げている。エチオピアをイタリアが侵略し併合することを問題視したのだ。エチオピアの王族に日本の華族を嫁入りさせる運動まで起こしていた。この動きについては『頭山満伝』(井川聡著)498頁に出ているが、この動きに敏感に反応したのが、北米大陸で黒人問題に取り組んでいた中根だった。「自称」黒龍会員は黒人にウケが良いと考えたのだろう。
アメリカでの黒人差別は奴隷解放後も続いていた。黒人というだけで、賃金は不当に安かった。いくら働いても、上級学校に進めるだけの給与ではない。ゆえに、永久に階級差別に苦しまなければならない黒人だった。その黒人達の朗報が日本とエチオピアの婚姻だった。同じ有色人種の日本人が黒人を真の解放へと導く。そう中根は黒人達に訴えるのだった。だから、もし、日本がアメリカと戦争をすることになったら、協力してくれというのだ。これに敵意を燃やしたのが、アメリカ連邦捜査局、通称FBIのフーヴァー長官だった。強烈な人種差別主義者として知られるフーヴァー(1935~1972)は、秘密警察を駆使し、現役大統領のプライベートに至るまで綿密に調べ上げ、半ば脅迫に近い状態で権力を行使した。仕えた大統領が8代に渡るというのも、ナチスのゲシュタポ並みの捜査力を持っていた証拠だ。そのフーヴァーが極右団体としてマークしたのが黒龍会だった。
大東亜戦争後、GHQによって黒龍会は玄洋社とともに解散させられたが、FBIの影響があったことは本書によって初めて知った事実だった。しかし、皮肉なことに、黒人の解放は日本との戦争に従軍した黒人達がその恩賞として奨学金を得て大学に進み、中流階級にのし上がったことにある。これが現代アメリカ社会における黒人の解放であり、人権の獲得に繋がったのだ。戦中、戦後史は解明の途次にあると言ってよい。
『占領史追跡』青木冨貴子著、新潮文庫、平成25年
・現在の「日米同盟」を深く理解するために
昭和20年(1945)8月30日、連合国軍総司令部の最高司令官としてマッカーサーが海軍厚木飛行場に降り立つ。コーンパイプを銜え周囲を睥睨する様は、勝者の貫禄を日本人に見せつけた。しかし、これがマッカーサーの大芝居であることは、随分と年数が経過して判明する。更に、昭和天皇との会見写真では正装の天皇に対し、マッカーサーは腰に手をそえたラフな軍服だった。この一枚の写真も日本人に強い衝撃を与えた。これが日本占領におけるプロパガンダ、洗脳工作の始まりだった。
そんなマッカーサーの占領政策を批判していたのが、本書の主人公であるパケナムである。ニューズ・ウィークの東京支局長という肩書きのパケナムはペンの力でマッカーサーに立ち向かう。その後ろ盾が何なのかは、読み進むうちに判明する。簡略にいえば、アメリカ国防総省と国務省との熾烈な利権戦いだった。パケナムは国務省のダレス特使、後の国務長官との確かなパイプをもっていたのだ。GHQこと連合国軍総司令部が一枚岩ではないように、アメリカも一枚岩ではない。コミンテルン・スパイが混入するGHQに対し、反共を推し進める国務省。この構図がわかると、日本の戦後占領政策の流れ、混乱、事件の背景が明確になってくる。
そんなアメリカ軍主導の占領政策が進む中、国務省は親米の政治集団構築を目論んでいた。しかし、国防総省主体のGHQは親米首相候補の鳩山一郎を公職追放する。このことから吉田茂に首相の座が転がり込んできた。この一件以来、先の先を見据えた国務省の仕掛けで、鳩山一郎、石橋湛山、岸信介という親米政権へと進む。背後で、このお膳立てをしていたのがパケナム記者だったが、昭和天皇とダレス国務長官までをも繋ぐ役目を果たしていたのだから驚く。
そのパケナムには、謎が多かった。公になっているパケナムの履歴に疑問を抱いた著者は、様々なルートを辿り、ついにパケナム記者の正体を暴く。戦後史の裏面をみながらも、同時並行でパケナムの正体を追い求める本書は推理小説を読み進むかの如くだった。数々の戦後占領史のノンフィクションを読んできたが、本書によって「なるほど」と疑問が氷解する箇所は多々だった。現在、「日米同盟」と盛んに口にされるが、戦後の日本で画策された事々の延長が今日であると氷解した一冊でもあった。
蛇足ながら、吉田茂の英語は通訳を必要とし、白洲次郎が吉田の腰巾着として嫌われ者だったのには、驚いた。
『かわいじゅんこのシン・人生劇場』かわいじゅんこ著、つむぎ書房、2025年
・社会のどこかで困っている人に推薦したい一冊
もし、自分自身が著者と同じ立場に置かれたらば、どうするだろうか?と考えながら読み進んだ。それというのも、評者も著者と同じく平成7年(1995)1月17日の早朝に起きた阪神淡路大震災を体験したからだ。まったく、何が起きたのかわからなかった。神戸市内、その周辺は実に言葉では言い尽くせないほど大変だった。
震災後、いわゆる陰謀論がまことしやかに流れ、明石海峡大橋の下に水爆がしかけられていて、それで日本を破滅に追い込みたい輩が地震を起こした。ユダヤのアメリカにあるホストコンピューターには、統計から割り出された地震発生のメカニズムから神戸の震災が分かっていた。地震前のアメリカ系損保会社の地震保険引き受けが阪神地区だけ引き受け不可だった。など、枚挙に暇が無いほどだった。しかし、それを誰も「そんなバカな!」と強く否定する者はいなかった。どこかで、「もしかして・・・」と思い込んでいたのだった。さほど、人間は強くはないという証拠だ。それだけに、著者が歩んできた半生を「アホちゃうか?」と笑い飛ばすことはできない。
逆に、著者は私たちのために、ありとあらゆる事々を体験し、究極まで自身の全てをさらけ出してくれたのではと思えてならない。食餌療法、密教、断食、自己催眠、古神道、断捨離、武家礼法、スピリチュアル、仮想通貨、陰謀論などなど。通常、人は「ほどほど」「ぼちぼち」と生きるものだが、「とことん」究めなければ納得できない著者の姿を、笑えない。誰しも、陥る「穴」ばかりだからだ。催眠療法で過去に遡り、現世の因果を解き明かす話もあったが、評者の友人ものめり込んで、今現在の自身の不幸の原因を突き詰めて安堵の表情を浮かべていたからだ。
それにしても、壮絶過ぎる半生に陥った「穴」の数々、その分析には恐れ入った。「こんな人もおりまっせ」、話を聞いてみますか?と、社会のどこかで困っている人がいたなら、推薦したい。シン・講談として、著者の半生を直に面白おかしく聞いても良いかもしれないが、まずは一読してからのほうが、真実味が増すのではと考える。
『黎明の世紀』深田祐介著、文春文庫、1994年
・大東亜戦争の戦争目的は自存自衛、アジア解放、独立戦争の3つがある
本書は昭和18年(1943)11月に東京で開催された「大東亜会議」についての話だ。この昭和18年の頃といえば、日本は米英を中心とする連合国軍との戦争の真っ只中である。なぜ、総力をあげての戦争中にこのような会議が開催されたかといえば、日本の敗戦の兆しがみえていたからだ。外務官僚の重光葵は戦後処理を考え「大東亜会議」開催を画策した.
本来の大東亜戦争(太平洋戦争)の目的は日本の自存自衛の戦いであった。しかし、ここにきて形勢不利となると、アジアの解放戦争を繰り込むことで、連合国軍との戦後処理を有利に進めようとする狙いがあった。アジア解放、独立戦争の意義を持たせることで、連合軍との戦後処理を有利に展開するためだ。日本の自存自衛戦争だけであれば、欧米列強の主張する正義の戦いの前に脆くも論破されてしまう。実際に、日本軍にはアジア解放運動に邁進していた者もいたので、それを追認するという意味合いもあった。
ところが、そんな重光の戦略とは関係なく、アジアにとっての大東亜戦争は独立戦争だった。言葉は悪いが、日本の自存自衛戦争であろうが、アジア解放戦争であろうが、そんな大義名分は植民地アジアにとって関係のないものなのだ。使えるものなら、日本の自存自衛戦争であろうが、使えるものは使えというのが「大東亜会議」に参加した首脳たちの一貫した考えだった.
今も、あの戦争を「侵略」戦争として日本を批判する意見がある。しかし、それに対し、アジア解放戦争だったと反論するむきもある。ところが、植民地支配下にあるアジア諸国にとって「大東亜会議」は独立戦争の手段の一つでしかなかった。ここにあの大東亜戦争を総括できない難しさが潜んでいる.
日本の陸海軍が進軍したアジア各地では、日本軍の躾の悪さが問題となっていた。行儀の悪さと言い換えても良いだろう。アジア人を下に見る風潮があり、日本はアジアの盟主と自慢する。しかし、アジア人は同じアジア人種として扱って欲しいと日本軍に求めるが、無視される。このことが、現代にも少なからず影響している。
ただ、現今日本が考えなければならないのは、アジアは欧米の植民地であったこと。その植民地支配がアジア人にとってどれほど過酷なものであったを共有することだ。そういう前提条件を知って読み進まなければ本書の意図するところは掴みきれない。日本の「侵略戦争」だと糾弾するだけでは、理解が及ばない。なぜ、あのような戦争に至ったのか、まず、そこから分析をしなければ、いつまでも堂々巡りで終わってしまう。本書は、その事々を振り返る一つの材料である。
『岩波茂雄伝』安倍能成著、岩波文庫、2023年
・個人の一代記でありながら、時代を検証する材料にもなる
新刊書店で見かけて、即座に購入したのが本書だ。岩波書店創業者である岩波茂雄の向学心を支えたのは杉浦重剛であり、頭山満だった。杉浦重剛と頭山満との関係は、頭山の口を借りれば「杉浦は五重塔の柱であり、おれはその屋根だ。杉浦が右に傾けばオレも右に傾き、杉浦が左に傾けばオレも左に傾く」である。岩波は杉浦に学びたいと熱烈な手紙を送り、杉浦はその手紙を頭山に示している。その杉浦、頭山と関係が深かった岩波茂雄の生涯を知りたいと思った。それにしても、文庫で550頁余の評伝だが、著者の安倍も仕上げるまでに10年を要したという。親友の安倍能成といえども岩波の名誉のため、書きたくはない箇所もあったと思う。しかし、岩波の女性問題、家庭不和からの別居に至るまでが綴られている。一代で、古本屋から稀代の出版社にのし上げた人物だけに、猛烈なエネルギーに満ちあふれた人が岩波茂雄だった。「我から古を成す」と豪語する人物だけはあるなと思う。
本書は岩波の一代記でありながら、夏目漱石との交際も垣間見える。一時、資金に窮した岩波が漱石に借金を申し込むと、3000円(当時)の株券を借用書も無しに預けるという関係だった。しかし、その実、互いに商取引のなんたるかも知らない間柄だった。それでも世間を渡ってこれたのは、周囲の人々の支えがあってのことが見えてくる。
また、岩波の一代記からは、時代の問題や世相すら見えてくる。316頁の敗戦後の日本国憲法は押しつけであり、421頁に大東亜戦争(太平洋戦争)を東亜の解放戦争と岩波が主張していたなど。さらに、375頁では岩波が貴族院議員に立候補するにあたり、葛生能久に推薦人を希望している。葛生は「右翼」と称される黒龍会幹事として戦争犯罪人指定を受けた人だった。そして、434頁には、戦後の日本放送協会会長人事にいわゆる「左翼」の人々とともに岩波が関与しているなど、左右の思想など無頓着な岩波の姿が見えてくる。
著者は、猪突猛進型の岩波を「他者に対して思いやりがありながら、傍若無人」と評する。敵も多ければ味方も多い。矛盾が同居する人が岩波だった。矛盾といえば、なぜ、岩波が頭山満を崇敬するのか理解出来ないと著者は述べる。岩波からすれば、頭山の中に常人には窺い知れない自身の片鱗を嗅ぎ取っていたのかも知れない。古くからの友人である著者も、この岩波の生態を理解できずにいたようだ。
蛇足ながら、196頁に井上準之助が岩波書店から『我国際金融の現状及改善策』という本を出版している記述がある。224頁には金解禁についての世相が著者によって述べられている。これはこれで、不明点が多い血盟団事件、五・一五事件、二・二六事件の分析に役立つ可能性がある。岩波茂雄の評伝とはいえ、あの時代の思想を俯瞰するにも有用な一冊である。
『バサラ将軍』安部龍太郎著、朝日文庫、2025年
かつて、司馬遼太郎に親しみ、吉村昭を読破したが、近年、歴史小説を読む機会は少ない。そんな中、本書を手にし、冒頭の「兄の横顔」から読み始めた。しかし、読めない。不思議に思い、「師直の恋」「狼藉なり」「矢口の渡」「知謀の淵」「バサラ将軍」「アーリアが来た」の短編の始まりをパラパラとめくってみる。ここで、歴史小説を読む思考が整っていないことに気づく。ふと、カタカナ表題の「アーリアが来た」を読み始めたら、これが面白く、読み終えた。足利義持将軍(第四代)に南蛮人が献上した象を都に届けるという話だ。
そして、「バサラ将軍」「知謀の淵」と通常とは逆のコースで読んだ。そこから最初の「兄の横顔」から読み始める。意外にも読める。そして、最終のトリとして「矢口の渡」を読了した。一冊読了して、この順番で読み進んで良かったと妙に納得した。
全編、南北朝時代の争闘が主となるが、武力だけが「正義」と信じ、権力を掌握した者から何をされても「仕方ない」と許される時代だ。その時代の底辺の人々の「義」「徳」という人の善(敬天思想)が覇者に向けられる。謀略という名の裏切り行為をはたらいた者に対し、覇権を誇る者が微妙な嫌悪を示すなど、実に現代人にも示唆に富む小説群だった。特に、「矢口の渡」は本書のクライマックスに読むべきと思った。
南北朝時代の底辺の人々の義と徳の生き様を見ながら、現代日本の日米関係すら想起させる。アメリカ大統領は実にバサラ将軍そのものであり、名も無き日本の庶民が皇なのではとすら思えてくる。歴史伝統文化の重層が共同体を生み出すが、その歴史伝統文化を岩盤に持たない覇権国家は経済力と軍事力でしか思考は機能しない。
巻末に大矢博子氏の「解説」があり、概要を知ることができる。しかし、ストーリーをばらしてしまうと歴史小説を読み進む醍醐味を奪ってしまうので、曖昧な心象風景しか述べられないが、読み手はそれぞれ、思い浮かべる事々が異なるのではないだろうか。
なぜ、幕末、京都の三条河原に足利三代の木像の首が梟首されたか。そこに、明治維新は南朝維新だという叫びが底辺にあったのではないだろうか。明治時代、教科書問題から派生した南北朝の正閏問題もこれら7つのストーリーを読み進むと、日本の国体にまで及ぶ源流が読み取れる。それは、著者の生まれ育った地域の特色ではとすら、思える。久しぶりに、考える小説だった。
『広瀬淡窓』深町浩一郎著、西日本新聞社、平成14年
・「三奪」「奪席」の咸宜園教育は現代においても再考の余地がある
広瀬淡窓といえば、豊後日田に咸宜園という塾を開き、多くの門弟を育てた人という印象が強い。しかし、淡窓自身、自らが背負った運命を受け入れ、そこから大きく才能を開花させた人であることに感銘を覚える。
広瀬淡窓は天明2年(1782)4月11日、豊後日田の両替商(銀行業)を営む商家の長男として誕生した。しかし、生来、病弱であり、家業は実弟に譲り、只管、学問を究めた。学問において淡窓に大きな影響を与えたのは筑前福岡の亀井南冥、昭陽父子だった。特に、南冥の存在は大きかった。
今では、豊後日田は九州の一地方都市に過ぎない。だが、江戸時代は幕府の天領として栄え、特に九州の諸大名への資金の貸し出しで一時は200万両という破格の資金力を誇る都市だった。その一翼を担っていたのが広瀬の実家だった。商家とはいえ、諸大名との交際もある。自然に、茶道、和歌、漢籍などの教養も必要となってくる。そういった家庭環境も淡窓を育む要素となった。
封建的身分制度の江戸時代、淡窓が開いた咸宜園は特異な存在だった。「三奪」といって身分、学歴、年齢に関係なく、入塾者は最下級から始まる。当時の塾は合宿形式が当たり前であり、炊事洗濯掃除など、自らの事は自ら行ない、塾運営も各人が規律に従い治めていく。要は民主的な学園自治が行なわれていたのだ。これは実に画期的であり、学問も幕府指定の官学(朱子学)に拘らず、自由だった。漢籍を究める者、医者を志す者、様々な動機で入塾し、切磋琢磨するのだった。ここで驚くのは等級が上がるための「奪席」という制度があることだ。単に学業成績だけでは通用しない。人間性も問われる。ここに淡窓が求める、学問は何のためにするのかという課題が塾生に投げかけられているのだ。
広くは知られていないが、淡窓は「敬天思想」の人だ。敬天といえば「敬天愛人」の西郷隆盛を想起するが、早くに淡窓が敬天思想を遺していたのだ。正しい行動をすれば天は報いてくれるという考えは、今後の研究課題としたい。
咸宜園からは多くの著名な塾生を輩出した。その中の大村益次郎は明治新政府において国民皆兵の基本的な考えを述べたとみられる。しかしながら、その淵源には淡窓の『迂言』があると考える。この『迂言』の中に農兵のことが記されているからだ。大村が淡窓から何らかの影響を受けていてもおかしくはない。
生来、病弱であるために、自身に課せられた使命は何なのかを考え抜いたのが淡窓だった。淡窓の生涯を簡明に記したものが本書だが、巻末の年表を確認するだけでも、病気との闘いに明け暮れた淡窓であったことがわかる。
『日露戦役秘録』東京府教育会編、博文館、昭和四年
・外交とは相手国に友人を持つことから始まる
枢密顧問官子爵金子堅太郎閣下講演と副題が付く本書は昭和3年(1928)の夏から秋にかけて開かれた金子堅太郎の講演を収録したものだ。都合、3回、講演が行なわれており、それぞれ、およそ2時間の講演となっている。空調設備が完全ではない中、金子の講演を聞きたいという聴衆が詰めかけていることに驚く。更には、第一回目の講演は金子の都合(天皇陛下臨席の会議が長引き)で開演時間に間に合わず、延期となっている。
3回の講演内容を300頁弱にまとめているが、その講演内容は明治37年に始まった日露戦争での対米交渉、いわゆるセオドア・ルーズベルト大統領との交渉に赴いた金子堅太郎の実情を語る内容だ。
金子とルーズベルトはハーバード大学の同窓という関係だが、在学中の面識は無い。金子が政府の官僚として欧米視察に渡航する際、在日アメリカ人美術家の紹介で金子はルーズベルトと会った。当時のルーズベルトは政府の一官僚に過ぎなかったが、将来、必ず大統領になる人物と早くから期待されていた人だ。これは日露戦争が始まる15年以上も前のことであり、金子との間でクリスマスカードの交換、書簡の往来が続いていたという。
この講演録を読むと、金子が親しい友人としてルーズベルトから優遇されていることがわかる。金子もルーズベルトと私的な食事をしたり、招かれてルーズベルトの私邸に宿泊したりもしている。この金子とルーズベルトとの緊密な関係があったからこそ、弾薬も戦費も使い果たした日本とロシアとの講和が進んだと言ってよい。
金子は伊藤博文の命を受けアメリカに出向くが、当初待ち受けていたのはロシアを支持するアメリカ世論だった。アメリカ・シカゴの富豪はロシア貴族とは縁戚関係にあり、旅順、ウラジオストックとの貿易で収益をあげていた。更に、アメリカ南北戦争でロシアは北軍を支援したことから、親露派が大多数だった。アメリカにはアイルランド移民も多かったが、日露戦争中のニューヨーク市長はアイルランド出身だった。北軍を支援したロシアに親しく、対外活動を行なう金子にとってやっかいな事でもあった。
ポーツマス講和条約が成立する過程は多くの書物が伝えるが、金子とルーズベルトとの関係を表す文献などは少ない。関東大震災で金子邸が被災し文書類が焼失したこともあるが、本書のように昭和4年に刊行されたものも戦災に遭遇している。更に、本書の類いは大東亜戦争(太平洋戦争)後の日本で行なわれた焚書被害にも遭った。そんななか、本書が遺っていることは奇跡なのかもしれない。
本書から見えてくるのは、外交はその相手国にどれほどの友人を持つかにかかっている。これは今も昔も変わらない。果たして、現今日本はどうなのか。金子の講演録から学ぶべき事々は実に多い。日米同盟を主張する前に、相手国の歴史も知っておかなければ同盟は名ばかりになってしまう。そう思わせる内容だった。
『近世人物夜話』森銑三著、講談社学術文庫、1989年
・人物評伝の面白さ
本書は、戦国末期から江戸時代の43の人物にまつわる話が短編小説風に紹介されている。その冒頭は、織田信長が明智光秀に討たれた「本能寺の変」での話。中国地方での戦闘を早々に和議で片付け、主君の仇討ちを大義に掲げ京に引き返す秀吉。だが、その心中を読み取ったのが官兵衛だった。「天下が廻ってきたな」と。この意中を見透かされた秀吉は「恐ろしい奴」と官兵衛の本質を見抜く。
実に興味深く、面白い出だしに引き込まれるが、人物伝につきものの誇大広告についても、著者は注意深く文献を調べて訂正を求める。こういった虚実を述べながらの人物評だけに、歴史上の人物といえども、鵜呑みにはできないことを知る。このことは、本書の405頁からの「人物研究に就いての私見」に詳しいが、ここでは森鷗外の研究姿勢を著者は高く評価している。鷗外は後世の人が再考しやすいように、参考文献の提示、資料提供者の紹介、資料の保管場所まで示した。自身の現世における名声ではなく、後世の研究者たちのために、精度を高めて欲しいとの願いからである。
296頁からは、本書の肝ともいうべき藤田東湖の話が出てくる。水戸学の大家でありながら、安政の大地震で不遇の死をとげる。その不慮の死の前、幕臣の川路聖謨との別れの酒は、実にもの悲しい。三十年来の交流があった両者が酒を酌み交わす。京に出張途中、川路は東湖の死を知る。酒の席で妙に尻の重たい東湖だったが、東湖の「最後の一本」が両者の永遠の別れになった。
著者の森銑三には『明治人物夜話』(岩波文庫)があるが、比較して読んで見ればわかるが、どれほど近世の事々について資料が少ないか、証言が少ないかがわかる。読みづらい箇所があるのも、明治時代とは異なる資料、証言の少なさの現れだ。
とはいえ、徳川慶喜と新門の辰五郎との話は、徳川慶喜という人物について、再評価をしたくなる痛快な裁きを慶喜はやった。「手討ちにしてくれる」と辰五郎に刃を落とすが、首に峰打ちをする慶喜。「早く、死体(辰五郎)を片付けろ」の一言で辰五郎は放免された。まるで、講談か浪曲を楽しんでいるかのような話だった。果たして現代、これほどの度量を持つ為政者がいるだろうか。
少しずつ、かみしめるように一話を読み進むのが良い一冊である。
『榎本武揚シベリア日記』諏訪部揚子・中村喜和 編注、平凡社、2010年
・将来の問題解決のため「歴史に学ぶ」
榎本武揚(えのもとたかあき)といえば、戊辰戦争の終末、箱館五稜郭に立てこもり、新政府軍と戦ったことで歴史に名を遺す。しかし、黒田清隆(薩摩藩)の強い申し入れにより明治2年(1869)5月18日降伏。木戸孝允(長州藩)らは榎本らの死罪を主張するが、黒田の助命嘆願で死を免れた。出獄後も黒田の計らいで新政府に仕官することになった榎本だが、その転機はロシア公使として赴任する予定であった沢宣嘉が急死したことからだった。急遽、榎本が代わりにロシアに派遣された。明治7年(1874)のことである。当初、榎本の公使としての使命は北方領土の問題解決と、マリア・ルス号事件だった。領土問題は国境線が未確定の樺太(サハリン)があり、新興国日本が大国のロシアと互角に交渉するには榎本の力量を必要とした。そしてマリア・ルス号事件は、支那(中国)人奴隷の解放について、その裁定をロシア皇帝に委ねたからだった。ロシア皇帝は日本を支持した。
本書は、それらの使命を果たして帰任する榎本の明治11年(1878)7月から9月の記録である。サンクトペテルブルグからウラジオストックまで、鉄道、馬車、汽船を乗り継ぎ、陸路1万キロを66日間旅した。宿泊施設も不十分な中、行程の72%は交通機関の中での宿泊だった。しかし、その旅では、スケッチ、風俗、人種、言語など、数値も交えて詳細に記録している。中途の食事も缶詰などで済ますこともあった大変な旅だった。
なぜ、榎本がこのような旅を試みたか。それは新生日本において、産業立国として立ちゆくためだった。ロシアの産業、鉱物資源開発に至るまでを見て、日本の輸出先としての可能性を探っていたのだ。榎本が着目したのは、清国(中国)からロシアに送られる膨大な茶葉だった。馬そり1台に積み上げられた茶葉の樽の数、すれ違った馬そりの台数の数を数えて、総量を計算するという気の遠くなる調査をこなした。この貪欲な榎本の努力が新興国日本の力になったのは間違いない。
今から15年ほど前に刊行された本書だが、あらためて手にしたのは国際環境が満洲、シベリアの地下資源などに着目しているからだ。明治時代半ば、経済シンクタンクの黒龍会が満洲、シベリアの調査をしているが、その先駆的立場の人が榎本だった。
尚、榎本とともに箱館五稜郭に立てこもった大鳥圭介の『英・米産業視察日記』も榎本に似た大鳥の詳細な報告書となっている。明治の先人達の苦労の積み重ねがあって、今がある。再度、彼らが何を見ていたのか、感じていたのか、振り返ることは今後の対応として重要と考える。本書と合わせて岩倉使節団記録、大鳥の視察日記を合わせて読むことで、西洋列強の本質が読み取れる。トランプ革命としてアメリカ政府の対応に振り回されるが、今こそ、歴史に学んでサラリと受け流したいものだ。
『私の昭和史(上・下)』末松太平著、中公文庫、2013年
・起きるべくして起きた陸軍青年将校の決起
本書は、昭和11年(1936)2月26日に起きた「二・二六事件」の渦中にいた人物による回顧録。直接、決起に関わってはいないが、思想的に煽動したとして禁固刑となった。唯一の事件中枢の生き残りだけに、なぜ、青年将校たちが部隊を率いて決起したかの背景も時系列で納得できる。事件に関して多々出版物はあるが、それらの消化不良の感を一掃してくれる内容だった。
一般に、この二・二六事件の前に起きた五・一五事件、血盟団事件は別物として扱われる。しかし、これらの事件は一連であり、時期、実行中心者が民間人か海軍か陸軍かの相違だけである。結論から言えば、二・二六事件の策謀者は大岸頼好(予備役陸軍大尉)であり、著者はそのグループの一人である。当然、決起して部隊を率いた青年将校たちもグループだが、陸軍憲兵隊の内偵が厳しく、連絡不十分のまま、決起に至ったというのが実情だった
陸軍青年将校たちは、なぜ、決起に至ったのかといえば、農村の困窮に心を致さない政財界に対し、政治刷新を求めたからだった。農民が小作争議を起こすと軍隊が出て鎮圧に廻るが、皮肉なことに鎮圧側の兵隊は小作人の次男、三男である。現代のように、成人男女に選挙権がある時代ではない。選挙権は男性のみであり、それも一定額の納税者に限られた。
限られた範囲での選挙では、社会の上層階級だけでものごとが成りたっていく。農民の苦しみは解消されず、次男三男が戦死すれば、その弔慰金を親族が奪い合う。借金のかたに娘は女郎として売り飛ばされる。さりとて、政治改革をといっても、軍人には選挙権がない。政治改革には実力行使しか遺されていなかった。いわば、追い詰められた者の反発である。
二・二六事件は「十月事件」「三月事件」「十一月事件」「相沢事件」など、いくつもの陸軍での事件があって起きている。さすれば、陸軍統括者の管理不行き届きを問題にしなければならない。しかし、それらは陸軍省という官僚機構において、有耶無耶にされている。いわば、これこそ「君側の奸」なのだが、上手に隠蔽し、決起した青年将校たちには「アカ(共産党)」のレッテルを貼って討伐したのだった。
従前、日本が未曾有の世界大戦に突入し、大敗北を喫した転換点は二・二六事件による軍の暴走からといわれる。しかし、それは為政者の責任逃れであり、政党政治の腐敗、ひいてはその政党を財閥がコントロールした結果でしかない。今もって、この事件を曖昧にするのは、明確な責任所在を明らかにされると困る輩がいるからに他ならない。
この当時、制限選挙から普通選挙へとなったことは、為政者からすれば都合の悪いことであり、圧力がかけられた。それでも社会を改革しようと決起したのが陸海軍の青年将校たちであり、民間の志士たちだった。血盟団事件当時の日本の社会状況を考えれば、起きるべくして起きた事件だった。今一度、事件の真相は振り返られなければならない。
『的野半介』和田新一郎著、私家版、1933年(昭和8)
・ここにも『近世怪人伝』のモデルが
夢野久作の『近世怪人伝』は、玄洋社の頭山満や関係があった人々との交遊録だが、中には常人には理解の及ばない人々が登場する。なかでも、魚屋の篠崎仁三郎などは爆笑ものの人物だ。こんな面白おかしく生きた「怪人」は特異な存在と思っていたら、そうではなかった。本書の主人公というべき的野半介(安政5~大正6、1858~1917)もそうだった。
的野半介の存在は玄洋社員の一人として名前は知っていた。初代玄洋社社長平岡浩太郎の義弟で、玄洋社の機関紙である「九州日報」の社長を務め、衆議院議員でもあった。更に、日本の近代国家への道程において八幡製鉄所の貢献度は大きいが、その八幡製鉄所の誘致、運営、とくに若松港の築港に大きく関係したのが的野半介だった。こう書くと、実業界、ジャーナリズムの優等生のように思われるかもしれない。
ところが、この伝記を読むと、とんでもない大飯食い。それも偏食、変態かと思うほどの食べっぷり。それでいて、酒が飲めない。貧乏な時には、正直に「金が無い」と口にするが、友人知人が金銭に窮すると、自身の全財産をなげうってでも金の工面をする。こうくると、正直実直の人と思うが、花弄(かろう)こと花札遊びが大好きという御仁。それも賭け花札を公然とやる。しかし、流石に警察幹部の注意が及び自宅で花札をする。ところが、座敷の障子を開け放して花札をする。警察も取り締まりたいが地元の名士ということでそれができない。障子の開けっぱなしも、「障子が勝手に開く」といって警察署長に弁解する豪快さ。
人の評価は柩の蓋がしまってからという。この的野半介の葬儀には一千人が参列したという。事業で多額の借金があったようだが、すべて安川家(明治鉱業、安川電機)が精算している風だ。損をするとか、儲けるとか、そんな自身のことより、国家、人々に有益であるか、ないかが的野半介の問題だった。ゆえに、頭山満が「アンナ男は作ろうとしたって作られん男」と言い切った。ともに、高場塾での同門の関係だけに、人間性については全てを知っていた頭山の言葉だった。
この的野半介がいたからこそ、あの八幡製鉄所は操業にこぎ着けたと言っても過言ではない。それでいて、「オレが、オレが」というところが何もない。損得で行動しない玄洋社の面々だが、その中でもやはり「怪人」の部類に押し込みたい的野半介だ。「人はエピソードで語れ」と言うが、尾籠の話も含め、あまりに有りすぎて語り尽くせない。
『西郷隆夫の「一点」で囲む』高岡修監修、ジャブラン、2018年
本書は西郷隆盛(1827~1877)の曽孫にあたる西郷隆夫氏との談話を纏めたものだ。西郷家というより隆夫氏と実父の西郷隆正との親子関係が中心となっている。その親子関係が、実に興味深い。西郷家というものは、平常の生活においても生命を懸けて今を生きているという情景に、驚きと感動がある。これは、受け止める人、それぞれなので、詳細に述べるべきではないと思えるほど、壮絶だ。しかし、親子の情がここまで深く強いのかとも思うのが、西郷隆正の葬儀での話。勘当したものの、子息の日常を心配して、二週に一度、子息の勤務先の課長と面会していた話は、重い。「柩を覆いて事定まる」とは古くからの言葉だが、実に、その言葉通りだった。
しかし、読み進みながら、こういう西郷家が近隣にいたら、はた迷惑だろうなあとも思った。熱烈なる巨人ファンの西郷隆正が壊したテレビの台数、帰宅後の潔癖なる足の洗い方。それも遊びに来た隆夫氏の友人にまで求める。息子の非行を糺すにあたり、生命を懸ける行動には、ただただ、恐れ入る。
西郷隆盛には「敬天愛人」という言葉の他に、「子孫に美田を残さず」という言葉もある。この子孫に美田を残さない、資産を残さないという言葉の裏には自立という意味が潜んでいる。野生動物の世界では、自立できない子供は親が食い殺すが、それを彷彿とさせるのが隆正、隆夫親子だ。実の子息には、自身に欠けていたものを求めるのが一般的な世の父親だが、そういった「一般」とは大きくかけ離れた姿が西郷家にはある。そこが他者とは異なる「一点」なのではと感じ入った。
本書の第3章には宮澤賢治(1896~1933)の子孫の宮澤和樹氏との対談も収められている。西郷家と宮澤家の関係が述べられているが、高村光雲、高村光太郎を介しての関係だ。この箇所を読みながら、玉利喜造を思い出した。玉利喜造は西南戦争前、西郷隆盛から押し出されるように東京へ向かい、アメリカ留学を果たした。帰国後は初代盛岡高等農林学校校長、鹿児島高等農林学校校長を務めた。盛岡高等農林学校は宮澤賢治が学んだ学校だ。歴史に名を残す人は、何かしら、どこかで結びついているのではと、思いを巡らした。
現代、物質的には恵まれた生活を送る日本人だが、喪ってしまった事も多い。その事実を振り返る語録ともいうべき一書ではと思う。

『僕には鳥の言葉がわかる』鈴木俊貴著、小学館、2025年
本書の優れているところは、シジュウカラの観察においてのアプローチ方法だ。これは動物の観察だけではなく、経営上の分析にも役立つものがある。なかでも、オッカムの剃刀という手法は「なるほど・・・」と感心してしまった。物事を分析するにあたり「仮定」を設定するが、必要以上に仮定を増やさない、変えないという意味だ。歴史においても「もし」という仮定を設定して事実確認を進めるが、動物の生態観察にも当てはまることが面白かった。更に、その「仮定」に至る研究のヒントが「ひらめき」であったりするのも、共感を得る。
本書の最終ステージでは、観察対象のシジュウカラが集団行動において言語を使っていることが証明される。「ジャージャー」「ピーツピ・ヂヂヂヂ」など、擬音のオンパレードだが、それぞれ、「天敵の蛇が来た」「警戒して集まれ」など、鳴き声に意味があることを突き止めるとは、著者の観察力に驚く。これはもう、好きを通り越している。この実験結果を論文にしたところ、世界の学会から「エクセレント!」と絶賛される箇所では、読み手も拍手を送っている。ワクワクしながら、ある意味、サクセス・ストーリーの爽快感すら楽しんでいる。
最終的に、古代ギリシャ時代からの定説を著者は実験結果によって覆すのだが、その世紀の大発見にもおごること無く、人類と動物との共生を考えていることが関心を誘う。西洋近代は、とかく、自然破壊、絶滅の道を進んできた。しかし、人間と同じく、この地球上に生を受けた動物と共生するという研究目標(井の中の蛙人間を救出)を掲げた点が素晴らしい。そして、この目標をいかにして拡大するかという考え、実行も学ぶべきだ。
著者は、シジュウカラ生態研究者として認められたのではない。人という生物の核心を掘り下げたことが大きく評価された。著者の思考の深さ、広さを汲み取るべき一書だ。
『二十歳の炎』穂高健一著、日新報道、2014年
本書は安芸広島藩の高間省三という実在の人物を中心に据えた幕末維新小説だ。全16章にエピローグを含め300ページ余で構成されている。幕末維新史といえば、「薩摩、長州に司馬遼太郎の小説を読んでおけば事足りる」として、関心は低い。そんな世間一般の認識に抗うかのように、本書は幕末維新における広島藩の動きを語っている。史実に基づかず「定説」の如く語り継がれることへの反発が随所に見られる。このことは、評者としても大いに同意するものだ。
幕末維新を一つの革命として捉えると、経済は必須だ。しかし、多くの維新史ではヒーローに武器弾薬、船舶についての記述がせいぜい。物流、兵站を含めての地政学的なものは少ない。江戸時代、日本の経済の中心は大坂(大阪)だったが、それは瀬戸内海という物流ルートがあってこそだった。しからば、その瀬戸内海の島々、港を擁する広島藩の動きは見逃せないはずだ。ところが、この瀬戸内海ルートでの幕末史に注視する史書は多くない。京の都での政治的なかけひき、騒動に話題の中心がおかれているからだ。
故に、いまだ幕末の一大トピックスである徳川幕府の「大政奉還」が土佐藩によるものと記されるのだ。「大政奉還」が広島藩を差し置いて土佐の後藤象二郎の抜け駆けであるとは、なんという結果なのか。いわゆる「歴史は勝者によって作られる」ではないが、薩長土肥によって作られた明治維新史には歪曲が多い。著者の憤りを感じながら読み進んだ。
本書の主人公高間省三が存命していたならば、帝国憲法、教育勅語の草案に加わっていたのではないだろうか。もしくは、海外留学を経て帝国大学の教壇に立っていたかもしれない。そう考えると、惜しい人物を喪ったとしか言えない。
評者には『維新秘話福岡』の著作があるが、その44ページに「勤皇論者の保護」として博多萬行寺の七里恒順住職が福岡藩に逃れきた芸備の志士を庇護したことを載せている。佐々木一郎という人物だが、多分に変名であろう。しかし、幕末、何らかの関係性が福岡藩と芸備との間に少なからずあったということだ。その動きを本書によって確認できたことは収穫だった。
最後に、高間省三という人が居たことを知らしめることは、弔いでもある。ここに本書の重要な存在意義があるのだ。
『海軍大将伊藤聖一伝 「大和」特攻を率いた提督』井川聡著 潮書房光人新社』
先崎彰容氏(日本大学教授)は、「何を求めれば、死の淵を飛び越す勇気をもつことができるのか」という疑問を持ったことから、西郷隆盛を追い求めた。西郷が勤皇僧月照を抱いて薩摩錦江湾に入水した事を指している。本書を通読しながら、著者の井川聡氏も戦艦大和とともに沖縄特攻を敢行した伊藤整一を西郷隆盛に重ね、本書を執筆していったのではと推察される。
今年、「昭和百年」として昭和を振り返る事々が多い。戦後復興の象徴ともいえる昭和39年(1964)の東京オリンピックは再生日本を確認することで、懐かしさとともに気分は高揚する。しかし、未曾有の大戦といわれた大東亜戦争を振り返る時、後悔の念ばかりが沸き立つ。その一つが本書に記される戦艦大和による沖縄特攻ではなかろうか。時代は艦隊決戦では無く、空母機動部隊による戦術に転換したにも関わらず、なぜ、巨大戦艦を沖縄に向かわせたのか。ここに、西南戦争での西郷隆盛率いる薩軍と戦艦大和座乗の艦隊司令官である伊藤整一が指揮官先頭として死地に赴いたことが重なる。
評者は早くから著者の『軍艦「矢矧」海戦記』を読了していたことから、伊藤整一の人物像、思想を知ることになった。しかし、この伊藤整一生い立ち、親族については、詳しくは知らない。それだけに、著者が年月をかけて、一つ一つ、確認作業を進めていった事実が本書に結実したことはありがたい。序章、終章を含め全5章、500頁余の大部だが、一言一句を疎かにできない文章が続く。ある意味、現代版西郷隆盛をなぞるかのような印象すら受けた。
筆者は福岡県大牟田市にある伊藤整一の墓参をしたことがある。決して、交通至便な場所ではない。それは、伊藤が開拓農地のど真ん中で生まれ育ったことの証明でもある。本書512頁に記載がある堺修氏が伊藤の墓守をし、資料を丹念に保管収集されていたからこそ、伊藤整一の核心に触れることができた。深く感謝申し上げる。
『柳川の殿さんとよばれて』立花和雄著、梓書院
福岡県柳川市にある料亭「御花」は柳川藩主の屋敷を料亭としていることで知られる。壇一雄をはじめ、長谷健、火野葦平、宮崎康平といった文人らが愛した料亭でもある。単に、彼らが殿様気分に浸りたがいが故に「御花」を愛用したのではない。文人らは、貴重な日本の文化遺産として認識していたからだ。
『米欧回覧実記1 アメリカ編』慶應義塾大学出版会編、2008年
『エマソン 自分を信じる言葉』佐藤けんいち著、ディスカバー・トゥェンティワン「月刊日本4月号」掲載
新版『凜』永畑道子著、藤原書店、2017年、初版1997年
『一人一殺』井上日召著、河出書房新社、2023年
「一人一殺」という危なっかしいタイトルに驚くが、それもそのはず。昭和7年(1932)に続けて起きた要人殺害事件の領袖が著者になるからだ。いわゆる「血盟団事件」と呼ばれる事件の首謀者が井上日召だが、その配下の菱沼五郎が井上準之助(蔵相、日銀総裁)を、小沼正(おぬましょう)が團琢磨(三井合名会社理事長)を殺害した。その井上日召が、大東亜戦争(太平洋戦争)後に、乞われて記述したのが本書になる。
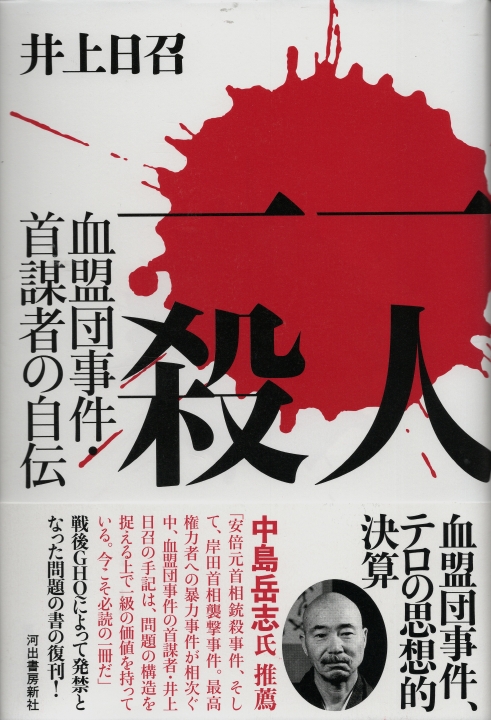
『大川周明』大塚健洋著、講談社学術文庫、2009年
「渡辺京二論」三浦小太郎著 弦書房「月刊日本3月号」掲載
『北一輝論』松本健一著、講談社学術文庫、2002年
この国家改造において、北は言論で主張した。これが陸軍青年将校の共感を呼び、その柱石として青年将校たちは北を据えたのだった。北はそのことに関与せず、我が道を行くを貫いていた。その一つが、三井からの過分な盆暮れの付け届けを厭わなかったことにある。しかしながら、二・二六事件においては、政府は北が危険思想を陸軍青年将校らに説いたとして闇の中で封じてしまった。天皇制中央集権国家を維持したい内務省、宮内省、財閥などは北が刑死によって二度と蘇らないことに安堵したのではないか。現今、この事件を陸軍の「皇道派」「統制派」の抗争として片付けるが、これは政権中枢の思惑による創作であり、責任逃れでしかない。これは、大東亜戦争(太平洋戦争)における戦争責任を陸軍首脳部などに押しつけた事にも見て取れる。
『田中清玄自伝』田中清玄著、大須賀瑞夫インタビュー、文藝春秋、1993
『日本がダメだと思っている人へ』江碕道朗・田北真樹子著、ビジネス社、2024年
『評伝 内田良平』滝沢誠著、大和書房、1976年
内田良平(1874~1936)というアジア主義者の評伝だが、内田を中心軸に据えての明治、大正、昭和という時代が垣間見える。全8章、330頁余で構成されるが、近現代の歴史教育が満足になされていない現状では、多くの方は読みこなしに苦労するだろう。もし、新装版が出る際には文字校正は当然として、要所に注釈や人物紹介、巻末に人名録を付して欲しい。
『緒方竹虎』修猷通信・大塚覚発行、私家版、昭和31年
『想い出の汀』岡田哲也著、花乱社、2024
その後のテツの道程については、高木護のような放浪生活を送りながらの詩作になるのだろうか。これは、次回に期待するしかない。
『民族自決と非戦』高井潔司著 集広舎
本書は、清水安三、吉野作造、石橋湛山、橘樸、尾崎秀実という人物を俎上に乗せ、大正デモクラシーという世相を反映させつつ、朝日新聞、毎日新聞というメディアがいかに日本の世論を好戦的に誘導していったかの記録となっている。読み進むにあたり、全11章、380頁余は一瞬の気を許すこともできない。さほど、辛辣なメディア批判、思想が固定した評論家を斬り刻んでいるからだ。

『在野と独学の近代』志村真幸著 中公新書「月刊日本12月号」掲載


『日本の禍機』朝河寛一著、由良君美校訂・解説、講談社学術文庫、2021年
本書の存在を知ったのは平成30年(2018)11月の読売新聞西部本社版「維新150年」での紙上だった。「おごる祖国 愛国の苦言」という見出しだが、ここで初めて朝河寛一という人物を知った。その朝河の記事中に本書が紹介されていたが、いつかは読んでみたいと思いながら数年が経過し、ようやくにして手にすることができた。
朝河寛一は現在の福島県二本松市に明治6年(1873)に誕生した。東京専門学校(早稲田大学)を経てアメリカのダートマス大学に留学、イエール大学の教授となる世界的な歴史学者だ。しかし、現在も、日本では無名に近い存在。
本書に記される朝河の論は、実に、日本の大東亜戦争(太平洋戦争)敗北を予言したものだった。それも明治四十一年(一九〇八)にである。故に、本書に記述される「戦後」とは、明治三十七年に始まった日本とロシアとの戦争、いわゆる日露戦争後のことを指す。さほど、早い時期に、朝河は日本とアメリカとの戦争が始まることを見抜いていたのだった。
日露戦争時、朝河寛一はアメリカで、日本の立場を擁護する論文を発表し、講演を続けていた。日本支持を求めての行動については、ハーバード大学の人脈を駆使した金子堅太郎の存在がクローズアップされる。しかしながら、この朝河貫一については影が薄い。穿った見方をすれば、明治新政府にとって迷惑な「入来文書」を解明したからかもしれない。更には、大東亜戦争後、進駐してきたコミンテルンからは世界革命の障害になる「入来文書」の研究者だったからかもしれない。いわば、朝河寛一という世界的な学者の研究成果は権力者にとって「あってはならない」ものだった。
その朝河が刊行した『日本の禍機』は、自然、無視される。しかし、240頁余の本書には愛国者である朝河寛一の熱情が、事細かに述べられる。日露戦争の大義名分は「支那領土保全(主権)」「機会均等(市場開放)」だった。それをアメリカや列国は支持したが、日本は戦勝気分のまま、日本に都合の良い政策を進めた。その状態が続けば、日本は世界の孤児となって「亡んで」しまうと朝河は警告していたのだ。
果たして、当時の日本人、とりわけ為政者がどれほど本書を手にし、肝に銘じただろうか。日露戦争時の唯一のマスコミである新聞人で、真剣に本書の警告を受け止めた人は、どれほどいたのだろうか。ただただ、悔やまれる。支那(中国)市場が欧米列強に開放されても、新興工業国の日本が地の利で優勢に立つ。しかし、これを欧米は理解せず、誹謗中傷を並べて日本攻撃に集中する。「日英同盟」によってロシアに戦勝したことで、イギリス連邦国家のオーストラリアが日本に敵対心を燃やす。果ては、アメリカ西海岸における日本人移民排斥問題である。
現代日本では、「日米同盟」を声高に主張する方は多い。しかし、同盟関係というからには、アメリカ建国史は理解しておかねばならない。日本支持に動いたアメリカのルーズベルト大統領が日露戦争後に海軍増強を行い、艦隊を日本に派遣した真意の裏に「誰が(マハンと思われるが)」影響力を及ぼしたのか。そのアメリカの国情を理解し、補う意味からも、本書は必読の書になる。
ただ、残念ながら、補記は加えてはあるものの、文体自体が古く、現代の日本人には読みづらい。改訂版として現代日本人も理解が進む内容のものを求めたい。
『落日燃ゆ』城山三郎著、新潮文庫
本書は、文官でありながらA級戦争犯罪人として絞首刑になった廣田弘毅の評伝小説だ。城山三郎の代表的な作品としても知られる。主人公の廣田弘毅は、昭和23年(1948)12月23日、A級戦争犯罪人である陸軍の将官らとともに刑場の露と消えた。廣田を極刑に処する具体的な理由らしき理由も釈然としない中、廣田は粛々と刑に従った。それも、一切、弁明をしなかったことから欧米人には理解の及ばない戦争犯罪人だった。
廣田は明治11年(1878)2月14日、福岡市の石屋の息子として生まれた。しかし、小学校の頃から頭脳明晰、旧福岡藩校の中学修猷館、東京帝国大学、外務省へと進む。外交官、外務大臣、総理大臣と出世したが、一貫して平和主義者であった。しかし、カナダの外交官ハーバート・ノーマンによって狂信的な超国家主義団体の玄洋社員であるとして、戦争犯罪人のリストに挙げられたようだ。城山三郎は、廣田を玄洋社員ではないとして小説に描いているが、廣田が玄洋社員であったことを知らなかったといわれる。更に、最終箇所の「今、マンザイをやってたんでしょう」と教誨師の花山に廣田が尋ねる場面がある。廣田弘毅をよく知る人に言わせると、「事に臨んで冗談を言うような人ではない」と言い切る。平常、廣田がジョークを口にすることから城山が思いついた件かもしれない。
とはいえ、何故に本書を手にして読み返したのかといえば、廣田の妻である静子のことを城山がどのように表現したのかを知りたかったからだ。静子の実父である月成功太郎も玄洋社員だが、それも外務大臣大隈重信を来島恒喜とともに襲撃しようとした人だった。大隈襲撃は大日本帝国憲法違反を諫止するためのものだったが、戦後の民主教育を受けた日本人には「テロ」としか理解されていない。むしろ、旧福岡藩士族としての教育を受けた月成にすれば黒田武士と大隈葉隠武士の果たし合いに等しいものだった。その娘である静子も武士の娘としての矜持を持つ人だった。静子の自決は連合国軍総司令部の非条理な仕打ちに毅然として対抗する意味もあったのではと考えるが、その真意はわからない。
いずれにしても、自由民権運動団体である玄洋社がアジア主義を標榜し、欧米列強のアジア侵略を看過できないとして対立したのは間違いない。そのために、玄洋社の代表、「みせしめ」として廣田は極刑に処されたと考える。そこには、欧米列強が説くところの民主主義も正義の欠片もない。ただ、利権のために邪魔者である廣田を消す欧米列強でしかない。
後年、廣田弘毅を含むA級戦争犯罪人7人は靖国神社に合祀された。国事に殉じたからという理由だが、廣田家では合祀について難色を示す。筋を通す廣田家の生き様が垣間見えるが、廣田が法廷で口を閉ざしたのは、「身を殺して仁を成す」という論語の言葉通りの事だった。無用な累が自身の証言によって多くの人に及ばないためだった。新たな廣田の評伝小説の登場を待ち望みたい。
『それでも日本人は「戦争」を選んだ』加藤陽子著、新潮文庫
・歴史認識を変える一石を投じた書
本書は平成19年(2007)末から翌年の始めまで、5日間にわたって著者(東京大学文学部教授)が神奈川県の中高一貫の栄光学園歴史部員に語った近現代史である。序章を含め全6章で構成されるが、記載の多くは日本の学校教育では教えられないものばかり。それというのも、近現代に到達する前に日本史の授業は終了してしまう。「時間が足りない」と多くの教師が言い訳するが・・・。
第1章日清戦争、第2章日露戦争、第3章第一次世界大戦、第4章満州事変と日中戦争、第5章太平洋戦争が語られる。中高生に語るにはレベルが高いのではと思うが、対象が歴史部員だけに大枠を理解している。むしろ、受験競争を経て大学に入り社会人となった人々にとっても、新鮮味を覚えるのではないだろうか。日清戦争、日露戦争は「侵略」戦争と刷り込まれるだけで、「なぜ」という疑問に回答してこなかった教育現場だけに、「そうだったのか」と合点がいく史実が列挙されるからだ。
特に、序章の43頁に日本国憲法制定の原理原則が明記されている。現在に至るも、日本国憲法は占領下における日本の主権不在の時のものだから「無効」と主張される方がいる。しかし、本来の憲法の基礎は社会契約であり、多くの戦死者を出した大東亜戦争(太平洋戦争)後の憲法としては、「不戦」が日本国民との社会契約であるとの認識はもっておくべきと考える。日本国憲法以前の大日本帝国憲法もアメリカの成文憲法を参考にしていることを考えれば、憲法は国民との社会契約との指摘は納得できる。そう考えると、現今日本での憲法論議は実に表層的な部分での論戦でしかないことが見えてくる。特に、49頁に出ているが、戦勝国は主権や社会契約を攻撃するという。その結果が日本国憲法であるという認識を持てば、なぜ、改正、護憲、創憲の憲法論争が着地点を得ないかが理解できる。
本書の特徴は、従来、日本の歴史にはなかった諸外国との関係性を明記していることにある。欧米列強の影響から日本の立ち位置が揺らいでいること、いかに外交政策を確立しようとも、情勢分析の甘さからヘタを打ってしまうことなど、大いに反省すべき事々が見えてくる。
中高生を対象に語られた内容だが、この特別授業を受けた生徒たちは平成世代である。今、新刊書店に出向いてみれば分かるが、過去の自虐史観的な歴史書もさることながら平成世代の論客が増えている。そこには「右派」「左派」に偏らない、史実を述べることに忠実な著書が多い。これは、学校教育に物足りなさを感じた世代が、自らの調査分析を基に語り始めたということだ。こういった現象を見ると、本書の果たした効果は年数をかけて日本の学術世界に浸透しているのではと思えてならない。

『南北朝異聞 碧鏡』河合保弘著、つむぎ書房
・後世の人々のために「鎮魂」を
南北朝異聞、野田氏三代記という副題のついた本書は、読了して、しばらく時間を置かなければ著書の思い、意図は見えてこない。本題の碧鏡(みどりのかがみ)という言葉自体、何を意味するのかが分からないからだ。自身の知識が及ぶ箇所に付箋を打って、考えて見る。
南北朝とは、西暦でいえば1318年、後醍醐天皇が即位されてからの約100年続いた騒乱の時代のことを指す。天皇親政を標榜する南朝。武家政治との妥協をもって政治を司る北朝。この両朝の主張を巡って各地の武士団が南朝に加勢し、北朝に加担しという対立の時代のことだ。想起しづらい時には、明治時代に民権(自由民権)と国権(新政府)とが対立した時代を想起すれば良いかと考える。
この対立において苦難を強いられるのは、名も無き庶民だ。権力が左右に振れようとも、頼る縁を持たない下層民にとって、主義主張よりも今日の糧をと言いたい。民の苦しみは自らの苦しみとして、最終的に南北朝は相互の主張を控えて「統合」する。その経緯についてフィクションを交えて記したのが碧鏡という書だが、ここではテレビ・アニメの「一休さん」を思い出していただきたい。本書にも11頁に「新右衛門さん」こと蜷川新右衛門の名前が登場する。「頓知の一休さん」としてテレビ・アニメを楽しんだが、その時代的な背景は深く知らず、だった。あの「一休さん」が誕生する時代を本書は南北朝異聞として解説する。
歴史を学ぶことは疑似体験によって、人の苦しみ、悲しみを知り、他者への配慮を生み出すことだ。感情移入することで、歴史の主人公に自身を重ね、後世に何を成すべきかを知る。体験に勝る知識は無いが、疑似とはいえ体験することで知識を得ることができるのが歴史だ。本書の疑似体験から「統合」というキーワードの重みを知ることができるだろう。
小説である本書はサラリと軽く読み終えることができる。しかし、本書の意味するところ、著者の願いは何かを考えるとき、「統合」という言葉が浮かび上がる。この「統合」という言葉を実践するには何が必須かといえば、相対立した関係とはいえ、時代に翻弄された人々の生きてきた証を認めることである。これは戦没者の慰霊において、敵味方に関係なく慰霊をすることにつながる。詰まるところ、鎮魂につながる。
勝者敗者に関係なく、さらに、その周辺で惨禍に巻き込まれた数多の人々の鎮魂となるが、これは外交関係において、訪問先の国立墓地なり英雄墓地を国の代表者が参拝、献花することが代表的な例だ。評者の勝手な想像だが、著者はこれからの時代を構築するにあたり、まずは「鎮魂」をと訴えているのではないかと考えた。ストーリーに沿って字面だけを追うのは簡単だが、この一書に込められた思いを汲み取るには思索の時間を要する。
『マハン海上権力論集』麻田貞雄編・訳、講談社学術文庫、2010年
・色あせない一書
本書の母体となる『海上権力の歴史に及ぼした影響』が出版されたのは、1890年(明治23)であり、著者はアメリカ海軍少将、海軍大学校校長(2代目)を務めたアルフレッド・セイヤー・マハン(1840~1914)だ。簡略に「海上権力史論」と呼ばれるマハンの一書が、現代にも有効な戦略、戦術論であることに驚きを隠せない。
マハンの「海上権力史論」を日本に紹介したのは金子堅太郎(1853~1942)だが、金子といえば、明治37年(1904)に始まった日露戦争で渡米し、アメリカ大統領ルーズベルト(1858~1919)に日本支持を訴求した人として著名だ。
金子はアメリカ出張中に「海上権力史論」を手にし、帰国後には海軍大臣西郷従道(1843~1902)に抄訳を提出。直ちに、水行社を通じて出版され、海軍大学校、陸軍大学校のテキストとなった。マハンを評価したもう一人が、先述のアメリカ大統領ルーズベルト。すでに、日露戦争における戦略はマハンの海上権力史論を基本に進んでいたことになる。
マハンの海上権力史論を読み返しながら、これほど幅広い知識、洞察力を有した海軍軍人がアメリカにいたことに驚きを隠せない。軍人でありながら、思想家、宗教家、歴史家でもある。故に、人間の不変の本質を見抜こうとする探究心に賛嘆の声があがる。
昭和16年(1941)12月に始まった日米戦争は避けることの出来ない一戦だった。帝国主義者を自認するマハンの理論からいえば、ハワイ王国をアメリカが侵略しなければ将来的なアメリカの勃興はあり得ず、中国市場も手中に収めることができないという考えだ。日本は日本で、ハワイ移民につづき、アメリカ西海岸への移民が経済摩擦、文化摩擦を引き起こし、アメリカとの全面戦争に至った。現在、日本に迫り来る有事として「台湾有事」があげられる。中国海軍の海洋進出が通商航路破壊の危険を伴うからだが、この中国海軍の海洋進出の裏面にもマハンの理論が生きている。
経済成長には海運が盛んでなければならない。しかし、商船を破壊する海賊行為は海軍の艦船で保護される。海軍があるから、民間の通商が安全安心に維持できるというものだ。
東洋の物質文明は西洋文明によってもたらされた。だから、東洋は西洋文明の基礎であるキリスト教を受容しなければならないとするマハン。しかしながら、ハワイ、アメリカ西海岸に移民した日系人は同化することなく独自の文化を維持し続けた。アジアは劣等民族と位置づけるマハンだが、その中でも日本は特殊だと見ていた。
本書41頁には対日戦を想定した「オレンジ作戦計画」が記載されるが、マハンは将来的な日米戦争に向けての理論も準備していたことに慨嘆するしかない。
いずれにしても、現在進行形で他国も参考にする海上権力史論だけに、本書の解説だけでも熟読しておくべきと考える。
『大鳥圭介の英・米産業視察日記』福本龍著、国書刊行会、2007年
・明治新政府草創期の裏面
本書は旧幕臣の大鳥圭介(1833~1911)が薩摩出身の吉田清成(1845~1891)に乞われて武士の秩禄処分の外債募集にアメリカ、イギリスを訪問した際の記録だ。当初、新興国アメリカで欧州のシフ組合や現地銀行での調達が可能かと思われたが、意外な障壁が登場した。森有礼(1847~1889)である。幕末、吉田と森は薩摩藩の密命を帯び、ともにイギリスに留学した仲だったが、外債募集は自身の任務と森は自認していたようだ。両者、ともに譲らず、森などはアメリカの地元紙に情報を流す、金融機関に注意勧告の文書を回すなどして吉田を妨害し続けた。そこで、吉田はアメリカでの外債募集を諦め、イギリスに渡る。
このイギリスに渡った際、明治4年(1871)に日本を出発した岩倉具視の使節団もやってきた。ここで、諸般の事情から時間だけが無駄に過ぎていく。そこで、大鳥はイギリスの工業力の裏付けになる工場見学を各地で精力的に行った。本書の大半は、その大鳥の詳細な記録であり、言葉で表現できない時にはイラストまでも付していた。日本人の西洋近代に対する関心の高さは有名だが、さらに、大鳥の場合は科学知識が豊富な立場にあった人物だけに緻密だ。
しかしながら、この大鳥圭介、海外渡航寸前まで牢獄生活を送っていた。戊辰戦争の最終決着である箱館戦争で榎本武揚の軍に所属していたからだ。しかし、榎本軍の野戦病院長高松凌雲の赤十字精神から、官軍側の黒田清隆が降伏勧告を続ける。惜しい人材だとしてだが、かつて、黒田の兵法、砲術の先生であったのが大鳥圭介だった。木戸孝允、大村益次郎などは榎本、大鳥を死罪と主張していたが、黒田の仲介で罪一等を減らされた。そして、大鳥が出獄すると黒田は自身が長官を務める開拓史の官吏に採用するのだった。どれほどの期待を黒田は大鳥にかけていたかが理解できる。
武士の秩禄処分は、無事にオリエンタル銀行が240万ポンド、金利7%、25年割賦、毎年40万石の米を担保にするとして応じてくれた。しかし、かつての武士たちの生活苦は早々には改まらない。大きなひずみを抱えての新生日本だけに、不平士族の反発が完全に沈静化するのは明治10年(1877)の西南戦争を待たなければならなかった。
ちなみに、森有礼は初代文部大臣として日本の文部行政に尽力したが、日本語を英語に変える、アルファベットを使え、キリスト教に改宗しろなど、様々な物議を醸す発言からか、明治22年(1889)の大日本帝国憲法発布の日に刺殺された。工業国イギリス、新興国アメリカに劣らぬ国作りには、人種改良として日本人は白人種と結婚すべきだとまで口にしていた森だった。
大東亜戦争後、外交の重点はアメリカにあるが、日英関係も押さえておくことは今後の外交政策を遂行するにあたり必須と考える。その参考となる一書。
『「米欧回覧」百二十年の旅』泉三郎著、国書出版社、1993年
・時代を俯瞰する旅行記
明治4年(1871)11月、岩倉具視を大使とする使節団が横浜から出航した。最初の目的地はアメリカだが、順次、欧州へと視察の範囲を広げる。この使節団は新国家建設のための西洋文明の吸収を目論んでいた。
本書の読み返しを試みたのは、金子堅太郎の「自叙伝」を読み進むにあたっての補完の意味からだった。金子も岩倉使節団に便乗し、アメリカ留学の途上にあったからだ。「米国編」「英国編」で構成された本書は全16章、300頁余だが、使節団がたどったルートを訪ねる旅行記でもある。佐賀藩出身の久米邦武が記した「米欧回覧」をベースにしている。
江戸時代、国を鎖していた日本だけに、海外渡航の経験者はごくわずか。その出で立ちからして珍妙極まるもので、大使の岩倉具視は衣冠束帯に革靴だった。洋服を知らない副使の大久保利通、木戸孝允は狩猟服姿だった。
アメリカ号という外輪蒸気帆船での食事風景は、「国辱」の何ものでもなかった。見かねた平賀義質(福岡藩)がイラスト入りのテーブルマナーを回覧すれば、久米邦武が猛反発。村田新八(薩摩藩)はステーキを食いちぎり、岡内重俊(土佐藩)はスープを音をたてて吸い、大声でボーイを呼び付ける。「薩長土肥」の勝ち組の鼻息は荒かったが、サンフランシスコに到着すると、多少なりとも英会話ができる團琢磨(福岡藩)に「よろしくお願い申す」と頭を下げる勝ち組だった。
新興国アメリカは使節を大歓迎した。イギリスに負けたくないとして、その歓待ぶりは大変なものだった。ところが、開通したばかりの大陸横断鉄道は大雪でロッキー山脈を越えられない。車中泊も経験したが、不幸中の幸い、インディアン、列車強盗の襲撃に遭遇しなかったのは大雪のおかげだった。
この岩倉使節の目的は西洋文明の吸収と同時に安政条約、いわゆる不平等条約の改正の下交渉だった。アメリカのリップサービスから大久保、伊藤の両名が急遽帰国するというハプニングもあり、無駄足になったが、大久保、伊藤の人間関係構築には良かったのではと思う。
新興国アメリカを見た一行はイギリスに渡る。アメリカの大歓迎とは打って変わって、極東の日本の一行という扱いだった。久米邦武もアメリカと大きく異なるイギリス工業に目を見張った。使節団の旅行記を読み返しながら、どれほど日本という国が急成長したかが理解できる。反面、大東亜戦争に至る背景は、新興国日本の経済成長を抑制するためであったことが理解できる。ふと、現在の中国に対する経済制裁は、かつての日本の姿に重なって仕方なかった。
明治維新から150年、外交、経済等を俯瞰できる本書は、時代の変遷、外交を考える上で、有益な一書であるといえる。
『軍都久留米』山口淳著 花乱社「月刊日本」7月号


『枝吉神陽』大園隆二郎著、佐賀県立佐賀城本丸歴史館
・再度、探ってみることで、新しい発見があるのではないか
本書は佐賀県の偉人シリーズで取り上げられた儒学者・枝吉神陽(1822~1862)の生涯を、ブックレットで紹介したもの。枝吉神陽は、幕末の佐賀藩において「義祭同盟」を主宰し、佐賀藩の尊皇思想をリードした。残念ながら、コレラに感染し早くに亡くなってしまった。存命であれば、佐賀藩を代表して明治新政府の官僚として活躍したのは確かだろう。ただ、枝吉神陽の弟である副島種臣が新政府の外交関係で活躍したのが、せめてもの救いか。
本書では、後醍醐天皇を祖とする南朝の忠臣・楠木正成を祀る楠神社の創設など、後期水戸学の影響を受けた枝吉の事々を紹介している。水戸学といえば、水戸藩の儒学者・藤田東湖が著名だが、その水戸学の思想を枝吉が佐賀藩にもたらした功績は大きい。しかし、学問上の思想と藩政を司る現実との乖離が大きかったのも佐賀藩の特徴だ。幕末、佐幕か勤皇かと日本全国が揺れ動いたが、佐賀藩も免れなかった。そのことは、藩主の意向として、筑後久留米藩と連携して幕府を再興しようとも企図したことに現れている。
本書では取り上げられていないが、佐賀本藩と支藩である小城藩とでは、尊皇思想の系譜が異なる。小城藩は前期水戸学の基となる思想を自藩の中で醸成していたのではないかと考えられる。それというのも、昭和7年の五・一五事件において、主導権を握っていたのが佐賀県出身の海軍青年将校であり、その多くが小城藩に関係する地域の者が多かったからだ。本藩の佐賀藩の義祭同盟も視野にあったとは考えるが、それとは異なるアジア主義を含有した尊皇思想ではなかったと考える。更には、筑後柳川藩の安東省庵と朱舜水との関係性からも、小城藩と佐賀本藩の水戸学に対する相違が明確になると考える。
いずれにしても、ブックレットでは枝吉神陽の概略しかわからない。どちらかといえば、本藩に忖度した内容になっている。再度、深く枝吉神陽、支藩を含めて探ってみたいと思う。
ちなみに、枝吉の実弟である副島種臣が日清修好条規締結にあたって、蛮族(満洲族)に五体投地なぞできるかと憤ったエピソードも付け加えて欲しかった。枝吉家の遠祖に関わる話だけに。
『工作・諜報の国際政治』黒井文太郎著、ワニブックス
・想像を絶する世界の現実に対応するために
つい最近までのニュースはロシアのウクライナ侵攻だった。今や、終着点の見えないウクライナ紛争に、諦めとも、厭戦ともつかない気分が蔓延している。そんな最中、2023年10月、ガザでの紛争が起きた。いったい、この世界はどうなっているのか・・・と慨嘆する。不思議に謀略論が頭をよぎる。しかし、その前に事実関係、状況を把握しておきたい。本書はそのための一書だが、特に工作・諜報の観点から情勢が述べられていることは興味深い。全7章で構成されるが、第1章はガザ紛争、第2章はウクライナ紛争、続いて中国、北朝鮮、日本、世界、アメリカなどが詳述される。とりわけ、第5章の日本の工作・諜報の現状については必須だ。
読み進みながら思い出したのは、戦後の首相を務めた吉田茂のこと。大東亜戦争中、吉田の自宅には身分を偽った憲兵が下男として住み込んでいた。さらに、その吉田の周辺には特高警察が監視していたという。いわば、陸軍省と内務省とが入り組んでいたのだ。現代日本も省庁の縦割りが問題視されるが、今も昔も何ら変化は無い。本書では述べられていないが、総務省にも情報収集機関があるだけに、日本のインテリジェンスは誰が、どのように統括するのかと危惧する。それこそ、吉田茂の幕僚の一人でもあった緒方竹虎は日本版CIAを創設する計画をもっていたが、潰えた。緒方が急死してしまったのは惜しまれる。一説には、謀殺ともいわれるが、玄洋社員でもあった緒方の発案に対し嫌悪感を抱く組織があったのかと訝る。
基本的に日本人は性善説に立つ。ある意味、大きな社会的弊害がなければ対応は緩やかだ。反面、危機意識も希薄だ。その現象の一つが社会問題とされたLINEである。いまだ「公式」として利用する機関、組織は多い。本来、「公式」から除外し、根本的な対策が必要だが、「便利」「今さら」という意見で存続している。問題が指摘されても、善処するという言葉で片付けられたが、「こんなはずではなかった」と後悔しても始まらない。この状況をいかに脱却するかを考えなければならないのだが・・・。
現代日本で懸念されるのは工作員によるシステム破壊。果たして、どこまで対処されているのか、懸念する。機密事項だけに、一般には周知されない。しかし、アナログ対応でどこまで対処できるのかも想定しておかねばならない。まずは、第5章の「問題だらけの『日本の情報機関』」を熟読すべきだろう。自衛隊、警察、外務省などが、有事に備えて「何かしら」対処しているのでは、という過度な期待を日本国民は抱いてはいないか。本書に述べられた事件、紛争の数々は解決したわけではない。現在進行形である。為政者、企業トップはもちろん、危機管理者も一読しておかねばならない。

『命の嘆願書』井手裕彦著、集広舎 「月刊日本」5月号掲載


『武田範之とその時代』滝沢誠著、三嶺書房
・日韓併合か合邦か
今も反日的な韓国人は日本の植民地支配について責任追及、謝罪を求める。しかし、日本による併合はやむを得なかった、もしくは、あの当時の状況からすれば良かったという意見もある。更には、日韓併合ではなく日韓合邦で話が進んでいたのが、日韓双方の思惑、裏切り等により併合になったという論もある。いずれにしても、日韓関係については、本書の主人公である武田範之(1863~1911)の存在抜きには語れない。
そもそも、なぜ、明治期の日本が朝鮮に介入したのか。佐田白芽(久留米藩士)の「征韓論」に始まる朝鮮への政治的圧力に始まり、江華島事件、金玉均(朝鮮開化党)の甲申事変、福澤諭吉の「脱亜論」、閔妃殺害事件など、枚挙に暇が無い。
振り返ってみれば、幕末の嘉永6年(1853)のペリー来航によって日本は諸外国との交易が始まるが、その際、締結した条約は国家としての扱いではなく、植民地に等しかった。このことは、隣国の朝鮮も同じであり、加えて、朝鮮はフランスによる宗教侵略を受けていた。しかし、日本は日清、日露の戦争を戦い抜いたことにより、対等の条約を婦米列強と結び直すことができたのだった。いわゆる、世界の「一等国」に成り上がった。しかしながら、隣国の朝鮮は相変わらず、王族、貴族階級の両班による権力闘争に明け暮れ、欧米列強に蚕食されるままだった。
この朝鮮の状況を改革する最終手段が日本と朝鮮(大韓帝国)との合邦だった。朝鮮が日本と一体化することで、朝鮮における欧米列強による治外法権、関税権という不平等を解消できる。この不平等条約解消が日韓合邦の最大目的だった。この日韓合邦にと行動したのが武田範之だった。更には、中国革命の孫文を支援した宮崎滔天を扇動したのが武田範之だ。中華民国の建国によって、日本の政治改革を行うという遠大にして壮大な計画だった。武田範之の実父(澤之高)、養父(武田禎助)は明治4年の藩難事件で処罰を受けた。久留米藩難事件は新政府に叛旗を翻したものの、事前に鎮圧された事件だ。武田の実父は福島県郡山の安積開拓地に赴いた。
朝鮮に介入し、中国に介入し、そして、外側から日本の政治体制を改革する。そう考えると、血盟団事件、5・15事件、2・26事件も起こるのは必然であり、久留米勤皇党の残滓が関わってくるのも宜なるかなである。
ただ、武田範之等が考えていたのは、日韓合邦という対等な関係での一体化だった。けれども、山縣有朋、桂太郎等の裏切りで併合となり、今日の日韓関係の溝となった。表題が「武田範之とその時代」となっているのも、個々の事件はつながっているという事を読者に示すためであるということが、見えてくるだろう。
『権藤成卿 その人と思想』滝沢誠著、ぺりかん社、1996年(再版)
・理想郷を創造したかった権藤成卿
本書は権藤成卿(1868~1937)の評伝だが、一般には知られていない人物だ。更に、思想関係においても「右翼」の範疇として見られるため、関心を抱く人は少ない。ゆえに、本書が再版されたことに驚きを隠せない。しかしながら、再版の「結び」に綴られる「あのころのこと」などを読み進むと、著名なる日本の思想家たちが在野の研究者である著者を支援していたことを知る。それは橋川文三であったり丸山真男であったりする。そう考えると、本書の主人公である権藤成卿について、橋川や丸山たちが一目置いていたということの証になると言える。
旧著の5章に注釈を加え、「結び」などを加えると全体で270頁ほどになる。事前に、大東亜戦争後にGHQによって言論弾圧を受けた玄洋社、黒龍会という団体についての知識が無ければ容易には本書の理解は進まない。加えて、権藤成卿の故郷である福岡県久留米市の前史である久留米藩の歴史も予備知識として必須となる。とりわけ、権藤成卿を語るに外せない「明治四年 久留米藩難事件」も理解しなければ、権藤の人物像は見えない。
権藤の名前がクローズアップされたのは、昭和の初めに起きた「血盟団事件」「五・一五事件」「二・二六事件」である。「テロリズム」とも「クーデター」ともいえる反政府行動の思想的指導者として権藤成卿の名前が登場したからだ。しかし、金鶏学院で共に教鞭をとった陽明学の安岡正篤(1898~1983)は長命だったが、権藤は早逝した。故に、広く思想界に名を遺すまでにはいたらなかった。更に、権藤の家は裕福な資産家であり、医者の家系だったが、事業失敗により資産を失った。家督相続人でもあった権藤成卿は一挙に貧窮世界に転落していったのだ。このことによって、親族の間でも権藤に対する批判の声は、今もって衰えることは無い。
この権藤成卿の思想を忠実に深く理解していたのは、五・一五事件での領袖であった藤井斉だ。しかし、この藤井は五・一五事件前の上海事変で戦死している。海軍の航空士官であった藤井の戦死は仲間であった三上卓らに引き継がれたのだが、徐々に権藤が説くところの「社稷」という言葉すら消えてしまった感がある。人が幸福に衣食住を心配することなく生活するためには共同体というものが必要と説いた権藤だった。しかし、この共同体も大東亜戦争後に解体され、個人主義が横行するようになってからは過去のものとなった。
人は「どこから来て、どこに行くのか」。人が現世に誕生した意味は。何を成すべきか。それらを考える東洋の知恵としての社稷を説いたのが権藤だが、欧米型の思考によって理解が及ばなくなってしまった。
権藤成卿の評伝である本書だが、読み手は考え考え、読み進まなければならない。明治時代以降の政策としての「近代化」によって、日本人は何を得、何を失ったのか。そして更に、今後の日本人は何を成すべきか。明治維新、敗戦によって何を失い、何を復活させなければならないか。こういった事々を考えるための書が本書になる。
『安東省菴』松野一郎著、西日本新聞社
・「水戸学」の源流にいた儒者
世に「水戸学」という学問体系があり、幕末維新の志士たちの精神的よりどころとなった。その「水戸学」は朱舜水という明国(中国)の儒学者の影響を強く受けている。その舜水は亡国の民として長崎に逃れ来たが、その長崎時代の生活費などの面倒を見ていたのが筑後柳河(柳川)藩の儒学者安東省菴(あんどうせいあん)であった。およそ六年もの間、朱舜水が水戸光圀から招聘を受けるまで、自身の俸禄の半分を師と奉る舜水に送り続けた。
朱舜水の長崎滞在中、安東省菴は楠正成、正行親子の事績について師に意見を求めている。このことで、舜水は後醍醐天皇に忠義を尽くす武将の存在を深く知ることになる。水戸光圀の手跡による湊川神社の楠正成の墳墓の裏面に舜水は讃を遺したが、これは安東省菴の影響が大きい。更に、このことは、水戸斉昭に影響を及ぼし、水戸藩校弘道館開設につながる。続いて、藤田幽谷、東湖父子による「水戸学」の体系化に連なる。
従前、「水戸学」が九州に齎されたのは筑後久留米藩、肥前佐賀藩からと見ていたが、意外にも「水戸学」の故地は九州であったのだ。更に、安東省菴に朱舜水の長崎亡命を知らせたのは権藤宕山(ごんどうとうざん)という久留米藩の医師。省菴の門弟の一人だが、この宕山の子孫が昭和維新の思想家権藤成卿になる。このことは権藤家の家譜に記されているだけで、広くは伝わっていない。
この昭和維新の思想家権藤成卿の影響を強く受けたのが海軍青年将校の藤井斉、三上卓らになるが、この藤井、三上らの出身地は現在の佐賀県小城市、多久市になる。ここは旧小城藩になるが、二代藩主の鍋島直能(なべしまなおよし)は朱舜水の長崎滞留にあたって長崎奉行宛て上申書に名前を記した人としても知られる。この鍋島直能は水戸光圀と書簡を交換するほどに親しい関係にあった。明国の著名な儒学者として朱舜水を光圀に推奨したのは想像に難くない。
本書の肝は、朱舜水と安東省菴との学問上の往復書簡の内容が示されていることだ。現代も、朱子学、陽明学などと二元論的に儒学を評する論が多い。しかし、このことが、いかに不毛な論争であるかを舜水と省菴の師弟関係は明らかにしている。
全9章、218頁の本書は簡略にして要点を外してはいない。「水戸学」の源流が那辺に存在したかを知る手がかりになる。
『命の嘆願書』井手裕彦著、集広舎
・いったい、人間とは
「これは、いったい、何なのだ・・・」。本書を手にした時、その分厚さ、重さに、訝った。いわゆる鈍器本といわれるものだが、それにしても1・8キロ、135万字、2段組1300ページ弱は、初めて手にした。昼寝の枕代わりもなり得るが、それでは著者に失礼になる。それというのも、タイトルが「命の嘆願書」だからだ。
本書は大東亜戦争(太平洋戦争)後、満洲等に展開していた旧日本軍、在留邦人がシベリア、モンゴルに抑留された実録。エピローグを含め全40章に渡り、旧ソ連軍、モンゴル軍に使役された日本人の史実が詰まっている。しかし、その内容は、まるで仏典か聖書の如く、人間の悪行から善行までが綴られている。
すでに、シベリア等の抑留記については多くの著作、記録が遺されている。評者も関心を抱いて抑留記録を読んできたが、本書の類いは初めて。現役の新聞記者が抑留者の記録を求め、厚生労働省の調査にも漏れた人々を探し出す物語だからだ。特に、広く知られる吉村隊の「暁に祈る事件」が朝日新聞記者による捏造であったなど、驚愕の事実が暴露される。
シベリア、モンゴルには約57万5千人が抑留され、約5万5千人が傷病死している。この数値は看過できない事実だが、その間隙を縫って真実が歪曲されている事に驚いた。それが、評者も感動のうちに読了した『収容所から来た遺書』の話だ。著者の辺見じゅんが感動を高めるため、意図的に事実と相違する記述をしていた。更には、遺族から預かった資料を紛失していたとは。「バカとアホウの騙し合い」だったのかと、嘆くばかりだった。
そんな中、久保昇、小林多美男、本木孝夫という三人の日本人の無私の生き様に、人間、捨てたものでは無いと大きな安堵を覚えた。本書を仏典、聖書に例えたのも、この自己犠牲の三者が中心に据えられるからだ。果たして、自身が同じ立場にある時、彼らのように生殺与奪権を握るソ連軍、モンゴル軍相手に正義の刃、嘆願書を突きつけることができるだろうか・・・逡巡する。
本書は、冒頭に述べた通り、通常の単行本10冊に匹敵する。なぜ、そこまで著者が固執するのかといえば、一人一人の命の重さは同じだからだ。その公平感を遺族の立場で考えた時、知り得た一人の記録を著者が路傍にうち捨てることができなかったからだ。
戦後の日本は、経済復興が国の重要命題だった。生きるため、多くの日本人がそれに従った。しかし、その成長の果て、人が人として生まれた意味、人格の成長を問う時代となった。その事を、本書は気づかせてくれる。戦争を引き起こすのも人間ならば、治めるのも人間。その過程において無辜の民が望まぬ死、病苦を受けなければならない。何のために、人は無益な争いを繰り広げるのか。「人権」などという綺麗事など、始めから存在しない世界を人はどう生きてきたのか。この人間ドラマを通じて、人の本質を知るべきと「鈍器本」は訴えている。無為の時間を過ごす前に、一日一ページでも良い、読み進んでいただきたい。
『出口王仁三郎 帝国の時代のカリスマ』ナンシー・K・ストーカー著、原書房
・著者には、同一テーマでの再執筆を願う
本書は大本教という神道系新興宗教団体の中興の祖・出口王仁三郎を中心に据えた一書。大本教本部(京都府亀岡市)での調査研究の中間発表とでもいうべき内容。序章、終章を含め全8章380頁弱で構成される本書は、大本教、出口王仁三郎の概略を示したものと言ってよい。
そもそも、本書を知ったのは松本健一(歴史家、思想史家)が日本経済新聞の書評欄に寄稿したものを読んだからだ。松本も書評に記述しているが、内容がアカデミズムの研究文献に左右されている。自身の感覚を研ぎ澄まして、大衆の中に身を置いての論というわけではない。ゆえに、表面をなでただけの出口王仁三郎像が浮かび上がる。
アカデミズムの研究論文に依拠した本書の何が問題なのかは、2009年の発行年から見えてくる。1945年(昭和20)、日本はイギリス、アメリカ、ソビエト(ロシア)を中心とする連合国軍との大東亜戦争(太平洋戦争)に敗北。以後、日本は占領政策下、徹底した国家解体、改造を余儀なくされた。それは、既存の大学改革にも及び、占領軍の意向に沿わない大学教員は追放を受けた。代わって、大学教員の座を射止めたのが、連合国軍が推奨する教員たちだった。いわゆる左派と呼ばれ、戦争中は弾圧下にあった人々だった。以後、日本の教育現場は左派系に迎合しなければ、言論も昇進を含む配置転換もいかんともしがたい状況にあった。松本が問題としているのは、この箇所である。要は、アカデミズムの文献を頼ると、左派での視点でしか大本教、出口王仁三郎は見えないからだ。
このことは一例をあげると、260頁の玄洋社、黒龍会を「悪」と断定し、権藤成卿、北一輝、大川周明の思想に踏み込むこともしていないことから容易に読み取れる。随所に「地域共同体」「農本主義」という社稷についての言葉が出てくるが、権藤成卿が唱えたところの「自治民範」という考え方に著者の関心が向いていない。大本教、出口王仁三郎は現代でいえば、環境社会、農業中心の理想郷、共同社会の創設を目標にしていたが、その基本概念を理解できていないことになる。
大本教、出口王仁三郎は「世の立て直し」をスローガンにしていた。それは血盟団事件、五・一五事件、二・二六事件という大東亜戦争前に起きた社会変革の事件にも関連する。しかし、それらの社会的背景と大本教との関係性が語られていない。2011年、新聞コード(検閲)を持つ朝日新聞に「玄洋社」の文字が出たことから、日本の言論に玄洋社が再び登場した。本書自体は2009年の初版だけに、玄洋社の頭山満、黒龍会の内田良平と出口王仁三郎との盟友関係は詳細に述べてはいない。冒頭、評者が「調査研究の中間発表」と述べるのも、こういった背景があるからだ。著者には今一度、同一テーマでの再執筆を願いたい。
『造船記』野田雅也著、集広舎
・漁師は魚を獲ることで、船大工は船を作ることでしか生きていけない
岩手県大槌町は津波被害によって壊滅してしまった。2011年(平成23)3月11日午後2時46分に起きた地震によってである。
本書は、いわゆる東日本大震災によって家族も家も職場も失いながら、辛うじて生き残った人々が、その後をどうやって生きてきたのかの記録写真集。とりわけ、岩手県大槌町は漁業によって生活の糧を得てきただけに、漁船の修復に携わった船大工の姿は大槌町の復興の姿に重なる。カメラマンでもある著者は、震災から10年余の期間、現地で取材を続けた。その1枚1枚が、記憶に残るものだが、これは、復興の全貌のほんの一部でしかない。1ページ、1ページ、写真と日本語キャプションを読み進む。時折、こういった表現を英語ではなんと言うのか・・・と思い、英文のキャプションから単語を拾い上げる。
津波に吸い込まれる寸前、妻はすがるように夫を呼ぶ。「あんた!」
これを英語では「You!」とする。
永年連れ添った夫婦は、「おまえ」「あんた」で互いを呼んでいたのだろうが、英語での「You!」では色気は表現しがたい。渋みも深みも感じない。しかし、真実を捕らえた写真が言葉のモヤモヤを吹き飛ばす。「あんた!」は「You!」。しかし、現実の1枚が深いドラマを想起させる。
240頁弱の写真集では、震災後の10年余のすべてを伝えるのは難しい。けれども、船大工たちは、黙々と被災した漁船を修復していく。流木を削り、瓦礫の山から部材を作り、エンジン、船体を修理していく。やがて、それらの漁船が漁場から鮭を港に持ち帰り、魚市場で競りにかけられる。いつもの風景を取り戻すために、黙々と、自らの作業を進めるだけだ。しかし、52頁の山崎力さん(当時56歳)の写真、キャプションは言葉を失う。深いシワに刻まれた笑顔だが、歯がボロボロと欠けている。辛うじて生き残ったにも関わらず、山崎さんの兄は前途に希望を見いだせず自死。酷な一枚だ。
それでも漁業で生きてきた人々は、この地を離れない。巨大な防潮堤、かさ上げされた旧市街。山を削っての住宅建設。祭りも復活して、いつもの風景に戻ろうとしている。人々は何かに夢中になる事で、震災を忘れようとしているのだ。
『造船記』。船を造る記録写真集。船を造ることで、夢中になることで、船大工たちは思いもかけない海の仕打ちを消し去ろうとしている。海とともに生きる人々は、本能として襲来した危難を消し去る術を知っているのか・・・。
地震とともに津波が襲来したこと。その自然の仕業に黙々と対峙する人々。後世に繋ぎたい記録だ。
『中国人権英雄画伝』宇宙大観著、集広舎
・現代版『靖献遺言』を広く世界に伝える
本書のページをめくりながら、ふと、思い出したのは浅見絅斎の『靖献遺言』だった。実在の中国の志士、屈平、諸葛亮、陶潜、顔真卿、文天祥、謝枋得、劉因、方孝孺という8人の物語だが、梅田雲浜が長州萩の吉田松陰に推奨。安政5年(1858)の「安政の大獄」を経て幕末の「志士の聖典」となり、維新を迎えた。
本書の水墨画に描かれる116人も、幕末維新の志士と同じだ。志士それぞれの風貌を描いた水墨画に「蔵頭詩」という賛歌が述べられる。それらの中で、68頁に劉暁波を見つけた。あの1989年の天安門事件では民主化を求める学生たちのリーダー的存在。非暴力で民主化を求め、従来の中国共産党による暴力革命に正面から立ち向かった人だ。
評者にとっても、劉暁波は思い入れがある。2010年、劉暁波は獄中でノーベル平和賞を受賞した。しかし、中国共産党は劉暁波を解放するどころか、無視を続けた。この時、世界は中国共産党が卑劣な非民主国家であると強く認識したのだった。その劉暁波も2017年7月に没する。翌年、ベルリン、ニューヨーク、フクオカ(福岡)で追悼集会が同時開催された。この時、評者はパネラーとして「中国革命の故郷・福岡」と題して壇上にあった。取材に訪れたメディアによって追悼集会は台湾に中継され、民主化を成し遂げた李登輝元総統が「中国革命の故郷フクオカ」と反応を示したのだった。
なぜ、ベルリン、ニューヨーク、トーキョーではなく、フクオカなのか。それは、孫文の革命を支援した自由民権運動団体・玄洋社の故地だったからに他ならない。世界は、この事実を知らない。大東亜戦争(太平洋戦争)後、GHQ(連合国軍総司令部)による言論弾圧で玄洋社は隠蔽された。アジアの植民地解放を推進した玄洋社は、欧米からすれば目の上のタンコブだからだ。
吉田松陰は「獄中この書(『靖献遺言』)を誦読し傍らに人なきがごとし」と言わしめた。同じく、この116名の義士伝である本書も、現世、後世の志士に読み継がれ、やがて、維新の時を迎える。孫文も「明治維新は中国革命の第一歩」と言い切った。しからば、『靖献遺言』の8名の英雄譚から明治維新に至ったのなら、この116名の英雄譚が民主化という革命をなし遂げられないはずがない。
ちなみに、孫文の革命を全面支援した玄洋社の「生みの親」とも「育ての母」とも呼ばれる高場乱(男装の女医)は、自身が開いた人参畑塾で『靖献遺言』を講義し、多くの志士を輩出したことでも著名だ。
中国共産党による一党独裁、暴力、人権弾圧を打破する聖典が本書だ。自由のために身も心も捧げた116名の志は、広く、世界に周知されなければならない。
『日本人最後のファンタジスタ』河合保弘・笹川能孝著、つむぎ書房
・ハンセン病への差別偏見を根絶するために
人物評価は難しい。「悪」と評される人ほど、難しい。本書の主人公、笹川良一もその一人だ。その笹川を舞台の脚本の如く、3幕、21場で描いたものが本書になる。人物、時代に馴染みのない読者の為に、登場人物のプロフィールが付されているのは有難い。
評者は『正翼の男』(佐藤誠三郎著)、『残心』(笹川陽平著)、『巣鴨日記』(笹川良一著)などを読了した。それだけに、笹川良一の輪郭は理解している。しかし、これを世間に解説するとなると厄介だ。その一例が、本書に登場するノーベル文学賞受賞者の川端康成と笹川とが古くからの友人関係にあったことだ。美しい日本を世界に紹介した川端と「右翼のドン」と呼ばれる笹川とが親しいはずがない。そう世間は曲解して見たがる。
更に、連合艦隊司令長官として昭和16年(1941)のハワイ真珠湾攻撃を指揮した海軍元帥山本五十六もだ。笹川と山本とが親しい関係にあったなど、「ありえない」として信用しない。大東亜戦争(太平洋戦争)後、戦争犯罪人を収容する巣鴨にいた笹川が山本五十六と親しいはずがないとして、世間は信じたくないのだ。さほど、世間は先入観、風評だけで人物を評価する。
このことはメディアの世界にも言える。文藝春秋社は「平成日本50人のレクエイム」という企画で笹川が選ばれたにも関わらず、掲載を見送った。研究者である佐藤誠三郎のインタビューも終わっていたにも関わらずだ。しかし、オピニオン誌の「月刊日本」が記事掲載した。このことで『正翼の男』が書籍化できたのだ。
「君の意見には反対だ。しかし、君の意見を封じる権利はない」として、出版の雄である文芸春秋社は伝えるのが本筋。しかし、真綿で首を絞めるがごとき、言論弾圧を加えた。このような目に見えない状況下、笹川良一を主人公とする小説が世に登場した。察するに、何かと波風があったのでは・・・。
本書が世に伝えたいのは、『残心』(笹川陽平著)でも述べられるハンセン病撲滅運動に笹川良一が貢献した事実だ。意外にも、日本人はこのことを知らない。世界は評価しているにも関わらずだ。ここにも、「まさか・・・」「信じられない」という偏見が横たわっている。ハンセン病患者は隔離され、病者を出した家は理由も無く差別を受けた。いまだ、ハンセン病は完全に世界から撲滅されたわけではない。その撲滅運動に先鞭をつけたのが笹川良一といっても過言ではない。笹川に対する偏見を解くのは容易ではない。しかし、笹川の願いであるハンセン病患者への差別偏見はやめて欲しい。その原点を笹川の生涯を通じて、本書は紹介しているのだ。
『風船ことはじめ』松尾龍之介著、弦書房
現代、人が空を飛ぶことは可能。飛行機はもちろん、パラグライダー、気球も然り。しかし、その昔は自由に空を飛行する鳥に憧れ、流れる雲に身を任せてみたいと願うだけだった。その空を飛びたいと願う人々の夢を叶えたのは気球。風船とも呼ばれた。本書はその風船こと気球の歴史を探った一書。とは言いながら、「はじめに」において、秋田県仙北市の「紙風船上げ」の行事を紹介する。これが、なぜ、この地に根付いたのか・・・。その答えは、東西文明の軋轢の結果だが、最後の最後に、なるほど・・・と合点がいく。しばし、この人類の壮大な夢が現実となる源流を遡ってみるのも一興ではないだろうか。
すでに、著者は『長崎蘭学の巨人』という一書において「鎖国」「真空」などの言葉を生み出したオランダ通詞の志筑忠雄の生涯を紹介した。同時にロシアのレザノフ使節によって気球が長崎の地で上げられた話を書いている。この一冊だけでも驚愕の史実と思ったが、更に、後継のオランダ通詞がロシア語を学んだ話を本書で解説する。江戸時代、西洋文明の唯一の入手先である長崎ならではの話にワクワクしながら読み進んだ。
西洋文明は長崎出島のオランダ商館から広まる。オランダ商館にはオランダ人やオランダ人と偽ってのドイツ人もいるが、日本人に広く知られるのはジーボルトだろう。更には、西洋医学を伝える大坂適塾に備えられていたオランダ語の辞書はヅーフというオランダ商館長がいたからこそのものだった。本書では、極東の日本に来航するイギリス、アメリカ、ロシアの艦船と幕府との外交も紹介される。その外交において、手腕を発揮したのもヅーフだった。現代と異なり、インターネットも携帯電話もテレビも何も無い時代、限られた情報を基に国益を保持するヅーフの能力は鑑みる必要がある。
更に、西洋の文物が流入すると感染症もやって来る。昨今のコロナではないが、江戸時代は天然痘という厄介なものが広まった。今ではイギリスのジェンナーによる牛痘によって天然痘は撲滅されたが、原因不明の感染症に日本人は苦悶した。風船こと気球の歴史書である本書でも、随所に天然痘と日本人の闘いの歴史が述べられる。
壮大な江戸時代における西洋文明の発展史ともいえる本書だが、先述のヅーフが俳句を詠んでいたことも驚きだった。「春風やアマコマ走る帆掛け舟」という句だが、ここから薩摩島津家が「抜け荷」、いわゆる密貿易をオランダとやっていた事実が露顕する。
9節29話、300頁に渡る本書は既刊の『絹と十字架』『幕末の奇跡』とあわせて長崎もの三部作という。いずれも、ネタ本として使える話が満載だ。とりわけ、小笠原諸島が何故、日本の領土なのか。その秘密は知っておいても損はないだろう。
『言志四録』佐藤けんいち編訳、ディスカヴァー・トゥエンティワン
・日々、一語を咀嚼
「心を磨く言葉」という副題のついた本書のページをめくると、実に余白が多い。第1節から第10節まで項目が設けられ、それぞれに言葉が述べられ、短い解釈が付されているだけだ。初めから最後まで、147の話を読み通すのは簡単。数時間で全ての話に目を通すことが可能。しかし、それは「見る」というだけの行為であって、考えながら「読む」となると、容易ではない。ゆえに、少しずつ自身の腑に落ちるように読んでいった。
本書は佐藤一斎(1772~1859)という江戸時代の儒学者が著した『言志録』を基本に据えて、主要な言葉を項目に沿って解説したもの。佐藤一斎といっても、誰なのかは分からずとも、西郷隆盛は知っていると思う。その西郷が遠島での読書で手にしたのが佐藤一斎の『言志録』だった。不自由な日々、俗世間から離れた環境の中、一斎の述べた言葉を西郷はどのように受け止め、何に感じ入ったのか。
1 志を高く持つ2 視野を広げる
3 運命を引き受けて人生を楽しむ
4 心の持ち方で人生は変わる
5 欲望に振り回されるな
6 人付き合いの秘訣
7 仕事をどう進めるか
8 リーダーの心得
9 生きることは学ぶことだ
10 真の自己を観る
以上の10節、自身の関心の及ぶどの項目から読み進めても、なんら支障はない。
しかし、本書の肝は10、の「真の自己を観る」だろう。静坐という禅宗の座禅とも異なる内省ともいうべき自身の内観を説いている箇所だ。これが、佐藤一斎を頂点として多くの儒学者や文人に大きな影響を与えた源と知る。おおよそ3000人に波紋が広がったというから、その影響力は計り知れない。それは主に二傑と呼ばれた佐久間象山(勝海舟の義弟)、山田方谷からだが、横に、下に、時に迂回しながら波及していく。筑前福岡の儒学者・亀井南冥の孫弟子にあたる女流漢詩人・原采蘋にまで及ぶのだから、先述の西郷が、島流し先で『言志録』を読んでいたというのも、偶然ではなく自然であったことが見えてくる。
冒頭、本書には余白が多いと述べた。ふと、読み込んだ言葉に反応し、様々な書き込みをしている自身に気付く。振り返りであり、さらなる前進のための内省である。情報過多といわれる現代だが、真実は何なのか、種々選択をしなければならない。
編訳者には失礼だが、本書は、「生きることは学ぶこと」としての練習帳なのかもしれない。書き込みで、余白が無くなるまで、読み解くものと思った。

『渋沢栄一(上・下)』鹿島茂著、文春文庫
令和6年(2024)、一万円札の顔が渋沢栄一(天保11~昭和6、1840~1931)になる。「日本資本主義の父」と呼称される渋沢だけに一万円札に相応しい。その渋沢の人物像を知っておくのも話題の接ぎ穂と思い、本書を手にした。渋沢といえば『論語と算盤』というテキストがあるが、本書も「算盤編」「論語編」と二巻に分冊されている。
渋沢は生涯に500を超える事業を興したが、生家は血洗島(埼玉県深谷市)の裕福な農家。地域の代官から無法な御用金(上納金)を求められ、幕府に反発。水戸学の思想から倒幕運動に身を投じる。しかし、渋沢の才能を惜しむ周囲の画策によって皮肉にも徳川慶喜の臣下に組み込まれる。そして、フランスでのパリ万博に幕府随員の一人として送られる。この一年半余のパリ滞在が、渋沢の未来を決定づけた。
国の富とは、国民一人一人が豊になること。この考えから、固定した収益分配を講じるより、収益拡大を図った方が良いと判断した渋沢。商業を盛んにし、新しい産業を興すことが近道と考えた。その手法が銀行創立、株式会社設立、社会福祉増進、労使の協調、学校教育の拡大だった。
渋沢は民間外交官にも熱心。新興国として膨張する日本に対し、アメリカは日本人移民排斥を主張する。日本脅威論、中国大陸の権益獲得が背景にあった。しかし、渋沢は粘り強くアメリカの誤解解消に動いた。その一つが、相互の文化を理解し、摩擦を避けるとしての人形交換だった。この意を受け行動した人に添田寿一(台湾銀行頭取)、安部磯雄(衆議院議員、学生野球の父)がいる。ともに、旧福岡藩の出身。
渋沢は日米の戦争回避にも動いた。頼みとしたのが金子堅太郎(農商務大臣、法務大臣)だが、金子も福岡藩の出身。この金子との姻戚関係もあってか、渋沢の米寿の祝いでの代表を務めたのが團琢磨(三井合名理事長)だった。奇しくも、この團も旧福岡藩。
本書では述べられないが、渋沢には『論語講義』という著作もある。この渋沢の論語理解の背景には、亀井南冥(福岡藩校甘棠館館長)の『論語語由』がある。『論語語由』を渋沢に紹介したのは安川敬一郎(明治鉱業、安川電機、玄洋社)だが、この安川も旧福岡藩出身だ。
これだけに留まらない。渋沢は教育に熱心だったが、国士舘(国士舘大学)創立にあたり、旧福岡藩の頭山満(玄洋社)への協力を惜しまなかった。頭山といえば亀井南冥の系譜に連なる男装の女医高場乱(玄洋社)の教えを受けた人だが、渋沢との会話に高場乱の人参畑塾などは話題になったのか、いささか気になる。
上下巻で千ページを超える大作だが、企業経営に対する渋沢の道徳感は参考になるものばかりだった。

『ガネフォ60周年記念誌』ガネフォ会・水球チーム編
・ガネフォを後世に伝え、現世に広めるために
本記念誌は、1963年(昭和38)11月10日から21日まで、インドネシア・ジャカルタで開催された新興国スポーツ大会(通称ガネフォ)に参加した水球チームの方々によってまとめられた記念誌。ガネフォには、51カ国、2700人余が参加する世界的なスポーツ大会だが、日本からは頭山立國団長(玄洋社・頭山満の直孫)をはじめ96名が参加した。結果、日本は金メダル3、銀メダル9,銅メダル9を獲得し、総合6位に入った。水球チームも健闘し、銀メダルを獲得している。
今回の記念誌には20名近くの方が寄稿され、当時の写真も含めて85頁余で構成されている。寄稿文のトップは衆議院議員・河野太郎氏(デジタル大臣)である。祖父の河野一郎(衆議院議員・1964年東京五輪担当大臣)の意向もガネフォにあったということが機縁。
今回の記念誌発行に先立ち、令和5年(2023)11月3日、東京・銀座で「ガネフォ会」と称しての会合が開かれた。毎年開催されていたがコロナ禍で中断。このこともあるが、惜しむらくは、往年の選手たちも80歳を過ぎ、なかには三途の川を渡った方もいる。今後、会を継続して開催できる余力も無いことから、今回の60周年をもって卒業となった。
ガネフォは、日本、アジア、世界のスポーツ史に記録されるべきスポーツの世界大会だが、当時の世界情勢から闇に葬られたスポーツ大会といえる。これほどの国際的なスポーツ大会でありながら、認知されないというのは後世の人々に対し、失礼というもの。そこに、ガネフォを主題に、一橋大学で博士号を取得した冨田幸祐氏(中京大学講師)がガネフォ会に参加された事は誠に喜ばしい。今後も継続して伝え、広めていきたいと考えている。
筆者は、2013年に『アジア独立と東京五輪』を上梓することで、歴史の流れに一本の杭を打ち込んだが、闇に封じられたガネフォを表に出したいとの希望からだった。それに反応されたのがガネフォ・水球チームの方々だった。これが機縁となり、筆者はガネフォ会に参加することとなった。
ガネフォについては、フランス帝国主義、イギリスの植民地主義、アメリカの覇権という背景から語らなければ近代オリンピックとガネフォの関係性、対立構造は理解できない。「スポーツは政治」とスカルノ大統領は言い切ったが、まさにその象徴がガネフォだ。そのガネフォの記録を日刊スポーツの記者であった宮澤正幸氏が拓殖大学100年誌に寄稿されていた。そのコピーをテレビマンユニオンの田中由美さんからいただいたが、そこには昭和7年(1932)の「五・一五事件」(犬養毅首相銃撃暗殺事件)の海軍将校(当時)の名前があった。このことも含め、このガネフォを後世に伝えたいと考える。
『江戸という幻景』渡辺京二著、弦書房
新装版となった本書を読了した。250頁余、11の章で構成されるが、江戸時代が教科書で教えられる「士農工商」という厳格な身分制度ではなく、緩い関係で成り立っていたことを知る。
まずは、23頁の権藤成卿の『自治民範』を引き合いにする。他家の行事に招かれた娘が家を出る時に着飾って玄関を後にしようとした。それを、晴れ着は招かれた家で着替えろと咎める。他者の妬み、誹りを招かない為だと諭す。自由だから、と自己主張する現代と比較して、自由の限度をおのずから弁えていたのが江戸時代だった。
さらに、笑ってしまうのが27頁の狸を愛し、狸を飼って暮らす人の話。これは、巻末の解説で評論家の三浦小太郎氏も「新橋の狸先生」を真っ先に挙げていることからも分かる。自由を謳歌する鑑ではなかろうか。「天の命」と言われればそれまでだが、犬を愛した西郷隆盛にも通ずる。そして、自由となれば人権が必須だが、それは84頁に紹介されている。その自由と人権では、102頁からの結婚観、男女の結びつきが、実に自由奔放。「家」を継承することが江戸時代の規範だが、家風にそぐわないとなれば簡単に相互が納得の上で離縁。西洋の「契約」という法律など存在しなくとも社会が安定運営できる制度となっている。俗にいうところのバツ一、バツ二は当たりまえ。婚前交渉どころか、北欧のフリーセックス顔負けの社会が近代化前の日本だった。
100頁の「労働は労役ではない」の箇所では、日本と西洋の労働観念の差異が描かれて面白い。日本人は古くから労働と遊びを混在化していた。田植えでは、早乙女を男衆がカネや太鼓ではやし立て、歌の応酬を繰り広げる。西洋であれば、男衆も田植えを手伝えば「効率的」と考えるが・・・。現代日本でも長距離通勤を苦にもしないのは、通勤時間を「遊び」に変えてしまからだ。「実働8時間」という西洋の規則を導入したことが由来だが、西洋の労働者にとって8時間労働は大幅な労働時間短縮を勝ち取った結果である。
本書では、庶民だけではなく、奉行を務めた川路聖謨の日常を紹介する。これが実に爆笑ものであり、臭い。奉行として白洲において裁きをするが、その厳粛な場でオヤジギャグを発する。周囲の者は、たまったものではなかったはずだ。インターネットで知る川路聖謨からは想像を絶する「生態」を知る。この人物に親近感を抱かない人はいないだろう。更には、勝海舟の実父である勝小吉も紹介されるが、名目は武士でも、正味は町人の勝小吉だけに、子息の勝海舟よりも小吉に人気が集まるのも致し方ない。
江戸時代の封建的身分制度に大いなる反発を抱いたのが渋澤栄一。渋澤が出現する時代は、すでに幕藩制度が疲弊し、大いなる改革が必須の時だった。今、私たちが知る江戸時代はこの幕末の過渡期が拡大解釈されただけではないだろうか。欧米勢力の出現によって、西洋化した日本がどこか窮屈に感じるのも、日本人の体質と西洋の規範とが乖離しているからに他ならない。その差異を知る一助になるのが本書だ。寝転がって、読み進むと、なおさら、良い。
『GANEFO その周辺』宮澤正幸著、拓殖大学創立百年史編纂室
・スポーツの歴史に意外な史実が
本書は、1963年(昭和38)11月にインドネシアのジャカルタで開催されたガネフォこと新興国スポーツ大会の記録。47カ国、2564名が参加した大会だけに「幻のオリンピック」とも呼ばれる。1964年(昭和39)の東京オリンピック開催にも大きな波紋を広げた。近代のスポーツ史を考える上で、記者、監督として参加した著者の記録は貴重。47カ国、2564名が参加した大会の記録だけに貴重。内容として「第四回アジア競技大会」「第一回新興国スポーツ大会」「第一回アジアGANEFO」の三部、約90頁で構成されている。
まず、このガネフォだが、第四回アジア大会での欧米の介入が発端となる。アジア大会にインドネシアが中華民国台湾、イスラエルに招請状を出さなかった。このことから、スポーツは公平でなければならないとするIOC(国際オリンピック委員会)が公式記録として認めないと牽制。これにインドネシアのスカルノ大統領が反発し、IOC、国連までをも脱退した。
そして、独自にソ連(現在のロシア)、中国(北京)の後ろ盾を得て、独自のスポーツ大会ガネフォを開催した。ここでIOCがガネフォに出場した選手には東京オリンピック出場資格は無いと宣言。東京オリンピック開催を控えた日本の体育協会、JOC(日本オリンピック委員会)は、ガネフォに選手団を送らなかった。しかし、アジアとの連帯を考える日本の政財界、有志は選手団を編成。ジャカルタへと乗り込んだ。インドネシア国民は、その日本の信義に大興奮したのだった。この選手団長を頭山満(玄洋社)の直孫である頭山立國氏、最高顧問に柳川宗城(元陸軍大尉、中野学校、インドネシア独立義勇軍教官)が就任して臨んだ。
翌年、東京ではアジア初のオリンピックが開催され。IOCを脱退していたインドネシア、ガネフォで問題となっていた北朝鮮も来日した。しかし、両国ともオリンピックには参加せずに帰国していった。以後、インドネシアでは政変によりスカルノ大統領が失脚。
評者は『アジア独立と東京五輪』において、このガネフォについて書き下ろした経緯があるので、本書に述べられる事々は手に取るように理解できた。しかしながら、ガネフォを初めて知る人には難しい。欧米のアジア侵略史、インドネシア独立戦争、インドネシア独立に至る歴史に関心が無い方にも、皆目、理解が及ばないだろう。ただ、本書の45頁には「五・一五事件秘史」という一文があり、これが実に驚きの内容だ。連合赤軍の重信房子、その娘の周辺との関係性などは、この昭和7年(1932)に起きた事件にまで遡らなければ理解は進まないからだ。
インドネシアのスカルノ大統領は「スポーツは政治」と言い切ったが、まさに、スポーツの陰に政治が顔を覗かせている。その意味でも、スポーツ史は近現代史の一部として読み通さねばならない。それを強く意識させる一書だった。
『カイザリンSAKURA』河合保弘著、つむぎ書房
まず、タイトルよりも女性コミックのような魚淵あかりさん作画の表紙に戸惑ってしまう。いったい、何なのだろう・・・。とりあえず、プロローグを読んでみるが、史実に従いながらもフィクションであるとの著者の断りがある。ならばとフィクションとして読み始めるが、これがなかなか、どうして、歴史小説のような作風。このようなスタイルでの小説形式に「面白い」と思う。芥川賞を受賞した黒田夏子さんの横書き小説『abさんご』にも似た軽い驚きも含んでの「面白い」だ。
ストーリーとしては歴史年表にも記載される第109代の後桜町天皇(1740~1813)の生涯をまとめたもの。全3章、各章を13話で構成しているので、少々肩の荷を下ろし、楽しんで読むことができる。それでいて水戸黄門こと水戸光圀が編纂を進めた『大日本史』から派生した後醍醐天皇を祖とする南朝を正統とする事と北朝との関係が述べられる。これは、小説とはいえスリリングだ。いや、フィクションだからこその問題提起か。朝廷と尾張(徳川家)はつながっているという記述も、『徳川幕府が恐れた尾張藩』(坪内隆彦著)で知っていたからこそ納得できるが、ここに著者の知識の深さを垣間見ることができる。皇室を守護するのは八咫烏である、長州毛利家と公家の鷹司家との金銭的関係などもそうだ。更には、竹内式部の名前も。幕末維新史に関心のある方にはフィクションといいながら、「そんな観点があったか・・・」と歴史を俯瞰する視点に気づかされるだろう。226ページの皇嗣についても「歴史に学ぶ」事と言える。
皇室は国の民の安寧を祈願するもの。現在の皇室と国民との関係性を考えると、この小説が内包する主張が見えてくる。歴史は勝者によって作られ、敗者の歴史は闇に封じ込められる。しかし、敗者の歴史にも真実が潜んでいる。この整合性のバランスが崩れるとき、一大転換点となり、いわゆる政変や革命となる。それはクーデターであったり、内部崩壊であったりするが、それを昔の人々は天変地異の現象に変化の兆しを見いだしていた。迷信として片付けるか、天の意思として受容するかは各人の立場、経験かもしれない。緊張感をもって意識を働かせるべきだろう。それが、今という時なのかもしれない。そのことを伝えたいという思いも、この作品には込められている。
『大日本史』から『日本外史』『弘道館記述義』へと変化し、正邪、黒白、善悪という二元論的思想が野火のように燃え広がったが、その動きを懸念していたのが朝廷ではなかったか。しかし、結果的に調和を旨とする皇室の意に反し、幕府は倒れるべくして倒れた。
「最後の女性天皇を巡るファンタジー」との副題が添えられる本書が意図するものは、大きい。皇室のありかた、皇室を戴く国の民としての在り方の再考を促すものだった。
『欧州統合の政治史』児玉昌己著、芦書房
・日本がEUから学ぶことは多い
本書はNHKラジオ第2放送で2011年1月から放送された「EU・ヨーロッパ統合の政治史―その成功と苦悩」のテキストを基にした一書。全13章、250ページで構成されている。
まず、日本人にとってのEUといえば、2020年のイギリスのEU離脱が記憶にあるだろう。イギリスがEUから離脱した後、日本経済にいかに影響するのか。連日、マスコミはその利害得失を報じていた。さらには、ギリシャの金融危機からEUの崩壊を予見する評論家、識者も多かった。しかしながら、現在、EUは存続している。どころか、ロシアのウクライナ侵攻の背後にEUを基盤とした軍事同盟の影すら意識しなければならない。その存在感を増すEUの成立の歴史を説いているのが本書だ。
EU加盟国の総人口は51000万人、GDPは15兆9850億ドル。このEUを一つの国家とみれば、あなどれない大国であることは一目瞭然。国連は安保理5大国の拒否権によって機能不全に陥っているが、EUはその成り立ちをみれば、欧州議会の結束の強さが窺える。一国だけの利害得失を是認しない。
さらに、小国の集まりである欧州では、集団での防衛力を結集しなければ大国のロシア(旧ソ連)の軍事的脅威に対抗できない歴史がある。154ページにロシアがEU加盟を打診し拒否された事実に、欧州が旧ソ連に受けた傷の深さが窺える。それを前提で、獅子身中の虫ともいえるドイツとの和解も成し遂げている。かつて、「勝者の愚行」と揶揄された第一次世界大戦でのベルサイユ条約の失敗を繰り返さない試みがなされている。国際連盟の機能不全からナチス・ドイツの勃興を許したが、その轍を踏まないための国際連合だった。しかし、その国連も機能不全であれば、欧州は欧州での経済、防衛の組織構築は必然だった。当然、小国であろうが、大国であろうが、国家主義者は存在する。それを超越しなければ、三度、欧州は戦場になるのだ。本書81ページの「ヨーロッパの制度にドイツを組み込めば、軍事的暴走を止められる」という記述は、ある意味、日米安保にも似ている。
欧州は、食糧、エネルギーなど、解決しなければ生きていけない問題が多々ある。その中で、世界各国に旧植民地という連邦を所持するイギリスとEUは基本的にスタンスが異なる。イギリスのEU離脱に、欧州に依存しなくても良い立ち位置にあるのが見えてくる。
EU成立の過程で、必然的に乗り越えなければならない葛藤がある。それが128ページに出ている第二次世界大戦でドイツに占領されたフランスの立場だ。ドイツとフランスの和解は簡単だが、個人史の積み上げ、個人が受けた傷は容易には消えない。これは日本にとって参考になりえる。今後、日本がEUとどう向き合うかも含めての参考書だ。

『今日も世界は迷走中』内藤陽介著、ワニブックス
・著者が論じる問題点を自身の立場で論じてみるとどうなるか
全5章、330頁余で構成される本書は、第1章「中国が仲介したサウジ・イランの国交回復から“世界を読む”」、第2章「取扱注意!今日も世界を動かす「陰謀論」」、第3章「日本が見習うべき“お手本”北欧の迷走」、第4章「みんな知らない韓国“反日の正体”」、第5章「日本社会の病理とその処方箋」の内容だ。いずれも、興味深いタイトルが並んでいる。しかし、「はじめに」を読み始めて間もなく、「まさかロシアがウクライナに軍事侵攻するとは・・・」と著者が率直に不明を詫びる箇所に、著者も迷走しているのかと興ざめしてしまった。欧州における中国とハンガリーの関係など、著者の情報分析が進んでいればと悔やまれた。
とはいえ、近年、欧州が移民を積極的に受け入れたことにより、欧州の情勢分析が難しいのも確かだ。国家として存在していても、移民を受け入れたことで旧来の欧州各国の文化や伝統がそのまま継承されているわけではない。本書の128頁にあるように、「なぜ、トルコはスェーデンのNATO加盟に反対なのか」など、複雑な移民事情が国家間の外交関係をややこしくしている。欧州の親日国であるフィンランドの英雄マンネルハイムといえども、かつての日露戦争時にはロシア軍として日本軍と対峙していたのだから、さらに複雑。加えて、移民政策の弊害については、ブレイディ・みかこの著書に「多様性ってやつは喧嘩や衝突が絶えない」「地雷だらけの多様性ワールド」と弊害が述べられている。それだけに、欧州のどこかに民族紛争の火種がいくつも転がっている。
第4章に韓国の反日について解説されているが、九州北岸、中国地方北岸地域からすれば、隣国ではなく古くからの「お隣さん」だけに、現実に韓国と直面する地域からすれば杓子定規の解釈に思えてならない。これは地政学の観点からも解き明かして欲しい。
そして、第5章の「日本社会の病理とその処方箋」については、やはり、具体的な解説が必要なのではと考える。レジ袋の有料化について、その広報において政府の対応に瑕疵があったことは確かだ。条件付きで無料であったりする制度の前に、レジ袋の全てが有料であるかのような告知は混乱を招いた。しかしながら、海浜に接する地域の浜辺や岩場を見てみれば海洋ゴミだらけ。それこそレジ袋、ペットボトル、空き缶、ガラス片で汚染されている。日本社会の病理といっても、首都圏と地方とでは異なるので、一概に「環境問題は過剰」との批判は机上の空論だ。狭いようで広い日本。地域、視点を変えて、外交関係も含め論じなければならない。
本書に掲げられている問題を、自身の立脚点で論じても面白いのではと思えたのだった。
『デュオする名言、響き合うメッセージ』立元幸治著、福村出版
・墓碑に学ぶ事は歴史に学ぶことに等しい
本書は、著者による霊園散策集であり、思索集というべきもの。政治、官民、戦争、志、文明、時代や世相、学びと医学、創作、芸術、人、生きるということ、人生というキーワードを基にテーマを設け、12章で構成されている。多数の著名人の言葉を47話、340頁弱に集約させている。ふと、これは著者が綴ってきた一連の霊園物語の集大成でもあると気づかされる。
読み進みながら、一つの時代を見る事ができる。インターネット全盛の現代、スマホ症候群ともいうべき、上っ面をなでた薄っぺらな文字の羅列に憤りを感じる。思案する前にインターネットが最大公約数の解答を用意してくれるからだが、それに慣れ切り、何ら疑問を抱かない人が増えた。言葉の重さ、大きさは感じられない。しかし、この一書からは逆に言葉の重厚さ、奥行きの深さを感じる。かつて、「行間と行間の間を読め」と言われたが、まさに、それが蘇ってくる。著者が、どれほどの読書量、それもジャンルに捉われず知識を吸収し、体験を経たかが窺える。それは、声なき民の代弁であり、人としてのモラルを求めるものであり、忙しい日々に流されてしまった大事な言葉への回帰だ。
「今だけ金だけ自分だけ」の世相は、いつの時代にもある。それでも、自身の信念を貫き通した人の紹介は清々しい。先が見えないと嘆くのがバカバカしくさえ思えてくる。とりわけ、第二章の「政治は玩具ではない」の井上ひさし、寺山修司の言葉は東京一極集中の弊害を具現化している。更には、言論弾圧の世があったことなど知らず、始めから「自由」があったと思っている世代には、絶対に紡ぎだす事のできない言葉は深く痛みを感じる。怒りを笑いに換える術を身につけなければならなかった人々の言葉は嚢中の錐でもある。
言葉の重さ、重要性については第六章の「時代迎合の記事論説読むに堪えず」(永井荷風)は、実に同感だ。「忖度」という単語が並んだ結果、新聞購読者数は激減し、出版不況を出版業界自らが招いた。全ては、上手く世渡りすることを評価した結果だ。世相を斬る言葉が無くなって久しいが、大宅壮一の「一億総白痴」「一億総評論家」の予言はテレビの教養番組にお笑い芸人が登場することで、適中した。第九章の黒澤明の「作家は歴史の被告人だ」という言葉は、テレビに限らずインターネットのユーチューブに映像を流す輩に知って欲しい。
墓碑を巡るとはどういうことか。それは、一人一人が生きていくこと、それも、自身に与えられた役目を果たし、生きていくことを深く考える行為だ。ある意味、「歴史に学ぶ」とでも言い換えることができる。著名人の言葉の中から、これは!と思う言葉に出会ったら、各人の作品をじっくりと味わってみる。そこから得るものは少なくないはずだ。著名人だけではなく、無名の方々の「ゆるり」「泡沫」も捨てがたい。
『現代ユーラシアの地政学 EU・中国関係とハンガリー』児玉昌己著、久留米大学法学部
・地政学という学問の必要性を気づかせてくれる論考
全7章で構成される本論考は、アジアに位置する日本もEUの動きに無関心であってはならない。むしろ、国防も含めてアメリカに追従するだけではならないと気づかせてくれる。それは第1章の「地政学とユーラシア」においても同じだ。地政学(Geopolitics)という言葉が、地理(geology)と政治(politics)の合成語であることの解説からして、知識、認識の欠如を気づかせてくれるからだ。
今では「地政学」という言葉は当然のように評論などに使われるが、「戦争を指導した思想として教育の場からも研究者の間からも、長く地政学は取り挙げられることはなかった。」という。この「地政学」については、第2章の「3人の地政学的思想家」としてマッキンダー(1861~1947)、ホブソン(1858~1940)、クーデンホーフ・カレルギー(1894~1972)の3人を紹介、比較、検討することで歴史における地政学の有用性を証明してみせる。
そして、第3章以降において、ユーラシアという大陸を舞台に1.ロシアの相対的後退、2.EUの発展、3.中国の台頭と急速な強大化が解き明かされる。従来、ロシア革命から続く思想的な歴史でしか論じられてこなかったロシアだが、ヨーロッパ諸国、東欧諸国との関係性からの変遷は、生物が環境に応じて成長を進める様を見ているようだった。そこに、ユーラシアの東端に位置した中国(中華人民共和国)が経済成長とともにEUにも影響を及ぼしてきたことに改めて関心をそそられる。
中国は、国際社会に覇を唱える以前から「遠交近攻」という外交政策を基本にしていた。アフリカ諸国には医療団を送り、アジアには技術援助や資金援助を申し出ていた。それが大きく転換したのは米中の接近、それにともなう日中の国交樹立だが、あの天安門広場が自転車で埋め尽くされていた時代の中国の印象が強かったのではないか。それが、今や軍事力を背景にアジア、太平洋に膨張するまでになった。この姿を見て、かつての大日本帝国が半島、大陸に拡大していった様に似ている。日本同様、中国が紛争に引き込まれなければ良いがと懸念する。
その中国とEU加盟国のハンガリーとの関係性を著者は一つの具体的な事例として紹介するが、利害得失による押し引きの外交のあり方とEU議会のあり方は実にEUの真骨頂を示している。特に、ハンガリーが中国を利用し、その中国にEU議会が不快と不信を抱き、EU議会が否決する様は爽快でもある。日本においても手の下しようのない中国のスパイ活動だが、丁々発止の経済制裁という外交カードは「政治は生き物」を見ているかのようだった。とりわけ、中国政府のウイグル族などへの人権弾圧は内政不干渉を楯に日本の介入を許さない中国だけに興味深い対応だった。
最終の結論にも記されているが、従来、日本の外交は東欧諸国に対して関心が低かった。故に、ロシアのウクライナ侵攻も予見できない日本の評論家を出すに至った。更に、ウクライナ紛争において、ドイツが存在感を示していることにも注目すべきだ。これは国連が機能不全状態に陥っていることを世界に見せつけるものだ。最近、日本各地にヨーロッパ各国の戦闘機が飛来し、艦船が寄港するのもEUの対中政策の一環とするならば、日本の社会はEU情勢の報道量を増やさなければならない。再び、道を誤らないためにも、必須ではないだろうか。
『45年余の欧州政治研究を振り返って』児玉昌己著、久留米大学法学部
・もしも日本がEUに加盟したとしたら・・・
今から45年前、筆者は西ドイツを中心にヨーロッパ各国を放浪した。どうせ、欧州に足を踏み入れたのならばと、東西ドイツの国境を越え、東ドイツにポツンと島のように存在していた西ベルリンに行った。一日だけのビザを買って、東ベルリンにも入域してみた。そこで目にしたのは、経済格差だった。そんな凋落の東ドイツに比して、欧州では統合の試みが進んでいた。国境を通過する列車の車内で、パスポートではなく共通の身分証明書を提示するだけ。実験的ともいうべき、欧州連盟の在り方を模索していたのだった。
本論は、日本において数少ないEU研究者である児玉昌己久留米大学名誉教授の半生の記ともいうべきもの。長崎県佐世保市の政治活動が盛んな高校を卒業し、同志社大学に進学。そして、大学院に進み、研究者の道を歩むところから始まる。欧州だけではなく、日本も朝鮮戦争、ベトナム戦争と続く中で、混沌とした時代にあった。
読了後、欧州は国連に対抗できる同盟を形成する考えがあるのではないかと訝った。国連は、ドイツと日本を包囲するために連合軍が形成し、日独の敗戦後は国際平和を維持する機関として機能するはずだった。しかし、早々に、常任理事国の拒否権という特権によって機能せず、世界各地での紛争は続く。
今回のウクライナ紛争において、ドイツの行方、判断を見ていた。日本同様、国連ではドイツは敵国条項に入ったままであり、貢献活動は求められるものの、軍事的拡大は制約を受ける。そんな中、ドイツ製の戦車がポーランドに送られることで、対ロシアとしての形式は整えられた。しかし、敵国条項に記載される国連加盟国としてはいかがなものなのか。ドイツに求められた対応を日本も求められるのか。そんな他国の都合に、ドイツ、日本は耐えられるのか。
ふと、もしかしたら、ドイツはEUという欧州同盟に存在することで、矛盾だらけの国連から脱退するのではと考えた。ロシア(旧ソ連)、中国(北京)という大国の拒否権によって物事が進まない組織よりも、新しく統合できる組織を設けようとしているのでは・・・。旧ソ連邦に所属していた国々がEUに加盟を希望するのも、無機能の国連を見限り、共存共栄のEUに加盟することで経済的にも軍事的にも安定した国家運営を求めているからではないか。
いまだアメリカに従属し、日本は欧州の動きに関心を向ける風ではない。しかし、もし、日本がEUに加盟したとしたならば、どうなるのか。日本が、ロシア、中国、北朝鮮を欧州と挟み撃ちする形になる。さすれば、世界情勢はどのように変化するのか。一つの仮定として、想定してもよいのではと考えた。考える事々が多い論考だった。
『儒学者 亀井南冥・ここが偉かった』早舩正夫著、花乱社
・亀井南冥の再評価の序章としての一書
亀井南冥(1743~1814)という名前に対し、南冥の出身地福岡でも誰のことなのか、ピンとくる方は少ない。国宝金印の鑑定をした人ですとつけ足すと、「ああっ、あの金印の」と思い出すかのように納得される。その亀井南冥について、子孫が詳細に業績などの解説を行ったのが本書になる。3部で構成され、序章、終章も入れると全31章、380頁弱という大部だ。子孫が執筆したとなると、心情的に甘くなりがちだが、著者自身、身びいきにならぬように心がけたという。
亀井南冥は姪浜(福岡市西区)の一介の町医者の子供として誕生した。封建的身分制度の江戸時代からいえば、町民身分。しかし、南冥は早くから学問での才能を発揮し、それは朝鮮通信使の江戸参府の際、接遇係の末席に連なったことが証明する。朝鮮側から漢籍に優れた人として評価された。天明二年(1874)、福岡藩は修猷館、甘棠館と二つの藩校を設けた。南冥は甘棠館の祭酒(館長)に就任し、士分格を得る。しかしながら、その能力の高さは生粋の武士階級の誹謗中傷の標的となる。水戸藩の藤田東湖も「古着屋の倅」として水戸藩士の妬みの対象だったが、南冥もそれに等しい異端児扱いを受けている。
寛政四年(1792)、南冥は詳細な理由も明らかにされず「終身禁足」という罰を受け、館長職を退役となる。以後、生涯にわたって外出もままならず、往来の人も途絶え、酒浸りの内に72歳にして没した。この南冥失脚については、徳川幕府の「寛政異学の禁」に触れたという説がある。けれども、福岡藩からすれば荻生徂徠派の教えのみならず、実学に等しい教育を武士階級に施すやり方に強い反感があったとしか思えない。学問の成績よりも武士家格を学業に優先させていた修猷館が存続したことから、教育内容に福岡藩の反発があった。
亀井南冥には多くの門弟がいたが、中でも著名な学者として豊後日田の廣瀬淡窓がいる。廣瀬も咸宜園という学塾を開いたことで全国から入門者がやってきた。能力主義の教育方針は師の亀井南冥、昭陽に従っている。弟子や孫弟子たちの華々しい活躍に反し、存命中に評価を受けなかった南冥だが、明治期になって日本資本主義の父と呼ばれる渋澤栄一によって再評価された。「終身禁足」中に書き残した『論語語由』が渋澤の目に留まり、渋澤が説くところの論語に多数、引用された。更には、あの明治の文豪・森鷗外からも高い評価を受けている。果たして、福岡藩の身分差別を受けなければ、どれほどの数の弟子を育て、新しい学問体系を形成し、経世家としての著作を遺したかは計り知れない。しかし、南冥の志は門弟、孫弟子がしっかりと受け継いでいた。
今一度、亀井南冥の何が偉かったのかは、幾度も振り返らなければわからない。本書はその序章に過ぎないことを述べておきたい。
『ハマのドン』松原文枝著、集英社新書
・ハマのドンこと藤木幸夫の原点は弁当
令和5年(2023)6月22日、KBCシネマ(福岡市中央区天神)で本書と同名のドキュメンタリー映画を鑑賞した。複数の編集者や友人から「観ておくべき」として推奨され、放映最終日になんとか間に合った。しかし、客の入りは、一割にも満たない。およそ2時間弱、そろそろ集中力が切れかかってきた頃に終了。パンフレットを購入し、その足で新刊書店に出向いた。
映像は感動的だが、それは徐々に記憶から消え去っていく。せっかくのドキュメンタリー映画も、場面、言葉などが思い出せなくなる。その補完の意味でも本書はありがたい。更には、全5章のうち、4章は映画で鑑賞した内容と重複する。小見出しを追えば、映像が蘇る。しかしながら、本書の肝は第5章の「闘い終えて映画化へ」だ。
崔洋一監督の遺言という箇所での「港湾労働者の姿が描ききれていない」という指摘は、まさしくと思った。事前に火野葦平の私小説『花と龍』の映像を見れば、沖仲士こと港湾労働者の生きざま、歴史がドキュメンタリーに色を添えたかもしれない。
本書を通読して面白いと思ったのは、「おわりに」の中で、ハマのドンこと藤木幸夫氏のところに元首相の菅義偉氏が挨拶に出向いたという箇所だった。これぞ、政治の世界そのままではないか。この政治世界の問題はIR(インテグレイティッド・リゾート)基本法が平成28年(2016)に成立したことが発端だ。意味不明の横文字に国会議員が大騒ぎしたが、いわゆるカジノ構想だ。その大々的な構想ターゲットになったのが、横浜港だった。カジノを誘致すれば税収増額、雇用が安定するとの謳い文句だった。しかし、これにはとんでもない落とし穴がある。それを具体的に示してくれたのが、新型コロナウイルスだった。
このカジノだが、本場アメリカのラスベガスでは衰退している。アジアでは香港、マカオ、シンガポールが有名だが、現地での実態を知れば知るほど、税収や雇用が「絵に描いた餅」であることがわかる。すでに、大阪市がカジノ誘致を本格化させているが、事業者として参画しているオリックスも不良債権を抱えることになるだろう。本来、カジノ事業者が負担すべき「夢洲(ゆめしま)」の造成費用を大阪市が負担するというから、先行きは暗い。
為政者を含めての事業者の見通しの甘さはどこからくるのか。それは、本書の75頁に示された弁当の写真が物語る。「食べることができるありがたさ、食べてもらいたい思い、弁当を持たせるということにこだりがあるのだ。」との記述だが、戦後の貧しい時、職を求めて集まる港湾労働者には弁当がふるまわれた。貧相な弁当ではあるが、労働者たちはその弁当のタイ米を家に持ち帰り、雑炊にして子供たちに食べさせた。額に汗し、日々の糧を得た港湾労働者が築き上げた横浜港を、道楽者のために明け渡すわけにはいかない。最高権力者に立ち向かう藤木幸夫の原点は、弁当にあった。ふと、この弁当の話から「港湾労働者の姿が描ききれていない」という崔洋一監督の言葉を思い返したのだった。
『詩集 サラフィータ』前野りりえ 著、書肆侃侃房
・時空が交錯する中で生じる聖と魔
サラフィータとは?何ぞや?
普段、詩集を手にする事が少ない筆者にとって、サラフィータとは詩の表現方法と思っていた。しかしながら、そのサラフィータが著者による造語であり、太宰府を意味する言葉と分かった時、やはり、思い浮かんだのはイーハトーブ。宮澤賢治がエスペラント語で自身の故郷である花巻を様々に呼び換えた手法が蘇った。
サラフィータとは太宰府。
そう意識づけをして、Ⅰ章のサラフィータ1月から12月を読み解いてみる。たちまちに蘇ってきたのは、大宰府政庁跡だった。遮蔽物がなく、四囲を山に抱かれ、それでいて規則的に並ぶ礎石群。
古の栄華を感じることができるが、永い永い年月の積み重ねがプロジェクターに映し出される映像の如く。それは、花であったり風であったりして、姿を変えて今に再現されているのではないか。そんな思いを抱くと、詩の中に織り込んである、今、目に映る自然が言葉に変身していることに気付かされる。これはもう、太宰府に愛着を持った者でなければ描けない言葉の風景だ。
帯に、詩人の岡田哲也氏の言葉があった。「前野りりえのリリシズム」と。詩人は詩人の言葉の表現手法を「リリシズム」と名付けた。納得。
そして、Ⅱ章のエニウェア。
これは、日々の風景、光景を言葉に置き換えたものだが、「なるほど」「わかるわかる」と腑に落ちるものもあれば、迷い込む詩もある。この迷い、自身の存在を隠してブラインドの隙間から見る風景が、岡田哲也氏の言うところの「魔が潜む」なのだろう。
歴史に正負があるように、詩にも聖と魔が交錯することを教えられた。それも、同時並行の時空の中に。
リリシズム、面白い。
『うどん屋おやじの冒険』語り・青木宣人、聞き手・宮原勝彦、集広舎
・人の存在意義は共同体が教えてくれる
本書は福岡県嘉麻市でうどん屋を営む青木宣人さんの語りを宮原勝彦さんがまとめたもの。しかし、うどん屋の経営書ではない。平たくいえば、地域おこしコンサルタントが生業としてうどん屋を営んでいるのだ。宮原勝彦さんが、週に一度、青木さんのうどん店を訪ねては、生い立ちから遠賀川のサケ放流までを楽しくまとめてくれた。
聞き書きとはいえ、通常、一章、二章と章立てにするのが本の形態。しかし、青木さんは現在進行形の人であり、これから新たに何をやり始めるか分からない。一応、12の項目を立て、280ページ余で構成している。青木さん同様、枠にはまらない、枠にとらわれない一書とでも言った方がよい。
まず、最初の「これからを生きる人たちへ」が、今を生きる私たちに「人とは何か」を示してくれる。少子化が問題とされる昨今だが、毎年3万人近い人の自殺は問題だ。少子化対策の前にうつべき策は自殺防止。イジメ、虐待もしかり。更には、生きるための農産物の自給率もだ。安く食料を輸入すれば良いという発想は捨てるべきであり、食糧輸出国の食物を略奪していることを知るべきだ。
次に、日本の地方都市が抱える「限界集落」の話に移るが、「地域おこし」の関係者は、自身の足下を見ず、体裁の良さ、見栄えの良いもの、外国人ウケを狙う。しかし、これがいかに自身の首を締めあげる行為であるかを自覚していない。大量生産大量消費ではなく、少量多品種が地方の「売り」であることを認識しなければならない。
ところで、この青木さんは遠賀川(福岡県)でサケの放流をおこなっている。サケは北海道、オホーツク近海の魚と思っている方がほとんど。しかし、九州の北部に位置する遠賀川にもサケは遡上してくる。そのサケを放流することが「地域おこし」になっている。ここでしかできない意外性があるから、他所から人が集まってくるのだ。そして、そのサケの遡上に欠かせない河川の整備、森林保護が、また更に人を集める。いわば、日本人の原点、先祖から受け継いできたDNAの再確認作業が無意識に「地域おこし」になっているのだ。人間も動物である。実に、この動物の本能を青木さんは、くすぐっている。
この青木さんの本能をキャッチする能力は、いったい、どこから・・・と思うが、青春時時代の海外放浪で身に着けたものだった。一所に命を懸ける日本人と異なり、移動する民族の特性を知る事で、青木さんは原始人の本能を自身に蘇らせたといって良い。中途に挟まれる漫才コラムも含め、面白おかしく読み進みながら、要は対面することで共同体を構築することが大事なことなのだと分かって来る。その人と人の繋がりの重厚さは、巻末の交友録が代弁してくれる。
およそ150年前、西洋近代化の道を選択した日本だったが、これからは自然と共生する地域共同体の在り方を西洋に伝える役目が日本にはある。そのモデルとなる人が青木さんである。じわじわ、噛みしめながら、その真髄を読み解いていっていただきたい。
『中国はなぜ軍拡を続けるのか』阿南友亮著、新潮新書
・東洋の安定のためには、皇帝による徳政のほうが良いのでは・・・
新書ながら、5部構成、全15章、330ページ余の本書をようやく読了した。「孫子・呉子の兵法」「韓非子」など、一連の中国古典の現代版を読んでいるかのようだった。大清帝国から中華民国建国に至る闘争、国民党と共産党との内戦、そして、現在の北京、台北との対立まで、何ら中国人の本質は変わっていない。今も、権謀術数を繰り広げる権力者がいることに、今後、この大国との付き合いはどうしたものかと大きなため息をついた。
昭和47年(1972)5月、首相の佐藤栄作は沖縄県の復帰をもって政権にピリオドを打った。続く田中角栄首相は中国(中華人民共和国)を訪問して、国交樹立の道を拓くことで華々しい政権トップとしてのデビューを飾った。その後、パンダ外交など日中の友好関係は続き、日本からのODAによって中国は国家としての基盤を整えた。そして、半世紀を経た今、中国は軍事大国の道をまっしぐらに走り、日本に帰属した尖閣諸島を巡って軍事対立に至っている。果たして、この国交樹立から50年という年月を、メディアも含め、日本の政財界はこの権力闘争の変遷をつぶさに見ていたのだろうか。世界の批判を受けながらも、情報非公開、言論弾圧、チベット・ウイグルの人権侵害、止まらない軍拡を、なぜ、中国は続けなければならなかったのか。
日中関係は冷え込んでいるとメディアは報じる。その一連の原因に対し、日本は誠実に対処してきたが、何ら、解決には至らない。二転三転する中国共産党に、ただ、振り回されてきただけだ。このモヤモヤした原因を本書は見事に解き明かしてくれた。要は、中国共産党内の権力闘争に日本は利用されているだけの事だった。
しからば、関与しなければ済むのだが、すでに日本の財界は中国にどっぷりと投資をして、抜き差しならない関係となっている。おいそれと、手を引くこともできない。この関係は、米中関係によっても大きく日本に影響を及ぼしている。毛沢東、鄧小平という人民解放軍トップを経験した権力者によって、米中の対外政策が波動となって日本に影響していたことに驚きを隠せなかった。軍拡を続ける中国に対しての安心材料は日米の軍事関係ということだが、昨今、国防費の増加が問題とされている。しかし、その日本の軍事費の増大も、もとはといえば、中国共産党の権力闘争にあった。
歴史を振り返ると、孫文の盟友であり革命を支援した末永節(1869~1960)が、大東亜戦争末期、中国の帝政復活を主張していたのも分からないでも無い。頂点に立つ皇帝が徳政を敷くことでしか、この大陸国家は治まらないのかもしれない。現主席の習近平氏の独裁が問題とされるが、意外にも氏に皇帝として君臨してもらった方が日中関係は安定するのかもしれない。かつて、中国共産党の権力闘争によって多くの中国人が生命を落としたが、その再来も避けなければならないからだ。
『絹と十字架』松尾龍之介著、弦書房
・西吉兵衛、こんな南蛮通詞がいたとは・・・
「鎖国」という言葉を生み出したオランダ通詞の志筑忠雄。その存在を知ったのは、著者の『長崎蘭学の巨人 志筑忠雄とその時代』(弦書房、2007)からだった。日常、何の意識もせずに使っている「名詞」「動詞」などの文法用語、物理学用語の「真空」など、それらが志筑の労作であったと知った時の驚き。言葉に深い意味があり、長い歴史が潜んでいることに「目からウロコ」だった。以降、著者の新作が出るのを楽しみにしている。
今回、その楽しみの新刊は、南蛮通詞(通訳)の西吉兵衛である。南蛮と聞くと、東南アジアからやってくるヨーロッパ人という印象がある。すでに、この時点で「南蛮」という言葉の定義が曖昧であることに気づく。本書は、その曖昧なままで理解を進めてきた歴史を確定するための一書。読み進みながら、歴史年表の知識しか持ちえなかった事を恥じ入った次第。
その最たるものが、一五四九年のザビエル来日からポルトガル人追放、更に、ポルトガル特使派遣の百年間だ。徳川幕府の「鎖国」政策によって、ある日を限りに一切、ポルトガル人との接触は無かった・・・と思っていた。ところが、事実は、そうではない。実に、国家の威信と貿易の実利を天秤にかけて、丁々発止のやり取りが徳川幕府とポルトガルとの間に続けられていたのだ。その狭間、為政者の意向で行われるキリシタンや宣教師らへの拷問。その手口も、温泉の熱湯を傷口にかける、糞尿の桶に首を押し付けるなど、とても人間の仕業とは思えない。そんなキリシタンや宣教師が苦痛に喘ぐ中、幕府とポルトガルとの間にあって、仲介の労をとる通詞は、ある意味、現代の外交官にも匹敵する。その代表が本書の主人公西吉兵衛だ。
全四部、二十三章、三百ページにわたる本書の端々に登場する通詞の重要性を見逃してはならない。更には、西吉兵衛が、南蛮医学を学び、継承した功績も高く評価されるべきと考える。
語学の天才とオランダ人が高く評価する志筑忠雄を著者に教えられたが、今回も西吉兵衛という南蛮通詞の存在を教えられた。歴史の襞に隠れた次の人物は誰だろうか。今から、ワクワクしながら、待ち焦がれることにしよう。
『幕末の奇跡』松尾龍之介著、弦書房
幕末、薩摩の大名行列をイギリス人が横切ったことで起きた生麦事件。その報復にイギリス軍艦が鹿児島を砲撃した。城下を焼かれ、五代才助らが捕虜となってしまうが、結果は薩摩の勝利に帰した。
その戦闘を詳細に見ていくと、薩摩は西洋砲術の理論を採用していた。「西洋科学の英知を集めた〈蒸気船〉から幕末を読み解く」と本書の帯にあるように、いわゆる西南雄藩は、西洋の科学技術を吸収し、実戦に用いたことが討幕戦争の勝敗を大きく分けた。
明治の産業革命遺産が世界遺産に登録された。その登録において、多くの方が見落としているのが産業革命にいたる人材の育成についてである。最先端の西洋科学を日本人がどのようにして吸収していったのか。どのように応用したのか。その過程が明らかにされていない。休日ともなれば、世界遺産の史跡は押すな押すなの大盛況ぶりだが、誰が、どのようにして具現化したかの説明はお粗末としか言えない。
まさに、今回の世界遺産登録を待っていたかのように本書は刊行された。幕末から明治にかけ、誰が、どのようにして西洋の技術を習得し、基礎となしたかが述べられる。阿部正弘、小野友五郎、中島三郎助、松本良順、佐野常民、西吉十郎、本木昌造、榎本武揚、田辺太一などが登場する。資源に乏しい日本と言われながらも、探究心旺盛な人材が揃っていたことが、西洋列強に対抗できうる唯一の資源だった。
ペリー来航以来、何かと分が悪い徳川幕府だが、長崎海軍伝習所を開き、オランダ海軍のファビウスを招聘したことは功績としなければならない。なかでも、その海軍の技術を重要視したのが佐賀藩だった。海軍と言えば薩摩藩と思うが、地の利からいえば佐賀藩である。長崎港は福岡藩と佐賀藩が隔年で警備する港だっただけに、外洋を走る南蛮船は平常から見慣れている。福岡脱藩浪士の平野國臣も江戸の人々がペリーの黒船に驚く様に呆れた。
長崎海軍伝習所は永井尚志が総督となり、勝海舟が生徒総監という立場だった。海舟も蘭学を習得していたからこその抜擢だった。ちなみに、海舟が蘭学を習得できたのは福岡藩主黒田長溥が召し抱える蘭学者永井青涯を差し向けてくれたからだった。
進取の精神に満ち溢れた長崎海軍伝習所だが、紆余曲折の末に閉鎖される。この場面は多くの歴史書、小説に描かれるので詳細な解説は無用。しかしながら、本書において注目しなければならないのは、第五章のオランダ通詞、第七章の長崎製鉄所、そして最終章の製糸業ではないだろうか。
西洋の科学を理解するにあたり、まず、直面するのが言語。とりわけ、長崎海軍伝習所の生徒はオランダ語を理解しなければならない。通詞を介しての授業は、教える方も教わる方も、ストレス満載だったことは想像に難くない。
ここでは、西洋科学の用語、とりわけ物理の単語を翻訳したオランダ通詞志筑忠雄の存在を忘れてはならない。鎖国、求心力、真空など、今でも日常的に使用している言葉は志筑の労作である。この志筑によって英語、フランス語、ロシア語などの基礎文法が整えられた。明治のジャーナリストとして名前が挙がる福地源一郎もオランダ通詞であった森山栄之助から英語を習い、頭角を現した一人だった。
鹿児島に攻め入ったイギリスを薩摩が撃退した。その命中弾の背景に、志筑が翻訳した「弾道論」があったとはイギリスも知らなかったのではないか。東京板橋の高島平という地名は西洋砲術の高島秋帆の高島にちなんでつけられた地名だが、その高島平の郷土資料館、図書館での資料に志筑忠雄の名を見ることができる。
長崎にはファビウスによって長崎製鉄所が開かれた。ここでは艦船の修復が可能な事から、多くの日本人が実地に蒸気船の構造を知ることができた。やがて、この習得した蒸気船技術は陸に上がり、製糸業を支える原動力となる。この製糸業の発展が日本の外貨獲得に貢献した。
一読後、明治の産業革命遺産は近代の基礎作りに貢献した人々がいてこそと再確認できる。それでいて、本書では、福澤諭吉、勝海舟に対する、喉に小骨が刺さったような評価も忘れていない。
巻末には海軍伝習生名簿が掲載されている。オランダ人教師団から、各藩別に分かれているが、士官、下士官、水兵教育の実際が見えてくる。これはこれで、一つのノンフィクションを構成しており、関連年表とともに日本の海防史として読み解ける。近代史研究必携の書ではないか。
『踏み絵とガリバー』松尾龍之介著、弦書房
・意外なモノが結びつく不思議
踏み絵とガリバー?
タイトルを見て、疑問に思わない人はいないだろう。あの隠れキリシタンを摘発する「踏み絵」と子供の頃から親しんだガリバー旅行記のガリバーと、何が、関係するのか。
そう思うのも仕方ない。多くの日本人にとって、ガリバー旅行記といえば、小人の国、巨人の国の印象が強いからだ。しかし、意外だったのは、ガリバーは日本を訪問していた。
そして、ガリバーが日本を訪問した時代は「踏み絵」をしなければ入国できない。けれども、ガリバーは「踏み絵」など、断じてやりたくない。そこには、江戸時代、日本との交易を独占するオランダを揶揄するイギリスの意図が隠れていた。この遠大な策略を考えだしたのが、原作者のスィフトだった。
この「踏み絵」の背景について、スィフトの作品を絶賛した文豪夏目漱石も見落としていた。著者は、この複雑怪奇なスィフトの深謀遠慮を簡明な言葉で解説していく。実に、読み聞かせのように構成された全7章を読了した。本書で感心するのは、鎖国時代の日本について、学校で教えられる事々は日本国内が中心。しかし、その江戸時代、欧州ではすさまじい覇権争いから新大陸発見、新大陸の侵略という歴史があったことだ。その事々が、簡明にして、謎解きのように説かれている。
今、日本を取り巻く環境、外交について、その論じられるフィールドは狭い。しかしながら、本来、なぜ、鎖国政策が打ち破られたのか。なぜ、日本市場を欧米が求めてきたのか。その背景が分かれば、現今日本における外交問題の焦点がいかにズレているかがわかるだろう。
外交問題を解決するには歴史を遡らなければならない。しかし、世界史、日本史を含め「面白くない」の一言で日本社会は歴史を軽視する。本書は、「踏み絵」と日本人が慣れ親しんだ「ガリバー旅行記」を組み合わせることで、歴史に興味を抱かせてくれる。
さて、文豪漱石が、本書を読んだら、どんな感想を抱くだろうか。
「行秋や歴史の紐の解け易き」とでも、詠むのだろうか。
『老子・列子』訳者・奥平卓、大村益夫、経営思潮研究会
・東洋思想の基本には、曖昧を抱合できる素地がある
『老子』は老耼(ろうたん)の説を記したものといわれるが、その老耼自身が謎の人物と言われる。同じく『列子』も古代の「寓話の宝庫」と言われながら、これも実在の人物なのか詳しくは分かっていない。それでいて、『老子』にも、『列子』にも、孔子が登場する。あまつさえ、老子は孔子に教えを授けたとまでいわれる。そう考えると、この『老子』『列子』は、中国民衆の間の話を架空の人物を設けて書き記したものではないかとさえ思える。著名な孔子でさえ回答に苦慮した話や、法家や道家の話も混在するところから、儒家では網羅しきれない事々が補足として綴られたものかもしれない。
その『老子』では、自然哲学、原理、本質を重要視している。例えば「雄の本質を把握した上で、雌の立場に身を置け。」や「運命に翻弄されることなく主体性をもってコントロールしろ」と教える。「絶対というものは無い」とも。なかでも、「一国の政治は農夫を手本として行なうべきである」との説には、「天壌無窮」という西郷隆盛も好んだ言葉を思い浮かべる。この「天壌無窮」は、自然の理に従う教育の原則ともいわれるが、徳を内に深く体することを示している。「絶えざる変化は宇宙の本質」「天の意志」「法三章」など、天と人との相互の在り方は、功利主義の西洋文明には想像も及ばないだろう。特に、「兵強ければ滅び、木強ければ折る」はけだし名言と考える。
『列子』は「寓話の宝庫」だが、あの中国共産党を率いた毛沢東も「愚公、山を移す」という話を引き合いにして、帝国主義、封建主義に対抗できるのは共産主義であると主張する。どうにも夢物語のような中国共産党による国造りを、この寓話に重ねたようだ。不可能と思う事でも、その強い意志があれば達成できると、毛沢東らしく民衆を扇動したのだ。
更に、寓話の宝庫としての『列子』には、「ものを知らない孔子」として子供が孔子を揶揄する話がある。「太陽は、朝、近くにいて、昼、遠くにいる」「いや、太陽は朝、遠くにいて、昼、近くにいる」という論争をする子供。通りかかった孔子にどちらが正しいか尋ねるが孔子は回答できず、子供たちから「それで物知りなの、おじさん」と呆れられた。
善か悪。白か黒かを法律で決めたがる西洋。これに対し、曖昧な形で物事を処理する術を知る東洋との文明の差を知る一冊でもあった。為政者は当然にしても、一般人にも分かり易く説いたのが「列子」ではないだろうか。
地政学的に、日本は大陸や半島の国々と関係を遮断できない。それだけに、共通理念として知っておくだけでも有益な『老子』『列子』ではないだろうか。
『CIAスパイ養成官』山田敏弘著、新潮社
・日本の国防には、経済の活性化。技術の向上が不可欠
「CIAスパイ養成官」というタイトルもさることながら、表紙のにこやかにほほ笑む女性、「私はCIAで、ガラスの天井を突き破ったのよ」という帯文字が目に留まる。小説のような印象を受けるが、写真や巻末の「主要参考資料」が、ノンフィクションであると主張する。
CIAとは、「CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY」の頭文字から付けられた略語だ。日本語では中央情報局とでも訳せばよいかもしれない。諜報活動で得た情報をもとに、国家危険に対し謀略を仕掛ける組織だが、そんなおどろおどろしい組織にキヨ・ヤマダこと山田清は属していた。そのCIAでキヨ・ヤマダは諜報員に日本語を教育し、自身の母国である日本に送り込む。日本はスパイ天国といわれるが、エージェント(協力者)を抱え込み、敵国情報を取集する。このエージェントをリクルートする手法も本書に紹介されるが、「困っていることを探る」のが第一の秘訣。じわりじわりと相手を信用させ、最終的にがんじがらめに絡め取る。この方法はKGB(ソ連)においても同じだ。
諜報員にとって最も重要な要素は言語。そこから他国の文化を学ぶことがインテリジェンスへとつながる。CIAでもハード、ディフィカルト、イージーの三段階に区分された言語において、日本語はハード、つまり習得困難な言語とされる。会話はもちろん、読み書きに至るまで日本人同様のレベルに到達しなければならない。それだけではなく、諜報員は敵国の海底ケーブルを切断するほどの特殊技能も要する。
そんなキヨ・ヤマダが何ゆえにCIAの養成官になったのかといえば、結婚によるものだった。恵まれた家庭に育ち、自身もキャリア・アップを目指していたキヨ・ヤマダだったが、駐日米軍将校と知り合い、結婚、渡米。更には、夫の転勤に伴いドイツにも滞在した。性格的に潔癖症ということもあり、ドイツ語についても完璧を目指す。当然、米国での生活に欠かせない英語も同様だった。CIAの日本語教師としては文句なしの存在だった。
スパイ映画でも観賞するかのように読み進んだが、同時に現代アメリカが抱える社会問題、つまりウィーク・ポイントも浮かび上がってくる。日本では当然と思われる戸籍制度がアメリカには無い。更に、人種差別、超格差社会であるということだ。表面的な「自由の国アメリカ」を信用すると、とんだしっぺ返しを食らう。キヨ・ヤマダもそうだった。全7章、200頁からは、「国家の為」という大義名分の下、非合法を容認する組織が存在することに戦慄を覚える。そんな組織を抱える米国からの自立を目指すのであれば、経済の活性化、技術の向上が不可欠。更に、武力にインテリジェンス機関が無ければ、自国を護るための情報も入手できないのだ。
日本のメディアは操作されているという。しかし、独自に情報分析くらいは身に着けておいた方がよい。本書が示唆する事々は実に多い。
『世界を動かした日本の銀』磯田道史、近藤誠一、伊藤謙ほか著、祥伝社新書
・機能不全の国連を活性化するユネスコ
本書は2007年(平成19)6月に世界遺産に登録された石見銀山(島根県大田市)に関する講演録。全5章、200頁で構成されるが、統計表、写真なども多く、講演録だけに読みやすい。
まず、第1章は磯田道史氏の「世界を動かした日本の銀」だが、大永6年(1526)に博多の商人・神屋寿禎によって開発が始まり、その後、灰吹き法という精錬技術によって飛躍的に銀の生産が高まった事実を歴史的に解説していく。なかでも、産出量、各国におけるGDPや貨幣価値、人口比などを使って、銀が世界経済にとってどれほど有益であったかを表している。
第2章は近藤誠一氏の「世界遺産登録の舞台裏」だが、これはユネスコ大使であった近藤氏が、石見銀山が世界遺産に登録されるまでの秘話を紹介している。特に、69ページに、なぜ、ユネスコが国連の機関として誕生したかを述べている件は必読だ。世界平和の機関としての国連が機能不全に陥っているのは昨今のウクライナ情勢で明白だが、それが、昨日今日の問題ではない。その解決策として誕生したのがユネスコだった。持続可能、環境に配慮した石見銀山だったから、世界遺産に登録されたという意味は大きい。経済効果のための世界遺産ではない事を理解しておく必要がある。
第3章は仲野義文氏の「石見銀山の歴史的価値」だが、これは第1章の磯田氏の解説を補足する形になっている。石見銀山は温泉津町(ゆのつまち)にあるが、温泉という文字から火山の存在が銀鉱山を生み出したことが見えてくる。更に温泉津というように津は港を表現する。江戸時代以前の交易は船によるものだが、港があったことで銀の搬出が可能だった。更に、灰吹き法という精錬技術が時代によって変化すること、付属の建物群が残っていることで往時の繁栄を証明できたのは貴重だ。
第4章は石橋隆氏の「江戸時代の鉱石標本の発見」だが、鉱石標本が残っていることには驚きだった。いつ、どこで採取され、銀の含有量などを肉眼で判断できたという事実に驚くしかない。鉱物の肉眼鑑定の第一人者である石橋氏も、鉱石標本を目にして興奮したことだろう。
第5章は講演会のコーディネート役を担った伊藤謙氏、福本理恵氏を交えての対談。この対談からは昨今の限界集落、人口減少問題など、現代日本が解決しなければならない問題を討議しており、「町づくり」の観点からも有益な情報が得られるものと考える。とりわけ、次世代にどのようにバトンタッチするかという事からも、考えることは多々だ。世界遺産登録にまでは至らないが、歴史遺産を観光資源として開発し、観光客を誘致したいと考える自治体の参考になる一書ではないか。石見銀山も世界遺産に登録された直後は爆発的に観光客が訪れたが、その後の減少から考える事々は多い。
『天誅組の変』舟久保藍著、中公新書
本書は武力による倒幕維新の魁として注目される「天誅組の変」についての研究書だ。前章、終章を加え全6章、210頁余で構成されている。本書の狙いは文久2年(1862)の「伏見挙兵」、翌年の「天誅組の変」、「生野の変」が一連の事件として繋がっていることを証明するものだ。その中心人物として平野國臣を置いている。
この平野國臣が活躍した時代の福岡藩主は黒田斉溥(長溥)だが、薩摩島津家からの養嗣子だ。父は蘭癖大名として名高い島津重豪であり、名君の誉高い島津斉彬とは2歳違い。江戸の薩摩藩邸では斉溥・斉彬は兄弟のようにして育てられた。この島津斉彬が藩主就任前に起きた事件がいわゆる「お由羅騒動」だが、この時、4人の薩摩藩士が福岡藩に亡命してきた。黒田斉溥としても、斉彬派の者であるならばと庇護下に置いた。その亡命者の一人が北条右門(木村仲之丞)であり、平野國臣に時勢を説いた人だった。入国が難しい薩摩に、平野が入国できたのも、この平田篤胤派の北条右門の存在があったからだが、この北条右門の妻女は福岡藩の吉永源八郎の養女である。更に、亡命者の一人である葛城彦一は海を介して馬関(下関)の白石正一郎ともつながっていた。
こういった縦横の人間関係に加え、久留米・水天宮の真木和泉守と平野とが結びついていれば、伏見(寺田屋)挙兵、天誅組の変、生野の変が連鎖反応を起こすのは自然の理である。ただ、ここで、なぜ、天誅組の変に真木和泉守の門下生が参画しているかだが、これは、後醍醐天皇を祖とする南朝の残滓が強く関係している。真木が南朝の忠臣・楠木正成を崇拝していたのは有名な話だが、天誅組の変が起きた奈良の吉野も南朝の故地だ。懐良親王の墓所、良成親王の陵墓がある福岡県八女市と吉野町は姉妹都市の関係だ。吉野町の地形と八女市の地形が酷似していることに驚きを覚えるが、年初、良成親王は吉野の方角に向けて遥拝していたという。
そういった事情のもとに本書を読み進んでいったが、いかに「天誅組の変」における挙兵に大きな意味が含まれていたが理解できた。加えて、先人たちの苦難の足跡にも、哀惜の情を覚えずにはいられなかった。波状的に挙兵が起きたことで、徳川幕府の屋台骨を揺るがすことができ、最終的には維新に至ったことを思えば、「伏見挙兵」「天誅組の変」「生野の変」を繋げるという展開は当然、あってしかるべきものだ。
終章210頁に平野國臣が宮内庁に献納したという『回天管見策』だが、平成26年(2014)に平野の遺族関係者から、「献納させられた」との報告がなされている。平野の弟である平山能忍は政府の官吏であったことから、献納という形式を選択せざる得なかったのだろう。「思想は為政者によって焚書される」というが、なんとも胸の痛む話だ。
最後に、伏見挙兵に関わった真木和泉守だけに、本書は「天狗党の変」「禁門の変」にまで繋げて解説して欲しかった。
『長崎蘭学の巨人』松尾龍之介著、弦書房
・日本の近代化に貢献したオランダ通詞
いまや日常生活に浸透している外来語だが、「お転婆」という言葉はオランダ語の「御しがたし」という意味のオンテンバーから来ている。その他、ピストル、ポンプ、ランドセル、メス、カバン、ブリキ、ガラスなど、これらは全てオランダ語由来の単語だ。日本人は外来のモノマネ上手と言われるが、このことは反面、国粋主義者ではないともいえるのではないか。
本書は今もオランダで「語学の天才」と賞賛されるオランダ通詞・志筑忠雄(しづきただお)の生涯と功績に焦点を合わせたものだ。日本を取り巻く環境の変化を雲中飛行船という西洋科学の発展と併走させるというダイナミックな展開が読み手を飽きさせない。日本における蘭学の発展について上方(大坂)では緒方洪庵、江戸では杉田玄白、前野良沢等の名前が出てくる。しかしながら、蘭学の本場である長崎といえばジーボルトの医学校ともいうべき「鳴滝塾」しか思い浮かばない。これはジーボルトが国禁の品々を国外に持ち出そうとしたことでオランダ通詞たちが責を問われ、大量に処分されたことが背景にあるからだろう。
しかし、明治の勃興期、文明開化を急ぐ多くの人々がオランダ通詞の流れを汲む志筑忠雄の恩恵に浴したことは知られていない。その志筑の名前は『日蘭交流400年の歴史と展望』(日蘭学会)に功績を称える一文が寄稿されている。皮肉なことにそれはオランダ人のヘンク・デ・フロート氏が絶賛している。志筑忠雄は「代名詞」「動詞」などの文法用語、天文、物理、地理に関する言葉を日本語に翻訳した。更に、オランダ語の文法書を編纂したことで、派生的に英語、フランス語、ロシア語などの文法書ができたことを多くの日本人は知るべきだろう。今もって、志筑がオランダ語から翻訳した言葉は日本で生きている。「真空」「重力」「求心力」などだが、極めつけは「鎖国」だ。
オランダ通詞志筑忠雄の功績を現代人に分かり易く解説した本書だが、それだけに近現代史の研究者にとって必読の書だ。
『新・「NO」と言える日本』金文学著、高木書房
・パンダのシャンシャンも人を襲撃する熊であると知るべき
令和5年(2023)2月、上野動物園の人気者パンダのシャンシャン(香香)が中国に送還された。シャンシャンは令和元年(2017)6月に上野動物園で誕生し、その独特の愛敬ぶりに熱狂的ファンが続出。シャンシャンを見送る様子はニュースにもなった。実に、平和でのどかな日本の風景だ。印象、気分、空気で物事の善悪を判断する日本人の気質からすれば、中国の印象はシャンシャンに重なっているのではないか。そうであれば、パンダは最高の外交道具だ。本書を読了して、ふと、思い浮かべたのは、このシャンシャンを外交利用する中国共産党の恐ろしさだった。
本書の著者は、日本に帰化した韓国系中国人だ。中国といっても55の民族部族から構成されるだけに、中華民族だの中国人だのと一括りにすると間違いを犯す。著者の出自を念頭に全6章、250頁余に展開される主張は現実味を覚える。更には、中国というよりも、一握りの中国共産党が55の民族部族を支配下に置いていることが見えてくるだろう。
著者が警告するのは、西日本を「東海自治区」、東日本を「日本自治区」として中国に組み込もうと中国共産党が画策していることだ。日本はアメリカの植民地支配にあるとしてアメリカを糾弾する一派がある。しかし、中国共産党も着々と日本支配を計画していることを知るべきだ。「戦争するより、植民地支配下にあった方が良いよね」と嘯く左派系の地方議会の議員がいたが、現実のチベット、ウイグル、モンゴル自治区の惨状を知らないのだろうか。強制収容所に送られての強制労働、臓器売買、洗脳教育。限り無い人権無視の環境に日本は取り込まれる危険があるというのにだ。
「クール・ジャパン」と称し、外国人による日本の歴史、伝統、文化の素晴らしさを取り上げるが、実態はどうなのか。体良く商業施設や水源地を含む土地の買い漁りが横行している。更には、定住外国人に対する手厚い医療保障、社会保障の陰で納税者である日本人が貧困に喘いでいる。じわり、じわりと「背乗り」手法で日本の侵略が始まっている。にも拘わらず、親中、媚中議員が横行して朝貢外交に暇がない。「今だけ金だけ自分だけ」の売国奴議員の多い事。それが内閣にまで存在するのだから、呆れてしまう。
本書243頁には「日本を救うための22ヶ条方策」と題しての、平和ボケした日本人への警告が書き連ねてある。パンダのシャンシャンの見送りに熱狂する日本人には、到底理解できない条項ばかりだろう。しかし、これは、現実の話なのだ。
日本の国土でアメリカ軍と中国人民解放軍とが、日本をめぐってウクライナのように熾烈な戦闘を繰り広げることになる。鷲は獲物を攻撃するが、まさかのパンダも人を襲撃する。本来は熊なのだから当然と言えば当然。ゆめゆめ、見かけに騙されてはならない。本書を読んで認識を改めていただきたい。
『ステルス・ドラゴンの正体』宮崎正弘著、ワニブックス
・足下の台湾有事に対処するには
ここのところ、台湾有事を危惧する論調が増えた。中国共産党による尖閣諸島海域での常態化した領海侵犯。ロシアのウクライナ侵攻が追い打ちをかけたからだ。従前、日本国憲法は平和憲法だから、九条を守れば平和は維持できると主張していた方々も、ウクライナの現実に声を失った。ウクライナ紛争と台湾有事とが、いかにして結びついているのか、明確な答えを導きだすことのできる論者は少ない。その中国共産党による侵略の方程式を解き明かしたのが本書になる。中国共産党をドラゴン(龍)に喩え、密かな侵略行為をステルスと示した。プロローグ、エピローグに7章を加えた250ページ余はどの章から読んでも良い。しかし、第7章の「悪人と矛盾だらけの国際情勢」は必読の章だ。
数年前、韓国発祥のLINEのデータが中国に流出していることがメディアで報じられた。その後、改善策を施したとして沈静化したようだが、すでに地方自治体だけではなく、日本社会において浸透してしまったが為に、容易には廃止できないのが実情。これこそ、ステルス・ドラゴンの思うつぼだ。このLINE同様、仮想通貨も日本人の射幸心を煽り、バブル経済の再来かと思えるほど賑やかだった。しかし、プリペイド・カードと異なる仮想空間の通貨は、どこに消えたのか・・・。
第4章、第5章を読み進みながら想起したのは、中国共産党の「遠交近攻」という戦略だ。これは孫子や呉子の兵法に従ったものだが、意外にも中国共産党は古典的な兵法を遵守している。中国共産党が中華人民共和国を建国して早々、アフリカ、アジアの国々に医療支援を施していた。大陸から遠く離れた国々に医療という親切を続けていたのである。その結果、世界中がコロナの感染源は中国であるとバッシングを続けても、WHOは中国共産党擁護に徹した。なぜ、中国共産党を叩くのかが理解できないという表情のWHOだった。まさに、孫子、呉子の成功例を見るかのようだった。今からでも遅くはない。孫子は読んでおいた方が良い。「敵を知り、己を知らば、百戦危うからず」だからだ。
そう考えると、第6章「『認知戦争』ではすでに負けている」の示唆する意味が十分に腑に落ちることだろう。「自虐史観」という言葉があるが、巧妙に仕掛けられた中国共産党の罠であることに気付く。短時間で効果が得られる「即戦力」という言葉に日本の経営者は弱い。十年、二十年、時には百年単位で攻めて来る中国共産党からすれば、日本の政財界に学界は、赤子の手をひねるに等しい。
最後に、第4章でのドイツ軍のレオポルト2A6戦車がウクライナ軍に提供される背景は在庫処理と著者は述べる。同時に、国連における敵国条項に記載される日本とドイツだが、戦費提供に集中する日本が、武器の現物支給を求められたらばという点も付け加えて欲しかった。それこそ「絵にかいた餅」の平和憲法と判明したからには、現実にどう対処するかが必須だからだ。
『なぜこれを知らないと日本の未来が見抜けないか』江崎道朗著、KADOKAWA
・国防には情報機関の構築が必須
まず、本書の副題にある「政治と経済をつなげて読み解くDIMEの力」に記されるDIMEとは何ぞや?と疑問を抱く。Diplomacy(外交)、Intelligence(情報)、Military(軍事)、Economy(経済)の頭文字を合わせたものがDIMEだが、この4つをキーワードに読み解いたのが本書になる。第1章から8章、終章まで250ページ余で構成されている。
本書を読み進みながら思い起こされたのは、旧福岡藩出身の金子堅太郎だった。金子は明治4年(1871)の岩倉使節団とともに渡米し、黒田家の奨学金を得てハーバード大学を卒業した。帰国後は伊藤博文の側近として帝国憲法の草案に参画し、自身も農商務大臣、司法大臣を務めた。金子は留学中、アメリカで濃密な人間関係を構築した。結果、明治37年(1904)に勃発した日露戦争において渡米。ハーバード大学同窓生のルーズベルト大統領に日本支持を要請した。ロシアとの講和条約締結においても親交が深かった全権の小村寿太郎を側面からサポート。これはまさに、著者が現今日本において必須と訴える内容と合致する。「歴史に学べ」とは、こういう事実確認ではないかと考えた。
現在日本での防衛において、喫緊の問題は台湾有事において、いかに対処するか。果たして日本は台湾に軍事侵攻する中国共産党の事を熟知しているだろうか。中華人民共和国の建国以後、中国共産党がどのような外交政策を進めていたか・・・。「遠交近攻」という孫呉の兵法に従ってのセオリーを中国共産党は行っている。これに対し、日本はいかなる方策を示したか、はなはだ、怪しい。
現在の岸田政権における反撃能力の有無は民主党政権時代の岡田外務大臣の核の持ち込み容認を追認していることは、与野党を含め、再認識しておかねばならない。更には、かつての大東亜戦争(太平洋戦争)では兵站思想が欠けていたといわれるが、弾薬などの資材を供給できる防衛産業自体も育成されているとは言い切れない。むしろ、不安要因の方が大きい。このことは、かつての満鉄(南満洲鉄道)調査部が重視していた産業基盤、統計分析が十二分に機能しなければならないという指摘と合致する。戦前は、全て悪という先入観を捨て、冷静に情勢分析が可能な精神構造を日本人は求められているのだ。そのための政府による規制緩和、学術分野の閉鎖性、民間企業の視野狭窄にまで著者は問題意識を広げている。
岸田政権において経済安全保障担当大臣というポストが設けられたが、この背景には、経済が強くなければ国防は成り立たないという著者の強い信念が潜んでいる。更には、抑止力には正面での武器使用だけでなく、総合的な情報管理がある。未然にリスクを回避する手段だが、この前例が冒頭で示した金子堅太郎である。本書を読み進みながら、考えることは多く、敗戦後の日本からは大きく環境が変貌していることを日本人に知らしめる書である。
『なぜこれを知らないと日本の未来が見抜けないか』江崎道朗著、KADOKAWA
『亀井昭陽と亀井塾』河村敬一著、花乱社 令和5年5月8日
・立場を弁えた人のありがたさ。
福岡市中央区地行の浄満寺門前には、「亀井南冥 昭陽両先生墓所」と刻まれた大きな石柱が立っている。福岡市中心部を東西に走る幹線道路の明治通りに寺は面している。それだけに、多くの方に認知されて良いはずだが、さほど市民の関心を集めているとは言えない。「あの国宝金印の解説をした亀井南冥」と付け加えると、合点がいくようだ。しかし、昭陽となると郷土史に踏み込んだ方でなければご存じで無いのが悲しい。本書は、その亀井昭陽を中心に、亀井塾の生成について述べられている。しかしながら、その前に、亀井昭陽(一七七三~一八三六)という人は亀井南冥(一七四三~一八一四)の嫡子であることを述べておきたい。
まず、四部構成140ページ弱の本書は手に取りやすい。しかしながら、その内容と言えば、荻生徂徠の古文辞学なることを知らなければ読み解けない。だいたい、「こぶんじがく」と読むのか、「こもんじがく」と読むのかすら判じがたい評者にとって、亀井昭陽の存在は遠い。ところが、二部の「昭陽の人柄と学問」以降は、亀井南冥を祖とする亀井の学問の基本的な物事の考え、教育方針が浮かび上がる。豊後日田・咸宜園の廣瀬淡窓による人物、学業の紹介は、とてもありがたかった。それはそのまま、本書の最終に登場する「男装の女医」として著名な高場乱の生き様を彷彿させるものだからだ。人には夫々、個性があり、その個性に応じて社会を形成する集合体の一人であるべきとの考えが、「なるほど!」と腑に落ちる。更に、「下々の苦しみを自らの苦しみとして世話する心」は、自由民権運動団体・玄洋社の思想にも重なってくる。やはり、玄洋社のルーツは亀井塾にあるのだと確信できる。高場乱が昭陽の嗣子である亀井暘洲を介して、亀井塾の考えを継承していたのだった。そう考えると、昭陽が不遇の日々を耐え忍び、亀井の学問を次につないだ功績は大きい。
第四部に「亀井塾に連なる人々」として亀井の門人である七名が紹介されている。先述の高場乱もその一人だが、この七名の他、評者の希望としては阪牧周太朗(高場乱の従兄弟)、権藤延陵(廣瀬淡窓の執刀医)、白水常人(福澤諭吉の師)も加えて欲しかった。しかし、本書にも述べられているように、亀門こと亀井塾の門人帳が完備されているわけではない。門人たちの活躍とその系譜を次作に期待したい。
『作戦術思考』小川清史著、ワニブックス 令和5年5月6日
・理想のチームを作るために
戦略、戦術という言葉は、今や企業のマーケティング手法に当然のように登場する。しかし、「作戦術」とは何なのか、ましてや「作戦術思考」とは何だろうと思い、本書を手にした。著者が陸上自衛隊元陸将だけに、軍事における新しい作戦のノウハウ書なのかと見たのは甘かった。第一章のページには老舗アパレルメーカーでの研修体験が述べられているからだ。おやっと、思いながらも読み進むと、日本企業にありがちな社風に疑問を抱く話に、共感を抱く。本書は市場を制圧するための「全体最適」を判断しなければならないチーム・リーダー必読のビジネス書だ。JAL、ゆうちょ銀行を事例にしての話には、「なるほど、なるほど」と腑に落ちる箇所が幾つもあった。
第二章では陸自陸将としての経験から、「作戦術」が要点を押さえながらも簡明に述べられる。アルビン・トフラーの「第三の波」を参考にしながら、波とは状況変化、環境変化をいち早く理解し、いかに適用させるかを説いている。要は、マーケットの変化をつかみ、それに組織が対応して市場を制圧するが、インテリジェンスが機能しなければ有効に機能しない。現今日本は、インテリジェンスに機敏だろうかと懸念する。
第三章はリーダー・シップ論だが、東日本大震災での安倍元首相の対応、判断が的確であったことは評価しなければならない。しかし、企業も軍隊も「勝つ」という目的での組織運用が著者の実体験を基に語られる。その集約が第三章146ページだ。更に、第四章において「作戦術」の応用編ともいうべき思考法についての解説では162ページの「問題のルーツは明治維新にまでさかのぼる?」は日本社会の硬直した組織の原因分析だけに「なるほど!」と腑に落ちたのだった。同時に、本質を見抜く力の必要性を説いているが、これは日本人の学校教育の弊害を気付かされる。
情報化社会における生き残りの方法が「作戦術」であるとの著者の視点は参考になる。とりわけ、第五章の事例集は企業の管理職者は必読ではなかろうか。全五章、238ページはスラスラ読めるが、頭の中では新たな刺激を得てクルクルと考えが回っていた。『陸・海・空 究極のブリーフィング』小川清史、伊藤俊幸、小野田治、桜林美佐、倉山満、江崎道朗 共著において、著者は「作戦術思考」の片鱗を語っていたが、本書はビジネス・バージョンに落とし込んだところが秀逸だった。
『指名手配議員』鈴木信行著、集広舎 令和4年11月13日
・「ならぬものは、なりませぬ」と行動する人。
第1部から7部まで、全230ページ余の本書は、著者の半生の記でありながら、戦後の「右翼」と呼ばれる人々の活動の歴史、運動の変遷、社会の変動を知ることができる。
「右翼」といえば、世間一般、黒い街宣車に日章旗、旭日旗を翻し、大音響で軍歌を流す集団という印象を抱く。しかし、その「右翼」も「左翼」の暴力から身を守るため、街宣車は大型で装甲車のようになった。火炎瓶を投げ、ゲバ棒、投石で攻撃してくる「左翼」に対峙するための防御の手段から生まれたものだと、本書で知った。更に、「右翼」と言いながら、その運動の実態は在日がやっているという誤解も、東西冷戦構造の崩壊から生まれた事実と知る。『指名手配議員』という題名に、本書を手にするのを躊躇したが、やはり、何事も歴史や事情があるのだと分かり、無駄ではなかった。
著者の鈴木信行氏とは面識がある。互いに、踏み込んだ話をするわけではない。先輩諸氏の話を傾聴する勉強会で一緒になったのが始まりだった。口ぶりは穏やかで、「残したら作ってくれた方にすまない」と言って、余ったサンドイッチをパクパク口に運んでいる姿を記憶に留めている。大隈重信外相に爆裂弾を投じて後に自決した玄洋社の来島恒喜烈士の法要、墓参で幾度か一緒になり、思想の方向性を同じくする人、という程度の認識だった。
しかし、驚いたのは、その後の著者の行動だった。韓国ソウルの日本大使館前に据えられた「慰安婦像」に「竹島は日本の領土」と記した杭を括りつけたのだ。ニュースのテロップに、「鈴木信行」との名前が流れた時には、同姓同名の別人の仕業と思った。が、しかし、私の知る鈴木信行だった。とても、そんな、行動をするとは思えないほど、温厚な人という印象があるだけに、驚きは倍化した。それ故に、表面的な鈴木信行しか知らなかった私にとって、著者の思想遍歴、経歴を知る上で、実に貴重な一書となった。
世間一般は、著者の行動、言動に「差別主義者」「ヘイトスピーチの人」とレッテル貼りをする。しかし、差別をするわけでも、ヘイトスピーチをする訳でもない。法治国家として、人として、法の下で、公平に「ならぬものは、なりませぬ」と主張、行動するだけだ。むしろ、「人権派」と自認しながら差別発言、行動に気づいていない輩に嫌悪感を抱く。
著者は現代版「玄洋社」を目指し、日本国民党を立ち上げた。福岡発祥の玄洋社という自由民権運動団体は、社員がそれぞれ、役割分担を認識していた。活動資金を準備する者、行動する者、言論機関として新聞社を切り盛りする者。そして、国政や地方議会に出馬する仲間を支援する者の集団である。そう考えると、「机上の空論」を嫌って炭鉱経営に身を投じた初代玄洋社社長の平岡浩太郎のような人物が著者の周辺に出現して欲しいと願う。
ちなみに、著者は松田聖子の熱狂的なファンだ。次回、会った時には、この話題から切り込んで、政治の核心に迫ってみたいと思う。
『ちいさきものの近代 Ⅰ』渡辺京二著、弦書房 令和4年11月4日
・ちいさきもの、とは敗者のことか。
「一身二生」とは、幕末から明治を生きた福澤諭吉の言葉だ。一度きりの人生でありながら、二度も人生を経験したという意味になる。この二度の人生とは明治維新を指すが、幕末、海外を見聞した福澤でさえ、驚きの大変革の時代だった。福澤が「親の仇」とまで言い切った封建的身分制度だったが、明治になればなったで官僚制度という新しい身分制度が誕生した。その新しい時代を迎えたのは旧武士階級だけではない。果たして、庶民はこの明治維新という大変革をどのように迎えたのか。近代に取りこぼされた人々を「ちいさきもの」として、「熊本日日新聞」に連載されたものを全九章に渡って述べている。その中で、第六章「幕臣たち」、第七章に「敗者たち」という章がある。いわゆる旧徳川幕府を支援した佐幕派の人々だが、明治新政府の時代においては冷や飯食いの人々である。
本書は、全体として、「敗者」の側にある人々が描かれている。特に、会津藩に対する異常ともいうべき扱いは、現代においても深い溝を遺したままだ。その溝の特異な例として薩摩の大山巌に嫁いだ山川捨松がいる。例外的な溝の代表としては勝海舟がいる。冷静に時代の趨勢を見ると、勝海舟にも言い分があり、優劣はつけがたい。第一、勝海舟自身も、根っからの武士の家柄ではない。武士の株を買っただけの家であり、徳川家に恩顧があるわけでもない。それこそ、「封建制度は親の仇」と言い切った福澤が、武士の論理で勝海舟を批判するのも、矛盾に満ちている。「一身二生」とは、矛盾という意味合いもある。
会津に代表されるように、東北諸藩が九州人を忌避し、卑下する喩えとして、著者は村上一郎と接した場面を出している。「僕は九州人は一切信用しません」と言われて著者は面喰った。(206ページ)しかし、その村上一郎の海軍時代の戦友である小島直記は根っからの九州人(福岡県)である。村上が三島由紀夫の後を追って自決する前、今生の暇乞いに出向いたのも小島の家であり、互いの墓所も小平霊園である。村上に師事した詩評家の岡田哲也氏は、九州は九州でも鹿児島の出身である。それを考えれば、著者の村上との遭遇を東北と九州との対立構造の引き合いに出すのは無理がある。
いずれにしても、過去に刊行された幕末維新の書物を読み返しているかの如く、繰り言を聞いているかのようだった。ゆえに、今一つの物足りなさを感じる。「一身二生」が内包する矛盾の解消が近代ということか。まずは、本書を土台に、次作から深い洞察が加わるということなのだろう。
木村武雄の日中国交正常化 王道アジア主義者石原莞爾の魂』坪内隆彦著、望楠書房 令和4年10月17日
・なぜ、日本は中国と戦ったのか・・・。そして、なぜ、国交を樹立したのか・・・。
本年は、日本と中国(中華人民共和国)との国交樹立から半世紀となる。熱烈な「中国ブーム」に「パンダ外交」に沸き立った時代を見聞した身からすれば、なんとも冷静な日本の様子を見て、本書の木村武雄、石原莞爾はどのような意見を発するだろうか。
本書は、『アジア英雄伝』の著者による日中国交樹立秘話とでもいうべき一書。日中国交樹立時の田中角栄政権の建設大臣木村武雄が黒子となって国交樹立に奔走し、その足跡を記したもの。全5章、200ページ余ながら、従来、「日中国交回復」「日中国交正常化」というマスコミの決まり文句で語られる日中間の国交についての経緯が窺えて、興味深い。本来、日中の国交樹立においては少なくとも明治時代にまで遡らねばならないが、学校教育の現場では近現代史を教えるまえに教科は終了してしまう。その点を踏まえても、本書の果たす役割は重要だ。
更に、木村武雄が師として崇拝する石原莞爾についても、東條英機と対立した陸軍軍人として見る向きが強い。戦争論を著したことから、内容を熟読することなく、世界戦争を鼓舞する軍人とみる向きが多い。故に、童話作家として著名な宮沢賢治と同じ在家宗教団体である国柱会の熱心な会員と紹介しても、にわかに信じられないと口にする人が多い。
しかし、最も大きな問題は、あの大東亜戦争(アジア・太平洋戦争)敗北後の日本社会が、いまだGHQ(連合国軍総司令部)の洗脳工作から覚醒しないことにある。二度と、欧米諸国に反抗できないように、巧妙に仕組まれた戦後であったことに気付いていない。いわゆる「自虐史観」に日本人は汚染され、公平に人間の犯す罪を検証できないようにしたことだ。
ところで、評者は本書の題名にも使用されている「正常化」という言葉に疑念を抱く。「正常化」ということは、それ以前は「異常」であったということだ。では、何が異常であったのか、何をもって正常化というのか、マスコミは明確に示すことはできない。そして、悲しいことに、多くの日本人は「正常化」という言葉に疑問の欠片すら抱かない。自身の頭で考えることすら日本人はGHQに奪われてしまったのだろうか。
蛇足ながら、本書を読み進みつつ、一人の人物が思い浮かべた。それは清水芳太郎という新聞人だ。一時、中野正剛が社長を務めた玄洋社系の新聞「九州日報」の主筆である。この清水は飛行機事故で落命してしまうが、存命であれば東條英機、石原莞爾の間を取り持ち、中野正剛の自決も防げたのではと噂された。果たして、清水は木村と同じく、日中の国交を進めたのか、はたまた、別の方法を考えたのか。
満洲の情報基地ハルビン学院』芳地隆之著、新潮社 令和4年10月5日
・ハルビン学院を軸に述べる日本の近代史
本書は、かつて満洲の地にあったハルビン学院の末期、いわゆる日本の敗戦に焦点を合わせて述べた内容。序章、終章を含め、全9章、250ページ余によって構成されている。日本の敗戦により、満洲にあった多くの貴重な資料は焼却、焚書、置き去りとなっただけに、わずかな記録とはいえ、貴重だ。
ハルビン学院といえば、初代満鉄総裁を務めた後藤新平を想起する。日清、日露の戦争を経験した日本が、国内で膨張し続ける人口の解消先に選んだのが満洲である。ハワイ、アメリカ西海岸へと移民は続くが、日系移民の排斥運動を回避させるにも満洲は最適の地だった。しかし、境界を接する中国とソ連とは友好的な外交関係を構築しなければならない。中国には上海に東亜同文書院という学校が設けられていた。ソ連には満洲のハルビンに学院を設置することで後藤新平が言うところの「文装的武備論」を実現したのだった。海外に移民した日本人の多くは、異国の地で奴隷に近い扱いを受けても、勤勉さから信頼を得、財産を築き、子弟には優先的に学校教育を受けさせた。更には、その土地に定着し、社会的地位すら築く人も出現した。
しかし、日本は大東亜戦争(アジア・太平洋戦争)に敗北。知識と技術力を有する日本人を中国共産党、ソ連に利用されると脅威になる。中国国民党と米国は、在満日本人の早期帰国を決定した。しかし、ソ連は満洲の開拓日本人を虐殺、婦女子を凌辱、資産を略奪。更には関東軍の将兵は捕虜としてシベリアに送り強制労働を強いた。ついには、中国国民党までもが在留日本人を自軍の戦力に流用する。その狭間、ソ連軍は南樺太、千島列島に攻めこみ、いまだ、北方領土を返還することなく居座っている。幕末、アメリカのペリー艦隊来航以後、日本という国は大陸の中国、ロシア、さらに米国という大国の狭間で翻弄されてきたことが見えてくる。
巷間、満洲という地は、日本国内で失敗した人々が再生を求めていくところと言われる。転向左翼は左翼運動よりも経済開発に従事した方が人々のためになるとして渡満する。問題を起こし出世の道を閉ざされた陸軍軍人も満洲で生きる道を模索する。一旗揚げたい浪人は大陸浪人と称して満洲、シベリア奥地、中央アジアにまで赴く。そんな猥雑とした異郷の満洲で生き残る人々にとって諜報活動に長けてくるのは致し方ない。そこにロシア語に堪能なハルビン学院卒業生であれば、方々で重宝される。安定した地位にあるハルビン学院卒業生を見て、続々と入学志望者が集まるのも無理はない。
『大アジア』松岡正剛著、KADOKAWA 令和4年10月2日
・アジアに立脚して歴史を俯瞰すると、なぜ、西洋の貧困さが際立つのか
本書は「大アジア」をテーマに、第一章「中華帝国とユーラシア」、第二章「近代アジア主義」、第三章「大東亜・日本・アジア」、第四章「リオリエント」として、全23冊の書籍の解説とともに、アジアを考える内容となっている。
現在の中国(中華人民共和国)が大国としての版図を確立したのは、秦の始皇帝による統一にある。わずか15年にして世界帝国を成したことをモデルに、現在の中国は統一を急ぐ。さらに、王朝の変遷はあるものの、唐の大帝国が誕生し、ここで百家争鳴の思想家たちの中から儒学を国教に据えたことから安定が始まる。儒教(儒学)以外の道教、法家などの教えは異端の扱いを受けた。儒教の孔子の「仁愛」は尊重されるが、墨子の「兼愛」は異端視される。しかしながら、ロシアのトルストイは墨子の「兼愛」が弾圧されたことで、キリストの優しい言葉で語る「愛」の思想が西洋に蔓延したと説く。この儒教は日本でも尊重され、結果、近代においてキリスト教や社会主義、マルクス経済が斬新な思想として広まる事にもなった。
従来、欧州を中心とした歴史が語られたが、アジアに特化して歴史を俯瞰すると、欧州の思想の空洞化が目につく。欧州人は仏教を知らず、あのチンギス・ハーンは欧州に魅力を感じなかった。しかし、15世紀になって、欧州は軍事力でアジアを制圧していった。文化の「徳」による王道ではなく、武力での覇道である。この一つの時代の流れからも、欧州の底の浅さが計り知れる。これは、市場原理に変わる価値観を有しない欧州と見ても良い。市場原理についても、『管子』に説いてあるのだが・・・。
「大アジア」といえば、福岡発祥の自由民権運動団体である玄洋社が孫文の辛亥革命を支援したことは外せない。欧米の覇道に苦しむアジア同胞の救援を進めたが、この情実を孫文は利用したという。しかし、日本側はアジアの改革によって日本の改革を進めていたことも事実ではなかろうか。
経済学という言葉は東洋と西洋では意味が異なる。東洋では「経世済民の学」として、質を重視し、循環させることを考える。翻って、西洋では量を重視するに留まる。いずれが好ましいかは、言うまでもない。かつて、宋代の中国は世界経済の中心だったことを考えると、量を優先させる西洋の経済が東洋を貧しくしていったことが理解できる。
現在、日韓トンネル問題が政治問題になっているが、この日韓トンネル構想は昭和15年(1940)9月の東京、北京間の新幹線構想の中に含まれていた。アジア主義者の観点からすれば、政治問題になること自体、時代遅れと言わざるを得ない。そんな事々を気づかせてくれる一書であった。

『墨子』和田武可訳、経営思潮研究会 令和4年9月11日
・トルストイが評価した思想家
孔子、孟子の名前は知っていても、墨子を知る人は少ない。『韓非子』が「禁断の書」などとして、儒者を信奉する人々から嫌われるように、この墨子も儒者から敬遠される。それというのも、孔子の考えを批判したからに他ならない。国を統治する為政者からすれば、先祖や上役を大事に扱う儒者の考えはありがたいが、庶民に至るまで大事にしようという墨子の考えは、革新的で扱いにくい。そこで、儒者の考えを「儒教」とし、国教に据えて民衆に至るまでをも支配下においた。封建的身分制度の日本においても、為政者である武士の教養として儒者の教えを儒学として信奉した。
しかし、明治になって、欧米の宣教師たちが大挙して新興国日本にやってくる。キリスト教という、「神の愛」を説く宣教師の教えは瞬く間に日本社会に浸透した。従来の儒教が説く「仁」ではなく、「愛」という言葉で神の教えを伝えた。旧武士階級にとって、まったく新しい革新的な教えがキリスト教だった。豊臣秀吉、徳川家康の時代、日本を侵略する宗教としてキリスト教は禁教だった。このキリスト教の説く「愛」に類似する教えが墨子の「兼愛」だ。争うな、他国を侵略すると相互に民衆が不幸になる。ひいては、為政者も不幸になるではないかという教えだ。この墨子の「兼愛」を読んだロシアのトルストイは「キリストが世にあらわれ、墨子と同じことを、墨子よりも分かりやすく教え説いた。」と述べた。もし、孔子と同じく墨子の思想が日本に伝わっていたならば、戦国期や開国後の日本にキリスト教が広まらなかったかもしれない。
儒者に対し手厳しい批判を展開した荀子でさえ、墨子を批判する。為政者からすれば、更に理解が進まなかったのが墨子の教えだろう。加地伸行著『儒教とは何か』で、わずかに墨子と孔子の対立が紹介されるだけで、いまだ日本でも『論語』が主流。墨子や韓非子などは、やはり異端の書なのだろう。そう考えると、明治から大正の時代、マルクス経済主義の考えが日本に入ってきた際、為政者が言論弾圧を加え、取締りを厳しくしたのも、分からないでもない。墨子は「兼愛」を説きながら、農業、手工業者による生活の安定を説いていたからだ。科学的な考えを導入すれば、為政者は聖人でなければ務まらない。いわゆる「君側の奸」にとっても、面倒な思想が墨子であり、マルクス経済主義だった。
封建的身分制度から自由民権運動、議会制民主主義を経た現代日本において、墨子の考えは特段の新鮮さは無い。しかし、その墨子の思想の基本となる「三表法」は基本となる教えを述べる。一、歴史に学べ 二、実態に即して 三、実地を想定する である。
墨子の教えは「屁理屈」とも「矛盾を突く」ともいわれる。しかしながら、あの『論語と算盤』を著した渋沢栄一が墨子を解釈したならば、どうだろうか。何ら、矛盾を抱かないのではないだろうか。日本人は、精神のデッサンを儒学によって形作ったといわれるが、開国後にキリスト教を受容したということに儒学の限界があったのではと思えてならない。
『人口から読む日本の歴史』鬼頭宏著、講談社学術文庫 令和4年9月7日
本書を手にしたのは、日本の少子高齢社会の対応策を考えたいと思ったからだ。高齢者に対する年金、医療という社会保障費は増加。反して、それを支える若年層は減少傾向にある。政府はこれを問題としながらも、具体的な方策は行き詰まっている。この少子高齢社会について、本書の終章には「少子高齢化はわれわれにとって初めての経験である。(中略)人口の停滞は成熟社会のもつ一面であることが明らかだからである。」と述べる。目先の対処にあたふたするより、墨子ではないが、まず、「歴史的根拠」を示すことが必須。
本書は、日本の人口変動について具体的事例、数値をもって証明を試みる。序章から終章まで、全9章を読み進むが、まず16ページ、17ページの日本の人口変遷について、縄文早期から平成7年(1995)までを俯瞰する。慶長5年(1600)の人口は1227万人であり、明治6年(1873)の人口は3330万人である。更に、明治6年から150年を経る2025年頃の予想人口は12091万人である。この統計数値から、何が人口増減の背景にあるのかを分析すれば、少子高齢社会を食い止める方策が見えてくるのではないだろうか。
ここで考えたいのは、江戸時代の徳川幕府が招いた江戸一極集中が都市の人口抑制機能を果たしていたということ。幕末、幕府は参勤交代を廃止したが、その結果、地方への移住が進み、人口は倍増していった。さすれば、人口減少を問題とする現代、東京一極集中を是正することが少子化に歯止めをかける事につながるのではないか。都市は「アリ地獄」と著者は指摘する。都市は次から次へと人を食いつくす。それでいて、人口増という生産性は無い。
しかし、これはこれで、地方も対策を考えなければ解決できない問題だ。交通、通信、衛生インフラの整備が必須となる。この首都東京の「アリ地獄」現象は、地方の中核都市も同じ現象を示している。このことから、都市への集中を改善する方策として日本全国に均等な人口配分を考えなければ少子化は防げない。単純に児童手当、託児所の増加だけが対策ではない。
次に高齢者対策だが、介護を必要とする高齢者を集中的に管理できるホームの増設で対処が可能ではないだろうか。介護を必要とする高齢者には、複数の介護者が必要だが、ホームでの管理に移行することで介護者の軽減負担が可能となる。
都市の一極集中解消は災害や感染症での機能不全を防ぐこともできる。大量生産、大量消費社会から自給自足社会への脱皮も考えなければならないだろう。人も動植物と同じ生物と考えれば、人口増減は生物の進化の法則。足りない食物は輸入すればよい。不足する労働力は移民を奨励するでは、ヒトが進化していないことを証明するようなもの。少子高齢化を問題とするのであれば、本書の統計数値を基に具体策を考えなければならない。
『戦国策』守屋洋訳、経営思潮研究会 令和4年8月16日
・強かな隣国との外交に備えるために
『戦国策』とは、紀元前の中国春秋戦国時代の秦、斉、楚、趙、魏、韓、燕という七つの国で起きた外交における謀略の歴史書である。その歴史においては、現代日本においても何気なく使っている諺の起源が載っている。それは「漁夫の利」「隗より始めよ」「かわいい子には旅(苦労)をさせよ」「虎の威を借る狐」などだ。元々、この『戦国策』は劉向(りゅうきょう)という前漢末の人物が書いたものといわれ、歴史家の司馬遷が『史記』執筆の折、参考にした文献といわれる。
このような中国古典を学ぶ意義は、現在の中華人民共和国との外交政策においての原理原則を知る為にある。表の看板は共産主義であっても、その本質は帝国主義に他ならない。その中国と、今後、どのように対応するかの戦略、戦術を知る縁が本書になる。秦が大帝国として中国を統一する以前、七つの国が鎬を削った。その秦の始皇帝を中国国家主席に重ねてみれば、紀元前の中国と現在の中国が何ら変わりのないものに見えるだろう。更に、欧米が言うところの民主主義がいかに陳腐なものであるかも理解できる。
幕末、日本は欧米列強に向け開国した。以後、追いつき追い越せで西洋の文物を吸収し、大東亜戦争(アジア・太平洋戦争)敗北後は完全にアメリカンナイズされた。思想までもが欧米のルールに従っているが、隣国の中国は今も東洋思想を基盤としている。その中国の本質を知り、対応策を見誤らないようにしなければならない。その為の中国古典の学習である。
一例として、「遠交近攻」という言葉の実態を述べたい。これは、遠方の国とは親しく交わり、近隣諸国とは一触即発状態に置く事を指す。中国は一九四九年(昭和二十四)の建国以来、アフリカ諸国に医療支援を続けた。二〇二〇年、世界を席巻した新型コロナだが、その対応においてWHO(世界保健機構)のテドロス事務局長は発生元の中国を糾弾するどころか、中国政府の対策を称賛した。この姿勢に世界はテドロス氏を批判し、不信を抱いた。しかし、当のテドロス氏は世界の反発が自身に集中することに意外な驚きを示した。この裏には長年の「遠交近攻」政策があったのだ。まさに『戦国策』に添って中国が外交を進めていたことが如実にわかる。
ちなみに、『戦国策』の「戦国」とは、「大国」を意味する。大国の中国に対し、どのような策を講じるか・・・。亡国の民となる前に、まず、中国の本質、歴史を知り、情報収集を怠らない事が必須。人の本質は、何ら変わらない。さすれば、中国の本質も何ら変わらない。さすれば、中国古典を研究し、今後の対中政策をと考えなければならない。その為の参考書が本書になる。
蛇足ながら(この言葉も本書に紹介されている)、大正7年(1918)に起きた朝日新聞の「白虹事件」という筆禍事件の「白虹」の意味も本書に紹介されている。
『新聞が伝えた通州事件 1937~1945』藤岡信勝、三浦小太郎、但馬オサム、石原隆夫編、集広舎
・報復の連鎖を止めるために
本書は昭和12年(1937)7月29日、中国の通州で起きた民間人虐殺事件についての一書。民間人虐殺事件といえば多くの方は日本軍による「南京大虐殺」を想起する。しかし、この通州事件は、中国国民党、中国保安隊、中国人学生らによる民間の日本人に対する虐殺事件である。蒋介石は人道に反する犯罪として絞首刑に処されても異論は無い。ところが、日本を占領した連合国軍によって有耶無耶のうちに封印されたままだった。
平成9年(1997)11月、『天皇様が泣いてござった』(しらべかんが著、教育社)という一冊の私家版が刊行される。著者は佐賀県基山町にある因通寺という寺院の住職。昭和24年(1949)5月、九州巡行中の昭和天皇が望んで訪ねた寺だ。ここでのエピソードは既知の方も多いので詳細に述べない。しかし、先に述べた通州事件の目撃談が収録されていた。事件当時、支那人(中国人)と結婚して通州にいた佐々木テンさんは残虐な事件現場を目撃。その聞き書きが調住職の手によって記録されていたのだ。
通州事件の全貌については連合国軍による言論封鎖、弾圧、加えてコミンテルンの影響下にある日本人が共産主義教宣活動のため事件を隠蔽。あろうことか、この事件の残虐性を逆に日本軍の仕業としても利用。亡国の民へと導く工作とも知らず、今の今まで、日本人は謝罪と戦時補償に追われていたのだ。本書の編者の一人である石原隆夫氏が事件発生時の1937年(昭和12)から1945年(昭和20)までの朝日、毎日、読売などの新聞記事を検索し、通州事件がどのように日本に伝えられたのかを調べ上げた。540ページにわたる大著ながら、本書の大部分は新聞記事と翻刻で占められる。その一つ、一つを追っていくとあまりの残虐性に憤慨しないほうがおかしい。しかし、当時の日本では在日の中国人に危害を加えるなと勧告し、報復の連鎖を押しとどめていたのだ。
もし、新聞報道が捏造だと見る向きには、526ページからの野嶋剛氏の論考を参考にされるとよい。朝日新聞が総力をあげて戦時報道に邁進していたことに驚く。社機23機、飛行距離50万8975キロ、飛行時間2303時間、飛行回数832回、他に報道用の車両としてトラック、自動車、サイドカーが127台、無線92台、伝書鳩1146羽という陣容である。孫子の兵法に「情報収集に金を惜しむな」というが、驚異的な資金が投入されていたことは想像に難くない。更に、殉職した朝日新聞の従軍記者は靖国神社に合祀されたという。
この通州事件をもって中国への反発、報復を煽る気持ちはない。ただ、今も続くウクライナ紛争の陰に何があるのかが透けて見えはしないだろうか。先の大戦において、日本が謝罪と賠償を繰り返しても、世界各地での紛争は鎮まらない。なにが原因なのか。それを考察するのが本書の目的である。各界を代表する論者が述べる意見を参考に、思考していただきたい。今後も人間の愚かさが続かないためにも、冷静に読み込んで欲しい一冊だ。
『人は鹿より賢いのか』立元幸治著、福村出版 令和4年7月3日
・平時の今こそ、心して読み進むべき一書
「人は鹿より賢いのか」。なんとも挑発的な題名に期待をもってページをめくった。まずは、このようなタイトルが付された背景を知るために「はじめに」を読んでみる。そこには「つもりちがい十ケ条」が示され、日々、生活を営む私たちを戒める標語が並ぶ。確かに、確かにと相槌を打ちながら、この条は誰誰さん、この条は誰誰さんと欠席裁判の裁判官にふんぞり返る自身に気付く。そこから、全十ケ条を自分自身に当て嵌めて内省を試みると、全てに当て嵌まる。愚かな自身に気付かされる。やはり、本書の大きな狙いは、ここにあるのではと、思いを巡らす。
本書が面白いのは寓話や昔話が紹介されていることだ。現代も江戸時代も時代は異なれど、人間の本質に大差はない。環境が異なっているだけで、「つもりちがい十ケ条」の世界は連綿と続いている。「京の蛙と大阪の蛙」という寓話が冒頭に紹介される。「鳥獣戯画」を見て、その滑稽さを笑った経験があるだけに、話の展開に違和感はない。面白く、おかしく、一つの噺を読了して、笑いの中の真実を見る。昔の人も、今の人も、人としての根本は変わらず、戒めの言葉としての話が今に伝わるのも納得できる。
本書の題名である「人は鹿より賢いのか」の話は、第一章の最後に出てくる。読み進みながら、どこかで読んだ記憶、聞いたような印象を受ける。落語だったか、講談であったかは忘れた。ただ、文字の読み聞かせが十分ではない時代、人の話を聞いて平生の生活を営む人は多かった。いわゆる「耳学問」というものだが、現代においても他人様の話はよく記憶にとどめる。明治時代の舞台俳優川上音二郎はオッペケペー節で民衆に自由民権を説き、革命浪人宮崎滔天も講談師に転じて全国津々浦々を民権運動で行脚した。時代は進めど、人の思考の過程にさしたる進歩はしていない。
さて、本書は柴田鳩翁という人物が乞われて倫理道徳を説いた事績をまとめたものだが、社会の安寧のために大衆が鳩翁の話を求めたというのは面白い。人は生まれながらにして性善説の人であるということにも頷ける。このことは第六章の「源頭に活水ありて」での「お石」という女性の話に心惹かれる。しかし、人には常に教育を続けなければ倦んでしまう。これを続けたところに鳩翁の凄みがある。それだけ、人間というものが「やっかいな」生き物。誰かが教え続けなければ、すぐに堕落してしまうのだ。反して、動物や植物は学校があるわけでもないのに、天地の理、自然の摂理に従うことができる。ここに「人は鹿より賢いのか」と言わせしめるものがある。
『荀子』杉本達夫訳、経営思潮研究会 令和4年6月5日
・為政者には耳の痛い事々
本書は荀卿こと荀子の思想をまとめた一書。荀子は『韓非子』を著した韓非の師としても知られる。いわば、孔子、孟子の性善説に対する性悪説の始祖ともいうべき人だ。故に、後世の儒者たちからは異端の扱いを受けた。孔子、孟子を儒者の右派とするならば、左派の源流が荀子だ。
右派儒者が説く法治主義が崩壊するとどうなるか。李氏朝鮮の末期、手の施しようのないほど世は乱れに乱れたが、でたらめなお告げで政治が行われ、民は牛馬の如く酷使され、搾取された。あのような乱世を防ぐために科学的な思考が必要だが、荀子はこの科学の重要性を政治に用いた。このことは現代においても、何ら不思議ではない。
荀子の考えが疎んじられるのは、世を治める人は世襲であってはならないと説いたことが大きい。為政者から否定されるのは致し方ない。しかし、この荀子の考えが支持されるのは、門人に韓非、李斯がいたからだ。彼らは秦を統一国家に仕立て上げた功労者だからだ。新興国が列強に囲まれながらも生き残るには富国強兵が必須。ある意味、現実主義的と言ってよい。
荀子は国家の統一にあたって「ことばの統一」を重視した。この「ことば」が統一されなければ、秩序はありえない。実に、至極まともな考えだが、それを実行するには様々な困難が行く手を阻む。維新後の日本においても、富国強兵、四民平等、国民皆兵、義務教育が導入されたが、列強の侵略から日本を守るのが目的だった。そう考えると、孔子、孟子の個人の内面と向き合う考えも大事だが、現実問題の解決として大久保利通が荀子や韓非の考えを重要視したのも頷ける。
荀子は、国を治めるにあたり、「年功序列」を用いた。年齢枠に集約し、同一の教育を施すことでずば抜けた才能の持ち主を選抜する方法。家柄などは関係ない。現代、年功序列に不満を抱く人がいるが、荀子に言わせれば、自ら無能であることを宣言しているようなもの。それは、たとえ王族といえども、能力が無ければ王位を継承させない。この点も、君側の奸が荀子を忌み嫌う要因だ。荀子は、王族の在り方も説く。王者は民心獲得に努め、覇者は同盟獲得に努め、強者は領土獲得に努める。民心獲得に努める者は諸侯を従え、同盟国獲得に努める者は諸侯を友とし、領土獲得に努める者は諸侯を敵とする。ここでいう王者を首相、諸侯を国会議員に置き換えて読み解いてみれば、荀子の時代も現代日本の政治も本質においてさしたる差異は無い。まさに「歴史に学ぶ」とはこの事を指すのだ。
この歴史から政治の世界を見てみれば、国が崩壊する始まりは近親者の重用にある。故に、国の崩壊を食い止めるには優秀な臣下を必要とする。荀子は、君主にゴマをすり、派閥を形成する者はダメ。民心を掴み、君主を思う臣下は良いと断言。更に、君主の権威を高め、民衆を大切にする臣下は理想とする。
荀子の説は、不完全ながら自治民範の基礎を形作った。為政者は『荀子』を一読しておいても良いのではと考える。
『インテリジェンスから読み解く米中と経済安保』江崎道朗著、扶桑社 令和4年6月2日
・軍事衝突を回避するために
ロシアの軍事侵攻によって今も紛争が続くウクライナ。しかし、マスコミが報じる内容とインターネットに投稿される内容とに乖離があり、いずれが正しいのか判断に苦慮する。ウクライナが発表する戦果の割に、紛争が終結しないのはなぜか。先の大戦における大本営発表を彷彿とさせ、情報が正しく日本に伝わっていない事を知る。更に、戦況を伝えるだけで、何が原因でロシアの侵攻に至ったのか・・・腑に落ちる国際政治学者の解説を耳にしない。ウクライナ情勢を窺いつつ、本書のページをめくった。
いまや、軍事衝突だけが戦争ではない。経済戦争、貿易戦争という言葉で明らかだ。二国間、多国間での輸出入の不均衡による結果、対抗措置、反発、報復が繰り返される。その結果、軍事衝突に至る。今回のウクライナ紛争もEUによるロシア包囲網の結果だ。このことは、著者の『インテリジェンスと保守自由主義』に旧ソ連(現ロシア)を2019年に戦争犯罪国家としてEUが議決したと述べられていることでも明らかだ。果たして、日本のマスコミはこの事実を伝えただろうか。イギリスのEU離脱報道は連日加熱したが、ロシアについては皆無だった。そのロシア包囲網は政治経済だけでなく、スポーツの分野にまで及ぶ。まるで、先の大戦に至る日本包囲網にその様が似ている。中国を含む満洲、シベリアの権益争奪から生じた紛争は、今回のウクライナ情勢に重なる。
本書は、日本独自の情報機関が存在しない事への警告を発する。アメリカを同盟国と見立て、沖縄を提供しての防衛に加え資金の迂回による経済政策。アメリカに追従しておけば大過なく過ごせた日本だった。しかし、本書の記述にあるように、アメリカが対中政策を誤りであったと認めた以上、日本は対米政策を含む対中政策を考えなければならない。特に、中国に技術移転してしまった日本としては、独自の情報収集が必須。ところが、残念なことに、情報機関が存在しない。分かりやすい事例でいえば、新型コロナウイルスにより、中国の工場から半導体が出荷されず、日本国内の家電製品、デジタル機器の組み立てができなくなった。急遽、半導体工場を熊本県に建設するというが、順調に稼働するまでに時間を要する。更に、看板は台湾メーカーだが、実態は中国本土という。技術漏洩など、いかにして防止するのか・・・。
経済も戦争であるという前提で物事を考えれば、本書の全8章は危機管理の書である。アメリカ、中国との外交を日本はどのように確立すべきか。その「提言」が各章末に付されている。参考にされたい。
本書の「はじめに」には、「国際情勢の動向は近現代史の流れを踏まえることだ」と著者は注意を促す。ウクライナの二の舞にならぬよう早急に近現代史の学習、情報機関の創設、産官学での連携を推進しなければならない。総合的にして横断的な情報収集は日本の自主独立の基本である。「知らなかった」では済まされない緊急事態が目前にあることを強く認識しなければならない。
『幕末・維新江戸庶民の楽しみ』青木宏一郎著、中公文庫 令和4年5月28日
・世界に輸出したい日本人の遊び
本書は幕末から維新期にかけての江戸の庶民が何を楽しんでいたかを全7章にまとめたもの。江戸文化を研究した三田村鳶魚、開国後の訪日外国人の日記、統計などを駆使して述べられている。
読み進んでいて面白いのは、江戸末期の庶民も現代の庶民も本質的な差異が無い事。嘉永6年(1853)のペリー来航では、初めて見る黒船に驚くものの、翌年の再来航では黒船見物へと「楽しみ」に変えている。奉行所による黒船見物禁止の「御触れ」が出れば出たで、川崎大師詣でと称してちゃっかり見物に繰り出す。首都圏を流れる多摩川にアザラシが登場した際、群集が押し寄せた珍事を思い出した。
江戸庶民にとって外交問題とか、政治問題は表面的なものであり、実態は日常生活を平穏に送ることができれば、外部の脅威など問題ではない。楽しむために食べ、健康を保つことが最大の関心事。この健康志向から庶民の風呂好きが生まれた。昨今のB級グルメ、健康食品、健康器具の通販など、本質は何も変わっていない。故に、庶民は治安の良さを求める。諸外国の人々が日本の治安の良さを感心するが、無意識のうちに秩序が必要と庶民は理解しているのだ。
楽しみといえば、庶民は日常生活にも楽しみを見い出す。その一つが園芸であり、釣りである。とりわけ、庶民の園芸好きは世界にも類のない国民性を有している。現代もBONSAIと称して盆栽が輸出品になるなど、その歴史は古い。更に、釣りは武士階級においての精神修養としても親しむものだった。これも、現在のテレビでの釣り番組の多さに顕著だ。これら庶民の楽しみについては、続々と指南書ならぬマニュアル本も出版されていた。園芸書の多さは世界でも稀。梅、桜、朝顔、菊、紅葉と四季を通じての楽しみを自然に求める。現代日本人が正月元旦に楽しむ「初日の出」も、江戸の庶民が生み出した。正月行事に色を添えるためだ。そう考えると、日本人は遊びの名人集団なのではとすら思ってしまう。
芝居や落語なども庶民の楽しみだが、これらもその発展過程を見て行けば、庶民の遊びの技術向上から文化へと昇華したものだった。しかし、維新後の日本では、庶民の楽しみは官製によるものが増えていく。ここから集団行動となり、やがて対外戦争での祝勝会、ちょうちん行列へと変化する。発意というより、群集心理に煽られてのもの。この現象は、現代のインターネット上で繰り広げられる事々を見れば、人間の行動原理にさしたる変化がないことが見て取れる。
庶民の楽しみというテーマで時代を解剖することで見えてくるのは、日本人の本質は何ら変わりがない事。しかし、その根底には、平穏な日々があってこそ。戦争を仕掛けてカネを儲けずとも、延々と資金が循環する方法を本書は示している。この技術は盆栽同様、世界に輸出して良いのではと考える。
『三十三年の夢』宮崎滔天著、岩波文庫 令和4年5月16日
本書は革命浪人宮崎滔天の半生の記である。幼少期の熊本荒尾での思い出から、多感な青年期、壮年期までが綴られる。特に、中国において革命の父とも国父とも呼ばれる孫文との交友は、日中関係の在り方を見ていく上で外すことのできない記録だ。孫文(孫中山、孫逸仙)の中国革命を支援した日本人は相当数にのぼるが、革命支援に至る背景や経緯について詳細に述べた文章が少ないだけに、本書は貴重な記録として扱われる。中国語訳を読み、熊本荒尾の宮崎家を訪ねる中国人も多い。
滔天は浪曲師となって各地を巡ったこともあり、文体が寄席や縁日での口上を聞いているかのような印象を受ける。しかし、その文中には歴史上の人物が多数登場し、明治、大正の日本の政治状況までもが窺える。とりわけ、政治家としては犬養毅が滔天の天衣無縫な性格を愛したことから、この犬養の政治姿勢を知る上でも重要な一書だ。
では、なぜ、ここまで滔天が中国革命にのめり込んだかといえば、東洋経綸にある。この時代、アジアやアフリカの多くはイギリス、フランス、オランダ、アメリカ、ロシアなど欧米列強の植民地だった。植民地民は奴隷として酷使され、石油を始めとする地下資源は収奪され、更に、欧米列強の商品市場だった。この情勢に猛然と反旗を翻したのが孫文であり、その孫文を支援したのが滔天、日本の志士たちだった。
明治38年(1905)、日本はロシアとの戦争に勝利した。この事は孫文の革命家としての魂に大きな希望の火を灯した。その10年前、日本は清国(満洲族政権の中国)との戦争に勝利した。欧米列強もさることながら、孫文らの漢民族は満洲族から植民地民としての支配を受けていた。孫文が、常に、日本を頼ってきたのは、この日清戦争に勝利したこともあった。当時の清国は、欧米列強の侵略を受けながらも民の痛みが通じず、崩壊の一途をたどっていたからだ。
ところで、滔天の息子の龍介の妻は大正天皇の従姉妹にあたる柳原白蓮だ。筑豊(福岡県)の炭鉱主である伊藤伝右衛門の後妻として嫁いだが出奔。「白蓮事件」として世間を騒がせた。後年、中華人民共和国は白蓮を滔天の一族として国賓扱いした。穿った見方をすれば、中国共産党といえども日本の皇室との関係を重要視したのでは・・・。
本書は文庫本ながら500ページにわたる大部だが、現代日本の読者のために巻末に詳細な人物評、注記、人名録がある。これら人物評、注記をみながら、改訂版の必要性を感じた。平成23年(2011)、新聞コードを有する朝日新聞紙上において、玄洋社の文字が大きく出た。これは、玄洋社報道を解禁する意味になるが、本書の人物評での頭山満(玄洋社)には、首を傾げる。言論弾圧から解放された今、再度、事実を検証し、改訂版を出す必要がある。
尚、本書には勝海舟の秘書も務めた宇佐隠岐彦が滔天の盟友として登場する。ともに孫文を支援した関係だが、近代史において今ひとつ、扱いがぞんざいな気がしてならない。この点も再考が必要と考える。
『また、いつか。』内野順子著、花乱社 令和4年5月5日
・絶対真実の現場から生き方を考える
本書は年間200件余の葬儀司会を務める著者の経験が基になっている。しかし、その体験談は、今に生きる私たちに対する「生きる」目的や目標が詰まった一冊となって仕上がった。
まず、第一部の第一章から読み進む。いつしか、第二部第五章までを読み切っている。どこにもフィクションは無く、事実、真実だけが語られている。それでいて、文体は語り口調であることから、無理がなく、肩がこらない。
第一章は、実際の葬儀の場で遭遇した感動の場面など、今生で縁の有った人との忘れられない事々が綴られている。これは何も人間だけではなく、動物も含まれる。48ページの「チャッピー君」が、まさにそれに該当する。人の言葉を発しない動物だけに、その感情表現にウソ、イツワリは無い。第二章96ページ「最後のメッセージ」を読みながら、死を覚悟した主婦が遺したメッセージに、その故人の生きざますら透けて見える。
そして、第三章からは現実問題が提起される。更には、現代葬儀考ともいうべき事々が述べられる。第一章、第二章では、読みながら涙が流れる場面があった。しかし、この章では時に場面を想像して、不謹慎ながら笑える話がある。それが140ページの「司会者はタイヘン」である。
第四章、第五章は、特に現在、どうという事はないにしろ、さほど先は長くないと自覚されている方に、現実問題として身につまされることではないか。ある意味、日本が抱える社会問題の縮図でもあるからだ。直木賞作家の安部龍太郎氏が「地域社会、家族の崩壊は、生きる信念、信仰の希薄から」と言われた。その言葉の意味が本書のそこここに散見される。
最終の第五章は、エンディング・ノートの必要性を説いている。死を考えるなど縁起でもないと言う方もいるが、この世に生を享けた以上、絶対に避けては通れないのが「死」だ。その絶対真実を直視できない事が、現代日本のイジメ、自殺、パワハラ、セクハラにつながっている。感動感銘の話から、司会者や裏方の大変さを知ることで他者への気配り、心配りの大事を知った。表しか知らない私たちに、その対応、対策を振り返る内容になっているのは有難い。書き言葉という政治性、話し言葉という社会性の両面を備えた本書を手にし、読者はそれぞれの思いを抱くことだろう。
「より速く、より高く、より強く」を合言葉に頂点を目指す事を是とする社会から、それぞれが、それぞれの生き方を選択する時代に来たと認識させてくれる書でもあり、誠心誠意という生き方のありがたさを気づかせてくれる書だった。
『明治人物夜話』森銑三著、岩波文庫 令和4年4月27日
・人物評価の難しさ、奥深さを知る
本書を手にしたきっかけは、勝海舟という人物を知るためだった。「海舟邸の玄関」として題しての一文があり、「栗本鋤雲の詩」にも海舟の事々が綴られている。その海舟の人物評も興味深かったが、「明治天皇の軍服」「大西郷の一言」など、感銘を覚える逸話が簡潔に述べられている。それらの話を読みながら、著者の森銑三がどれほどの文献、資料を読み込んでいたかが行間から窺えるものだった。
39名の実在の人物が紹介されているが、そのどれもこれもが面白い。ゆえに、軽く読み飛ばしをするのは、もったいない。人物はエピソードで語れと言われるが、微に入り細に入りの人物描写の観察眼に驚く。更には、意外な人物の出会いが道を決めた話もある。それが伊藤博文の女婿であり、源氏物語の英訳を行った末松謙澄と高橋是清。末松は漢学を高橋に教え、高橋は末松に英語や西洋史を教える。人と人との出会いは、偶然なのか、必然なのか、わからない。
さらに、史実としては記録されないが、あの大隈重信に爆裂弾を投じた来嶋恒喜(くるしまつねき)だが、見張り役の協力者がいた。三多摩壮士の三田村鳶魚(みたむらえんぎょ)だ。この大隈襲撃事件はテロと称されるが、その目的が大隈の大日本帝国憲法抵触であったことは論じられない。大隈の憲法に抵触することを止める手段が爆裂弾だった。陸羯南(くがかつなん)の「新聞日本」も大隈の条約改正問題を指摘したが、発禁処分という言論弾圧を食らう。来嶋は襲撃後に自決。身元も明らか。果たして、この来嶋の行動をテロと言えるのか、はなはだ疑問に思う。
本書の人物評論は、著名な人物だけではなく、歴史の襞に押し込められた人々も丹念に掘り出している。その著者の探求心には感心するやら、驚くやら。その中でも、落語家の三遊亭円朝が今の時代においても大切に扱われる背景を描いている。中国古典を翻案しての創作話の背骨には陽明学があった。ここに三遊亭円朝の人気と高い評価の真髄を見た気がする。第二部に「三遊亭円朝」としての章を読み進みながら、「人物」としてこの落語家を著者が取り上げるのも、森銑三が自身の生きざまが円朝に重なる部分があるからではないか。
一日一話、大事に読み進み、そして、繰り返し読み続けたい一書だ。46ページに「信夫恕軒」の章に依田学海の人物評の書き方を述べた箇所がある。人の一面としてのエピソードだけで語る事の愚かしさも織り込んである。著者も著者なら編者も編者の技が生きる秀逸本だった。
『中国を変えよう アメリカ議会を動かした証言』楊建利著、井上一葉訳、集広舎 令和4年4月21日
・一石を投じ、波紋を広げた演説集
本書は1989年の天安門民主化運動に参加し、事件に遭遇しながらも難を逃れた楊建利の講演集。2000年5月から2020年11月までの78篇の演説が収められている。主に欧米での講演が主だが、2017年11月には東京でも講演会が開かれた。世界各地で行われた講演だけに重複する箇所がある。しかし、そのいずれにもブレやズレが無いのは、楊建利自身が天安門事件での現場を目撃しているからに他ならない。
建国以来、アメリカは言論によって世論が変化する。実際、楊建利が演説という一石を投じたことで、アメリカ社会に波紋が広がった。第1章から第78章までを通読してみればわかるが、アメリカ市民の意識改革、行動変化が明らかだ。その最たるものが、天安門民主化運動のリーダー劉暁波の2010年ノーベル平和賞受賞である。
翻って、国連(日独連合軍を壊滅させるための連合国軍)が機能不全に陥っていることに慨嘆する。国連は戦勝国による権益確保の談合機関を経て、今や、常任理事国の利権追及の機関でしかない。人権問題を糾弾しても、常任理事国である中華人民共和国(中国共産党)によって、ものの見事に楊建利の期待は粉砕される。
第58章(348ページ)に日本での演説内容が出ている。そこにはアジア最強の民主主義国家である日本に対し指導的役割を果たすべきと楊建利は主張する。だがしかし、第二次世界大戦での敗戦国であり、いまだ国連の敵国条項に組み込まれたままの日本にとって酷な要求である。なぜなら、日本国民が永年、国連を国際平和、人権保護の機関と盲信しているからだ。
本来、本書は中国共産党による人権問題を糾弾し、中国の民主化運動を支援すべき演説集だ。しかし、日本人への意識改革を求める、啓蒙、警告の書でもあることに気づく。中国共産党がチベット、ウイグル、南モンゴル、そして香港、漢族に加えている弾圧、人権侵害を対岸の火事と見ることは、日本の民主主義の崩壊、独裁政権を確立することに繋がる。中国共産党によるインターネットの情報遮断、日本のマスコミに対する情報操作工作を慎重に暴いていく必要がある。日本は楊建利が求めるアジア最強の民主主義国家となり、隣国の人権侵害の実態を知り、本書に述べられる一つ一つの問題を解決していかなければならない。
アメリカ議会を言論で動かせるのなら、日本の議会も言論で変えなければならない。本書は、「中国を変えよう」というタイトルだが、「日本を変えよう」に置き換えて読み進むべきだ。一人一人が自主独立の気概を持たなければ一握りの独裁者に支配される。身をもって体験し、訴え続ける楊建利の言葉を、他者へと伝播させなければならない。明日は我が身にならないためにも。
『韓非子』西野広祥・市川宏 訳 松枝茂夫・竹内好 監修 経営思潮研究会 令和4年4月13日
・儒家の楯を貫く法家の矛
本書は韓非の論説をまとめたものだが、韓非は前三世紀初め、春秋戦国時代の中国の韓王安の庶子(身分の低い母親の子)として生まれた。韓非子(韓非が書いた書)は孔子を代表とする儒家の性善説に対し、性悪説ともいわれ「不徳の書」として忌み嫌われる。その多くが、君子が人民を従わせ、君子が臣下を支配する「法術」を述べているからだ。
とはいえ、現代人が韓非子に縁が無いわけではない。「矛盾」という言葉は韓非子に納められている説話。この「矛盾」からもわかるように、韓非の説話は参考にすべき例え話が多い。特に人民の統治においての法令を明確にし、賞罰を明らかにすべしという論は傾聴に値する。この法令の運用を掌るのは君主の臣下だが、その臣下に対する成果の目標達成に狂いがあった場合の罰は厳しい。一般に、目標数値を上回った場合、褒賞を期待するが、韓非子においては成果の超過に対しても罰を加えよと述べる。臣下の私欲の競争激化により国の基礎が維持できなくなると危惧するからに他ならない。
「悪徳の書」とも呼ばれる韓非子が誕生した背景には、中国の春秋戦国時代の過酷な環境があったからだ。小国が大国に簡単に大義名分も無く侵略される。あの手この手の策を講じて外圧を防ぐが、内部は内部で君主は気に食わない臣下、人民を平気で殺し、体罰と称しての手切り、足切りの刑を行った。国と国との外交も命がけなら、臣下も人民も、身命をかけての対応を求められ、忠実に仕えなければならなかった。反面、臣下の謀略によって君主も生命、財産を狙われるのが常だった。
この「悪徳の書」と呼ばれる韓非子を好んだのが明治の元勲大久保利通。欧米列強の侵略をいかにして防ぐかのテキストとして愛読し、小国の日本が生き残るための富国強兵の手練手管の参考書として利用した。
人民を統治するには法令の徹底をと説く韓非子だが、この法令は法治主義という言葉に置き換えてもわかりやすい。その法治主義を徹底させたのは江藤新平だが、その江藤も大久保から討伐された。そのような歴史を見ると、王政復古という維新を単純には喜んでばかりもいられない。幕末、尊王攘夷のスローガンの下、多くの志士が立ち上がったが、王(天皇)の為に蛮族(欧米)を討つといいながら、その実、政権の正統性の争奪戦であったことを知るべきだ。それだけに、明治新政府に対する反乱、決起が起こるのは当然のことだった。大久保は巧妙に韓非子の事例を実践したものの、自身が謀殺されたのも、テキスト通りだった。
いつの時代においても、人間の本質は変わらない。そう考えれば人間心理の絶妙な隙を突く韓非子が性悪説として糾弾されるのも納得がいく。「矛盾」という説話どおり、儒家の「楯」(性善説)を貫く「矛」(性悪説)だからだ。しかし、不徳の書として忌み嫌う前に、一読しておいても、損は無い。
『シルクロード』安部龍太郎著、潮出版社 令和4年3月16日
・西洋近代を超越するシルクロードでの気づき
シルクロードという表題から、東西交易の道であり、仏教伝来の道に関する一書と即断できる。しかし、現在、チベット、ウイグル、内モンゴルの民族弾圧が問題視される地域だけに、容易に足を踏み入れる事のできない秘境と思ってしまう。ところが、意に反し、著者はシルクロードを旅し、一冊の紀行文にまとめあげた。これは、強い興味を抱かずにはいられない。本書は2部構成になっており、それぞれ、第1部(2018~2019)、第2部(2019~2020)各10回、計20回の紀行文となっている。第1部の第1回から読み進むと、著者とシルクロードを旅する疑似体験ができる。
シルクロードといえば、孫悟空の「西遊記」を真っ先に思い出す。三蔵法師に従い、真理を求めてインドへと向かう物語は想像の世界でありながらも、現実世界のようでもある。その過酷なシルクロードの旅も、現代ではキントン雲ならぬ飛行機で中国へと飛び、列車、車を乗り継いでの旅になる。とはいえ、扉の地図を広げてみれば、いかに広大な大地の移動であるかがわかる。人間という動物は好奇心から移動する生き物だが、何があるのか、危険も省みず、好奇心という欲望を抑えることができない動物だ。
本書の内容については紀行文だけに、ああだ、こうだ、と解説するのは野暮。しかし、全ページの写真がカラーというのは、実に豪華。まずは、写真とキャプションだけを追ってみても、楽しい。そこで、ハタと気づく。全ページがモノクロ写真であれば、砂漠、岩山、雪山が続く景色は何を見ても同じ。ましてや西域であるウイグルのカラフルな民族衣装は言葉の限りを尽くしても、尽くしきれない。さらに、284ページにある日本の正倉院と新疆ウイグル自治区博物館にしか残っていない唐の時代の室内履きも、モノクロ写真であっては、そのありがたさも半減してしまう。
しかしながら、読了後、筆者は不完全燃焼に陥った。230ページの中段の写真に掲載されていた桃の種である。偶然、著者が見つけた1800年前のものだが、その結果の記述が無い。次回に続く、なのか。あの大賀ハスのように、芽を出し、花を咲かせと、現代の奇跡を期待していたのだが。
ともあれ、著者の「在るがままで尊い」というインドでの体験(啓示)、103ページの「目まいが起こした二つの可能性」など、非日常空間で得られる事々から、旅は真実を求める行為でもあるのだと納得できる。ページをめくり、文字を追いつつ、著者とシルクロードを旅することは、真理とは何かを考える時間でもあった。西洋近代という物質的充足の次に来るのは、東洋的な心の充足なのではないか。そうした振り返り、気づきを求める書であった。
『読書尚友のすすめ』小島直記著、致知出版社 令和4年3月14日
・対談者との知識の応酬は人間関係の構築でもある
本書は伝記作家の小島直記が、読書家の友人知人との対談で構成されている。平岩外四(東京電力会長、経団連会長)、城山三郎(小説家、直木賞作家)、会田雄次(京都大学名誉教授)、橋口収(広島銀行会長)、川島廣守(プロ野球セ・リーグ会長)の5人との対談だが、昭和58年(1983)から平成4年(1992)まで、雑誌の『致知』に掲載されたコラムから抜粋したもの。掲載時期を見てみると、先の大戦の敗戦を経て、高度経済成長、そして、バブル経済が破綻した期間に重なる。著者が対談者と交わす話の内容は簡潔ながら、重い。それだけ、従軍経験も含め、背負ってきた体験、読書量が現代日本人と違うということだ。この5人のなかで、作家の城山三郎は当然ながら、他の財界人の読書に対する取り組み、姿勢には、流石というべきものがある。広く、深く、知識、知恵を吸収し、考え、見識を広めていることが窺える。
著者の児島直記には「電力の鬼」の異名をとる松永安左ヱ門の評伝作品がある。それだけに、東京電力の平岩外四との対談は楽しみだったようだ。城山三郎には廣田弘毅の評伝小説『落日燃ゆ』がある。小島も同郷(福岡県)の廣田弘毅(首相、外交官)に関心があることから、廣田弘毅が玄洋社員であることを知っていた。しかし、城山はそれを知らなかったようだ。その事は、小島が他のコラムに城山の名前を伏せて書いていた。城山がその事実を知ったのは、この会談だったのではと推察する。会田雄次には『アーロン収容所』というイギリス軍の捕虜体験記があるが、東西文明の差異を知るにも優れた一書。イギリス軍の日本人捕虜への虐待など、筆者も悲憤慷慨しながら読了した事を思い出した。海軍経理学校を経た小島としても、会田との対談では、従軍経験という時代の悲哀を感じるものだったのではないか。
そして、著者の児島直記は橋口収、川島廣守とは海軍経理学校、いわゆる「短現」と呼ばれる組織の戦友である。この短現、穿った見方をすれば大東亜戦争(アジア・太平洋戦争)敗戦後、日本再興のために海軍が人材を温存するために設けたのではと思ってしまう。
なぜ、小説も含めて読書が重要なのか。それは、広く、深く、知識、知恵を吸収し、考え、見識を広めるためであり、人間の本質を知る為である。そこから、判断し、決断を下すためである。これは、どれほどインターネットが発達して情報量が増えても、AIが物事を判別してくれるようになっても、人間の持つ知力には追い付いていかないからだ。その意味でも、読書家同志の対談は、更に深い知識の吸収の場であったと想像する。
本書を読みながら、その昔、取引先の方が何気なく口にした人名が気になり、関連書籍を三冊読破。次回のアポイントの際は、相互に人物論を語り合った事を思い出した。その人間関係は、今も続いている。
『肩書のない人生』渡辺京二著、弦書房 令和4年2月27日
・書生を自認する人の言葉から気づかされる
本書は、渡辺京二氏の「肩書のない人生」「寄る辺なき時代を生きる」「あなたにとって文学とは何か」「道子の原郷」という4つの講演録、「コロナと人間」というインタビュー、「日記抄」で構成されている。特に、「日記抄」は昭和45年(1970)10月から12月のものだが、ここには三島由紀夫の自決について著者の正直な感想が述べられている。これは時代を表象する意識として実に貴重な箇所だ。
とはいえ、今回、本書を手にしたのは、著者が2021年(令和3)から熊本日日新聞に連載予定の「小さきものの近代」という維新に関する予告を知ったからだ。事前に著者の考えを読んでおかなければ、その方向性がわからない。この連載は、明治維新に至る過程での「地べた」に生きた人々を取り上げているという。新たな明治維新、近代というものを知る喜びがある。従来の、明治維新は無名の下級武士の青年たちが新国家を成したと伝えられる。しかし、果たして、それは新日本の庶民にとって幸せだったのかという問いかけである。明治維新を一つの革命であるとするならば、革命の後には庶民が幸福でなければならない。そのことを著者は問題にしているという。実に興味深い。
本書に納められている講演録、インタビューの中で、やはり「コロナと人間」というインタビュー記録は現実の問題として、考えさせられる。近代化によって人権尊重の時代を迎えた日本において、思いもつかない著者の答えに「信じられない!」という声が起きるだろう。コロナの出現は自然界における生物間の淘汰であって、人間の死も自然界の死と同じ。ゆえに、無駄な抵抗を試みようが、増えすぎたものは数量調整を図るからという。しかし、読み進めば、著者がコロナという感染症よりも怖い結核の闘病を体験しているだけに、その言葉からは不動の信念を感じる。
だらだらと、著者の頭を濾過して落ちて来た言葉の数々の中に、はたと膝を打つ言葉を汲み上げる。「庶民の知恵が無いのが現代」など、その最たるもの。世間の妬みを意図的に買うように仕向けているのがインターネットのSNSという。まさしく、正鵠を射ている。生活保護を受けている者が、実は、日常生活において王侯貴族の生活を送っていることに気づいていないと。ゆえに、日本社会全体が行けど果てない経済成長のジレンマに陥る。「まさしく」と気づかされる。さらに、本書を読み進む事で、著者が、何を読んできたのかという事に関心が向く。誰の、何に、影響を受けたのか、など興味はつきない。
インターネットも含めたマスコミが垂れ流す情報に左右されることなく、自身の頭で考える。著者はそう訴える。講演録が主体なだけに、軽く一読できる。しかし、その文字起こしされた行間から滲み出る事々は多い。考えることも多い。
ちなみに、若き日の著者を嫌った村上一郎は、三島の決起、自決を予言していた。三島の死後、追い腹を切った村上の自裁を渡辺京二氏はどのように評するのか。知りたいと思った。
『中国から独立せよ』小滝透著、集広舎 令和4年2月18日
・今後の対中政策に必読の一書
本書は、現今日本の対中国政策への提言である。とはいえ、多くの日本人は戦後教育の影響で、中国に対して「侵略」したという後ろめたさから、反発もしなければ反論もしない。近年海洋進出を強める中国だが、尖閣諸島での海上保安庁の取締りも警告に留まるのがせいぜい。日本が、この体たらくに至った原因は、かつての大陸政策での詳細が明らかにされず、民族、歴史が伝わっていないからに他ならない。
著者は築山力、小村不二男という実在の人物を描くことで、大陸での政策、歴史を述べていく。その始まりは、モンゴルの遊牧民との接触だけに、なじみが薄い分、理解に苦しむ。しかしながら、現代日本の対中政策において乗り越えなければならない必須の知識だ。ラマ教(チベット仏教)寺院での生活体験は、実に貴重だ。
中国共産党によるチベット、ウイグル、内モンゴルにおける民族弾圧は、苛烈を極めているが、そのことに対し、日本の知識人は発言をしない。目に見えない力で言論を封じられているのではなく、前提となる歴史認識が大きく欠如しているからに他ならない。本書は、広く、深く、その事々を気づかせてくれる。
仮に、著者の意図するところを早急に理解しようとすれば、最終第六章の十一節、もしくは、巻末の久野潤氏の解説を先に読了するのが良い。大東亜戦争(アジア・太平洋戦争)を巡って、左右両派の知識人が対立する中、第三の論点、視点が欠如していることを著者はものの見事に喝破している。久野潤氏は簡潔に現代日本の歴史認識の問題を提起しているからだ。
今、大量に安く、メイドイン・チャイナの衣料品、電気製品などが日本市場に流入しているが、それは中国共産党の圧力に苦しむチベット、ウイグル、内モンゴルの人々の血と汗と涙の結晶であると、日本人は知らねばならない。安易に、「安い」という資本主義の価値観を受容してはならない。
いずれ、共産主義体制の中国は崩壊する。その時に備え、何をなすべきか。本書を参考に考えておかねばならない。日本の為政者も、日本国民も、必読の一書だ。
蛇足ながら、巻頭の写真の数葉を見ていた時、山高帽の正装姿のタタール人に気づいた。『頭山満写真集』にも納められているクルバンガリーではないだろうか。玄洋社はアジア主義を標榜したが、興亜義塾との結びつきにも関心を向けたいと思った。
『孫文と神戸』陳徳仁、安井三吉著、神戸新聞出版センター 令和4年2月4日
・東洋の視点で多角的に物事を見る
「孫文と神戸」と題し、陳徳仁、安井三吉の両氏の対談で構成された一書。全8章、280ページ余の本書からは、孫文の生涯、革命、理想社会建設の過程を簡潔に知る事ができる。この中で、124ページに孫文が理想とする社会実現に向けての具体的な施策が述べられている。
- 拷問用具、刑罰の道具廃止
- 被差別民の解放
- 華僑の保護
- 人身売買の禁止
- アヘンの栽培、吸飲の禁止
- 纏足禁止
- 弁髪禁止
- 教育の改革
- 実業の新興
などである。一瞬、信じがたい事々が述べてあるが、これがつい一世紀前の中国の実態だった。さして、現代と変わらぬこともあるが、こういった事々の改革から取り組まねばならないほど清国(満洲族政権の中国)は疲弊していたということだ。加えて、イギリスを始めとする欧米列強の清国侵略が苛烈であったという事も含めて。
その孫文の革命を支援したのは日本人だった。特に玄洋社の頭山満、その盟友の犬養毅は双璧だった。しかし、帝政の清国から共和制の中国に移行することを嫌う藩閥の山縣有朋、井上馨らは、ことごとく孫文の足を引っ張った。どころか、日本国内の政治不満を回避するため、第一次世界大戦に参戦した。「日英同盟」を口実にして青島のドイツ軍陣地を攻めた。更には、その租借、権益の移譲を求めた。この対応に、中国の若者が反発したことから反日の火種がくすぶった。いかにアジア解放の旗を立てても、三井、三菱という財閥の意向を優先すれば、反発が起きるのは必至。大隈重信内閣の加藤高明外相の財閥優先政策が、後日まで尾を引いた。大隈を善と見る方には信じたくないかもしれないが、政治家としての大隈はすでに財閥の走狗としてしか中国には映っていなかったのだ。この点を厳しく追及していたのが中野正剛だった。中野の師は頭山満だが、その頭山の心中も中野と同じであったと想像する。
現今、孫文の「容共主義」から、ソ連と結びついたとして孫文を批判する人がいる。しかし、大東亜戦争後(アジア・太平洋戦争)、インド独立の闘志チャンドラ・ボースはソ連に亡命しようとすらした。この行動を「容共主義者」とみなす人はいない。「独立できるのなら悪魔とでも手を結ぶ」と言い切ったチャンドラ・ボース。反英反米の対極にいたのがソ連である。「夷をもって夷を制す」である。数世紀にわたって異民族支配を受けて来たアジアの民を思うと、孫文批判に傲慢さを感じる。
孫文の神戸での「大アジア主義」演説前、孫文は頭山満と会見した。その孫文の後継である蒋介石は終生、頭山に信頼を寄せていた。神戸での孫文と頭山を満洲問題での「対立」関係と見るのがいかに早計であるかがわかるだろう。本書は、西洋の視点ではなく、東洋の視点で多角的に物事を見なければと示唆してくれるものだった。
『アジア主義者中野正剛』中野泰雄著、亜紀書房 令和4年1月20日
・停滞するアジア主義研究の再開は中野正剛から
すでに中野正剛についての伝記はいくつかある。中野の盟友と呼ばれる緒方竹虎の『人間中野正剛』、日下藤吾の『獅子の道・中野正剛』などだ。これらの著作によって中野の評伝は完結したかにある。しかし、本書は中野の四男であり亜細亜大学教授(当時)の中野泰雄の手によるもので、昭和63年(1988)に刊行された。直系だけに、中野正剛を神格化した内容に満ちているのではと訝る。しかしながら、さにあらず。中野正剛の情勢の見込みの甘さ、弱点を指摘する。ある時には、斬り捨てる。これは、著者が別人格として中野正剛の評価を試みていることの証だが、爽快さすら憶える。このことは、逆に読者の信頼を大いに増している。
世間一般は中野正剛を政治家として見る向きが多い。しかし、著者は正剛を歴史家として見るべきではと示す。この点は、実に合点がいく。新聞記者、衆議院議員という履歴から中野を言論人、政治家と見るのが通例。それだけに、これは新たな蒙を啓かれた。全8章、260ページで構成される内容は、中野正剛の紹介もさることながら、『日本及び日本人』『東方時論』『東大陸』などに寄稿した政治評論家・中野正剛の筆を介して、時代の変遷、大東亜戦争(アジア・太平洋戦争)突入前の日本が置かれた環境が如実に浮かび上がる。中野が評論を通じて、何を日本社会に訴えてきたかが明確。
中野正剛は韓国の独立、中国の統一、民族自決というアジア主義者としての考えを打ち出した。これは玄洋社の総帥・頭山満の考えと重なる。頭山、および玄洋社には思想が無いと斬り捨てた研究者がいるが、これは知識不足から生じた弁である。
また、著者「あとがき」には、アジア主義研究者の竹内好の論にも及ぶ。竹内によって中野正剛が「玄洋社直系の右翼」と短絡されていることに著者は反発を示す。いまだ竹内の著作から引用し、アジア主義を論じる方がいる。この竹内を引き合いに出すことが、いかに浅い論であることに気づかなければならない。このことは、竹内好が監修した評論において、明らかな誤りが散見される著作が放り出されていることからもわかる。アジア主義と大東亜共栄圏を同列と理解し論ずる評者が存在するのも、見直し改訂が行われてこなかったからだ。情けない限りだが、ここに日本の出版界の限界を見る思いだった。256ページに著者の痛烈な批判の言葉が並んでいるのを参照されたい。
東條英機首相に抗議して自決した人が中野正剛であるとの評価で締めくくるには、もったいない。停滞するアジア主義研究の再開は中野正剛から。つくづく、そう思う一書だった。
『岸田総理に伝えたい 新自由主義の転換はふるさとの復活から』小野耕資著、望楠書房 令和4年1月11日
・新自由主義の検証、打開策への現状報告
本書は令和3年(2021)10月に誕生した岸田総理への要望書ともいうべきもの。10の論と2つの補論とで構成されている。全体に一貫しているのは、日本の国家の在り方の見直しを求めている事。訪日観光客による経済活性化策としてのインバウンド、エネルギー政策、グローバル化見直しの提言である。
本書を読了して思い出したのは熊沢蕃山(1619~1691、元和5~元禄4)だった。蕃山は備前岡山の池田光政に仕え、家老にまで出世した人。思想家であり、政務に通じ、土木家でもあった。その蕃山は遠い将来を考え、恒久性のある仕事を行った。特に、政治の要諦である「治山治水」においての水防工事において卓越した功績を遺した。とはいえ、目先の効果を表すライバルに政務の座を明け渡し、不遇の晩年を送った。しかし、後世にその名を遺したのは、蕃山であった。著者は、岸田総理に蕃山の如くあれと求めているのではないか。
日本の近代を振り返ってみれば、嘉永6年(1853)のペリー来航は、欧米列強の「ならず者」によって蹂躙される時代の幕開けだった。日本は、西洋の金と銀の交換レートでもって日本の金小判の大量流出という被害を被った。隣国の清国(満洲族政権の中国)は、アヘンによって国庫も人も骨抜きにされたのだった。欧米の「ならず者」にとって、アジアの人々は獣以下であり、その生き死には関心すらなかった。あの西郷隆盛は、文明とは知らざる者には親切に教え、導くものであると説いた。故に、「ならず者」の欧米は文明国ではない。
現代日本においても、150年以上も前と同じ状況が続いている。あろうことか、その「ならず者」に媚びを売り、「今だけ、カネだけ、自分だけ」の輩が岸田総理の周辺にはびこっている。このことに著者は義憤を覚えているのだ。「ならず者」の欧米に対抗するために無理やりに仕立て上げた中央集権国家だったが、その結果が東京一極集中による国土の疲弊である。格差が拡大し、「上級国民」という言葉さえ誕生する日本社会となったのだ。本来、人が生きる糧である農作物は「農産物」という言葉に置き換えられ、商品となった。この不思議な現象に対し、三世、四世議員に理解できるはずもなく、国民は期待すらしていない。
選挙における投票を呼び掛けても、小選挙区制度による選択肢の無い現状においては、政権の中央集権に拍車をかけるだけの結果となった。著者は、この日本社会の現状を述べたのだが、岸田総理に著者の思いは届くであろうか。
著者はインバウンドを論じているが、コロナ禍によって訪日外国人が減少した今こそ、費用対効果の検証を行う良い機会ではないかと考える。大量生産、大量消費が利益を生み出さなくなったこと。逆に、インフラ整備に税金を投入することで、純利益には結びつかないことなど、数値で示してみてはどうだろうか。その深い堀り下げを期待したい。

『日本人が知らない近現代史の虚妄』江崎道朗著、SB新書 令和4年1月4日
・世界の歴史認識の変化に日本は追いついているか
歴史認識において齟齬をきたす代表的な言葉に「太平洋戦争」という呼称がある。いまだにテレビ、新聞、インターネットでも目にする。長い年月、耳にし、目にしてきた言葉だけに、日本国民に浸透し、誰もその言葉に疑問すら抱かない。しかし、日本国民であっても、この言葉が通用しない世代がある。それが「大東亜戦争」体験者たちである。日本は昭和16年(1941)12月8日から太平洋だけで戦争をしたのではないという認識を持つ世代。更に、教科書でさんざん「太平洋戦争」という言葉を教えられてきた世代が、「アジア・太平洋戦争」という言葉を使い始めた。そもそも、「太平洋戦争」という言葉は、昭和20年(1945)12月8日から、新聞各紙において用いられたのが始まり。ここに、日本を占領統治する国連(連合国軍)の隠れた意図が見え隠れする。
本書は、国連(連合国軍)の術中にはまり、いまだ覚醒できずにいる日本人に、分かりやすく、具体例をあげ、世界の歴史認識の変化を解いたもの。例えば、EU議会が旧ソ連(ロシア)を侵略国家として議決し、プーチン大統領が猛反発している様を伝える。日本人の関心である真珠湾攻撃が、アメリカでどのように評価されているかなど。全8章、260ページ余にわたって述べられる。
二度と、悲惨な戦争を繰り返さないために国際連盟が設けられた。それにも関わらず、なぜ、再びドイツは日本、イタリアとともに、主義主張を超えた国連(連合国軍)と干戈を交えたのか。更には、悪の枢軸と言われた日本、ドイツが国連(連合国軍)に大敗したにも関わらず、世界から戦争は無くならないのか。この事実から、本当の悪は滅んではいなかった事が証明される。本当の悪は誰なのか、何なのか。
本書では、リッツキドーニ文書、ヴェノナ文書、米国共産党調書という資料を基に、その悪が何かを見事にあぶりだした。持論として大東亜戦争(アジア・太平洋戦争)の発生から、経緯、結果までをも日本の好戦的な姿勢と結論付けている方には、定説を覆されたくはないと思う。しかし、今、世界が歴史認識においてどのように変化しているのか。その時流に対処したいと思われる方には必読の書。
人物評価や歴史認識は、利害得失の関係者が死滅しなければ真実は浮上してこない。これからさらに、深く掘り下げることで、また新たな新事実が発見されることだろう。「アジア・太平洋戦争」という言葉を生み出した世代が登場した現代、従来の歴史解釈では世界に通用しない事を如実に知るだろう。
『花山院隊「偽官軍」事件』長野浩典著、弦書房 令和3年12月25日
・維新史の忘れものとして再検証が必須の事件
幕末維新史における「偽官軍」事件といえば、慶応三年(一八六八)一月に起きた相楽総三の「赤報隊事件」が著名だ。官軍の魁として危険に身を晒したにも関わらず、突然、「偽官軍」として身内に討伐された。後世の人々は、この新政府の理不尽な対応に怒りを覚えた。同時に、維新の一翼を担った相楽総三らの名誉回復、慰霊、顕彰にと思いを致した。その思いに応えたのが長谷川伸の『相楽総三とその同志』だが、これは、多くの日本人から称賛を浴びた。
その赤報隊の「偽官軍」事件よりも一か月ほど早く起きた「偽官軍」事件が「花山院隊事件」だ。本書は、その事件の全貌を解説したものだ。これは、従前の固定した維新史に、新たな一石を投じることになるだろう。実際に『幕末維新全殉難者名鑑四』のページをめくると、赤報隊の次に「花山院隊党」として事件関係者の名前が綴られている。この花山院隊とも花山院党とも呼ばれる集団は、花山院家理という公卿を擁し、九州の幕府所領を制圧するという目的で編成された。九州における幕府の所領としては、豊後の日田、長崎、天草の富岡などがある。花山院隊は、慶応三年(一八六七)十二月六日、天草の富岡を襲撃。続いて、翌年の一月十四日に豊前宇佐の四日市陣屋を襲撃した。襲撃にあたっては、賊の幕府を制圧、いまだ佐幕か勤皇かを決しかねる九州の諸藩に勤皇を迫る目的があった。しかし、官軍としての制圧にあたって、各陣屋に蓄えられたカネやコメを強奪したことから、盗賊の仕業とみなされた。これが、「偽官軍」の烙印を押される由縁となった。更に、官軍であれば天皇の勅書を携帯していなければならないが、これが無い。いかに位の高い公卿を頭領に戴いても、「官軍」とは認められない。ここの事情は、滑稽でもあり、哀れでもある。
最終的に公卿である花山院は騙された、担がれただけとなり、保護される。他は討伐という名の下に処分されて終わり。「草莽崛起」として吉田松陰が身分の低い武士や町民、農民を鼓舞したが、結果的に利用されるだけで、結末は使い捨てだった。
このような使い捨ての事例は他にも多いが、ふと想起したのは、海援隊の坂本龍馬、陸援隊の中岡慎太郎の襲撃事件である。彼等もまた、無用の輩として葬られたのではないか。
歴史の襞に押し込められた、維新史の陰の部分は、実に悲しい。参画した人々の志が、純粋で、高いだけに、なおさらだ。
本書には、事件関係者の詳細な名簿が付されている。ここからさらに、事件の本質の深堀が可能だ。例えば、喜多川重四郎は後の「秋月の乱」鎮圧において斬殺された穂波半太郎である。まだまだ、何か、隠れた真実があるのではないか。維新史は「知っている」つもりでも、小説の域を超えていない事が多い。本書を読了し、維新史の大きな忘れ物を見せられた気がした。
『海舟語録』勝海舟著、江藤淳・松浦玲編、講談社学術文庫 令和3年12月21 日
・口述筆記の難しさ
本書は明治28年(1895)7月から、明治32年(1899)1月まで、勝海舟の口述を編纂したもの。雑誌『日本宗教』の巌本善治が海舟の家を訪ね、長時間にわたって海舟の話をまとめた。
勝海舟は文化6年(1823)1月30日に生まれ、明治32年(1899)1月19日に死没した。故に、海舟の最晩年の記録である。読み進むと分かるが、剣と禅とで心身を鍛えた海舟といえども、流石に、その衰えを感じさせる。老人特有の「あれ」「それ」に加え、記憶の相違や主語の欠如などが気になる。維新という革命の最前線に居た人物だが、言葉にキレ、鋭さを感じないのは、悲しい。
しかし、特筆すべきは主家である徳川家、最後の将軍である徳川慶喜の名誉回復に尽力したことだろう。その慶喜からも当初は「裏切り者」として遠ざけられていた海舟だった。更に、盟友ともいうべき西郷隆盛の名誉回復については、「西郷さんのお祭り」という節に述べている通り、最終最後まで西郷を信じての言動は、何物をも寄せ付けないものがある。海舟を批判した福澤諭吉も西郷を擁護したが、内容と迫力とにおいては海舟の足元にも及ばない。
113話が収められている本書だが、日めくりのように、一日一話を読み進むと、無理がない。一話ごとに編者による補記があることは、より理解を深めてくれる。加えて、編者の松浦玲が「解題」を巻末に記していることで、この一書の価値の在りかもわかる。聞き書きした巌本が意図的に天皇制や軍部批判を書き換え、削除したことも見逃していない。ある意味、口述筆記の記録を後世に遺す事の難しさを認識させてもくれた。
いずれにしても、幾度か、読み返すうちに、小説を読んで「幕末維新史を解かったつもり」になっている史実を覆す箇所もあり、人の評価は多面的に見なければならないと示唆してくれる一書だった。
米中ソに翻弄されたアジア史』江崎道朗、福島香織、宮脇淳子著、扶桑社 令和3年12月16日
・アジア戦略に必須の一書
本書は江崎道朗氏、福島香織氏、宮脇淳子氏の三者が、令和元年(2019)12月にカンボジアを訪れた際の紀行であり、各氏の専門分野における東南アジア論でもある。第一章の歴史編を宮脇淳子氏、第二章の政治編を江崎道朗氏、第三章の国際関係編を福島香織氏、そして、第四章は三氏による鼎談という構成になっている。
本書を読み進むにあたって、筆者は第四章の「鼎談」から読み始めた。カンボジアの気候風土を含む現在の姿を見ることによって、各氏が述べる立体的な論が際立ってくると思ったからだ。単なる、物見遊山ではない、日本の対アジア戦略を構築するための旅だけに、各氏がどこに焦点をおいているのかも興味深い。
鼎談に続いて、第一章の歴史編を読み込む。ふと、カンボジアに特化した歴史を通読するのは初めてであることに気づく。従前、大東亜戦争(アジア・太平洋戦争)でのタイと日本が独立国であり、他の国々は欧米列強の植民地であったという理解に留まっていた。しかし、独立国のタイといえども、イギリスとフランスとの緩衝地帯でしかなかった。その事実に複雑な感情が沸き上がる。ふりかえれば、欧米列強によるアジア侵略、植民地支配が今日のカンボジアの悲劇の源にあることを知らなければならない。
次に、第二章の江崎道朗氏の政治編。大東亜戦争後に独立したカンボジアといえば、シアヌーク殿下は外すことはできない。ベトナムを巡ってのフランス、アメリカ、中国、ソ連(現ロシア)の武力の均衡を図るため、シアヌーク殿下が政治の舵取りにおいて泥沼を招いた。その中で、大東亜戦争後、カンボジアに残留し、道立運動を支援した旧日本軍の只熊元(陸軍大尉)らが紹介されていることに、一服の清涼剤を得た思いだった。
更に、第三章での福島香織氏の国際関係編では、中国共産党の一帯一路政策により、東南アジアで繰り広げられる「民族戦」の現実を知る。国境など無視し、東南アジアに土足で侵入する漢民族に、国の根幹が翻弄されている事を知る。もし、これが、日本で起きているならば、日本国の存在はあり得ない。新型コロナウイルスのワクチン接種に翻弄される日本だが、産業情報漏洩問題、外国人による重要拠点の土地の買い占め、半導体工場誘致における水源地の買い占めなど、腰を据えて議論しなければならない。しかし、国会で議論される風もないことに、慨嘆。
本書の帯にあるように「それは、日本にとって決して他人事ではない」の通り。「侵略」といえば、武力による地域支配しか日本人は想起しない。しかし、砂糖に群がりくるアリの大群のように「民族戦」「歴史戦」という中国共産党の侵略が進んでいることを強く認識しなければならない。その問題提起が本書である。手もとに置いて、折々、読み返すことになるだろう。
『世界史のなかの蒙古襲来』宮脇淳子著、扶桑社 令和3年12月12日
・植民地軍の高麗に攻められた日本
韓国政府の要人が「日本の植民地支配を一千年忘れない」と発言した。このニュースがテレビで流れた時、画面に向かって「二度の蒙古襲来から一千年経っていないから、日本もあの残虐を忘れていない」と呟いた。蒙古といいながら、日本に攻め込んできたのは高麗人だからだ。
蒙古襲来こと元寇について、歴史教科書、年表には文永11年(1274)、弘安4年(1281)に二度の元寇襲来があった。更に、いずれもの襲来時、「神風」が吹き、一夜にして軍勢が消えてしまったとは記される。しかし、男や老人は虐殺、女は慰安婦、子供は奴隷として連れ去られたことなど、一行も記述がない。この事実を韓国政府の要人が知っていれば、「日本の植民地支配を一千年忘れない」などとは、口にはできないはずだ。
本書は全6章、260ページにわたって、「蒙古襲来」の実態が述べられている。まず、第一章において日本人がモンゴルに抱く先入観が覆される。それは、言葉、文字、文学作品に至るまで、詳細な分析。
次の第二章において、日本人は同じアジア人種として中国、朝鮮、モンゴルを見る傾向がある。けれども、国家、社会制度が日本とは明らかに異なる事が解説される。「家」を基軸にする日本、「血」を重視する中国、朝鮮、モンゴル。この事を読みながら、昨今、しきりに主張されるグローバル化だが、日本は「家」という制度によってグローバル化を実現していると思い至った。
では、なぜ、現在、日中韓の間で歴史認識が対立するのか・・・。日本では諸外国にとって都合の悪い歴史は消され、中国、韓国では歴史が捏造されるからだ。これでは、いつまで経っても平行線をたどるしかない。その背景が第三章で具体的に説かれている。第四章では、蒙古襲来こと元寇襲来での日本側の状況が述べられる。それは、鎌倉幕府であったり、日蓮上人の『立正安国論』であったりする。このあたりは、日本史の教科書でも少しは聞き知っている。ここで、今も福岡市周辺に遺る「防塁」が紹介されることで、文献だけではない現地確によって史実が立体的に浮かび上がる。
そして、終章。ここで、本書刊行の目的である「歴史に何を学ぶか」という要点が述べられる。ただ単に知識だけを詰め込めば良いというだけでは残念。過去から今につながる事実から、今、起きている問題に、いかに向き合うか。特に「歴史は繰り返す」という教訓に従えば、本書を読了し、外交においても活用しなければならない。タイトルは蒙古襲来でも、本書は外交問題にいかに対処するかの提言書である。なにしろ、隣国は簡単に取り替えられないのだから。
『伊藤半次の絵手紙』伊藤博文編著、集広舎 令和3年12月7日
・後世に伝えるべき一冊から
伊藤半次の絵手紙については、すでに多くのメディアで紹介され、編著者であり伊藤半次の孫にあたる伊藤博文氏(初代首相と同姓同名)によって絵手紙集も出版された。故に、大東亜戦争(アジア・太平洋戦争)の戦記、原爆、空襲体験、大陸や半島からの引揚体験集と同類に見えるかもしれない。しかし、本書の特異な点は、伊藤半次(1913~1945、大正2~昭和20)が、兵役にある約5年間、家族に宛てた手紙がおよそ400通にのぼり、それが絵手紙という異例の手法で占められているということだ。
昭和15年(1940)9月、27歳にして徴兵された伊藤半次は、実にこまめに家族へ手紙を送った。その一つ、一つを読み進むと、写真とは異なる時代の風景、光景が浮かび上がる。夫婦間の立ち入った私生活については、符丁とも暗号ともいうべき単語で互いの気持ちを通じ合わせる。そこからは、几帳面、気配り、良い意味での忖度の働く伊藤半次の人物像が見えてくる。四角四面、融通の利かない軍隊においても、上官、同僚への心配りを怠らず、さすが博多商人ともいうべき手練手管を発揮する伊藤半次だった。
提灯屋の主であった伊藤半次は、絵を描くことはプロ。このプロの腕が、見事に軍隊で重宝された。では、なぜ、その絵を描く技術が家族に宛てての絵手紙になったのか・・・。不思議だった。第3章、65ページ、71ページにその真相を発見した時、「ナルホド!」と合点がいったのだった。更に、軍隊には検閲がつきものだが、全てにおいて合格。その背後関係も絵手紙の腕があったればこそだった。
ただ、発信年月日順に絵手紙が並んでいるが、徐々に徐々に、戦況が厳しくなっていく様子が窺える。最後の任地である沖縄からの手紙は、わずかに三通しか家族の手もとに届かなかった。博多に残した家族、特に妻との再会は叶ったのか・・・。その結果は、全7章のどこかに潜んでいるので、探求していただきたい。260ページ余に及ぶ絵手紙集だが、絵手紙から見透かせる体験だからこそ、読み手を飽きさせない。
家族を案ずる絵手紙で占められる本書だが、文面のそこここから当時の物価を知ることができる。その意味からも、この絵手紙集は貴重な資料といえる。ただただ、よくぞ、この貴重な絵手紙を遺してくれたものと伊藤半次の妻禮子に感謝しつつ、その全てを公開してくれた編著者の覚悟にも敬意を表したい。
巻末には、編著者が遭遇した不思議なつながりが記録されている。誰もが記憶にも留めないような事々から、次第に判明していく事実。その履歴を追うと、もはや、目に見えない方々によって本書は完成したといっても過言ではない。
果たして、私たちは、この一冊から何をきづき、何を後世に伝えなければならないか。考えることは多い。
『水戸学で固めた男 渋沢栄一』坪内隆彦著、望楠書房 令和3年11月23日
・日本とは、日本人とは何か・・・
本書は「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一(1840~1931、天保11~昭和6)の思想面に特化した評伝である。「資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一の生涯からは、功利的な観点から人物像を見る傾向が強い。しかし、著者は渋沢に水戸学という思想の水脈が流れていることに着目した。そこで、渋沢の業績に水戸学の思想を重ねて論じることを試みた。その全三章は、
第一章「水戸学國體思想を守り抜く」
第二章「『慶喜公伝』編纂を支えた情熱―義公尊皇思想の継承」
第三章「水戸学によって読み解く産業人・渋沢」
という構成になっている。
ここで、水戸学というものを理解しておかなければならない。水戸学とは、水戸藩主・水戸光圀が始めた『大日本史』編纂事業に源流がある。水戸光圀といえば、勧善懲悪のテレビドラマ「水戸黄門」の黄門様のことだが、別に義公とも呼ばれる。この水戸光圀が始めた日本國史編纂事業はやがて、幕末の漢詩人・頼山陽の『日本外史』となって広まり、日本という国が天皇家を一本の大きな柱として成り立つ國であることが認識された。ここから、天皇と臣民との関係性、為政者としてあるべき姿が如実に浮かび上がり、藤田幽谷、東湖父子、会沢正志斎によって学問としての体系化を見るに至った。その水戸学を基礎に、近代日本の社会を構築したのが渋沢栄一だった。幕末の志士・梅田雲浜が「靖献遺言で固めた男」と吉田松陰から評された事から、著者は渋沢を「水戸学で固めた男」との冠を付けた。
水戸学の根幹を為す『大日本史』は、南北朝並立では南朝を正統とした。(14ページ)更に、北朝方の足利尊氏を「國体の念を欠くこと甚だしい」と手厳しい。(24ページ)故に、南朝の史実にも本書は言及する。
著者は本書を通じ、渋沢が功利一辺倒の経済人ではないと主張する。それは、社会の底辺で蠢く貧民の救済法である「救護法」成立に渋沢が尽力したと述べる。(71ページ)この箇所を読み進みながら、血盟団事件で大蔵大臣井上準之助が銃弾に倒れたのは、この「救護法」成立に反対した事もあったのではと考えた。
また、障害児教育にも渋沢が関与していた事を取り上げるが、渡辺清の娘・筆子との縁が紹介されている。これには、驚いた。渡辺清が福岡県令(県知事)にある時、玄洋社生みの親と呼ばれる高場乱と物議を醸し、32ページに名前がある古松簡二の門弟・川島澄之助とも派手に争いを演じたからだ。
渋沢は中国革命の孫文とも縁がある事が83ページに述べられている。同時に、先述の高場乱の門弟である頭山満と渋沢とが深い人間関係で結びついていたことも驚きだった。
本書は118ページほどの冊子にも近いものだが、その行間から読み取れる情報は、広く深い。この一冊から、日本、アジア、世界の再構築の発想が生まれる事を願うばかり。更には、日本人が抱える使命とは何かに気づいて欲しい。
『頭山満 アジア主義者の実像』嵯峨隆著、ちくま新書 令和3年11月7日
・ようやく、研究者が着手した頭山満
本書は、全5章、250ページ余にわたる頭山満(1855~1944、安政2~昭和19)の評伝。頭山満、玄洋社に関する既存の著作に述べられた事々を新書としてまとめている。故に、取り立てての特長は無い。しかし、唯一の特異点は、著者が大学教員であること。
大東亜戦争(アジア・太平洋戦争)敗戦後の昭和21年(1946)1月、GHQ(連合国軍総司令部)の指図で玄洋社は解散を命令された。超国家主義団体という事からだが、本書にも名前が登場するGHQの調査分析課長のハーバート・ノーマンの仕業によるものだ。このノーマンは、その後の調査研究からGHQに忍び込んだコミンテルン・スパイであったことが判明した。このノーマンの謀略から、戦後の日本における玄洋社は「右翼」と決めつけられ、頭山満は「右翼の巨頭」とのレッテル貼りをされた。レッテル貼りのみならず、見えない言論弾圧により、玄洋社も頭山満も封印され、歴史の襞に塗り込まれたままとなっていた。
ようやく、玄洋社に対するプレス・コードが外れたのが約10年前だが、それでも、一度こびりついたレッテルは容易にはがれない。その為、大学の研究者も気にはなるものの、研究に着手する風はなかった。それが今回、大学教員によって頭山満の導入本ともいうべき一書が出たのだから、時代の流れが変わったという明確な証拠。文献からの引用に加え、著者の研究成果、見解が付されている。今後、この一書から詳細な玄洋社論、頭山満論が刊行されることだろう。
一例をあげれば、17ページに頭山満の「満」という名前の由来が述べられている。これは頭山の盟友である杉山茂丸の嫡男である小説家の夢野久作(本名杉山直樹)の『近世快人伝』からの引用と思う。しかし、頭山家は菅原道真の子孫であると伝わる。その証拠となる墓碑も頭山の出身地である福岡市には遺されている。
本書の読了後、アジアの玄関口である福岡に研究者たちが続々と来福するのではないか。勝手に想像しながら、本書を読了したのだった。

ニコライの見た幕末日本』ニコライ著、中村健之介訳、講談社学術文庫 令和3年11月3日
・日本人はニコライを見習って、歴史、伝統、文化を学び直すべきでは
神田駿河台のニコライ堂は、首都東京の近代史のひとつ。ここは、ロシア正教の宣教師であったニコライが、日本布教の拠点として設けた教会。本書は、そのニコライが幕末期の日本に渡来しての見聞記。1869年(明治2)、一時帰国したニコライは雑誌「ロシア報知」に日本事情として自身の見聞したものを紹介した。その訳文が本書だが、ロシアにとって貴重な対日交渉のテキストとなった。同時に、ニコライが日本通のエキスパートとして母国に認知された機縁ともなった。
ニコライ(1836~1912、文政7~明治45)は、1861年(文久元)にロシアの箱館(函館)領事館付主任司祭として来日。ロシア正教の布教という大きな希望を抱いていた。しかし、当時、外国人と見れば理由のいかんを問わず襲撃をする。ニコライも問答無用で押し入った沢辺琢磨に刃を突き付けられた。ところが、沢辺を説き伏せ、逆に弟子にしてしまった。沢辺とは、あの坂本龍馬の親族の一人である。
8年に渡る滞日記録のなかで、多くは宗教を語っているが、ニコライが見た日本や日本人、日本事情が細部に至る事に驚く。これは、歴史、伝統、文化、日本語を習得した結果だ。日本の歴史といえば『古事記』『日本書紀』だが、同志社を創立した新島襄がニコライに解説し、新島はニコライを介してキリスト教の基礎を習得したといわれる。興味深いのは、日本は他の東洋と異なる国というところ。東洋は専制君主、民は盲従する。しかし、日本は真逆。民は愚鈍でも無学でもなく、よく本を読む。可能な限り貪欲に新知識を取り入れる。宗教においては、日本人は極めつくした無神論者。成熟しており、常に変化しなければ気が済まない。廃仏毀釈は抑圧されていた天皇に支配権を付与する方策であったとニコライは分析する。
ニコライはフランスのカトリック、アメリカのプロテスタントについても述べている。幕末、長崎の大浦にフランスは天主堂を建てた。これは在留フランス人のためではなく、潜伏する日本人キリシタンを呼び寄せるためのものだった。ここに見事、浦上地区の潜伏信徒が訪ねて来た。これは、フランスによる日本の植民地支配の手段だったのかもしれない。
明治37年(1904)、日露戦争が勃発。この時ニコライは、日本人信者に向かって「日本勝利を祈りなさい。それは日本人の務めです」と説いた。いまだ靖国神社参拝を問題にする隣国の為政者に教えたいエピソードだ。本書は危機管理に疎くなった現代日本人にとって教訓ともいうべき内容。ニコライの視点での日本を振り返っても良いのでは・・・。
ちなみに、『東京を愛したスパイたち』(A・クラーノフ著)には、日露戦後、ロシアからニコライの下に10名ほどの工作員候補者が送り込まれたと記されている。この事は、記憶に留めておくべきだろう。
『マオイズム革命』程映虹著、劉燕子編訳、集広舎 令和3年10月31日
・戦慄が走る、狂気の革命記録
いまだ、北京の天安門広場には大きな毛沢東の肖像画が掲げられている。中華人民共和国を建国した偉大な指導者としての毛沢東は、不動の地位を得ているかのようだ。しかし、本書は、帯にもあるように「中国の革命は人類文明に対する破壊であった」との記述の通り、毛沢東主義ことマオイズムが世界中(東南アジア、南米、アフリカ、ヨーロッパ、日本)に「悪」影響を及ぼした記録集だ。
反資本主義、反自由主義に唯一対抗できる主義として、マオイズムは世界各地に送り出され、実行に移された。日本においても『毛沢東語録』を持つこと、読むことが伝染病のように蔓延していった。それは反権力のシンボルであり、大音響が売りのロックのようだった。しばらくすれば、麻疹のように沈静化するかと思われたが、それは水面下で活動を続けていた。日本におけるマオイズム革命の影響については、468ページの宮原勝彦氏の箇所を事前に読了されることを薦めたい。昭和47年(1972)2月に起きた「あさま山荘事件」が、このマオイズムに端を発していたことに、背筋が凍った。
毛沢東といえば、文化大革命。文化大革命といえば毛沢東と、両者は表裏一体を為す。紅衛兵による中国知識人の糾弾が続いたが、やがて、それは利己的な保身の口実として利用され、混乱をきたした。しかし、その元凶である毛沢東自身も、自身が主導した経済政策の批判回避のための文化大革命であった。いわば、不純な動機から始まったマオイズム革命である。それだけに、ウソでウソを塗り固める行為の連続でしかなかった。
その悪影響の過程と結果が全14章、500ページ余に述べられている。読み進むと、その狂気の狭間で命を落とし、不遇の人生を送らなければならなかった人々の怒り、嘆き、悔しさが聞こえてくる。その数、把握するにも困難なほど膨大。この狂気の台風の目であった毛沢東を礼賛した日本の知識人は、この実態に対し、何と弁明するのだろうか。更に、このマオイズム革命に似た動きが、現在の中国である。膨張主義の過程と毛沢東主義とが重複して見えることに、どのような反応を示すのだろうか。
本書刊行の目的は、現在の習近平政権の動きと毛沢東主義とを比較することで、中国という国が抱える問題点を明確化にすることにある。他国の事だから口出し無用、過去のことだからと傍観すると、手痛いしっぺ返しを食らう。
本書は、今後の対中国との外交関係を考えるための参考書である。為政者のみならず、マオイズムの時代を経た人々こそ熟読し、問題点を振り返らなければならない。世界の崩壊を食い止めるためにも、かつてのカンボジアでの大虐殺を繰り返さないためにもだ。
蛇足ながら、日中間での平和条約が締結されながらも、日本の「侵略」戦争批判がどこに沈殿しているかを考える一書でもある。
『漢民族に支配された中国の本質』三浦小太郎著、ハート出版 令和3年10月24日
・新型コロナ・ウイルスは「令和の神風」
本書は長野朗(1888~1975)というチャイナ・ウォッチャーが書きのこした論を基に、現代中国の実像を炙り出したもの。序章を含む全8章、200ページ余に渡るものだが、著者自身がチベット、ウイグル、南モンゴルの人権問題に深くかかわっているだけに、その指摘する問題への切込みは鋭い。
では、表題にあるような漢民族の本質とは、何なのか。それを具体的に説明するには、現在のチベット、ウイグル、南モンゴルの問題を知っておくと良い。この人権問題については、『ナクツァン』(ナクツァン・ヌロ著、集広舎)、『ウイグル ジェノサイド』(ムカイダンス著、ハート出版)など、多くの著作が問題として糾弾している。地域住民の利便性を高める商人として漢民族は移住をする。次に、漢民族は害の無い民と信じ込ませた頃、開拓団と称する漢民族の移民が本格化する。気づけば、地域は漢民族が多数を占め、漢民族の道理が常識となる。そして、ある日突然、中国共産党軍が武力によって完全支配をしてしまう。漢民族が巧妙に民族侵略を行うかを知ることが先決。
次に、なぜ今頃、このような著書が出版されるのか。その答えは、大東亜戦争後、日本を占領支配したGHQ(連合国軍総司令部)が長野の著書を没収、廃棄処分にしたからだ。長野は漢民族の侵略性を早くから見抜いていたが、後世に警告すべき文書が無かった。そこで、僅かながらも遺った長野の論を著者は読み込み、そこから、現代の中国共産党の民族性ともいうべき侵略を解説したのである。更には、大東亜戦争終結後、日本人は歪んだ歴史を叩き込まれてきたが、いかに現在の歴史教育が間違っているかをも気づかされる。中国共産党は日本の「侵略」戦争を糾弾し、抗日戦争勝利のパレードまで行う。しかしながら、この漢民族(中国国民党、中国共産党の別なく)の侵略性向を基に、明治時代以降に起きた中国との紛争、戦争、謀略の数々を再検証すれば、従前の歴史観は大きく変わってしまう。それ故に、GHQとすれば、この長野の論は封印しておかなければならなかったのだ。
新型コロナ・ウイルスによって日本社会は停滞した。それ以前、日本の港には中国人観光客を満載した大型クルーズ船が寄港していた。インバウンドと称し、中国人観光客による経済効果を日本は求めた。その実、これが民族による侵略の前哨戦であることに気づいた日本人はどれほどいただろうか。この漢民族による「民族戦」は、蒋介石、毛沢東、江沢民、習近平のいずれの権力者の時代においても変わらない。富のあるところ、砂糖に群がりくるアリの如く、追い払っても、潰しても、次々にやってくる。そう考えると、新型コロナ・ウイルスによって日本は封鎖され、守られたのである。まさに、コロナは漢民族の侵略を防いだ「令和の神風」だった。
尚、本書の第5章は「昭和維新と長野朗」だが、権藤成卿の共治、自治という思想に長野がいかに共鳴、傾倒していたかを述べている。アジアの安寧の基礎をどこに据えるかの理想が見えて興味深かい。

『天皇制と日本史』矢吹晋著、集広舎 令和3年9月28日
・驚愕の史実、重たい問題提起の一書
表紙写真の人物に見覚えがあった。平成30年(2018)11月24日付、読売新聞西部版「維新150年」特集に取り上げられた朝河寛一(1873~1948)だ。「おごる祖国 愛国の苦言」という見出しの脇に表紙と同じ表情があった。
本書は、全9章、600ページに及ぶ大著。なかでも、第2章の『入来文書』において、朝河が早くに文書を読み解いていたことに驚く。中世日本(鎌倉時代)の封建制成立過程を知りえる資料として貴重なものだ。この『入来文書』については九州大学名誉教授の秀村選三氏(81ページ)から直接に話を聞いたことがある。『入来文書』解読は朝河が勤めていたイェール大学の委嘱が発端だが、その先駆者が朝河であったと知り、驚いた。日本の連作可能の稲作、欧州の休耕地、牧草地を必要とする畑作との比較は斬新。ふと、欧州の海洋進出の理由の一つが、肥料となる海鳥の化石化した糞鉱石を求めてであったことを思い出した。
本書第4章の「ペリーの白旗騒動は対米従属の原点である」は必読の箇所だ。第6章、第7章において提起される問題の「原点」でもあるからだ。嘉永6年(1853)、ペリーが黒船を率いて来航した。この時のペリーの通訳官であるウィリアムズに注目した朝河の慧眼には恐れ入った。歴史の現場の生き証人である通訳官の記録は、今後の歴史解説の見本ともいうべきものだ。この通訳官の存在の重要性を受けての第7章「日中誤解は『メイワク』に始まる」は、歴史に残る誤訳事件。事件の背後を丹念に追った著者の記述はミステリーを読んでいるが如くで、読み手を飽きさせない。一般に「マーファン事件」ともいわれるこの事件は、1972年(昭和47)、日中国交樹立の最終場面で起きた。田中角栄首相(当時)の「迷惑」と発言した箇所が中国側の誤解を招いた。通訳官がスカートに水がかかった程度の「麻煩(マーファン)」という中国語に翻訳したからだ。この「マーファン事件」を読みながら、日本人の記録文書に対する曖昧さを再認識した。根本に、記録を重視しない、解読しようとしない国民性とでもいうべき感覚があるのだろうかと訝る。そう考えると、本書が大分であることの意味も納得できる。
余談ながら、この「マーファン事件」については、筆者が初級中国語講座を受講している時、横地剛先生から教えていただいた。同文同種と思って安易に中国語を理解しないようにとの戒めを込めてだった。
冒頭、読売新聞の記事を紹介したが、その締めくくりは「戊辰戦争の敗者の側から朝河という世界的な知性が生まれたことも、近代日本の一断片だった。」である。まさに、本書の総括にふさわしい言葉である。なぜ、日本の歴史学会は、このような学者の存在を無視し続けたのだろうか。
ちなみに、実名を挙げての研究者らを批判する文章が目につく。しかし、朝河寛一の如くあれとの著者の警告ではと感じた。歴史は、何のために存在するのか。それは、後世の人々に同じ失敗の轍を踏ませないためだ。驚愕の史実が開陳されると同時に、歴史解読の問題提起の書であった。
『台湾を目覚めさせた男』木村健一郎著、梓書院 令和3年9月26日
・児玉源太郎、その早すぎた死
本書は台湾総督であった児玉源太郎の評伝だ。児玉については、『天辺の椅子』(古川薫著)などの評伝小説によってその生涯は紹介されている。しかし、あえて、再び、著者が児玉の伝記を刊行するに至った背景に李登輝(1923~2020、大正12~令和2)の存在がある。1988年(昭和63)年、李登輝が台湾の総統に就任し、教育改革が行われた。「台湾の近代化は、日本統治によるもの」と学校で教えることになった。すでに、1972年(昭和47)、日本は中華人民共和国との国交を樹立し、中華民国台湾との国交を断絶していた。それでも、李登輝は日本の植民統治を肯定的に評価したのだ。このことから、現在の親日国台湾が誕生した。
しかし、台湾の植民統治に日本が失敗していたのであれば、いかな李登輝といえども「台湾の近代化は、日本統治によるもの」と、学校教育の現場で教えることはない。これは、台湾総督であった児玉源太郎の手腕が優れていたからに他ならない。その児玉の生涯、業績を全5章、300ページにまとめたものが本書だ。
児玉といえば、明治37年(1904)から始まった日露戦争での203高地での戦いが評価される。乃木希典から一時的とはいえ指揮を代わり、勝利の目途をつけて去っていった。その姿は、深く、記憶に刻まれている。しかし、武の人というより、児玉の真骨頂は平時の文治における台湾統治によって評価されるべきだ。日本による台湾統治は、国内外から不可能と評されていた。その不可能を可能にした児玉の業績は、称賛されなければならない。大山巌という人間的魅力にあふれた上司に恵まれたこともある。後藤新平(医師、初代満鉄総裁)という優秀な部下を抱えていた事もある。しかし、その上司、部下の関係も、精神の感激がなければ成立しない。このことは、身分の上下を問わず、自由に発言させ、その意見を聞く耳を児玉が持っていた証拠である。これは治政における情報収集の基本でもある。
児玉については、本書の中だけでは語り切れないエピソードがある。それだけ、常人の枠を超えた奇想天外の発想力があったとうことになる。その奇抜な考えを実行するにあたり、やはり、多岐にわたる情報分析力を備えていたからだ。
あの大東亜戦争(太平洋戦争、アジア・太平洋戦争)の敗戦後、全ての過去を否定された日本。しかし、李登輝によってその再評価の道が開かれた。その礎として、児玉源太郎という人物がいたことは、日本にとって実に僥倖と言わなくてはならない。その児玉の全貌を伝える本書を通じ、今後、日本人がいかように受け止めるか、興味のつきないところだ。
『人間の条件1942』劉震雲著、 劉燕子訳、集広舎 令和3年9月25日
・民の真実は権力者によって葬られる
不思議なことに、本書は、同一内容の小説、映画の脚本が収められている。訝りながらも読了したのだが、理解が及ばない「空白」が生じた。それは、この作品が抱える問題が複雑、多岐にわたっていたからだ。
舞台は1942年の中国大陸の河南省。日本では昭和17年にあたる。当時、日本と中国は戦闘状態だった。中国国民党からいえば日本は「侵略者」。日本からいえば中国国民党は治安を乱した欧米の走狗。トップの蒋介石は、米国、英国、ソ連などの連合国軍の一員でもあった。
事件は中国国民党支配下の河南省で起きた。大旱魃で3000万人が難民となり、300万人が餓死したという。直ちに難民救済を進めるべきだが、蒋介石は連合国軍における地位保全が最重要課題。日本軍との戦闘において功績を挙げることが急務。国際世論に自国の難民救済を要請することは、面子が許さない。3000万人の難民、300万人の餓死者は蒋介石の頭脳が「無かった」こととして処理した。逆に、蒋介石の忠実な部下は軍費調達のため、過酷な徴税を河南省に課すのだった。
しかし、蒋介石が「無かった」ことにした難民は、日本軍が放出した救援物資によって救われた。「貨幣に色(善悪)はついていない」といって世間は揶揄するが、餓死寸前の難民にとって、食糧の色の識別は不可能。売国奴と罵られようが、危機を救ってくれるものが「善」である。敵対する日本軍が中国民衆を救援したという事実は、本書で初めて知った。従前、日本軍は中国を蹂躙した「侵略者」と教えられてきた。それだけに、驚きだった。
驚愕するのは、難民の実態である。すでに、樹皮、雑草の類までをも食べつくしていた難民は、娘や若い妻を娼妓として人買いに売り渡す。それも、わずかな穀物と引き換えにである。売り渡す肉親を持たない難民は餓死し、野犬の御馳走になるだけ。大旱魃は1942年だけではない。341ページから347ページにわたって旱魃による悲劇がズラリと並んでいる。その悲劇の陰には、蒋介石夫妻の喜劇ともいうべき飽食が彩を添えているのだ。
冒頭、小説と脚本の二部構成になっていると述べた。その重複の理由については「訳者あとがき」に詳しい。解説を兼ねる一文からは、想像を超えた事実が判明する。台湾に逃亡した蒋介石。その後をうけ、毛沢東の共産党軍が政権を握った。その施政において、河南省の難民に劣らぬ、いや、それ以上の餓死者が発生していたというのだ。読了後、頭を悩ます「空白」の正体は、為政者が「無かったこと」として歴史の襞に押し込めた「事実」であり、民を顧みる事の無い「傲慢」だった。この「空白」には、主義主張、宗教すらも割り込む隙がない。本書が私たちに示唆する問題は複雑多岐と述べたが、人間とは何ぞや、人間の条件とは何ぞや。次々と問いかけてくるからだ。
『政治こそ最高の道徳たれ!』 原田義昭著、集広舎 令和3年9月20日
・批判の声を次の政治に生かして欲しい
本書は、衆議院議員・前環境大臣である原田義昭氏の政務報告書だ。
令和2年(2020)10月から、令和3年(2021)7月末までのもの。周知の如く、国民も政府も新型コロナに翻弄されている。しかし、地球環境、福島原発処理水海洋投棄、尖閣諸島、中国の民族弾圧、東京オリンピック・パラリンピック、アジア諸国との連携など、待ったなしの問題に対応した事が述べられている。更には、新聞やテレビで幾度も報道された次期衆議院議員選挙での候補者選択についても、忸怩たる心中が・・・。自身の不徳の致すところと述べながら、粛々と、為すべき事を為し、正々堂々、選挙戦に臨むとの不退転の決意が読み取れる。
日付順の記録となっているので、世相の変遷を気づかせてくれる。気になる項目を集中して読んでも良い。天命とはいえ、原田氏に安息の日々は有るのかと訝りながら、その行動力、発言に驚く。特に、隣国の中国共産党に対する諫言、抗議行動は、遠慮がちに口をモゾモゾさせる議員が多いだけに、絶賛したい。かつて、日本が東洋の一小国であった時、プロイセン(ドイツ)の宰相ビスマルクは伊藤博文(初代首相)に注意を促した。「国際条約、国際公法は大国の権利保全のためにある。利益を争う場合は公法を楯にとり、不利益ならば公法を無視して兵力を用いる」と。日本が近代国家の仲間入りを果たした時点で肝に銘じておかねばならぬ原理原則だ。翻って、原田氏の主張、信念の背景に歴史の教訓が生きていることが窺える。それでいて、日本として世界に貢献できる事には援助、協力を惜しまない。それは、アジアからの農業研修生の研修施設であるオイスカの修了式(卒業式)の話に表れている。「農は国の本」という国の存立の基本を考えれば、その農業の技術支援も立派な世界貢献。このオイスカでの修了式では「仰げば尊し」が合唱されるという。かつての日本の原風景であっただけに、場を想像しただけでもジンとくる。良い話を教えてもらった。(67~68ページ)
随所に、次期衆議院議員選挙での事々が述べられている。しかし、その争点が「世代交代」というのは、いかがなものか。奇しくも、本書の156ページに「電力の鬼」こと松永安左ヱ衛門の名があった。松永は79歳にして、現役の財界人。それも、単なる名誉職ではなく、複数の役職を兼務する創造型リーダー。社会を支える人々の為に何を為すべきかという松永の信念に、原田氏の姿が重なる。そのことは、国政にありながら、氏が地域の交通体系、経済、歴史、伝統、文化に目を配っていることに見て取れる。「一隅を照らす」ではないが、従軍経験のある井出貞一さんが遺された文章、デッサンを地域の「文化遺産」として後世に遺せないかとの提案には拍手を贈りたい。(33~34ページ)
自民党の複数の国会議員が不祥事を起こし、辞職した。原田氏は党の一員として、有権者の厳しい批判の声に晒される。しかし、氏は、それを覚悟で出馬する。有権者の不満を期待に好転すべく、更なる政治手腕の発揮を願う。
『緒方竹虎と日本のインテリジェンス』江崎道朗著、PHP新書 令和3年8月8日
・日本再興の為に、情報機関の創設を
緒方竹虎(1888~1956)といっても、現代、その名前、功績を知る人は少ない。現在の自由民主党の基礎となる自由党、日本民主党との「保守合同」、いわゆる「55年体制」の立役者の一人。存命であれば、総理総裁の座も夢ではなかった。
本書は、その緒方竹虎の生涯を追いつつ、現代日本に最も欠けている情報機関設置を訴求する内容だ。緒方が追い求めながら、果たせなかった日本版CIAの創設をと著者は訴える。情報収集、分析、運用においての最大の失敗は大東亜戦争(太平洋戦争、アジア・太平洋戦争)である。近代日本の対外戦争である日清、日露戦争では、民間が提供する情報収集機能が有効に機能した。しかし、本来、情報機関は対外戦争遂行のために存在するのではなく、紛争の火の手が上がる前に消し止めるもの。いわゆる、リスクヘッジというものだ。ところが、戦前の日本においては、陸軍憲兵隊、特高警察による弾圧が強かったことから、情報機関設立に難色を示す人が多い。
しかし、独立国家として主権の存在を示すためにも、情報機関は必須。それも、戦前の内務省、外務省、陸軍、海軍のような縦割り機構での情報機関では、意味をなさない。緒方は、民間の情報機関も含めた総合的な情報機関創設を考えていた。本書を読み進みながら、情報機関があれば、新型コロナウイルスの感染拡大も、早期に対処できたのではと思えて悔いが残る。
新書ながら、全10章、400ページに及ぶ本書は、教訓というべき事々が述べられている。例えば、264ページの「都合の悪い情報に耳を貸さなくなってしまいがち。」などは、その代表例ではなかろうか。更に、誠に残念に思えてならないのは、第8章からの「和平・終戦を模索」であり、182ページに記される頭山満の蒋介石政権への派遣が実らなかったことである。従前、『失敗の本質 日本軍の組織論的研究』という大東亜戦争遂行を反省する名著もあるが、本書はインテリジェンスという観点からの失敗を振り返るに適した一書。日本という国家を再興するには、まだまだ随分と年数を要する。しかし、後世を考え、失敗も成功も、包み隠すことなく伝え、再興を果たさなければならない。その著者の思いを是非、汲み取って、自身に何が果たせるのかを考えたい。
『世界史から読み解く「コロナ後」の現代』佐藤けんいち著、ディスカバー携書 令和3年8月1日
・これからを世界史から考える参考書
令和2年(2020)、日本は未曽有のパニック状態にあった。中国武漢を発生源とする新型コロナ・ウイルスによって、人間の思考を含む全ての機能が停止したからだ。この現象について、政府のみならず、日本国民も何をどのように対処して良いのかわからなかった。しかし、このような世界的感染症拡大は、今回だけのことではない。およそ100年前のスペイン風邪もそうだった。全ては歴史の中に答えが用意してあるが、「歴史を勉強しても儲からない」「歴史を勉強する意味がない」などといって、先人の知恵を無視し続けたツケが、今に表れたに過ぎない。
本書は、その歴史を世界史の視点から解き明かし、「なぜ、今があるのか」「過去から学ぶヒントは無いのか」という事々を俯瞰するものだ。第1章から終章まで4章に分類されているが、終章の教訓1から6に今後の指針が示されている。その教訓1には「現代人だけが生きづらいわけではない」と記されている。まさに正鵠を射ている。教訓2には、内需比率の高かった日本であれば、少額でもよいので、内需を刺激すれば景気はよくなる。一発、大型予算を組んでも中抜きされるので、下々は潤わない。教訓3には、「自分の判断や行動は、けっして他人にゆだねきってしまわない」とある。まさに、ワクチンを接種する、しないは、自己判断であって、他者の言動に惑わされるべきではない。教訓4には、「ローカルをつねに意識する」。まさに、自己の足元をよく見つめることが肝要だ。教訓5では、新たなる日本文化の構築が世界貢献につながる。これは、教訓1に結びつくヒントとして日本モデルの創出ということか。教訓6では、コロナ禍から「なんらかのヒントなり教訓なりを見つけ出してほしい」と述べてある。自宅時間は思考の時間である。
明治維新から150年。日本は西洋列強による植民地支配を回避するため、西洋近代を取り込み、中央集権国家を維持してきた。しかし、原理原則を振り返り、日本モデルを確立するときにきたのではとのメッセージが、今回のコロナ禍である。リモート・ワークの拡大から、住宅の新規購入が増えている。企業内での人間関係から、家庭内での人間関係構築の必需品としての結果である。これに伴い、エネルギーの地産地消が求められ、休耕田はもとより耕作地の田んぼでも太陽光発電が始まっている。すでに経済需要の変化は起きている。
ふと、空を見上げれば、青空が広がっている。旅客機パイロットの飲酒が問題となっていたが、それも、どこへやら。原理原則を考える時をコロナ・ウイルスがもたらしてくれたと思えば、未来に悲観する必要はない。たくましく生き抜いた人間の、400年前からの世界の動きから、これからを考える。その一助が本書である。

『米国共産党調書』江崎道朗編訳、育鵬社 令和3年7月25日
・過ちを繰り返さないために情報機関の創設を
本書は、『日本外務省はソ連の対米工作を知っていた』(江崎道朗著、扶桑社)の続編ともいうべきもの。巻末資料も含め300ページ余にわたる内容は、ただただ、その精緻な分析調書に感嘆。日米戦争が始まる前のアメリカにおける共産党組織について外務省専任総領事としてニューヨークに送り込まれた若杉要の調査書が本書になる。この調書は、第1章から第3章と大きく分類され、第3章以降は10節、20項目、さらに細分化された項目が並ぶ。一度でもアメリカ共産党に関与したならば、人種、民族、階級に関係なく、相互監視され、離脱は許されない。財源確保も含め、新興宗教も真っ青の組織運営マニュアルだ。特に、プロパガンダ部門ともいうべき出版、演劇、映画、ラジオ、美術、教育分野における対外宣伝の巧みさに驚く。アメリカ共産党をダミーとして、ソ連が敵としたのは、日本とナチス・ドイツ。どれほど日本がアメリカに対し和平交渉を行おうとも、徹底してつぶされていく仕組みになっている。とりわけ、驚くのは、138ページの「米国作家連盟」の項目だ。シンパとして中国革命の孫文夫人・宋慶齢の名前までもが出ている。212ページには、工場におけるサボタージュの具体的な方法がマニュアル化されている。例えば、発電機内にレコード針を落として使用不能にするなど。
日米戦争前、外務省の外交の無能さが批判の対象にもなったが、正面からアメリカ側と交渉しようにも、結果は見えていたのだ。日本の背後に位置する中国への工作も巧妙だ。日本軍の戦闘行動を残虐極まる行為と過剰に糾弾。YMCA、YWCAというプロテスタント系キリスト教団体も背乗りし、その中国支部も支配下に置く。
本書をつぶさに読み込みながら思い起こしたのは近衛文麿の『戦後欧米見聞録』だ。近衛は欧州大戦(第一次世界大戦)後のパリに乗り込み、共産主義、アメリカの反日プロパガンダについて述べている。いわゆる東京裁判前に服毒自殺したヘタレの近衛と見られるが、実は早くから日米戦争を予見し、その対処を考えていた。近衛は、この対日プロパガンダの元凶であるホーンベックの存在も知っていた。そこで、松岡洋右、廣田弘毅が動いたが、近衛も含め、松岡、廣田も口を封じられた。
振り返って、戦後の学校教育現場では、ヘミングウェイ、スタインベックという共産党シンパの作品を教科書で読み、読書感想文の推薦図書にもなった。映画も鑑賞した。知らず、知らず、洗脳されていたのだ。
あの「だまし討ち」と言われた真珠湾攻撃はプロパガンダであると判明したが、これほどの仕組みが作られていたならば、日本は破滅の道を選択するしかなかった。近現代史の研究者にとって、本書は必携だが、過ちを繰り返さないためにも、情報機関の創設は必須と考える。
『激震』西村健著、講談社 令和3年7月13日
・本質として何も変わらない25年
「激震」という表題、「1995大地が裂けた。」という帯から、阪神淡路大震災に関する作品と直感した。しかし、この平成7年(1995)には、オウム真理教の地下鉄サリン事件も起きた。バブル経済がはじけ、それでも、持ち直しに懸命な時期に止めを刺すような災害に事件だった。あの未曽有の大戦と言われた大東亜戦争(アジア太平洋戦争)復興から半世紀。再び振り出しに戻ったかのような印象すらあった。それでいて、その災害や事件を渦中の外の人々は、対岸の火事として見ていたのではないか。
本作品は雑誌記者の古毛が主人公。怠惰な東京での女子高校生の「売春」事情の取材から始まる。そして、「本質としては何も変わらない」25年前の思い出に変っていく。阪神淡路大震災の一報は、まだお屠蘇気分が完全に抜けきらない1月に起きた。地震大国ニッポンでは地震は珍しいことではない。しかし、まさかの阪神地区での大地震だった。革新系の強い地域だっただけに、緊急事態でありながら、自衛隊の出動は大幅に遅れた。
事件は、その瓦礫の山となった神戸の街で起きた。倒壊した建物の下敷きで亡くなったと思われた遺体に刃物による刺し傷。捜査担当の刑事の如く、古毛は聞き込みに歩き回る。雑誌記者の本能というか、勘というものが働いたからだろう。ここから急展開でオウム真理教の地下鉄サリン事件に話が飛ぶ。一瞬、ストーリーの展開が分からなくなる。しかし、この地下鉄サリン事件は意外な結びつきを見せる。
ここから先は、著者の思惑に従って、話の展開を楽しむしかない。次は、どうなるのか。ここから、どう広がるのか。どう膨らむのか・・・。400ページ超の作品だが、300ページを過ぎる頃から、ページをめくるのがもどかしい。先に、先にと急ぐ気持ちを抑えて読み進む。結末は、今話題のGAFAのあの方?と思える意外な話に、安堵もした作品でした。
新型コロナ・ウイルスの出現で、日本人の多くは予想もつかない日常を強いられた。従来、右肩上がりで成長するのが当然という資本主義の展開を疑わなかった。幾度も幾度も、谷底を経験して、這い上がってきた日本だった。自宅待機の時間は、個人の内面と向き合う時間とまで言われた。しかし、果たして、そのようになるだろうか。本作品では、「本質としては何も変わらない」「後悔しても、それが遅過ぎたら、もう取り返しはつかない」。この二つの言葉が、キーワードだ。
四半世紀前の大きな災害、事件でありながら、その後も東日本大震災、新型コロナ・ウイルスと、次々に襲い来る災害、驚愕の出来事に翻弄され、阪神淡路大震災も地下鉄サリン事件も記憶から抜け落ちていた。
まだまだ、未曽有の災難に遭遇しなければ、人間は覚醒できないのだろうか。推理小説のようでいて、そうではない。一歩、立ち止まって、自身を振り返る作品である。

『九州の精神的風土』高松光彦著、葦書房 令和3年7月1日
・九州一国で物事を考える
本書は3部構成、500ページにわたっての九州の歴史書である。これほどの大部を著すに至った経緯は、九州経済同友会の席上、長崎経済同友会の清島代表幹事(十八銀行頭取)が、「もはや、県境に拘泥して事業を行う時代ではない。」との提案がきっかけだった。それを受け、各地域の「歴史的諸条件の考究が先決ではなかろうか」と著者は考えた。時折、「九州はひとつ」「九州独立論」という話や、経済における業績数値や人口変動についての報告は種々目にする。しかし、その歴史的背景までは理解が及んでいない。それでいて、本書の類が今まで刊行されなかったのが不思議なほどだ。
第一部は「九州学へむけて」、第二部は「九州の風土と歴史」、第三部は「九州の精神的風土」だが、面白い事に沖縄県については第三部の第8章に登場するだけ。「九州・沖縄八県連合博覧会」の第一回が明治15年(1882)に長崎で開かれたが、沖縄県は九州に入るのか、入らないのか。言語学的には確かに沖縄の方言は日本語の流れなので、九州に入れるべきと思う。しかし、さほど、歴史的な立ち位置が複雑な地域であったということが本書の構成をみても分かる。
現在の九州沖縄八県は明治維新の版籍奉還、廃藩置県を経た結果だが、廃藩置県後も各県の離合集散の末が現在の県単位となった。幕藩時代、藩にごとに法も税も異なる。それを明治6年の地租改正で統一を図ったが、各地でもめた。年貢という税制から、土地に課税する制度改革についていけない人々の不満が噴出したからだ。
それら歴史的背景を踏まえておかなければ、県境に拘泥しないとはいえ事業展開は難しい。実際に佐賀県鳥栖市は佐賀県に属しても、隣接する福岡県の住民が通勤し、他県への移動の通過点として、九州各県の意向も尊重しなければならない。佐賀県だけの地区ではないことが分かる。これは鉄道、道路の整備が進み、移動手段も多岐にわたるからだ。空港、新幹線、高速道路、私鉄を含む鉄路の総合的な施策が必須となる。県境を「またぐ」からには、自治体首長は当然のこと、九州電力、JR九州が九州全域を視野に入れてのリーダー・シップを発揮すべきと考える。
本書は平成4年(1992)に刊行されたが、玄洋社に対する評価が厳しい。罵倒に近いものもあり、まだまだ、GHQによる言論弾圧、統制の残滓の影響が残っている時代を感じた。しかし、本書を刊行した葦書房は、同年の三か月後に『玄洋社社史』を復刻再刊している。出版社なりの、言論弾圧に対する抵抗と思うが、果たして著者はこの事に気づかれただろうか。著者の娘婿は前福岡県知事の小川洋氏だが、小川氏は玄洋社をどのように見ておられるのか、知りたいと思った。
尚、本書の扉に、学徒動員で散華した学友に捧げる言葉が出ている。その無念さ、覚悟のほどには、胸をうつものがある。
『威風凛々 烈士 鐘崎三郎』鐘崎三郎顕彰会編、花乱社 令和3年6月28日
・次世代に語り継ぎたい歴史的人物
赤穂浪士の墓碑が並ぶ寺として泉岳寺(東京都港区)は知られる。その泉岳寺に福岡県人の墓もある。まず、赤穂浪士の正伝といわれる『元禄快挙録』を著し、「中央義士会」を設けたジャーナリストの福本日南。「オッペケぺー節」で有名な演劇人・川上音二郎。そして、本書の鐘崎三郎、山崎羔三郎(玄洋社員)である。
鐘崎三郎と関わることになったのは、この泉岳寺山門脇にあるという「殉節三烈士」碑を探しに出かけたことからだった。明治27年(1894)日清戦争が勃発。鐘崎はこの戦役に軍事探偵として従軍したが、清国兵に捕縛され山崎羔三郎、藤崎秀(鹿児島県出身)とともに処刑された。この三人の墓碑が「殉節三烈士」碑である。ところが、当該墓碑は見当たらない。幾度も幾度も探すが、無い。寺に尋ねると檀家墓地にあり、今、参拝はできないという。墓地入り口の鉄扉には頑丈な鎖が巻かれ施錠されていた。
ところが、ある時、檀家墓地に入る事ができた。秋の彼岸、檀家の群れに紛れて「殉節三烈士」碑を拝む事ができたが、見るも無残な姿だった。墓碑は斜めに傾き、雑草に紛れ、頭山満(玄洋社員)題額の顕彰碑は地面に横倒しとなっていた。寺側が、頑として参拝を拒絶したはず。
この「殉節三烈士」の墓碑については拙著『東京の片隅からみた近代日本』に書き綴ったが、それを読んだ読者から電話があった。その方が、鐘崎三郎の三代目を継承される角隆恵さんだった。ここから、青木天満宮(福岡県久留米市城島町)での鐘崎三郎墓前祭に参列し、更には、本書の企画編集に携わることになったのだ。
本書は四部構成、360ページ余の大部だが、『鐘崎三郎伝』(納戸鹿之助著)の復刻も兼ねている。この中で、鐘崎三郎の四代目になる森部眞由美さんの聞き書きが秀逸だ。実母の角隆恵さんの口述を文字起こししたものだが、鐘崎三郎を中心に据えながら、南北朝時代から幕末、明治、大正、昭和の歴史が目前に蘇るかのように纏められている。いわば、躍動感のある郷土史(58ページ。福岡県大川市の若津港など)であり、日本史、アジア史である。当然、筆者の関心事である玄洋社(福岡発祥の自由民権運動団体)の頭山満(56ページ)、男装の女医・玄洋社生みの親・高場乱の人参畑塾(80ページ)についても述べられている。
学校の教科書に記述がない、教わる事も無かった史実だけに、一気に読了するのは困難と思う。さほど、戦後(大東亜戦争、アジア太平洋戦争)世代が、真実の歴史から遠ざけられていたからに他ならない。未来を託す子供たちに遺すべき歴史の基礎となる一書だが、27ページには「若い読者の皆さんへ」として編集委員会の総意が述べられている。是非、編集委員会の願いを汲み取っていただけたら幸いに思う。
尚、211ページには、鎌瀬新平(九州女子、現福岡大学附属若葉高校)、水月哲英(筑紫女学園)、菊竹惇(福岡日日新聞、現西日本新聞社)、進藤喜平太(玄洋社社長、進藤一馬福岡市長の実父)など、郷土福岡ゆかりの方々の名前も見つけることができる。
『大東亜会議の真実』深田裕介著、PHP新書 令和3年6月22日
・大東亜会議に留まらず、更に、真実を押し広げて欲しい
大東亜戦争(アジア太平洋戦争、太平洋戦争)の敗戦から75年余。現代日本では、日本とアメリカが戦争をしたことすら知らない世代が増えている。日本の各都市はアメリカ軍の無差別爆撃で灰燼と帰し、無辜の民が大量殺戮された。沖縄でも虐殺に近い地上戦が繰り広げられ、広島、長崎には大量破壊兵器である原爆が投下された。歴史教科書には、勝者アメリカに都合の悪い事々は、伏せられている。
本書は、その歴史教科書で取り扱わない「大東亜会議」という史実を再検証したもの。著者は『黎明の世紀』(文藝春秋)によって大東亜会議という事実、民族自決の会議があったことを世に投げかけた。更に今回、加筆、資料を追加しての、『大東亜会議の真実』を著した。著者には『炎熱商人』『神鷲商人』など、ビジネスライクの観点から描いたアジアを舞台にした作品がある。本書にもその視点が生きている。
「大東亜会議」は大東亜戦争肯定と見られかねない。しかし、事実は事実として記録されなければならない。欧米や中国共産党はプロパガンダによって捏造の歴史を残そうとする。その反論も試みておかなければ後世に正しく歴史は伝わらない。それだけに、本書は貴重な作品といえる。新書と言う形態は、広く、多くの方に事実を知って欲しいという著者の願いが含まれている。
現代に至るも、世界の各地で止まらない民族紛争、資源を巡る戦いがある。その背景となる歴史を追えば、著者の意図するところが明確になる。それが、本書におけるインドネシアだ。132~133ページの「大東亜会議」の集合写真を見ていただきたい。そこには、インドネシア代表のスカルノの姿は無い。ここに、インドネシアにとって大東亜戦争が「解放」戦争であったと断言できない要因が隠れている。インドネシア独立運動に関わったアジア主義者から見れば、噴飯ものの「大東亜会議」だった。その会議から除外されたスカルノの悔しさ、悲しみを理解され、心を痛められたのは昭和天皇であった。このことは記憶に留めておきたい。(「手を差し出した天皇」186ページ)
尚、アジア主義者の活動は、戦後も継続している。国交樹立交渉、農業支援、産業支援、スポーツ交流と、アジア主義者はアジア諸国の興隆を支援した。「大東亜会議」は大東亜戦争の産物である。アジア主義者は、戦前も戦後も継続してアジアと向き合っている。ここに、大東亜戦争のスローガンとなった「大東亜共栄圏」とアジア主義が似て非なる存在であることがわかるだろう。本書から更に、広く深く真実を掘り下げていただきたいと願う。
『国家社会主義とは何か』杉本延博著、展転社 令和3年6月21日
・日本型社会主義の定着を願う
表題に含まれる「社会主義」という言葉から、多くの方は左派系の本と思うだろう。しかし、7ページの後ろ6行目に権藤成卿の名前を見ることから、社会主義は社会主義でも日本型の社会主義についての論考ということがわかる。その社会主義の一形態としての国家社会主義である。13章からなる本書の随所にも、「日本型」という言葉が意図的に使用されている。極めつけは82ページの「マルクス主義的社会主義のことではむろんなく」という一行だ。社会主義、共産主義、イコール危険思想と字面だけで判断するのではなく、日本型として物事を見なければならない。同時に、資本主義においても、日本型を研究する方が増えてきた。原理原則、日本は折衷型として思想は理解した方が良いと考える。
さて、本書は昭和9年(1934)、奈良県において設立された「大日本国家社会党」掖上支部の活動報告であり、その活動報告手段が「街頭新聞」だ。明治以降、欧米列強のアジア侵略は止まるところを知らず、その毒牙に食い荒らされないため、日本は懸命に西洋近代化を急いだ。同時に、金融を含む欧米の資本主義も導入したが、あまりの急展開に各地で摩擦が起き、取りこぼされる人が出てきた。その摩擦の大きなものが士族の反乱であり、民は娘を海外に「からゆきさん」として「輸出」しなければ生きていけなかった。しかし、一向に社会格差は解消されず、血盟団事件、515事件、226事件を引き起こした。
これらの社会問題の根本に何があるか。それは公平な富の分配がなされなかったからだ。明治維新の目標であった「一君万民、四民平等」という天皇親政が果たされなかったことにある。
国の本は農業である。まず、何といっても、民の食を確保することが為政者の責任だが、それがないがしろにされたことを、「街頭新聞」で世間に訴えたのである。本書はその軌跡であるが、読み進みながら、現今日本の姿に重なる。根本的に、何ら変わりがない。愕然とするばかり。
なぜ、著者はこの「街頭新聞」を世に問うたか。「今だけ、カネだけ、自分だけ」の為政者、官僚、財界人に覚醒を求める為である。本書の内容を、ごく一部の日本国民の意見として流されてはいけない。日々、生きるため、考える時間も無い民の声を代弁し、くみ上げなければならない。皇国の理想は、万民が安心安寧に暮らせること。民主主義を越えた日本型社会主義を地上に実現しなければならないとして、誕生したのが本書である。日本型社会主義の定着を願うばかりだ。
『ウイグル ジェノサイド』ムカイダイス著、ハート出版 令和3年6月15日
・親日の東トルキスタンの実情を知る為に
まず、本書の46ページに示されるアジアの地図を確認していただきたい。そこには、満洲、中国、モンゴル、南モンゴル、東トルキスタン、チベットなど、現代、私達が目にする地図と異なる国々が描かれている。本書の表題に記される「ウイグル」はどこにあるのかといえば、東トルキスタンのことである。しかし、今、東トルキスタンは「新疆ウイグル自治区」として、中国の植民地支配下にある。
2021年(令和3)6月13日、G7サミットが閉幕した。議長国イギリスに集まった主要国の代表らは、「ウイグル」の人権問題を議題とした。東トルキスタンで起きている、重大な人権問題を提起したのだった。従前、中国共産党の侵略を受け、東トルキスタンは石油、石炭、天然ガスという豊富な地下資源を略奪された。それだけにとどまらず、おびただしい回数の核実験場としても利用された。更には、近年、「ハラール臓器」として、ウイグル人の臓器は高値で取引される。豚肉を食べない「清浄」なイスラム教徒の臓器として、ウイグル人の臓器は同じイスラム教徒の国々に好まれるからだ。
海洋進出のみならず、一帯一路政策として、東トルキスタンは中国にとって重要な地域である。そこでは、数百万人の人々が、教育という名の虐待を受けている。特に、女性に対してはレイプ、避妊手術は日常茶飯事。残念なことに、中国共産党の影響下にある日本のマスコミでは一切、これらの残虐な事実は報道されない。わずかに、心ある日本人活動家たちが、日本国民に東トルキスタンの実情を訴求するにとどまっている。ゆえに、G7サミットでの決議内容の意味するものが即座に理解されないかもしれない。果たして、日本の識者、マスコミが世界標準の問題意識に追いつけるか否かは不明だ。そこで、有用なテキストとなりえるのが本書だ。全6章、240ページ余の構成。東トルキスタンの歴史、政治、強制収容所の実態、そして、ウイグル文学についてである。一国の歴史、現在の状況を在日ウイグル人のムカイダンス氏が簡潔にまとめている。なかでも、70ページに記される「ウイグル人の親日と中国共産党の反日教育」は必読。巻末に三浦小太郎氏の解説が付されているので、本書全体の要点が掴める。同時に、関岡英之氏の『防共回廊』についての件は、重要だ。
尚、『中国臓器移植の真実』(野村旗守監修、集広舎)と併せて一読されると、東トルキスタンで起きている虐待の実情が理解できる。世界の情報孤児にならぬよう、日本は中国共産党の蛮行を注視しなければならない。「ならぬものは、なりませぬ!」と注意をするのが、真の隣人、友人関係なのだから。
『中国臓器移植の真実』野村旗守編、SMGネットワーク監修、集広舎
・カネの亡者中国は臓器も売る
時折、街角で「臓器狩り」に抗議する人に遭遇する。無残に切り裂かれた肉体の写真。いったい、何が起きているのか分からない。それもそのはず、日本のマスコミが一切、報道しないからだ。本書は、その「臓器狩り」の真実に迫った内容。
令和2年(2020)6月16日、フジテレビ「特ダネ!」において、「命のリレー」が報道された。これは日本で技能研修生として働く20代の中国人女性が心臓病を患い、愛知県の藤田医科大学病院に入院。人工心臓で、彼女は一命をとりとめた。更に、この女性は、新型コロナウイルスで出入国が制限されるなか、中国が派遣したチャーター機で中国・武漢に帰国、心臓移植手術を受けた。驚くのは、この一人の女性のために、中国側は4つの移植用心臓を用意していたことだ。この間、わずかに二か月ほど。
現代日本では、移植用臓器提供のドナー出現は奇跡。臓器移植を希望する人々は、推定でも数万人に上る。それが、わずか二か月ほどで、一人に4つの心臓が準備できた。単純に人口の比較だけでは説明がつかない。しかし、その奇跡が中国では可能だった。推定ながら、過去、中国では6万から10万の臓器移植手術が行われたという。これこそが、街角で「臓器狩り」に抗議する人が訴求していた秘密である。これらの臓器は、一時、中国で飛躍的に広まった「法輪功」信者のものといわれる。呼吸法によって細胞が活性化されている法輪功信者の臓器は好まれるからという。
更に驚くのは、「ハラール臓器」と言われるもの。これは、豚肉を食べないイスラム教徒の臓器である。この「ハラール臓器」の提供も、中国は群を抜いているという。イスラム教徒である新疆ウイグル自治区のウイグル人の臓器である。この「ハラール臓器」は、同じイスラム教徒のアラブの富豪たちがこぞって求める「清浄」なる臓器だ。しかし、日本でも、中近東でも、欧州でも、臓器の提供を受けた側の国々は、声を発しない。マスコミも報道しない。そのため、世界中の人々は、この中国の蛮行を知らず、中国としても、金儲けのために、何もなかったことにしているのだ。「イスタンブール宣言」という臓器移植ツアーで手術を受けた人の診療を拒否できる事々も、本書で初めて知った。戦慄の事実が次々に識者によって明らかにされていくが、中国で、なぜ、ウイグル人が弾圧されるのか。その背景には、金儲けのための臓器売買がシステム化されていたからだった。食用の家畜の如く、罪もないウイグル人が日々、臓器売買目的で殺されているのだ。
本書の168ページ、韓国の韓熙哲医師による証言が秀逸だ。韓国では報道番組として「生きるために殺す」臓器売買の実態をテレビ放送した。巻末には、中谷元衆議院議員(元防衛大臣)のインタビューも紹介されている。中国の海洋進出、武漢ウイルスだけではない、臓器売買という悪事を繰り返す中国の実態を日本人は知るべきだ。ウイグル、チベット、南モンゴルの人々の人権を守るためにも、日本人はこの事実に声を上げなければならない。
『日中戦争と中国の抗戦』馬場毅著、集広舎 令和3年6月9日
・中国共産党軍に使役される農民たちが、実に哀れ
本書の表題にある「日中戦争」だが、29ページに示される「山東抗日根拠地形勢図」(1940年頃)の青島、徐州、済南、威海衛、天津、塘沽という山東地域での紛争についての記録である。
当初、旧日本軍による残虐な「侵略」戦争の実録かと思いきや、そうではない。複雑怪奇に入り組んだ中国の権力闘争を述べた内容だった。本書の第一部は「山東抗日根拠地と八路軍の発展」、第二部は「山東抗日根拠地の抗戦力強化政策および日本軍の対策」として全九章で構成されている。450ページ余、巻末には人名録、事項録を備える大部の資料集とでもいうべき一書。本書の「はじめに」の10ページに、中国側の資料開示を拒否する件が出ている。著者は入手可能な資料を駆使して本書を記述した。戦争記録として見落としがちな物流、経済、通貨の問題に至るまでを詳細に記録している。本書の強み、価値はここにある。更に、親切なことに、著者は各章に「はじめに」と「おわりに」を記している。このことで、各章の枠組みが頭に入り、熟読の後には、振り返りができるようになっている。
そもそも、日本軍が、なぜ、中国大陸に駐屯したのかは、邦人保護からだった。明治33年(1900)、清国(満洲族政権の中国)が日本を含む欧米列強に宣戦布告をした。いわゆる「北清事変」とも「義和団の変」とも呼ばれる戦争だが、講和条約締結の条件として邦人保護を目的とする日本軍の駐屯となった。そして、満洲を占領し、植民地化するロシアとの日露戦争に勝利したことから南満洲鉄道の守備隊としての関東軍駐屯となった。この歴史認識は必須である。
戦争というものに正義は存在しない。本書を読み込んでも分かるが、主義主張、思想の有無に関係なく、武力を背景にした為政者の権力闘争である。それは、共産党軍であれ、国民党軍であれ、日本軍であれ、何ら変わりはない。「謀略」「寝返り」「裏切り」という単語が随所にみられ、日本と中国の戦争としての日中戦争と一括りにすることに、大きな錯誤が存在している。『朝鮮戦争と日本・台湾「侵略:工作』(江崎道朗著、PHP新書)と並行して読み進むと、共産党軍、国民党軍の背後に蠢くコミンテルンの謀略が、いわゆる「日中戦争」ともいえる。
そんな中、実に哀れなのは、中国の小作農や貧しい階層の人々だ。共産党軍、国民党軍、土匪(ゲリラ)、ゴロツキ、幇(結社)などに恫喝され、搾取され、使役される。日中戦争は日本が英米を中心とする連合国軍に敗れたことで終決。「棚ぼた」勝利でありながら、中国は勝者として日本に歪な歴史を押し付ける。本書は、その歪な歴史認識を覆す資料集である。権力者の中国共産党軍は、小作農、貧民を農兵として駆り出した。その人民の生命を生命とも思わぬ体質が、人民を虫けらの如く踏みつぶした1989年の「天安門事件」へと帰着するのである。
本書の濃密な内容が評価されるには、半世紀、一世紀の年数を要すると考える。故に、本書は後世のために、タイムカプセルに詰め込まねばならない歴史書なのだ。
『からつ塾』 からつ塾運営委員会編著、花書院 令和3年5月30日
・「からつ塾」の道標として
本書は、佐賀県唐津市で開かれている「からつ塾」という民間塾の成り立ち、143回にわたる講演内容をまとめたもの。2部構成、第1章から第11章まで280ページ余に及ぶ重厚な内容。
日々、一章ずつを読み進んだ。16年余の「からつ塾」の歴史を考えれば、速読するのが実に申し訳なく思ったからだ。気に入った箇所には傍線を引き、該当する文章、言葉はノートに書き写していった。深い意味が潜んでいるので、是非とも書き留めておきたい。そんな衝動にかられる。急がず、考え考え、読んだ一書だった。
早速、第1章、24ページにあった「インターネット上に表れる知性は、言葉や論文としては完成されたものであっても、人間としては捨象された表象に過ぎない。」という短くも重い言葉に、考えさせられた。現代、インターネットにおけるSNS(ソーシャル・ネットワーク・システム)上においては、誹謗中傷から殺人事件、自殺を誘発し、社会問題になっている。本来、インターネットは、地球に接近する隕石の情報共有を目的として軍事技術を民間に転用したものだ。世界中の天文学者の熱意があったればこその結果である。それが軍事レベルと同じ「殺人兵器」となっている現実に、インターネットを利用する人々は認知しているのだろうか。その警鐘の意味からも、この言葉が放った真意は深く、重い。
第6章、141ページにあった「対立するものも共存できるようにする精神こそが日本の真の伝統である。」という言葉からは、「右翼の源流」と呼ばれた玄洋社の頭山満を思い出した。頭山の一族には、あの無政府主義者の伊藤野枝がいる。頭山と伊藤との間には交流があったが、多くの方は「右と左が・・・、絶対に信じられない」と口にする。しかし、事実は事実。頭山は伊藤だけではなく、他の無政府主義者、共産党員までをも庇護下に置いた。これこそが伝統的「右翼」と呼ばれる頭山の真骨頂ではないだろうか。ちなみに、筆者も尊敬の念を込めた「頭山満」の名前を無政府主義者の方から聞いた。
一つ、一つ、言葉を追っていくとキリがない。次々に思い起こす事々が湧いて来る。さほど「からつ塾」の講演内容が素晴らしいからだ。
四国にはお遍路さんの為に一キロごとに道標が設けられているという。本書は「からつ塾」の道標の第一本目になる。この世界に人類が存在する限り、「からつ塾」の道標が一本ずつ、増えていくことだろう。
『鄭燗明詩集 抵抗の詩学』鄭燗明著、集広舎 令和3年5月28日
・台湾の「芋っ子」の心の叫び
この詩集を手にし、はたして、どれほどの日本人が、鄭燗明の心の叫びを聞き取る事ができるだろうか。現代の日本人からすれば、温暖で豊かな島国台湾と見ている。その台湾の詩人が発する過激な言葉に、正直、困惑するのではないか。
比喩(メタファー)思考は科学の母といわれる。事実を正面から受け取る際、何かに例えると伝達がしやすく、理解度も高まる。そこから新しい発見が生まれるからだ。詩も比喩によって、言葉に秘められた事実から新しい発見があるはずだ。しかし、その前提として、鄭燗明が体験した台湾での歴史を知識として持っていなければ、言葉の裏に隠された真実は見つからない。
昭和20年(1945)、日本は連合国軍に敗れた。ここから、大陸での中華民国国民党軍、共産党軍の主導権争いの内戦に発展した。追い詰められた国民党軍は、かつての日本の植民地であった台湾に逃げ込み、国民党軍の政府を置いた。更に、大陸からの共産党軍の侵攻を防ぐために、台湾全島に戒厳令を敷き、共産党スパイ摘発に躍起となった。無辜の台湾の民が、どれほど、犠牲になったかは計り知れない。同時に、戒厳令下、言論も厳しく統制された。そもそも、なぜ、医師でもある著者が詩という形態、体裁を取らなければならなかったかといえば、戒厳令による言論弾圧があったからだ。小説、ノンフィクション、エッセイで、様々な表現手段が認められるのは現代日本だけである。この言論弾圧下、いかにして民衆に真実を伝えるかを考える時、残された手段は「詩」であった。
もともと台湾に生まれ育った台湾人にとって、国民党軍が戒厳令を敷いたことは迷惑この上ないことだった。かつて、犬と呼んだ為政者の日本人が居なくなったと思ったら、国民党の豚がやってきた。豚はあたりかまわず、台湾の芋畑を食い荒らした。台湾は、その形がサツマイモに似ていることから、芋と呼ばれる。翻って、台湾人は自身の事を芋と呼ぶ。これは、豚には意味が分からない隠語でもある。その歴史を知れば、この台湾が、いかに苦難の果てに勝ち取った民主化であるかが理解できるだろう。
本詩集は1971年から2018年まで、8つの章に分けられているが、中でも第3章の「芋の歌」は詩人鄭燗明の心の叫びそのものである。凄まじい弾圧を体験してきた者だけに分かる詩だ。民主化を勝ち取った台湾の「芋っ子」にとって、綴られた詩の数々は、検閲を逃れるための術の結晶であり、記録である。
この詩集から何を読み取るか。何を、私たち日本人に警告しているのか、気づいて欲しい。
慰安婦と兵士 煙の中に忍ぶ恋』 山田正行著、集広舎 令和3年5月26日
・戦場慰安婦から、人の本質を教わる
新聞やテレビが伝える、いわゆる「従軍慰安婦問題」とは何なのか。本書を読了して、そんな疑念が沸き起った。従前、私達が理解の範疇に納めていた慰安婦とは、大きく乖離する事々が述べられている。その違いは何なのかと考える。それは、慰安婦を問題にしたがる方々が、「人権」という正義の剣を手にして、高い位置から慰安婦を論じていることだ。著者は「地べた」、いわゆる社会の底辺に生きる人間の視点から慰安婦を説いている。そのことは、権力者によって戦場に引きずり出された兵隊と、その兵隊の相手をするために戦場に向かった慰安婦との人間関係から垣間見える。人権を前面に出した「似非正義」の言葉で慰安婦を切り刻んではいないことを痛切に感じる。
「小説でしか語れない事がある」。これは、なぜ、小説が存在するのかという問いに対する回答だが、別の意味で、市井の人々を社会の蔑視、嘲笑から護るためである。本書には、小説からの引用が多い。そのことに訝る向きもあると思う。しかし、著者は巻末に参考文献を列記し、小説の背景に潜む事実の裏付けを試みた。この誠実な対応に筆者は疑う術を持たない。むしろ、著者の真実を追求する姿勢に感銘を覚える。全ては、「地べた」に生きる人々の生きざま、弱き立場の人々を尊重しているからだ。
全12章の中でも、第3章2節の「乳房効能」は秀逸だ。人は現世に生まれ落ちた瞬間から本能で「生きる」。その生きる術の源は乳房である。男女、洋の東西、身分差などモノともしない強さが乳房にある。人が人として生きる完全なる平等の原点が乳房だ。その原点が生死の境目である戦場にあった。それが慰安婦の乳房であった。戦場における兵隊にとって永遠の女神が慰安婦なのだ。
更に、第4章8節の「勲章もらえますか」は、なんと悲しい話だろうか。「生命」を賭した証は、天皇陛下からいただく「勲章」しかない。兵隊と同じく、戦場に身命を投げ出す慰安婦が「勲章もらえますか」との問いかけを、誰が笑えるだろうか。本書の表題は『兵士と慰安婦』だが、根本的な人の本質を浮き彫りにしたものだ。召集令状で駆り出された兵隊と、貧困から脱却する手段として集められた慰安婦の立場に、毛一筋の違いもない。いずれも、権力者に対し拒否も反抗もできない。実名も、仮名すらも記録に残る事のない「地べた」に生きた人々には、民族や人種を越え、ただ、男と女の関係だけが真実として語り継がれる。
翻って、党員の女子学生たちを「慰安婦」として弄ぶ権力者・毛沢東の横暴に憤りながらも、人間とは、いったい、何なのだと。そう自問自答を繰り返した。
本書は、慰安婦を利権の対象にする風潮に一石を投じた書である。同時に、後世に伝えたい、遺したい、思想書でもある。
『ナクツァン』ナクツァン・ヌロ著、棚瀬慈郎訳、集広舎 令和3年5月25日
・「三峡ダム」の淵源はチベット弾圧から
今や、世界が人権問題の対象とするチベット。本書は、そのチベット遊牧民出身のナクツァン・ヌロによる、中国によって殲滅されたチベット人の歴史、伝統、文化の記録だ。全5章、490ページ余の本書の表紙には、チベット遊牧民の穏やかな昔が描かれている。第1章からページをめくると、天と地の間に生きる遊牧民の日常が広がる。家畜の乳を搾り、バター、ヨーグルトを作り、生きるためだけに一頭の家畜を屠る。チベット仏教の敬虔なる信仰者でもある遊牧民は、家畜を殺すのではなく「(生命を)いただく」という。日本人と同じ、「いただきます」と食事前に唱える死生観に親近感を覚える。しかし、驚くのは、著者の母が若くして亡くなっての葬儀の様子。日本では火葬だが、遊牧民の場合、それは「鳥葬」である。ハゲワシらに死体を食べさせるのだが、一連の葬儀の進め方は知らなかった。それだけに、文化の違いと一言で片づけられない衝撃を受けた。
亡き母の為、著者兄弟は父と共にチベット仏教の聖地、太陽の都ラサへの巡礼の旅に出る。その旅の過酷さに、そこまでして信仰を貫く姿に感銘する。そんなチベット遊牧民の生活が一変したのは、1956年(昭和31)の事だ。東西冷戦の時代、ソ連でフルシチョフが前政権のスターリン批判を始めハンガリー動乱が起きる。建国間もない中華人民共和国の主席・毛沢東は慌てた。「鳴放運動」で人民の不満を解消しようとしたが、逆に「反右派闘争」として批判者を弾圧した。更に、周恩来によってモンゴル、ウイグル、カザフ、チベットなどの民族弾圧へと拡大する。
中国軍はチベット仏教の僧院破壊に加え、僧侶や仏教徒の殲滅に奔走した。内モンゴルの騎兵隊までが駆り出された。この時、家畜を含むチベット人の財産略奪が行われた。老若男女の別なく、虫けらでも叩きつぶすかのように殺す。投降しても家畜小屋以下の牢獄に送り、そこでも人々は日々死んでいく。進むも地獄、退くも地獄。万単位でしか表現できないチベット人の殺戮が、中国軍によって粛々と行われた。
そんな中国軍の圧政下、著者ナクツァン・ヌロは生き抜いた。食糧配給が途絶し、人々は餓死する。それでも、野生動物を捕まえて食べる。その逞しさには驚愕を越えて称賛しかない。ナクツァン・ヌロが生き残ったからこそ、中国軍の蛮行、毛沢東、周恩来の悪行を知りえたのだから。今や、崩壊の危機にさらされている三峡ダムは、チベット人が逃げ込んだ森林を中国軍が伐採したことで誕生した。この森を消滅させたことが黄河流域での大洪水につながる。そこで作られたのが三峡ダムなのだ。
本書は、チベット人であれば誰もが知っている話であり、所持する一冊といわれる。チベット、ウイグル、内モンゴルの人権問題に関心のある方は必読の書といえる。
もし、可能であれば、著者が固く口を閉ざす「文化大革命」の証言も読んでみたい。人類共通の「業」として、後世に伝えて欲しいからだ。
『絹と十字架』松尾龍之介著、弦書房 令和3年5月16日
・西吉兵衛、こんな南蛮通詞がいたとは・・・
「鎖国」という言葉を生み出したオランダ通詞の志筑忠雄。その存在を知ったのは、著者の『長崎蘭学の巨人 志筑忠雄とその時代』(弦書房、2007)からだった。日常、何の意識もせずに使っている言葉の数々、文法用語、物理学の用語など、それらが志筑の労作であったと知った時の驚き。言葉に深い意味があり、長い歴史が潜んでいることに「目からウロコ」だった。以降、著者の新作が出るのを楽しみにしている。
今回、その楽しみの新刊は、南蛮通詞(通訳)の西吉兵衛である。南蛮と聞くと、東南アジアからやってくるヨーロッパ人という印象がある。すでに、この時点で「南蛮」という言葉の定義が曖昧であることに気づく。本書は、その曖昧なままで理解を進めてきた歴史を確定するための一書。読み進みながら、歴史年表の知識しか持ちえなかった事を恥じ入った次第。
その最たるものが、一五四九年のザビエル来日からポルトガル人追放、更に、ポルトガル特使派遣の百年間だ。徳川幕府の「鎖国」政策によって、ある日を限りに一切、ポルトガル人との接触は無かった・・・と思っていた。ところが、事実は、そうではない。実に、国家の威信と貿易の実利を天秤にかけて、丁々発止のやり取りが徳川幕府とポルトガルとの間に続けられていたのだ。その狭間、為政者の意向で行われるキリシタンや宣教師らへの拷問。その手口も、温泉の熱湯を傷口にかける、糞尿の桶に首を押し付けるなど、とても人間の仕業とは思えない。そんなキリシタンや宣教師が苦痛に喘ぐ中、幕府とポルトガルとの間にあって、仲介の労をとる通詞は、ある意味、現代の外交官にも匹敵する。その代表が本書の主人公西吉兵衛だ。
全四部、二十三章、三百ページにわたる本書の端々に登場する通詞の重要性を見逃してはならない。更には、西吉兵衛が、南蛮医学を学び、継承した功績も高く評価されるべきと考える。
語学の天才とオランダ人が高く評価する志筑忠雄を著者に教えられたが、今回も西吉兵衛という南蛮通詞の存在を教えられた。歴史の襞に隠れた次の人物は誰だろうか。今から、ワクワクしながら、待ち焦がれることにしよう。
『知の噴火口』大嶋仁著、福岡ペン倶楽部 令和3年5月4日
・不思議なご縁の記念すべき一書だが、祈念すべき一書でもある
副題に「九州の思想をたどる」と記された本書は、150ページ余、全6章で構成されている。その目次を追ってみても、実に、日本の近代に影響を及ぼした九州の人、団体、事件が並んでいる。いずれも興味深い。一つの項目がおよそ2ページに納まっている。故に、すぐさま読了できるかといえば、さにあらず。実に、一言一句を玩味し、咀嚼しなければ、先に進めない。
まず、序章の7「三浦梅園」が手ごわい。しかし、発行所である「福岡ペン倶楽部」で著者の講演を拝聴した事から、梅園が説く「反観合一」という言葉が腑に落ちた。福澤諭吉の「矛盾」した論に理解しがたいものがあったが、梅園の影響を受けたと思える福澤だけに、「一身二生」なのだと。
第1章の10「浦上天主堂と原爆投下」では、「国家を聖とする人間」、「国家を超えたものを聖とする人間」の違いを知る事ができた。私事ながら、筆者は若き日、ドイツ(当時は西ドイツ)を旅している時、アメリカ軍の爆撃被害を受けた教会堂を幾つも目にした。攻守の双方が同じキリスト教徒でありながら、このような仕業を簡単にやってのける事実に驚いた。日本人学生と議論を続けたのを思い出す。更には、現在の東京九段にある靖国神社である。境内には、飲食の売店、土産物店、ベンチでは食事をする人、読書する人がいる。側には、「一杯の水」に苦しんだ兵士の碑、モニュメントがありながら。
第2章の5には帆足万里が登場し、なんといっても、志筑忠雄の名前があるのが、実に嬉しい。語学の天才とオランダ人が絶賛するオランダ通詞のことを、現代日本でどれほどの人が知っているだろうか。「名詞」「動詞」という文法用語を生み出し、今では日常に使っている「真空」という言葉も志筑が考えた。明治以降の日本が急速な西洋近代化を図れたのも、この志筑がいたればこそなのだが・・・。
序章の「日本思想史と九州」、第1章の「聖と俗 九州の宗教思想は熱い」、第2章「近代科学への道 九州は科学思想の先進地帯」、第3章「乱と役 反権力の闘いは九州から起こる」、第4章「権力と反権力 社会思想をはばたかせる九州人」、第5章「新しい社会に向けて 九州で生まれた近代ジャーナリズム」と続く。西日本新聞に20年ほど前に連載され、刊行もされたが絶版。その復刻版だけに、読めば、読むほど、深く、速読するのが惜しい。
蛇足ながら、「初版あとがき」を読み、懐かしい方の名前があった。山で遭難し亡くなられた野中彰久氏である。筆者が西日本新聞に書評を寄稿している時の担当であった。さらに、これはもう、驚きでしかないが、「復刻版あとがき」での川崎隆生氏だ。10年ほど前、東京で会ったのが最初だった。その川崎氏が、「福岡ペン倶楽部」での著者の講演終了からわずか一週間。帰らぬ人となった。本書は、実に、記念すべき一書であり、祈念すべき一書となったのだった。
『拉致問題と日朝関係』村主道美著、集広舎 令和3年4月15日
・義憤に燃える著者の執念が
本書は北朝鮮による日本人拉致被害についての論考。3部構成480ページ弱、1ページ平均700文字という大部だけに、読み下すことに躊躇を覚える。しかし、拉致問題についての3冊を1冊にまとめたと思えば良い。
まず、日本人の拉致被害が広く認識されたのは、昭和62年(1987)11月29日の大韓航空機爆破事件だった。この事件では、自殺に失敗した北朝鮮の工作員金賢姫の自白から、日本人拉致被害者の存在が明らかになった。平成14年(2002)9月の小泉純一郎首相(当時)の訪朝により、日本人拉致被害者5名が帰国。このことで、北朝鮮による組織的犯罪が確定した。
しかし、この一連の拉致事件の背景に浮かび上がるのは、日本の政界、官界、財界の「今だけ、カネだけ、自分だけ」という無責任体質だ。加えれば、今や「進歩的知識人」と揶揄される大学教員、評論家の無関心ぶり。これらの政官財、進歩的知識人に対し、激しい怒りを覚える。まさに、「国交正常化」「国益」という美名に酔いしれる売国奴集団。そのごく一部の名前を記せば、政界では金丸信、村山富一、土井たか子、官界では外務省の阿南惟茂、槙田邦彦がいる。特に、槙田などは「(拉致された)たった十人のことで、国交正常化が止まっていいのか」と発言。国賊の何者でもない。(175ページ)この妄言ともとれる発言の裏付けは「児戯としての外交論」(188ページ)に詳しいが、稚拙な外交の背後に外務省チャイナ・スクールの存在がある。対中外交でのポイントを稼ぐことで外務省の官僚は自己の出世に利用するのである。
無知な与野党の国会議員、強欲な上級国民の外務官僚、対中ビジネスを促進したい財界人。これら三悪の巨魁がタッグを組んで権力を乱用した結果、北朝鮮による日本人拉致被害者救出を阻害したのだ。この劣化した日本の現実は政官財だけではなく、警察、自衛隊、海上保安庁など、国家国民を保護すべき組織までが「機能不全」に陥っていることに、愕然とする。
けれども、最も問題なのは日本国民ではないか。マスコミ報道に疑問を懐かず、日々、自身が幸せに過ごすことができればヨシとする風潮。「人権」「人道」という「正義の剣」を振りかざしながら、拉致被害者の「人権」は無視し、北朝鮮への「人道」支援をとの矛盾を口にする。
最終ページ最終行の「人権の革命的改善は、市場経済になっても、改革開放によっても、実現しないことは既に西側諸国との国交正常化、改革開放以後の中国の例が示している。全体主義国はいかに社会の民主化要求を封印するかを学び始めている」という著者の言葉は、ミャンマー、香港の現実に恐ろしいほど、ピタリと当て嵌まる。
本書は拉致問題に特化した一冊だが、どの章、どのページから読み進んでも問題点が要約され、各部の最終には引用したマスコミ媒体、文献、発言の事実が確認できるようになっている。拉致問題から失敗と成功を学ぶことは多い。マスコミ関係者、研究者にとって必携の一冊になるだろう。
『3つの用意』福永博建築研究所著、海鳥社 令和3年3月31日
・道義国家日本の建設手段としての3つの用意
本書の「3つ」の用意という表題、著したのが建築研究所ということから、建築設計におけるノウハウ本と思われる方が多いのではないだろうか。しかし、本書における「3つ」とは、1・田んぼで電気をつくる、2・マンションを無料で建て替える、3・シルバータウンをつくるという3つの目的のことだ。
田んぼで電気をつくることについては、同研究所が刊行しておる『田んぼの発電所』(海鳥社)に詳しいが、耕作地である田んぼを有効利用し、その上面に太陽光パネルを張り巡らせて発電、売電するという仕組み。農家の現金収入につなげる目的がある。この田んぼでの太陽光発電が可能ならば、側溝での小型水力発電、小型風力発電、さらには里山の間伐材をチップにしての火力発電も可能だ。売電だけではなく、自家消費、温室栽培の暖房、電気自動車への充電などもできる。特に、過疎地ではガソリンスタンド不足が懸念されるだけに、電気自動車、果ては電気トラクターも考えても良いのではと思う。
マンションを無料で建て替えるという目的は、大阪の千里ニュータウンの老朽化に伴う建て替えが容易に進まない現状を考えても、有効な手段と考える。この建て替え時、CLT(クロス・ラミネイティッド・ティンパー)という異なる木材を張り合わせた建材を利用すれば、国内の山林資源の再利用が可能になる。海外では木造高層ビルが建設されており、このことも視野に入れての建て替えを進めたらオモシロイと思った。
シルバータウンをつくるにおいては、すでにモデルケースがある。ゴルフ場、テニスコート、温泉、医療施設を併設したものだが、有機野菜を育てるハウスがあれば良いだろうなと思った。更には、昨今のコロナ禍で郊外を求める目的からもシルバータウンは有用だ。ただ、リモート・ワークのためのインターネット環境を整備しなければならないだろう。電気のコンセントのように、各戸建て住宅に有線でのインターネットを敷設すればすむのではないか。できれば、テレビ画面がパソコン画面に転用できれば、高齢者でも操作は簡単ではないだろうか。
と、様々な構想が「3つの用意」から膨らむ。一極集中を緩和することで、資本主義の過度な進行によって生じた資源の無駄遣いを減らすことができる。解決しなければならない問題は多々あるが、少しでも改善することで自国のみならず、他国への支援に展開するものと考える。このことは日本を道義国家へと導く道標になるものと確信する。
『里山資本主義』藻谷浩介、NHK広島取材班著、角川書店 令和3年3月29日
・地産地消の有用性を証明
本書を手にした背景は、『3つの用意』(福永博建築研究所)の内容を更に深く理解したいと思ってだった。田んぼで発電するなどを提唱しているが、手段は異なるものの、本書の目的と同じ。その手段の相違を確認したいと思ったからだった。
本書は第1章から第5章で構成されているが、その第1章に岡山県真庭市で行われている木材チップでの発電が紹介されていた。国土のおよそ7割が山林という日本。それでいて「安い」という理由から木材を輸入し、その結果、住宅建材を目的として植林したスギやヒノキの山林が荒地となっている。田畑と同じく、山林も手入れをしなければ荒廃するばかり。みすみす、大切な資源を放置しているというのが現実だ。その木材をチップにして、エネルギーに転換する。万が一の災害や海峡封鎖による石油の輸入が停止された場合も回避できる。いわば、エネルギーの地産地消である。
さらに、第2章では、異なる木材を張り合わせて建築資材に利用できることに驚く。それも一般の戸建て住宅ではなく、ビルまでできてしまうことに驚愕する。第1章、第2章だけでも、一読に値する。
第3章は「グローバル経済からの奴隷解放」という衝撃的なタイトルだが、やみくもにグローバル化を推奨、称賛してきた向きには「自国第一主義」に捉えるかもしれない。しかし、そうではない。右肩上がりの経済成長ではなく、人があってこその経済であり、その人の生活における充足感を高めるための内容だ。いわば、数値のみで評価する経済至上主義ではなく、数値に表れない満足度をという提案である。このことは、コロナ禍、目に見えないウイルスによって、経済基盤がいかに脆弱であるかを認識されたのではないだろうか。拡大一途の経済成長過程で、他国から資源を輸入し、廃棄することは他国への「侵略」であり、グローバル経済とはいわない。
本書を読み進みながら疑問に思うのは、里山でのトイレはどうなっているのかということだった。都会から里山に移り住みたがらない理由の一つに、水洗トイレではないからという意見がある。さらに、インターネットなどの通信回線の不備もある。里山という地域だけの有線、テレビ画面がそのままパソコン画面に転用できれば、高齢者といえども用意に里山暮らしを楽しめるのではと思った。いずれにしても、本書が2014年の新書大賞を受賞した理由がよく分かる。地産地消の有用性を証明しているからだ。
尚、木材をエネルギーとして利用しているオーストリアが紹介されていた。地下資源に恵まれない国との記述があるが、ウィーン郊外には油田があり、オーストリアは産油国である。隣国のナチス・ドイツがオーストリアを併合した背景には、戦争遂行に不可欠な油田を確保する目的があったからだ。
『月形洗蔵』力武豊隆著、のぶ工房 令和3年3月28日
・従前の維新史の誤解を解く一書
本書は筑前(福岡藩)勤皇党の月形洗蔵を中心に据えた維新史だ。従来、司馬遼太郎の小説『竜馬がゆく』の印象が強いため、薩長同盟は坂本龍馬が一人で為したものと信じられている。しかし、龍馬以前に薩摩と長州との連携は筑前勤皇党によって成し遂げられていた。その中心をなすのが月形洗蔵だが、筑前福岡藩の内訌(内紛)で、闇に封じられた洗蔵による薩長連合の経緯を述べたもの。
月形洗蔵については、「辛酉の獄」において幽閉された際の石碑、菩提寺の少林寺に遺る月形家三代の墓碑、月形家住居跡碑が遺っている。しかしながら、いったい月形が何を成し遂げたのか、どのような人物であったのかは、輪郭程度でしかわからない。長州藩の高杉晋作、薩摩藩の西郷隆盛という両雄を仲介し、薩長和解の労をとったにも関わらずである。
著者は、およそ10年の歳月を要し、全8章、人名録などを付して300ページに及ぶ力作を完結させた。事実の裏付けのため、地道に一次資料を読み説いていった姿勢には敬服する。今でこそ、「維新の策源地・太宰府」と言われるが、それ以前は、維新史の中心は京都であり、薩摩に長州だった。「学問の神様」太宰府天満宮という先入観が強いからか、維新史にまで関心が向かなかったのは致しかたない。更には、月形洗蔵らが筑前福岡藩の内訌である「乙丑の獄」で壊滅的打撃を受けたのも大きい。それら陰に隠れた部分が、ようやくにして陽の目をみるに至った。
しかしながら、なぜ、今まで月形洗蔵の確たる評伝が存在しなかったのか。単なる、一地方史の人ととらえられていたのか。それとも、藩主の黒田長溥に遠慮したのか、いずれかは分からない。従前のフィクションであれ、維新史であれ、本書を熟読して理解をさらに進めなければと思うが、ただただ、著者の努力に感謝するのみ。
尚、薩長連合は岩国藩主の吉川経幹が早くから進めていたとの話がある。本書を読む限り、長州藩主に対する薩長和解工作の説得の使者であったと見るべきだろう。
『戦争と農業』藤原辰史著、インターナショナル新書 令和3年3月24日
・物事は、両刃の剣
読み始めて早々、大きな関心を懐いたのが太平洋の島々の争奪戦だった。従来、鯨油を目的とする捕鯨船の停泊地としか見ていなかった。しかし、島に堆積された海鳥の化石化したフンが農作物を育てるチッソ、リンを含んでいる。それを獲得できることが自国の農産物の収穫を増大させることにつながることから、諸国が争奪戦を繰り広げていた。そう考えると、尖閣諸島、南沙諸島を中国共産党が求める背景に、食糧増産につなげたい目論見が見えた気がする。
本書は、この農業における肥料の問題から、機械化、農薬、品種改良にまで及んだ論説で構成されている。トラクターは戦車に、化学肥料は火薬に、農薬が毒ガスに転用され、農業と軍事とが両刃の剣の関係であることがわかる。要は、用いる人間、権力者が農業に使うか、戦争に使うかの腹一つである。人間を飢餓から救うべく開発された物が、人間を殺戮する道具になった歴史に人間の愚かしさを見る。
もっと、おぞましいのは、戦争における兵糧攻めである。物流ルートを封鎖し、敵国の婦女子に至るまでを殲滅させるというもの。大量破壊兵器を使用せずとも、食糧の供給ルートを遮断すれば容易であり、現場を見ずして殺戮することができる。
大量に、効率的に動植物を育てたいという欲望から品種改良が進んだが、これが狂牛病、鳥インフルエンザというパンデミックを引き起こした。現代日本における食糧廃棄率は30%を超えるというが、そのことがパンデミックの一因というのも皮肉なもの。フードバンクなど組織的活動はあるが、庶民の意識改革が進まない限り、今後も、様々な食物連鎖にも似た危機が人間を襲うだろう。
まず諸問題への対処として、大量生産、大量消費における食物廃棄率を下げる工夫、意識改革だろう。次に、日本の自治体が、食糧自給率を上げる事。つまり、地産地消だが、それには、地方への移住は欠かせない。政府主導の地方創成から地域主導の地方創成である。コロナ禍の今、足元を見つめ直す良い時期だが、本書はそのための参考書である。
惜しむらくは、スターリンのウクライナでの食糧徴発で400万人が餓死したこと。中国国民党が黄河を決壊させて100万人ともいわれる餓死者を出し、中国人難民に日本陸軍が食糧支援をしたことなども述べて欲しかった。
改・姫田小夏著『ポストコロナと中国の世界観』集広舎 令和3年4月号『月間日本』掲載
本書は、上海と北京で日本人向けビジネス雑誌を創刊した姫田小夏氏のレポートである。
レポートとはいえ、中国の事情を紹介しながらも、日本の危機感喪失の実態を諸々指摘する。その一つが、マスクの不足。2011年の東日本大震災では、マスクと防護服は必須だった。それにも関わらず、新型コロナウイルスの発生においてマスクに防護服が大幅に不足した。生産拠点を中国に移転したままが要因だが、この事は悔やんでも悔やみきれない。緊急事態において機能不全に陥る原因を幾つも気づかされた。
新型コロナウイルス発生後、世界は中国バッシングに集中し、怒りの矛先は世界保健機関(WHO)にも向いた。テドロス事務局長は中国擁護ともとられる発言に終始し、更なる疑惑を増加させた。しかし、半世紀以上に渡り中国からの医療支援を受けたアフリカ諸国として、テドロス氏は当たり障りのない発言しか許されなかったのだ。平常、日本のマスコミが報じない中国とアフリカの関係を著者は見事に暴いてみせた。
では、肝心の日本はと考えるヒントは、第7章の「アジアで起きる地殻変動」である。インドと台湾の関係強化の仲介が、一つの展望として残されている。
『田んぼの発電所』福永博建築研究所、海鳥社 令和3年3月8日
・海峡封鎖に備えて、地産地消のエネルギーを
明治元年(1868)からおよそ100年、日本は戦争の渦中にあった。日清戦争(明治27年~28年、1894~95)、日露戦争(明治37年~38年、1904~05)は、国家(国土、国民、主権)を防衛するための戦いだった。しかし、大正3年(1914)に起きた世界大戦(第一次)、大正6年(1917)のシベリア出兵、そして、昭和16年(1941)の第二次世界大戦(大東亜戦争、太平洋戦争、アジア・太平洋戦争)を俯瞰すると、経済を主軸とする戦いであった。
この第二次世界大戦は、日本やドイツの軍国主義が引き起こしたといわれる。しかし、その日本やドイツが敗戦しても、平和の時代は訪れなかった。昭和25年(1950)には朝鮮戦争、昭和40年(1965)にはベトナム戦争が起きた。日本は間接的にこれらの戦争に関係していた。そのベトナム戦争が終決したのは昭和50年(1975)のことだった。大義名分は資本主義と共産主義の思想の戦いといわれたが、資源確保、及びその資源を安全に流通させるための戦争だった。
日本は、石油、ガス、電気は欠かすことができない。ホルムズ海峡、マラッカ海峡を封鎖されれば、資源は届かない。なんとかしなければ・・・。そこで、著者は冷静に日本の自立の道を考えた。その日本の環境を振り返れば、資源を得られる場所がある。それが「田んぼ」だった。通常、田んぼは稲を育て、食の基本となる米を収穫する場だ。米を収穫した後、麦を植える農家もある。しかしながら、海外から安い農産物が輸入できるようになると、田んぼだけの収益だけでは、農家は生活できない。そこで、現金を得るために出稼ぎに行く。何か、現金を得る術を生みださなければ・・・。そこで考えられたのが「田んぼの発電所」だった。稲を育てながら発電をし、その電気を現金に換えるというもの。
食糧の自給、電力の自給を図る事で他国を間接的に「侵略」しなくとも良いようにとの考えが本書の根底にある。電力の安定供給という課題は残されているが、想定可能な実験は進めておくべきと考える。新型コロナ・ウイルスの発生ではマスク、防護服が入手できなかった。危機管理としての自給自足、地産地消の考えが無かったからだ。現在の日本経済の下支えとしての「田んぼ発電所」の電気供給量ははるかに少ない。しかし、機能不全に陥る前に、備える手段として考えておく必要はある。
常夏のハワイでは太陽光発電のエネルギーを電気自動車に利用している。「田んぼ発電所」のエネルギーも電気自動車に供給する日が近いかもしれない。特に、過疎地ではガソリンスタンドが消滅しているだけに、「田んぼ発電所」の電気を電気自動車に利用すれば良いのではと考える。
以上
『ブレグジット狂騒曲』ブレイディ・みかこ著、弦書房 令和3年3月5日
・「経済政策でも人は死ぬ」という現実
本冊子は、2017年8月19日に福岡ユネスコ協会で開かれた講演会「英国のいま、そして日本は?」の講演録である。
まず、表題のブレグジットという言葉に馴染みがないが、Britain(英国)と Exit(離脱)という言葉を組み合わせた造語。つまり、イギリスのEU(ヨーロッパ連合)離脱問題を論じる際に誕生した言葉である。このイギリスのEU離脱については、日本のテレビニュースでも盛んに報道され、在英日本企業の英国離れなど、経済的な損失を中心に語られることが多かった。しかし、なぜ、イギリスが離脱を選択したのか。国民投票における結果、そこに至る過程を述べたものが本冊子である。
著者のブレイディ・みかこさんは、福岡市出身。地元の著名な高校を卒業したものの、進学せずに働き、ロック好きが高じてイギリスで働き、定住することに。この経緯は著者の『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』に詳しい。さらには、グローバル化、多様性社会をと叫ばれる昨今だが、その先駆者であるイギリスではEUに加盟した結果として様々な障害が発生した。ブレイディ・みかこさんの言葉ではないが、「多様性は地雷原を進むがごとく」だ。
本題のイギリスのEU離脱の革新的な問題は、「移民制限のほうが単一市場に残ることより重要」という意見と「移民制限より単一市場に残るほうが大事」という主張との対立だった。移民を受け入れ、多文化共生を体験したイギリスでは、様々な文化摩擦が各地域で起きた。もともと、貴族を抱える階級社会のイギリスだが、そこに民族差別、階級差別が加わり、経済格差も大きい。上下社会であり、上下社会を維持するイギリスに異種が混在するとどうなるか。国柄を取るか、経済を取るかの、究極の選択がイギリスのEU離脱の背景だった。
巻末に質疑応答の箇所も記されていたが、その中で感心したのが資格制度だった。イギリスで保育士の資格を取得したブレイディ・みかこさんだが、職務に関する知識、経験だけではなく、マクロ(なぜなのか?背景は何なのか?など、政治、経済、法律に至るまでを理解する)についても必須となっていることだった。
このことは、「経済政策でも人は死ぬのです」という言葉に表れている。現場で働く保育士といえども、社会が分からなければ、社会全体の問題解決につながらないということだ。
冒頭、日本の識者たちが、イギリスのEU離脱とトランプ・アメリカ大統領誕生の背景を「グローバル化と反グローバル化」で捉えて論評していたが、それは違うとブレイディ・みかこさんは述べる。このことを、具体的に支持者の階層をもって解説していた。このことも、イギリスにおける資格制度のマクロ、ミクロの視点を持つという過程の相違であると思った。同時に、ブレイディ・みかこさんの著書が支持される背景を垣間見た気がした。
以上
『五人の庄屋の物語』家庭読本編纂会編、明成社 令和3年3月2日
・後世に伝えたい物語
小学生の副読本として作成された一冊。「五人の庄屋」「青の洞門」「佐吉と自動織機」「夕日に映えた柿の色」「通潤橋」「稲むらの火」の6つの物語が収められている。いずれの話も、どこかで一度は読んだ記憶のあるものばかり。
しかし、今回、改めて読み返してみて、これは是非とも、後世に遺さなければならない話と思った。大東亜戦争(太平洋戦争、アジア・太平洋戦争)敗戦後、占領軍の支配下を経て、物質的な充足を満たしたものの、「何か」不足を感じる。それは、生命には限りがあり、人生の目的を果たすために現世があることを教えていないことだ。試験で良い点数を取り、良い学校に進学し、良い企業に就職して、良い待遇を受ける。これが、敗戦後の日本社会の成功物語だった。
ところが、昔の日本人は「世の為、人の為、国の為」として、公に努める人々を物語として伝えてきた。戦後の日本において、家族制度を失い、先人の遺業を語る老人たちが家庭にいない。道徳教育も含めて、子供たちに物語をしてくれる家族がいない。その代役として、本書は実によい教育のお手本ではないか。他者に勧めたくなる内容だ。
子供でも読めるようにフリガナを付し、難解な単語には補足がつけられている。さらには、挿絵は西島伊佐雄。大人が読んでも、十二分に楽しめ、感動する。
本書の表題の脇に「アフガニスタン かんがい事業に生きる」と記されている。アフガニスタンで銃弾に倒れた医師・中村哲さんのことだが、現代においても、カンボジアで地雷撤去活動を継続される大谷賢二氏、ミャンマーで部族間対立を収め、旧日本兵の遺骨収集を続けられる井本勝幸氏、ミャンマーで医療活動を続ける名知仁子氏がいる。その前に、インドの砂漠を緑に変えた杉山龍丸さんの偉業も広く、後世に伝えたい。
以上
『人類の敵』掛谷英紀著、集広舎 令和3年2月25日
・ビッグデータから見える「左翼」への傾向と対策
本書の著者は、筑波大学でシステム情報系の准教授を務めるメディア工学の専門家。『人類の敵』という表題、帯のバイデン大統領、習近平国家主席の顔写真から、新型コロナウイルス対策の関係書と思ってしまう。しかし、さにあらず。この両者が今後、世界に引き起こす危険情勢の分析書である。
本書は、第1章から第4章までを24節に分類し、「左翼」「左傾化」「中国共産党」というキーワードで270ページにわたって、危険性を警告する。第1章の「左翼を理解する」は、日本および世界のマスコミの「なんか、おかしい」を見事に炙り出している。それもビッグデータと呼ばれるインターネット上を浮遊する言葉を集約して解析したものだ。ある意味、「左翼」の大好きな科学の分野でもある。この章からは、マスコミを支配する左翼エリートの手法、左翼エリートを論破する手法までが述べられる。
第2章においては、左翼エリートの巣窟である大学の分析が、実に興味深い。菅政権になって起きた「日本学術会議」の任命問題が、いかに左翼学者のワガママであるかがデータを基に記される。直截に言えば、特権階級の住人が左翼エリートである。革命における階級闘争では真っ先に討伐されなければならない輩なのだ。菅総理も、このデータを基に答弁していれば、野党の質疑を片っ端から論破していたのではないか。
第3章では、左翼の思想が人間社会の破壊しか考えていない悪魔の思想であることが見えてくる。簡単に言えば、宗教の否定でも、科学の尊重でもなく、ナルシストである。それも、自身が全知全能の神であると信じる宗教団体の熱烈信者である。ただ、「左翼」のことだけではなく、自集団勝手の「右翼」にも「似た者同士」として著者が評している点もオモシロイ。
そして、本書の肝ともいうべきものが第4章の「中国共産党とどう戦うか」である。世界の政治家たちが無法国家中国を国際社会に取り込めば国際ルールに従い、民主化するものと判断したのが間違いの始まりだった。天安門事件での反省もなく、事件そのものも無かった事にし、軍事大国化して他国を侵略、経済も侵略して平気。批判すれば逆切れして反論するのみ。ちょうど筆者がこの一文を書き進んでいる時、バイデン大統領がウイグル、チベット、内モンゴル、台湾は中国の統一過程における内政であるとして、何ら干渉はしないと演説した。CNNはこの箇所はカットして報じた。このことで、日本の著名なニュース解説者は、バイデンは人権問題を憂慮していると真逆のことを述べた。日本のマスコミ報道が、いかに偏向しているかの具体例である。
この日本に迫りくる危機、策略に気づいて欲しいと、本書は訴える。人類の敵に対峙し、回避するためにも、本書を参考にして欲しい。
以上
『今読めない読みたい本』出久根達郎著、ポプラ社 令和3年1月27日
・本は時代の証人である
いつしか、昭和という時代がノスタルジーの世界になった。貧しかった。とにかく、貧しかった。普段、静かな男が、突如、酒を飲んで狂暴になる。戦場での過酷な場面。取り戻すことのできない自身の人生。誰もが、抑えに抑えていた感情が爆発するのが、安酒を飲んだ瞬間だった。あんな、時代の何が良かったのか・・・。しかし、貧しかったけれどあの頃は良かったと、本書を読んで思ってしまうのは、なぜだろうか。
1部には49本、2部には19本の本にまつわるエッセイが収録されている。その中の「勤労中学生」は夜間中学生の生活記録である『電灯のある教室』という本から引用した内容だ。義務教育でありながら、夜間でなければ中学校に通えない青少年がいたことを知る。更には、昨今、不登校が問題になっているが昭和31年(1956)当時、長期欠席生徒数が全国に13万人もいたことが報告されている。親の病気や戦争による家庭崩壊から学校に通えないというのが、その半数以上を占めている。
そうかと思えば、「連呼」というエッセイでは、NHKラジオのアナウンサーであった和田信賢が、突如入ってきた大本営発表のニュースに「軍艦マーチ」を使った裏話が紹介されている。結果、筆者が通っていた保育園の近くには米軍のハウスがあり、米軍兵士の子供達に通せんぼをされていじめられた。親達からは決して逆らってはいけないと強く諭されていた覚えがある。何も悪いことをしていなくても、子供ながらに戦争に負けるとは惨めなことであると思った。朝鮮戦争後の板付基地(現在の福岡国際空港)周辺の、我が物顔で飛び回る米軍機には敵わなかった。金網の外から窺う米軍住宅は豊かさの象徴だった。
70編弱の本にまつわるエッセイが収められているが、「なにくそ あとがきにかえて」に紹介してある昭和三十二年の映画「つづり方兄妹」は戦後の貧困の象徴のようなものである。幼い頃、白黒テレビでこの映画を見た覚えがあるだけに、昭和三十年代を貧しいけれども希望に満ちた日々であったという風に受け取られるのには抵抗がある。そんな鬱陶しい話は「ごめん!」と思う向きには、「司馬さんの蔵書」という司馬遼太郎の執筆に関する参考文献の話は一読に値すると思う。
出久根達郎氏(1944~、昭和19~、直木賞受賞作家)の「本は時代の証人である」という言葉に強く感じ入った。しかしながら、インターネットに寄稿した書評も、いつかは「時代の一証人」になるのだろうか・・・と思った。
以上

『魔群の通過』山田風太郎著、ちくま文庫 ・水戸藩の骨肉の争いを描いた物語 令和3年1月10日
・水戸藩の骨肉の争いを描いた物語
本作品は幕末の水戸藩を舞台にした天狗党(尊王攘夷派)の顛末を描いた物語である。この小説を読む前、吉村昭の『天狗争乱』を読了したが、同じ天狗党を扱った内容でありながら、読みやすさと印象は大きく分かれる。
吉村昭の場合は膨大な文献資料から事件を忠実に描いている。山田風太郎の場合は事件の渦中から、少しばかり離れた位置に立って、物語風に描いている。人情の機微の絶妙さとしては、山田風太郎に軍配をあげたい。山田は資料を渉猟しながらも実際に天狗党たちが通過した断崖絶壁の道も歩いている。地の気、風の音、広大な風景は、やはり、現地を訪ねなければわからない。
元治元年(1864)3月、尊皇攘夷を旗印に、武田耕雲斎、藤田小四郎ら水戸天狗党は決起した。有無を言わせぬ武威によって恐れられた天狗党だが、その天狗党を迎え討ち、通過させた諸藩が残した文書は、偽政者に都合よく書き換えられている。このことを山田は見逃していない。文献資料に忠実に従う事も大切だが、その資料自体の信用度にまで踏み込まねば、実態はわからないということになる。それを看破した山田の眼力に恐れ入った。
もともと、本書を手にしたのは玄洋社の杉山茂丸が遺した「過去帳(交友録)」に横浜富貴楼倉の名前があったからだ。杉山茂丸とは、玄洋社の総帥頭山満と半世紀に渡る盟友関係にあった人だ。その杉山の記録にあった倉の名前が「天下の糸平」こと田中平八(1834~1884、天保5~明治17)の顕彰碑にあるという。碑が立つ東京都墨田区の木母寺を訪ねたが、顕彰碑に手跡を遺すのは、あの伊藤博文だった。倉の名前は、裏面の賛同者の一群のなかにあった。田中は幕末から明治初期、横浜を中心に莫大な富を築き上げた生糸商人であり相場師である。水戸天狗党の決起にも参画したが、維新後は長州藩を後ろ盾に財を成した一人である。倉を介して、杉山茂丸も田中平八と親交があったのではと想像した。
山田はこの天狗党を描くことで主義主張、事件というよりも人間というものの性を描きたかったのだろうが、行間と行間、その後ろに垣間見える大きな主張に考え込んでしまった。この作品を読了し、小説とはなんぞや、しばし、再考したのだった。
同時に、伊藤博文がハルビンで安重根の銃弾に倒れたが、この伊藤の一団の中に室田義文という随行員がいた。この室田は水戸天狗党の一員であった。ここから、伊藤暗殺事件の真実は、銃弾を5発も食らった室田が標的であったのではと考えた。骨肉の争いを演じた、水戸藩の市川党(佐幕派)によるものとして。さほど、水戸藩の分裂は修復しがたい内訌(内紛)だった。
尚、本書では島崎藤村の代表作『夜明け前』の舞台である中山道の木曽路を天狗党が通過した件も紹介されている。併せて『夜明け前』も読まれると、本作品の背景がより深く理解できる。
以上

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』ブレイディみかこ著、新潮社 令和3年1月9日
多様性とは、地雷原を進むがごとく。
本書を手にしたきっかけは、大学時代の恩師が示してくれたからだ。著者のブレイディみかこ氏と恩師の娘さんが高校で同級生という。「娘に勧められてね」と恩師は付け加えた。
著者の通った高校は、福岡藩の藩校の系譜に連なる。旧制中学時代からの卒業生には、政財界は当然の事、医師、文学、芸術の分野に至るまで多士済々。人材を輩出する伝統校であり、有名国立大、私立大への進学率もずば抜けている。ところが著者は進学せず、好きな音楽の道に入り、イギリスに渡った。進学しようと思えば可能だったと思うが、何がなんでも大学という明治近代からの風潮を真逆に行く姿は、階級闘争の革命戦士にも見える。
本書に綴られている16のストーリーには、アイルランド人の夫、その息子とのイギリスでの日常が描かれている。アメリカのような原色が入り乱れる国と比べ、堅実で質素で、伝統を重んじるイギリスと思ってみてしまう。ところが、そこにあるイギリスは、多種多様な移民によって構成される国だった。共通言語として英語があるだけで、そもそもの大英帝国自体が連合国家であることを知れば、何の不思議も無いのかもしれない。
本書に展開する日常のイギリスは、日本にいては到底想像もできない混とんとした社会である。日本でも話題になるLGBT、家庭内暴力、イジメ、ヘイトスピーチ、民族差別、家庭崩壊、その全てがイギリスの日常である。一匹の野生の猿が都心に侵入し、大捕り物になったことが全国ニュースになる日本とは大違いである。唖然、茫然とする話ばかり。「だから、LGBTは・・・」「だから、移民は・・・」と大上段に振りかぶっての討論の前に、根本的な対策を取らなければ日常が進まないのが、イギリスである。だからといって、このイギリスの様を対岸の火事として見てはならない。本書でも、日本社会に潜む問題が炙り出されている。
近年、日本の知識人は「多様性」という言葉に酔いしれている。金科玉条の如く用いる。しかし、本書の帯にもあるように、「多様性ってやつは喧嘩や衝突が絶えない」のだ。ストーリー9の「地雷だらけの多様性ワールド」がそれを如実に指し示している。
本書を深く読み説くには、英国が4つの国で構成される連合国家であること。その中心を成すイングランドが大英帝国として世界を制覇し、植民地を支配していたこと。それらの歴史も踏まえて読むと、より深化した現代イギリスの問題を理解できるだろう。
著者の日常が、大東亜戦争に敗戦し、経済復興を遂げる日本の姿と重なって見えて仕方なかった。初刷りは2019年6月だが、2020年12月で26刷。すでに50万部が売れたという。本を読まなくなった日本で、これほども部数を伸ばす事実に、イギリスの日常が日本社会に忍び寄っていることに日本人が気づき始めたからかもしれない。
以上
『日本がアジアを目覚めさせた』プロビール・ビカシュ・シャーカー著、ハート出版 令和3年1月1日
現代日本人が知らないアジアとの真実
本書の著者、プロビール・ビカシュ・シャーカーはバングラデシュ人だ。1984年(昭和59年)に初来日したが、中曽根康弘(1918~2019、大正7~令和元)首相(当時)が提唱した「留学生10万人計画」での留学生である。以後、日本人女性と結婚し、職を得て、日本で生活を営んでいる。
来日に至る経緯については「おわりに」に述べてあるが、日本に向かう前、父親からパール博士の名前を知らされる。パール博士といっても、現代の日本人でも即座に思い出す人は少ない。75年前の東京裁判こと極東国際軍事裁判で、戦争犯罪人として訴追された日本人被告の全員無罪を主張した判事である。
現代日本において、戦争は絶対悪として教えられる。日本は進んでアジアに「侵略」戦争をした国であるとも教えられる。その戦争を起こした「戦争犯罪人」を無罪であるとパール判事(当時はインド代表)は述べた。そんな判事がいたことを、日本人は知る由もない。故に、被告人全員を無罪としたパール判事の主張は理解されない。加えて、明治時代以降の近現代史を教育現場では教えない。教えることができる教師も少ない。
嘉永6年(1853)、アメリカのパリーが来航し、限定的であった外交が全ての国を対象とするようになった。世界は弱肉強食。欧米による植民地支配の時代だった。日本も一歩間違えば、欧米列強の餌食になっていた事だろう。幸い、先人らの尊い犠牲の上に植民地支配を避けることができた。屈辱的ではあるものの、一応の独立国としての体裁を日本は保つことができた。
その日本にインド独立の闘志ラス・ビハリ・ボースが逃れ来た。そのボースを身命を賭して守り抜いたのが、玄洋社の頭山満らであった。以後、イギリスからの独立を求めるインド人たちへの支援が始まる。その最終が、あの大東亜戦争(太平洋戦争、アジア・太平洋戦争)である。この時、インド軍の先鋒に立ったのが、ネタジことチャンドラ・ボースである。ありとあらゆる資産をイギリスに奪われ、インド人がどれほど飢餓で命を落とそうとも無関係、構いなしのイギリスだった。アジアの人々の生命を助ける解放戦争が大東亜戦争である。その戦争を起こし、欧米の利権を奪ったとして、日本の要人たちが「戦争犯罪人」として処刑されたのである。このような理不尽な歴史を知らずして、日本を「侵略」戦争に駆り立てたとして糾弾することが、いかに愚劣なことであるかがわかるだろう。
外交は、経済的な利害でいかようにも変転する。しかし、真実は、その国の都合で二転三転しない。全7章、その史実が簡潔に述べられている。著者は、この日本人が知らない事実を伝えたかったのだ。
尚、本書に、幾度も名前が登場する岡倉天心の『東洋の理想』は必読の書であることを付け加えておきたい。
以上
『東洋の理想』岡倉天心著、講談社学術文庫 令和2年12月24日
「アジアは一つである。」で始まる岡倉天心(1862~1913、文久2~大正2)の代表作『東洋の理想』は、現代の人々に何を伝えようとしているのか。
もともと、英文で書かれた本書だが、その日本語訳を通読すると、西洋文明による物質的豊さは「今だけ、金だけ、自分だけ」の極めて短期的な人の欲望しか表現できない、エゴであると喝破している。
天心は「アジアの思想と文化を託す真の貯蔵庫」「アジア文明の博物館」として、日本を評した。そのアジアとは、インドと中国を含むが、そのインド、中国も時代や地域によって複雑に分かれる。その長い歴史を遡れば遡るほど、文明の糸はからんで、もつれ、系統だった理解を阻害する。しかし、日本においてはその複雑怪奇なアジアの文明を融合させ、人々の生活の中に生かしている。その代表が、日常的に何の疑問も抱かずに眺めている「七福神」だが、その由来を紐解けば、アジア文明の融合体である。このように日本にはアジアの文明が生かされ、生きているのである。
その日本の背景を探ると、万世一系の皇統が途切れることなくアジアを受け入れ、存立していたからだった。本書は第一章から第十五章までで構成されるが、第六章の飛鳥時代から明治時代まで、時代という括りで文明が述べられている。その時代、時代で括る事ができるのも、皇統が続いているからである。人類史の中でも、稀な事実として、はたして、どれほどの日本人が気づいているだろうか。「ユダヤ人とは何か」という定義で考えると、それは人種、民族ではなく、ユダヤ教信徒であることがユダヤ人であるといわれる。さすれば、「日本人とは何か」という定義を考えた時、万世一系の皇統を尊ぶ人を日本人と呼んで良いのではと考える。そのことを如実に気づかせてくれる一書でもあった。
西洋が日本に持ち込んだ近代の一つが近代法だが、かつての日本には複雑な近代法は存在せず、法三章の世界だった。多様性、グローバリズムという言葉が氾濫するが、よくよく見れば、多様性、グローバリズムの縮図が日本である。蒸気と電気のために存在するヨーロッパに対し、アジアの簡素な生活様式こそ、今日的世界の在り方ではないか。ふと、そんな考えも思い浮かぶ。
天心は第十五章の「展望」において、「今もアジアのなすべき仕事は様式を擁護し回復する仕事となる。」と示している。しかし、その天心の説く言葉の前に、「自身は何者であるか」を自問自答しなければならない。アジアは悠久の昔から、人は何故生まれ来たのか、どこに行くのかを一生の課題として求めてきたからだ。
天心は、「われわれの歴史の中に、われわれの未来の秘密が隠されていることを本能的に知っている。」と述べる。そう考えると、歴史に学ぶのは今ではないか。世界がコロナ禍にある時、『東洋の理想』を『人類の理想』に置き換えて読んでみても良いのではないか。
以上
『日米戦争を策謀したのは誰だ!』 林千勝著、ワック出版 令和2年12月21日
日米戦争は、昭和16年(1941)12月8日のハワイ真珠湾への奇襲攻撃から始まった。そう信じている日本人は多い。しかしながら、近年、江崎道朗氏の先行研究でもわかるように、アメリカによる計画的封鎖に日本側が引き込まれたとの見方に変った。ルーズベルト政権に巣くうコミンテルン・スパイによって日本は追い込まれ、「だまし討ち」に仕立て上げられたのだ。
アメリカ公文書館が公開しているJB355には、やはりコミンテルン・スパイのカナダ人、ラフリン・クリーの名前がある。日本との戦争を提案する「戦争委員会」の報告書にルーズベルト大統領の承認を求めている。その日付は、日本海軍によるハワイ襲撃の、およそ5か月前である。更に、本書では示されてはいないが、JB355の日付と同じ頃、アメリカ領パナマ運河が無通告で封鎖され、防空体制も敷かれた。
今回、近衛文麿を中心として、ロックフェラー財団の影響、日本人共産主義者の動きを見ながら日米戦争を見ていくものだった。敗戦後、東京裁判こと極東国際軍事裁判前に自殺した近衛だったが、某によって殺されたとみるべきだろう。
そう考えれば、東京裁判の被告として巣鴨に収監された松岡洋右、廣田弘毅も口封じの対象であったと見るべきだ。本書の146ページに、スタンレー・K・ホーンベック国務省極東部長の名前が出てくる。この人物については、松岡も廣田も強い関心をもって注視していた。松岡は満鉄総裁時の昭和12年(1937)、満鉄の課長であった武田胤雄に潤沢な予算を付けて、ニューヨーク駐在所長の肩書で渡米させた。同じ頃、第一次近衛内閣の外相であった廣田はニューヨークの若杉要総領事からの報告を受けている。アメリカ共産党が日米の対立を煽り、戦争を画策していると。その背後に、ホーンベックがいると伝えている。この時点で、松岡も廣田も日米戦争不可避と見ていた。
先述のJB355、パナマ運河封鎖、松岡、廣田の情報収集のプロセスを見て行けば、コミンテルン・スパイが日本に戦争を仕掛けたのは明白である。風見章、尾崎秀美、松本重治、白洲次郎、牛場友彦、西園寺公一ら、理想主義のお坊ちゃんたちが、「敗戦革命」に夢とロマンスを抱いたのは、日本にとって大きな不幸だった。没落商店の倅(松岡)、石屋の倅(廣田)など、下賤の成り上がりにしか見えなかったのだろう。
本書を読了し、今の中国共産党の世界覇権が重なって見えて仕方ない。戦後75年、3S(スクリーン、スポーツ、セックス)で洗脳された日本人が、どこで、どのように気づき、日本を守るかを真剣に考えなければならない。そのことを、本書は警告している。過去の事ではない。現実の問題として危機であることをどれほどの日本人が本書を読んで気づくだろうか。
著者には、続いて、警鐘のための作品を世に送り出して欲しい。暴力を肯定する共産主義が世にはびこる限り、戦争は無くならない。全6章、380ページ余に及ぶ本書は、実に重厚にして興味深い警告の書だった。
以上
『幻のえにし』渡辺京二発言集 渡辺京二著、弦書房 令和2年12月12日
語りの名手といわれる渡辺京二の発言
語りというものは、面白い。従前、渡辺京二氏の著作を読み、評もしてきた立場からして、人物的に硬い印象があった。どこか、寄り付きがたいとも。しかし、問われるままに口をついて出てきた発言集の本書からは、渡辺京二という人物が、目前で昔語りの老翁の姿で登場してきた。ふと訪ねた時、「おおっ」と小さく声を発し、「まぁ、茶でも飲んでいけ」といった具合に、逝きし世の面影を語っている。
三部構成、二五〇ページ余の本書では、やはり、第一部の石牟礼道子についての思い出は必読というか、熟読、玩味すべきものだ。本書の表題である「幻のえにし」も、この第一部に含まれる章からとられている。
石牟礼道子は、周囲を巻き込み、そして、巧みに振り回すことができる天才だった。人々は、その石牟礼に従順に従い、使役されることを喜びとした。渡辺氏の語りからは、冷静な立場で、その事々を見ていたかのように語られる。しかし、石牟礼に最も魅了されていたのは、渡辺氏本人である。その事を自覚して、他者のドタバタぶりを面白、おかしく、語っているのが微笑ましかった。
第二部では、熊本在住の作家であえる坂口恭平、スタジオジブリの鈴木敏夫らとの対談である。ここでは言いたい放題。問われるままに、自身の思い、考えを述べていく。その詳細は、ここでは述べない。しかし、谷川雁、吉本隆明と接触した時の話は、なかなか、聞き出せないので、ここも素通りができない。惜しむらくは、三島由紀夫が自決した後、追い腹を切った村上一郎との話が無かったのは残念だった。
第三部は、第一部、第二部の語りと重複する箇所があるが、ブレがないところから、逆に第一部、第二部の語りの内容に齟齬をきたしていないことが見て取れる。語りは、場所、相手、時間によって尾ひれが付きがちだが、それがない。
全体を読み通して感じたのは、世の中の様々な意見に振り回されるな、ということだった。本書の帯にもあるが、「自分が自分の主人公として独立する、この世(現実)と、もうひとつのこの世(アナザーワールド)のはざまを生きる、とはどういうことか。」自分で考えるという事。それが、自分の人生、生き方を納得できる最上の道ではないか。
もうひとつのこの世。このことを渡辺京二氏に如実に実感させてくれたのが石牟礼道子であった。ゆえに「幻のえにし」なのだ。
以上
『コロナ時代を乗り切ろう』原田義昭著 (集広舎)令和2年12月12日
本書は、第4次安倍改造内閣で環境大臣を務めた原田義昭氏の活動日誌である。令和元年(2019)8月6日から令和2年(2020)9月29日まで、インターネットのフェイスブックに投稿し続けた政治報告だ。220ページ余にわたる内容は、環境大臣として果たした事々、衆議院議員として国事に奔走する姿が赤裸々に綴られている。
読了後、なんともいない爽快感を感じた。中国が尖閣諸島で主権侵害を繰り返すなか、習近平国家主席を「国賓」として招くという矛盾に果敢に挑戦したからだ。真の友好国であるならば、新型コロナ・ウィルス対応で必死の中、領海に公船を乗り込ませるだろうか。強い危機感を抱いた原田氏は、中国大使館で駐日大使に思いのたけをぶつけた。(116ページ)誰もが尻ごみするなか、よくぞ、言ってくださいましたと拍手を贈りたい。
そして、レジ袋の有料化も、いつかは、誰かが先頭きってやり遂げなければならなかった。従前、産業界、人々の批判を恐れ、対応を後回しにしていただけである。たかがレジ袋と思うなかれ。白砂青松といわれた日本の海浜は、ペットボトル、レジ袋、ガラス瓶の破片で汚染され尽くされている。一刻も早い環境回復を考えなければとの決断は称賛に値する。(175ページ)
更には、福島第一原発の処理水の海洋放出、希釈についても。「いつかは、誰かが、決断しなければならない」「先送り、時間稼ぎは子々孫々へのツケ」としての発言だった。その波紋、批判は大きい。勝海舟は福沢諭吉からの批判を受け「行蔵は我に存す、毀誉褒貶は他人の主張」と受け流した。しかし、原田氏は信念をもって、マスコミ対応を行った。それは、やはり、現場に何度も足を運んで現実を見たからに他ならない。(38ページ)
発言し、決断し、信念を貫くだけの話ばかりが綴られているわけではない。つい、ホロリとする良い話もある。それは、原田氏の地元にある「福岡視覚特別支援学校」の開校110周年記念事業での一コマ。生徒たちの生活発表、コーラスなどが披露されても拍手がない。これに違和感を抱いた原田氏が来賓席に向かい「拍手を!」と求めたのである。弱き人、悩める人たちをどう支えるか。それが政治の原点だが、原田氏の仁愛を見た瞬間だった。視覚障害者と聞くと、多くの日本人はヘレン・ケラー女史を想起する。しかし、この「福岡視覚特別支援学校」の校長室には、もう一人、「貝島嘉蔵」の写真が掲げてあった。あの石炭で巨富を築いた貝島太助の実弟だが、全盲ながら実業家として手腕を発揮し、社会福祉事業に貢献した人である。地元福岡でも、貝島嘉蔵の名前をどれほどの人が知っているだろうか。(82ページ)
国家国民の為に為政者は存在する。しかし、一隅を照らす視点がなければ世の中は治まらない。自助と共助の感覚を持つ原田氏の正論は心地よかった。忌憚のない「原田節」をまだまだ聞いてみたいが、選挙民はどう判断するだろうか。
以上
『陸羯南』小野耕資著、K&Kプレス 令和2年12月2日
弘前(青森県)では、粘り強く強情なことを「じょっぱり」という。陸羯南の評伝である本書を読了し、ふと、浮かんだ言葉が「じょっぱり」だ。目前の利益など関係ない。自身の信念を曲げてまでも、他者に阿る事はしない。全十五章、陸羯南の「じょっぱり」人生が満載である。
陸羯南といえば、新聞人として知られ、すでにその評伝も出ている。しかし、なぜ、今、「陸羯南」なのか。それは、現今日本における新聞、テレビ、ラジオという情報媒体の内容が稚拙だからである。まずもって、「面白くない」。なぜ、面白くないか。それは、読者に迎合し、広告収入を優先することから企業に忖度するからである。本来、有料購読者を基盤に新聞経営をしなければならないが、いまや広告主が主体である。編集局の匙加減でせっかくの記事が消滅もする。
さらに、近年、連載、特集記事が少ない。単なる回覧板的な、当たり障りのない記事が多い。これは記者の知識量の少なさにも起因するが、インターネットで流されるニュースのスピード感、画像、動画に軍配が上がる。自然、新聞は不要のものとなる。然らば、新聞の存在意義は何なのか。そのことを、現在の新聞人は真剣に考察しているのだろうか。
やはり、新聞の役割は、為政者が独善に陥り、「裸の王様」を演じる権力を牽制することにある。有料購読者に、社会の在り方を考える機会を提供することにある。意に沿わぬ考えでも、掲載することで、議論の対象とならなければならないはずだ。しかし、新聞の多くが「事なかれ主義」に走り、守りに入っている。この新聞各紙の凋落ぶりに警鐘を鳴らすために、著者は本書を上梓したのである。原点に戻れと。
十五章の終わりに、「現代人は、「愛国」と称してその実政権にすり寄っているだけの人物が多すぎる。」との苦言が呈されている。この言葉の背景には、現代日本の新聞人が「何を言っても無駄」として、事なかれの曖昧な論調を展開している証拠ではないだろうか。読み進みながら、陸羯南であれば現今日本のマスメディアをどのように評しただろうかと想像した。
また、羯南は足尾鉱毒事件を批判した。その足尾鉱毒事件に関わった原敬をどのように見ていたのだろうか。司法省学校時代、校長に逆らったことで退学となった旧知の仲間である。両者の関係性を見ながら、西郷隆盛、大久保利通の最期を連想してしまった。
尚、巻末に人名録が付与されていたならば、陸羯南に交友録にもなるのではと思った。
以上
『徳川幕府が恐れた尾張藩』坪内隆彦著、望楠書房 令和2年11月21日
尾張藩という名を目にして、何を思い浮かべるだろうか。「尾張名古屋は城でもつ」という地口が、すぐさま口に出る。その割に、尾張名古屋に対し、さほど深い関心を抱くわけでもなかった。しかし、本書の第一章から第七章までの目次、小見出しを追っていた時、第七章の「明治維新と尾張藩―栄光と悲劇の結末」での第二節で目が留まった。「徳川慶勝による楠公社造立建議」である。徳川慶勝といえば、元治元年(一八六四)の「長州征伐」での征長総督として、維新史に名を遺す。あらためて、征長総督が尾張藩主であったと再認識する。まずは、第七章を読み進んだ。
幕府の中心を成す徳川家は、基盤のしっかりした一枚岩の関係と思い込んでいた。徳川将軍家を支える佐幕派、朝廷の下に各大名が居並ぶ勤皇派という図式をもって維新史をみていた。しかしながら、それはあくまでも、大きな分類であって、水戸、尾張、紀州の徳川家が夫々の思想を持っていたことに、自身の知識の浅さを恥じた。
水戸学を生み出した水戸藩に対しては、徳川家の中でも異端であると思い込んでいたが、そうではなかった。むしろ、あの「大日本史」編纂に取り組んだ水戸光圀に大きな影響を及ぼしたのが、尾張徳川家であった。その系譜が、幕末の長州征伐での征討総督・徳川慶勝であった。ゆえに、勤皇派の徳川慶勝として「長州解兵」へと進んだのは自然の流れだった。
ちなみに、この「長州解兵」においては薩摩藩の西郷隆盛が慶勝から長州処分を委任されたことで解決したと史書は伝える。しかし、これは、従前の伝え方では不十分であると思った。たまたま、筑前(福岡藩)勤皇党の領袖である加藤司書の顕彰文を読み込んでいたところ、追討総督大納言慶勝卿、成瀬隼人、田宮如雲の名前があることに気づいた。これは、福岡藩の藩校修猷館の教員を務めた正木昌陽が明治三十年に書き起こした撰文にあった。徳川慶勝との関係性を探ってみなければ真実はわからない。
恥の上塗りだが、あの会津藩の松平容保、桑名藩の松平定敬が、徳川慶勝の実弟であった事に、今更ながら、驚いた。一六〇ページ余の一冊ながら、歴史を読み解く視点の偏りに気づかされた一書だった。
以上
『回り道を選んだ男たち』小島直記著、新潮社 令和2年11月10日
今年(令和2年、2020)は、三島由紀夫、森田必勝が自決して50年の節目の年になる。この三島の自決後、追い腹を切った男がいる。それが村上一郎という作家だが、あの三島事件の際、市ヶ谷に駆け付け、「俺は、海軍主計大尉だ!開けろ!」と絶叫した。その村上と海軍経理学校での戦友が著者の小島直記だ。本書の296ページから304ページにかけ、村上を含めての海軍時代の戦友の履歴が紹介されている。本書を手にしたきっかけは、この村上一郎の事を少しでも知りたいという欲求からだった。
本書は「明治人の気骨」、「書物の深淵」、「人生紀行」の章からなり、人物評が58話にまとめられている。人物評とは、小さな事実の集積と取捨選択とによって出来上がるといわれる。それぞれの人物の生きざまが興味深く、考えさせられる。著者が論語の裏付けを身体に染みこませた人であると分かる。故に、本書では「明治人の気骨」での人物譚がより一層生きてくる。
127ページの「兆民塾」の一文には、「右翼」とも「テロリスト集団」とも評される玄洋社の事が出てくる。大隈重信に爆裂弾を投じた来島恒喜が中江兆民の門下生であることを知る人は少ない。同じく、「右翼の源流」とも呼ばれる頭山満が、「左翼の源流」である中江兆民と昵懇の仲であることも。日本の敗戦後、右翼と左翼は対立するものと刷り込まれてきたが、「極めれば、右も左も紙一重」という真実をどこかに置き忘れてきたからだ。
「電力の鬼」とも称された松永安左衛門は、プロカメラマンが撮影した一時の姿で評価される。しかし、それは、ファインダーという管見であって、写真を見た者が勝手に松永の面相からイメージを膨らませ、「鬼」と思っているに過ぎない。そんな松永に対する誤解を解いてくれる書でもある。極めつけは、森銑三の名著『史伝閑話』の存在を思い出させてくれたことだった。
まだまだ、知らぬことは多い。もっと学べ、もっと読め。そう示唆してくれた書であり、一日一話、静かに読み込む時間を持ちたいと思わせてくれる書である。
以上
『ミトロヒン文書』山内智恵子著 ワニブックス 令和2年11月8日
あの大東亜戦争(太平洋戦争、アジア・太平洋戦争)が終結して75年。アメリカの軍事力の下、経済発展のみを追求してきた日本。その間、オイル・ショックなど、アメリカの政治事情のダメージを受けながらも、アメリカに依存しておけば日々安寧に過ごすことができた日本だった。
しかし、長い人類の歴史を振り返ってみればわかるが、泰平の世が永遠に続くはずもない。快楽の日々を過ごし、安定成長が続くと信じ、保守的な考えに凝り固まった時から崩壊は始まる。その大きな打撃となったのが、令和元年(2019)末から令和二年(2020)初に出現した新型コロナ・ウィルスだった。欧米先進国での万単位の感染者、死者を報じるニュースに日本も巻き込まれた。後手に回り、無為無策の政府対応に、国民は心理的不安に陥り、経済は大打撃を受けた。ひとえに、海外情報の入手、分析の遅れがもたらした人災に他ならない。早くから、情報機関の創設を図らなければと警鐘を鳴らしていたのが、本書の監修者である江崎道朗氏である。果たして、今回のコロナ騒動において、江崎氏の警告は政府中枢に届いただろうか。
本書の著者は、その江崎氏の資料翻訳、分析を担当されている山内智恵子氏によるものだ。文体、内容は江崎氏に劣らぬものであり、時に軽いジョークを挟んでの語りかける内容も面白い。江崎氏が世に問うたコミンテルンの「ヴェノナ文書」もさることながら、今回のKGBの「ミトロヒン文書」の内容も驚愕だった。本書105ページでは、なぜ、共産主義が各国で支持されたかが示されている。大恐慌とナチス・ドイツのファシズムの台頭という指摘は的を射ている。「資本主義はもうだめだ・・・」とエリートが判断し、共産主義に救いを求めたからに他ならない。
更には、第一次世界大戦での講和条約で再起不能にまでドイツを追い込んだ反動がファシズムとなり、逆に旧連合国を悩ませることになった。ここに旧ソ連は忍び込み、世界支配の謀略戦を展開する。その支配欲はソ連が崩壊したとしても、簡単に治まる気配はない。KGB出身のプーチンがロシアの大統領でいる限り、体制はなんら変わらないと見てよい。
本書の一読後、従前の近現代史の読み直しが必要と感じた。更には、為政者が一時の権力を行使して利得を図ろうとも、必ず崩れ去るという原則を知るべきだろう。
「大衆を味方につけなければ、為政者は見放される。」
かつての徳川幕府の幕臣であった勝海舟が言った言葉だが、まさに歴史はそれらの事実を幾つも証明している。
ちなみに、本書では本名が明かされていない旧ソ連の日本人工作員の名前は『東京を愛したスパイたち』(A・クラーノフ著)に記されている。保守革新に関わらず、日本の新聞社にKGBの工作員が暗躍している事実には戦慄を覚える。共産主義が日本のインテリ層に食い込んだ歴史的背景については、元東大総長の林健太郎著『昭和史と私』がオススメである。両書を熟読されると、より、本書の真実味が増すことだろう。
以上

『ハンコの文化史』新関欽哉著、PHP新書 令和2年11月2日
「これは差別なのか」
「なぜ、君らが持っているものを呉れないのか」
「これは差別なのか」
「なぜ、君らが持っているものを呉れないのか」
「なんて、システマティックなものを使っているのか」
これらの言葉は、外資系企業に勤めている時、オーストラリアから転任してきた外人役員がハンコに対して発した言葉である。
日本人従業員は当たり前のように使い、それぞれがオリジナルのハンコを所持している。ハンコは企業が従業員に支給してくれるものと外人役員は思い込んでいた。ゆえに、自分のハンコが無い事に民族差別ではないかと文句を言ったのだ。
欧米では書類の決裁はサインで済ませる。しかし、大量の決裁書類を目の前にし、サインをするのは手が疲れると文句を言う外人役員。日本人はスタンプ・シール(ハンコ)を持っていて、それで処理している。実に便利なものを使っている。外人役員は羨望の眼差しでハンコを見ていたのだった。
監査を務める海外の部員が来日し、法人代表社員、銀行届出印などについて説明する機会があった。国家が法人を証明する機能として、印鑑証明書があることに、「凄い!」と感心しきりだった。日本には、極めて信頼性の高い決済システムがあり、郵便においても内容証明郵便という優れた機能があることも絶賛する。外国人に教えられ初めて理解した印鑑などの機能だった。
ハンコにまつわる意外な経験に接しただけに、ハンコの文化に興味があった。そこで、簡単に読めるものとして本書は便利である。封筒の始まりが粘土であり、その封緘にスタンプが使われていたことが古代欧州の慣習であったこと。さらには、身分の証明として奴隷までもがスタンプを所持していたことに驚く。
ただ、欧州のハンコの文化については詳細に述べられているが、日本については不足を感じる。江戸時代の古文書には、花押、印鑑、筆印、爪印などがあるが、そこまでは言及されていない。
本書で笑ったのは、114ページの金印(漢委奴国王)が発見された場所を博多藩と記していることだった。福岡藩、もしくは黒田家であればわかるが・・・。
今、行政改革でハンコの廃止が話題になっているが、そもそものハンコの歴史を知ってから、現実の状況から判断すべきと考える。
以上

『漱石の師マードック先生』平川祐弘著、講談社学術文庫 令和2年10月22日
夏目漱石の師としては、東京帝国大学予備門長であった杉浦重剛が知られている。文部省の指示で、登校時の学生は靴を履かなければならなかった。これも、明治の欧化政策の一つだが、これに若き日の漱石は反発心を抱いた。下駄ばきで、校舎の廊下をこれ見よがしに歩いた。そこに出くわしたのが、杉浦予備門長だった。
「夏目、オマエは下駄と靴の底との摩擦面積の比較をしとるのか・・・」
何喰わぬ顔で、漱石の校則違反を見逃した杉浦だった。以後、漱石は終生の師として杉浦を尊敬していた。
そんなエピソードを持つ漱石に、もう一人、師と呼ぶべき人がいた。ジェームス・マードックである。漱石は、このマードック先生からきついスコットランド訛りの英語や歴史を学んだが、休日には早朝から自宅を訪ね、教えを乞う間柄でもあった。
明治四十四年(一九一一)、漱石に文学博士号を授与するとの通知がきた。同じく、医学博士としては、あの野口英世の名前もあった。しかし、漱石は、この文学博士を辞退した。文学博士授与、辞退という一連の報道を新聞は伝えていたが、この頃、鹿児島七校で教鞭をとっていたマードックが漱石に手紙をよこした。
「今回の事(文学博士号辞退)は君がモラル・バックボーンを有している証拠になるから目出度(めでたい)」との文面だった。
この漱石とマードックの人間関係は、日本の西洋化が過熱する中において、文明とは何ぞやと考えさせてくれる貴重な一編である。
この漱石とマードックとの関係性に続き、本書の後編では、漱石と森鷗外との比較文学の検討だった。漢文の素養を叩き込まれた両者の小説文体の比較は、それぞれが留学した国の相違も見て取れる。大英帝国の首都ロンドンに留学した漱石。欧州の新興国であるドイツに留学した鷗外。漱石、鷗外が漢文という基礎固めをした上に、英語、ドイツ語の影響が、文学にどのような反映したのか。いずれも甲乙つけがたいが、日本の文明度の高さを窺い知る検証は面白いものだった。
「あとがき」を読むと、著者の論文に対し、西尾幹二、竹内好などの研究者からの批判があったことを関心をもって読んだ。
昨今、名誉を欲しがる輩が多い中、明治の男の心意気とでもいうべき姿を漱石、マードックに見い出し、心地よい読後感に浸ることができた。
以上

「福岡地方史研究」58号 令和2年9月22日
元号「令和」の発表と同時に、福岡県太宰府市にある坂本八幡宮が一躍、脚光を浴びた。この坂本八幡宮が、大伴旅人の自邸跡であると某全国区の報道機関が配信したからだ。元号「令和」の令和は大伴旅人が詠んだ歌の中にあり、その歌を詠んだ「梅花の宴」が開かれたのが大伴旅人邸。日本全国から、その大伴旅人邸跡を目指して人々がやってきた。神社周辺は大渋滞を起こし、氏子衆も慣れぬご朱印発行に悲鳴を上げた。
そんな様を、冷ややかに見ていたのが、本書の「大伴旅人の館跡(大宰帥公邸)を探る」として寄稿された赤司善彦氏である。氏は、大伴旅人も赴任した大宰府政庁周辺の発掘調査に関わった方だ。赤司氏が言われるには、「坂本八幡宮は大伴旅人邸跡と言われる候補の一つでしかない」と。発掘調査時の記録写真も挿入しての論文は一読に値する。某全国区の報道機関の作為的ともいえる報道だったが、その後、訂正の報道がなされたとは耳にしない。ふと、国民を煽る、かつての大本営発表を想起した。
今回、本号は太宰府特集だが、太宰府天満宮参道にある茶店「松屋」に遺る古文書の紹介が出ている。太宰府天満宮は「維新の策源地」といわれる。その「松屋」は旧薩摩藩の定宿であり、西郷隆盛、大久保利通、平野國臣、勤皇僧月照の手跡を目にすることができる。悲しいかな、その筆文字を正確に読み下すことは難しい。しかし、それらの翻刻が竹川克幸氏(日本経済大学教授)によって詳細に述べられているのは、ありがたい。
また、本誌を発行している「福岡地方史研究会」会長の石瀧豊美氏による寄稿「案外わがままだった太宰府の五卿」も興味深い。一般に、「司馬遼太郎はよく調べている」として小説の内容を史実として語る方がいる。小説は小説、史実は史実として異なった視点で見ることを多くの日本人は知らない。その差異を具体的に知る事ができる内容でもある。ただ、小説には小説としての役割があり、司馬遼太郎を否定しているのではないことはお断りしておきたい。
今、地方史から日本史を見る動きが増加中だ。これは、多角的に物事を見なければ真実は見えないということからだが、考古学、民俗学と並んで「地方史学」という新しい学問体系が誕生するかもしれない。商業誌ではないだけに、面白みに欠ける。しかし、後世に伝えなければ、という思いが詰まった研究会誌である。
筆者も福岡県久留米市に遺る北野天満宮を考察した「北野天満宮・・・」として一文を寄稿している。
以上

『川の中の美しい島・輪中』長野浩典著、弦書房 令和2年9月11日
とはいえ、今回、この本を手にしたのは、第四章「輪中の近代」に登場する毛利空桑(もうり・くうそう)の事績を知るためだった。幕末史を調べていて困惑するのは、飛び地である。現在の大分市鶴崎は、熊本藩が参勤交代のための御座船「波奈之丸(なみなしまる)」の港として利用していた飛び地であった。空桑は寛政9年(1797)、輪中がある熊本藩の飛び地に生まれた。空桑は熊本藩の儒学者、勤皇家として知られる。
明治3年(1870)、空桑は長州藩の奇兵隊脱退騒動に巻き込まれた。長州藩の大楽源太郎が騒動の首謀者として嫌疑をかけられ、旧知の空桑、そして、高田源兵衛こと河上彦斎を頼ってきたからだ。この大楽を匿ったことから、空桑、河上は熊本藩の処罰を受けている。
昨今、日本全国で悲惨な大水害が発生する。堤防を築いても、いつしか、破られる。科学がどれほど発達しようとも、水と争うのではなく、水と共生することを人々は知り、それを生活に生かしてきた。自然を前に、人は謙虚であるべきと教えてくれる。
本書は「輪中」の歴史を全7章、200ページ余から、人々が水とともに生きてきた関係性を余すことなく述べている。歴史研究者のみならず、地方自治体、土木関係者にも一読していただきたい内容だ。
以上

『京築の文学群像』城戸淳一著、花乱社 令和2年9月5日
『京築の文学群像』という表題だが、京築とは、福岡県東部、瀬戸内に面した地域。現在の、福岡県京都郡、築上郡、行橋市、豊前市一帯になる。福岡県といっても、明治の廃藩置県により、旧小倉県などが統合されて福岡県が誕生した。現代においても、旧藩が異なれば、気質も異なるといわれる。京築は、旧小倉藩(豊津藩)の文化を受け継いだ地域と考えた方が分かりやすい。幕末、旧小倉藩は関門海峡を挟んだ長州藩(山口県)との戦いで小倉城を自焼し、この京築に旧小倉藩士たちが移り住み、新たに豊津藩を設けた。ゆえに、文化としては旧小倉藩の藩校「思永館」の系譜に連なる。
この京築は、あの『源氏物語』を英訳した末松謙澄を輩出した。その末松は「水哉園」という学塾で学んだが、塾を主宰する村上仏仙は厳しく漢詩を指導したという。その甲斐あってか、漢詩を好む伊藤博文の知遇を得ることができた。
また、この京築においては、あの堺利彦は外せない。社稷を忘れ、権門に驕る旧長州藩出身の桂太郎は、この旧小倉藩の系譜に連なる社会主義者・堺利彦を恐れたことだろう。
続々と京築の文学話が紹介されるが、『ホトトギス』を主宰する高浜虚子によって汚名を被った杉田久女について言及するのは必須。権力者・桂太郎によって堺利彦は封印されたが、文壇の権力者・高浜虚子の巧妙な政治手腕で杉田久女は貶められた。これは、文の世界において、許されることではない。まさに、名前の通り、高浜虚子は「虚の子」であった。その虚子の偽りを暴いたのが、増田連(ますだ・むらじ)の著作だが、はたして、広く世間に伝わっているのだろうかと懸念する。
本書を読み進む中で、筆者にとって興味深かったのは、「幕末―明治の郷土を知る」の章だった。会津藩から豊津藩(旧小倉藩)の藩校育徳館に留学した郡長正の自刃の話である。自決に至る様々な説があることに驚くが、是非、会津に残る誤解が解消されることを願うばかりだ。
- 京築を彩る文化と歴史
- 郷土、美夜古の文献と歴史
300ページ余に及ぶエピソードには飽きることが無い。膨大な文献を収集し、読破した者でなければ書けない内容であり、インターネット情報では知りえない新しい発見がいくつもあった。山内公二氏の「序」ではないが、本書は「郷土史学」という新しい学問体系を確立する礎になりうる一書といえる。
以上

『戦後欧米見聞録』近衛文麿著、新潮文庫 令和2年8月25日
本書は、1919年(大正8)に終結した第一次世界大戦の講和会議に随従した近衛文麿の見聞録。近衛は全権の西園寺公望の随員として渡欧しているが、26歳という年齢で世界を見通している眼力に驚く。
近衛に対する評価は一定しない。大東亜戦争後、戦争犯罪人指定を受け、服毒自殺したためもあるが、首相在任中の平和を希求する姿勢と、実際の政策が矛盾しているからだ。中国大陸に対する見識(この当時はシナ通と呼んでいた)がありながら、蒋介石の国民党政府を相手にせず、などの声明を発表している。さらに、昭和13年(1938)3月には、国家総動員法を成立させている。軍部に阿り、対外交渉の手詰まりを、政策で誤魔化しているとの誤解を受けても致し方ない。しかし、ここでは、第一次世界大戦後の欧州、そして、排日移民の声があがるアメリカの状況を知るには、貴重な見聞録となっている。
第一次世界大戦の終末期、ロシアでは二月革命、十月革命が起きた。戦争の当事国であるドイツでも十一月革命が起きている。近衛の見聞録においても、ボルシェビズム(ロシアの共産主義者たち)として、その危険性が述べられている。
1920年(大正9)、国際連盟が創設され、近衛は世界の平和のために喜ばしいとしている。反面、日本が提案した人種差別撤廃については、否定されている。国際連盟ができたからといって、すぐさま世界に平和がもたらされるわけではない。事実、1921年(大正10)には、ドイツにおいてナチス党が結成され、11年後の1933年(昭和8)には、ヒトラーが首相に就任し、1939年(昭和14)には、ポーランドにドイツ軍が侵攻した。その結果、世界は再び、未曽有の世界大戦に突入したのである。
すでに、昭和11年(1936)の二二六事件で証明されたように、日本は世界の金融経済の枠組みにしっかりと組み込まれていた。反乱軍の青年将校たちを早期に鎮圧しなければ、為替決済の電信線が使用できなかったのである。
世界の平和を希求した近衛でありながら、首相在任中に大本営が設置され、戦闘体制に備えていたのか。それとも、日米戦争は回避不可能と判断したのか。
本書には、細川護貞の解説が付されているが、その中に米国が「多量の好戦的尚武的素質」があることを近衛が見抜いていたとの記述がある。まさに、近衛はこの米国の本質に対処していたということだ。その米国との経済格差を承知の上で。
戦争は嫌だと言っても回避できない事実があることを本書は示している。果たして、大東亜戦争直後の近衛評のままで良いのかと考える。世界的な視点で、歴史の詳細な振り返りが必要と痛感させられた。
以上
『壊れる日本人 ケータイ・ネット依存症への告別』柳田邦男著、新潮文庫
新型コロナ・ウィルスの蔓延防止から外出自粛が求められ、不要不急の外出を控えるということから自宅に籠る生活が続いた。その中で、改めて渡辺京二氏の『荒野に立つ虹』を読み返した。講演録や過去に寄稿した文章をまとめたものだが、特に哲学者のイヴァン・イリイチの章は、じっくりと読み返してみたいと思っていた。イヴァン・イリイチの唱える言葉に日本人は飛びついたものの、それでいて「信じたい」と思う事と真逆の発言をイリイチがしたことから掌を返した。上野千鶴子氏に引きずられるように大衆はイリイチを見放したが、この行為は「自分の頭で考える」という時間と過程を現代日本人が失ったことを表している。少年による殺人事件が発生しても、マスコミ報道の間は記憶にあるが、マスコミが別の問題を報じ始めると、そちらに誘導されるのと似ている。
本書は、そんな、忘れっぽい、対岸の火事で問題を見たがる日本人の観察記録といってよいかもしれない。すでに起きた事件、忘れ去られた事件を、架空ではなく、現実に自身の生活に「存在」していることを示してくれる。少年少女による殺人事件、工場での事故など、12章に分け、問題点を鋭くえぐりだし、さらに、その対処法までをも提示する。非効率主義とでもいうべき対処法だが、逆に理にかなっていると言える。
人は、断食によって、感覚を鋭敏にする。同じく、副題にあるように、ケータイ・ネット情報を遮断して、自身で考えることをしなければ、人生の目的も何も見えなくなる。自身で考える事は、「自身で考える訓練」と置き換えても良いのかもしれない。新型コロナ・ウィルスによって非効率な社会に放り込まれ、人は右往左往する。しかし、飛行機が飛ばなくなって久しい。その結果、人間の頭上には青空が広がり、夜空の星の輝きを認めることができる。このことに、どれほどの日本人が気づいているだろうか。
もうひとつ、航空機パイロットの飲酒が問題として報道されていた。パイロットの飲酒問題では、職業倫理を問う意見が多かった。しかしながら、その根本的な問題はパイロットではなく、効率を求めての運行プログラムを組んだ航空会社にある。そのことに言及する評論家がいなかったのは、残念だ。しかし、柳田氏は見抜いていた。氏には『マッハの恐怖』という著作がある。航空機事故を扱った内容だが、その事故原因は組織と制度にありながら、事故原因はパイロットの操縦ミスである。
重大な事故が起きた時、「想定外」という言葉で責任回避をする人が多い。しかし、すべては「想定内」である。対処方法を蔑ろにしてきた人間に問題があると柳田氏は指摘する。「想定外」とは、「普通」が異常であることに気づかない人間の意識のなかにある。副題に「ケータイ・ネット依存症への告別」と出ているが、まずは、洪水のごとき情報を、一度、試しに遮断してみてはと柳田氏は提案する。何か見えてくるものが、あるはずだ。渡辺京二氏の『荒野に立つ虹』と並列で読むと、東洋哲学の意味深さをも知る事ができるだろう。
以上
『維新の残り火・近代の原風景』山城滋著、弦書房 令和2年7月28日
本書は中国新聞(本社・広島市)に2017年(平成29)4月から、2018年(平成30)9月まで、毎月2回、連載された維新の話である。その全35話を「グローバリーゼーション」「ナショナリズムとテロリズム」「敗者の系譜」「近代の原風景」として、4章に分類したもの。この中で注目したいのは、やはり、第3章の「敗者の系譜」である。明治維新において、勝者であるはずの長州藩だが、その実、敗者の系譜が歴史の襞に塗りこめられていたのである。
その代表的史実が、戊辰戦争での勝者として故国に凱旋しながら、反乱軍として木戸孝允(桂小五郎)に討伐された農商兵の話だろう。いわゆる「脱退兵騒動」だが、「四民平等、一君万民」という維新のスローガンと異なり、長州藩には歴然たる身分差別が横たわっていた。被差別部落出身を含む農商兵は、反政府勢力として殺戮されたのである。本書では述べられていないが、海防僧月性の影響を受けた大楽源太郎は九州へと逃れ、既知の久留米藩の仲間に庇護を要請した。明治4年(1871)に起きた最初の武士の反乱事件である「久留米藩難事件」において大楽源太郎らは久留米藩の仲間に殺された。四方を政府軍に囲まれた久留米藩としては、苦肉の策として大楽らを殺害したのである。しかし、大楽暗殺事件として「久留米藩難事件」は処理された。このことは、明治9年(1876)に起きた「萩の乱」において再燃したが、松陰精神の継承者である前原一誠は反政府勢力として処断された。木戸を始めとする新政府の主要な人物がかつての仲間を封殺したのである。
明治維新150年としてNHKの大河ドラマは「西郷どん」だった。林真理子原作、監修には「篤姫」の監修も手掛けた原口泉氏だったが、その視聴率は伸びなかった。本来、明治維新100年と150年とは、何がどのように異なるか、どのように変化したかを検証すべきだったが、明治維新100年の焼き直しでは、関心が薄れるのも致し方ない。振り返れば、西郷隆盛も明治10年の「西南戦争」では敗者になる。しかし、今もって、その人気は衰えない。その点を強調すべきだったのではと、悔やまれてならない。
明治という時代の変化は、日本の生存のために必要であった。西洋が100年を要した近代化を、50年で達成しなければ生き残れなかったのである。必然、歪みが生じ、何にしても斃れる(敗戦)しかなかった。
明治維新での敗者の系譜を辿る事は、昭和20年(1945)8月15日の敗戦国日本の事実を冷静に判断できる材料と考える。全35話の端々に、著者の昭和20年の敗戦に対する事実認識の欠如が如実に見て取れるが、このことは、いまだ、明治維新史が勝者の視点からでしか伝わっていないことに起因していることが見えてくる。本書は、いみじくも、その歴史の陥穽を炙り出している。
以上
『荒野に立つ虹』渡辺京二著、弦書房 令和2年7月28日
本書は渡辺京二氏の論考などをまとめたものである。「現代文明」「現代政治」「イヴァン・イリイチ」「日本早期近代」と大きく4つに分類し、32のタイトルで構成されている。いずれも興味深い内容だが、新型コロナ・ウィルスの感染防止に振り回される現代においては、「イヴァン・イリイチ」という哲学者が語った内容は外せない。しかし、このイヴァン・イリイチは、現代日本の進歩的文化人たちによって疎外されてしまった。このことは、進歩的文化人の読みの浅さ、日本の思想界の層の薄さを露呈した感がある。
日本は1990年代後半以降、新自由主義に移行し、それを受け容れた。しかし、そこで露呈したのは、日本及び日本人が自分たちの感覚や倫理を意識し、言語化、体系化、正当化してこなかったことだ。この指摘は、正直にうなづくしかない。TPPにしても、マスコミ報道に疑問を抱かず、「安いから」という事を前面に出し、密かに背後のアメリカの圧力をにおわせることで、大人のフリをして納得していた。しかし、アメリカのトランプ政権はTPPなど見向きもせず、日本の政官財界は為す術がなく、マスコミは声を潜めてしまった。このことは、農業とはなんぞや、ということを日本の農家も考えていなかったことに起因する。「生きることは食べること。食べることは生きること」という原則を考えれば、日本人にとっての農産物は生きる糧。大量生産、大量消費するエサではない。欧米の農業は狩猟型であり、東洋の農業は循環型である。そう体系的に認識していれば、金銭での評価対象でもなく、共同体という制度における給付、分配の対象であったと認識できたはずだ。
この認識の欠如は歴史認識においても同じである。敗戦後、日本の歴史は占領軍によって書き換えられた。これは、欧米の植民地支配の実態を見れば容易に判断がつくのだが、巧妙に仕組まれたプログラムにより、多くの日本人は疑問を挟む隙さえ与えられなかった。著者は、明治新政府によって創造された暗黒の江戸時代が、じつはそうではないことを描いた。その批判、批評にことごとく反論する展開には、爽快すら覚えた。著者の手法で、今一度、戦後の歴史を見直してもよいのではないか、
著者の515事件、226事件との明確な相違の指摘は、「なるほど!」と腑に落ちるものであった。将校のみの権力に対抗する行動か、兵(国家)も加担した決起かの相違である。余談ながら、夏目漱石の日本の敗戦を予見した小説の読み込み方の深さにも、感服する。
本書は、平成28年(2016)の西日本新聞・書評欄「今年の一冊」に寄稿したが、再読し、驚いたのは、2017年ノーベル文学賞を授賞した日系イギリス人のカズオ・イシグロについて、著者は2002年の段階で「The Remains of the Day」を「偉大なる小説」として評価していたことだった。この先を見通す著者の眼力に感服した。手元に置いて、何か、迷った時にはページをめくる。そんな一書である。
以上
『昭和維新』田中健之著、学研プラス 令和2年7月21日
本書を手にしたのは、著者が「玄洋社」初代社長平岡浩太郎の曾孫であり、「黒龍会」創設者内田良平の血脈であるということが大きい。「昭和維新」との題名だが、ある意味、玄洋社からみた昭和維新史と言える。
本書は三部構成であり、第一部は「昭和維新」の胎動、第二部は五・一五事件から二・二六事件、第三部は二・二六事件と「昭和維新」の挫折となっている。総ページ数は580ページ弱の大部となっている。
この「昭和維新」について、多くは二・二六事件を最終決着点として語られる。ゆえに、青年将校の周辺、青年将校に影響を与えた北一輝から語られる。しかし、本書は大川周明から始まる。大川周明は、いわゆる東京裁判で東條英機の頭を背後から叩くなどの奇行がクローズアップされるが、その思想、背景については語られない。その大川周明を著者が取り上げたのも、東京裁判の映像によって封じ込まれている大川の真実を引きずり出したいという思いからに他ならない。
著者は、本書の「はじめに」において、こう述べている。
「日本を敗戦に導いた権力者の責任を日本人自身が総括しないまま、戦後政治に引き継がれてきた。日本を敗戦に導いた指導者たちは、本来ならば連合国にその責任を負わされるのではなく、天皇と国民に対して祖国を亡国の危機に導いた責任を負わなくてはならない。」
東京裁判における大川周明は東京裁判で晒し者、ピエロを演じ、そのことで、戦争指導者、日本国民は免罪符を得たのだった。いまだ、日本という国は、日本国憲法という衣装に変っても、その実、大日本帝国憲法の時代と変わらないと揶揄される由縁である。
著者は「昭和維新」というテーマから五・一五事件を説いた。五・一五事件は昭和七(一九三二)年五月十五日に起きた。首相犬養毅を襲撃した陸海軍青年将校のみならず、頭山秀三も関係した。本書にも記されているが、犬養毅の墓所は東京都立青山霊園にある。その少し斜め前に、犬養の盟友ともいうべき頭山満、そして、頭山秀三の墓石が有る。なかなか、この両家の関係については深く立ち入れない。しかし、著者はその両者、心情を綴っている。本書の200ページから始まる件は、興味深いものだった。過去、表層をなぜた著述はあっても、ここまで頭山と犬養の関係を表現したものを読んだことがない。
次に、二・二六事件の引き金ともいうべき「永田鉄山惨殺事件」は興味深い。この永田鉄山を刺殺した相澤三郎中佐の弁護士は鵜沢総明だが、鵜沢は東京裁判での日本人弁護団長として知られる。鵜沢が相澤の弁護をどのように展開しようとしたのだろうか。平成二十七年二月二十六日、東京麻布の賢崇寺で二・二六事件、永田鉄山惨殺事件関係者の慰霊に参列した。賢崇寺とは佐賀鍋島藩主の菩提寺だが、処刑された二・二六事件での青年将校らの墓所があることでも知られる。この法要で、相澤三郎の娘からの手紙が読み上げられた。あの子煩悩だった相澤の娘が存命であることに感慨を覚えた。さらには、その所在すら不明であった二・二六事件での公判記録が東京地検に保管されており、公文書館に移されることになったとの報告も。
最後に、本書の最終章である東條英機暗殺未遂事件である。この章では、中野正剛に対する東條英機の言論弾圧が述べられている。憲兵を総動員し、委細洩らさぬ情報統制を敷いた東條だった。その東條の独裁に、生命を顧みず反対闘争を繰り広げた中野だった。その自決に際して、机上には西郷隆盛の全集が広げられていたという。中野が、西郷精神を継承する玄洋社の人でもあったのだと再認識させられる場面である。毀誉褒貶はありながらも、断固として権力者東條に叛旗を翻した中野の慰霊祭は今も地元福岡で続けられている。
昨今、庶民の暮らし向きを考えず、金銭、異性問題で世間を騒がす政治家が多い。ここに、戦後を総括しなかったツケが日本社会の混迷を招いたといえる。今、亡国の危機にある日本に対し、政治家は自戒し、必死の覚悟をと著者は主張する。
今回、本書を世に問うた著者の決意はここにある。そのことを汲み取っていただきたい。
以上
『北欧諸国はなぜ幸福なのか』(鈴木賢志著、弦書房)令和2年7月4日
本書は2019年(令和元年)7月27日、福岡ユネスコ協会が主催する講演会での内容をまとめたもの。60ページ弱のブックレットである。
まず、著者(演者)は、明治大学国際日本学部の教授であり、イギリスに留学したものの、家計の問題で家賃無料のスウェーデンの大学研究員となる。以後、10年ほどを現地で過ごし、本書はその時の体験をもとにスウェーデンの内実を述べたものである。
スウェーデンといえば、高福祉、高税率の制度を導入している。この制度に国民の不満は生じないのかという疑問が生じるが、人口1000万人のスウェーデンでは、高い経済水準を維持しており、この制度を当然の帰結と認識している。家具のIKEA(イケア)、ファッション衣料のH&M、自動車のVOLVO(ボルボ),薬のAstraZeneca(アストラゼネカ)、紙パックのTetraPak(テトラ・パック)、音楽配信のSportify(スポーティファイ)、インターネット通信のSkype(スカイプ),Ericsson(エリクソン)などの企業がスウェーデンの稼ぎ頭。
さらに、労働をシェアするというより、より働ける者は働くという環境になっている。女性でも、障害者でも、働いて利益を上げる制度になっている。日本との労働時間を比較しても各人の労働時間は短いが、高収益体制となっている。この、より働ける者は働くという感覚は、経済水準と幸福度は相関関係にあると国民が認識しているからだ。
そして、高福祉政策については、権利と義務という相関関係が厳格に認識されている。仮に移民がスウェーデンで就労を希望すると、スウェーデン語は必須であり、そのための学校(無料)に行かなければならない。さらに、その出席率は厳格にチェックされ、甘えは許されない。
大学も無料。しかし、成績が下がれば奨学金の打ち切りがあるので、必然的によく学ぶ。兵役もある。スイスのみならず、スウェーデンも永世中立国だが、紛争に関与しない代わりに、他国の侵略、侵入を受けない軍事力の保持を当然と考えている。実際に、第二次世界大戦時、ナチス・ドイツは北欧諸国を侵略したが、スウェーデンのみは対象外だった。ゆえに、戦闘機も国産化するが、自動車メーカーであったSAAB(サーブ)は戦闘機メーカーである。
スウェーデンといえば、近年、環境問題でのグレタ・トゥーンベリという女子高校生が世界的に話題になった。しかし、これはスウェーデンでは普通のことであって、騒ぎ立てたマスコミの認識レベルが低い。恣意的に彼女を利用したということである。環境問題は、半世紀近く前から問題視されており、それをおざなりにしてきたマスコミの怠慢であることを、皮肉にも、グレタさんが露呈したに過ぎない。
本書では、日本の憲法改正、教育制度についての問題提起が潜んでいる。原理原則、根本原理を無視した、表層部分での議論しかなされなかったかを痛感する。要は、議論が存在しない。これでは、日本ではコメンテーターにはなれても、思想家にはなれない。スウェーデンの長期戦略から学ぶべき事々は多い。
以上
『インテリジェンスと保守自由主義』(江崎道朗著、青林社)令和2年7月2日
インテリジェンスという言葉から、現代の日本人は何を思い浮かべるだろうか。戦前の特別高等警察(特高)、陸軍憲兵隊(憲兵)と言われるかもしれない。しかし、戦後75年、戦争を経験していない日本では、特高、憲兵といっても死語に近い。故に、『インテリジェンスと保守自由主義』という題名を見ても、敏感に反応する方が少ないのではないか。しかし、副題に「新型コロナに見る日本の動向」と記載されていることから、本書を手にされる期待大だ。現実問題として、新型コロナウィルス対策の遅れは、情報収集能力の低さだった。本書は全9章で構成されているが、第7章の「新型コロナ対策が後手後手になったのはなぜか」から読み進んでもよいだろう。
まず、本書を読み進みながら、日本の報道機関に対する不平、不満、不安が募る。2019年(令和元年)9月19日、EU(欧州議会)は旧ソ連(現在のロシア)を戦争犯罪、侵略国家として議決したことが、日本に伝わっていない。連日、日本に届いたニュースは、イギリスがEUを離脱する、しない、であった。経済にどのような影響が起きるしか、伝えなかったのである。ソ連を侵略国家と議決したEUからすれば、次に、侵略国家として議決されるのはイギリスである。経済的な事由からのイギリスのEU離脱が報道されたが、その背後には、ソ連の侵略国家議決があったのではないか。このEU議会でのソ連批判は、北方領土問題が解決していない日本にとって、重要なニュースである。日本の報道機関が意図的にイギリスのEU離脱だけを報じ続けたのであれば、国益に反する対応であったとして批判されなければならない。恣意的であったとすれば、なおさらである。
著者の一連の著作を読むと、コミンテルンの動きについて書かれたものが多い。大局的な視点でとらえた内容には、あの昭和16年(1941)から始まるアメリカとの戦争も、用意周到に仕掛けられた戦争であったことがわかる。それもアメリカのルーズベルト大統領、その側近による戦争計画に基づいたものであることが明白だ。しかし、いまだに、多くの日本人は「日本が戦争を始めた」「日本は侵略国家」だと、信じている。このことで、憲法9条を楯にし、「平和憲法」を守るとして外交、国防に齟齬をきたしていることに気づいていない。
さらに、日清、日露戦争までをも「侵略」戦争と定義づけ、世界の、アジアの平和を崩壊させたのは日本であると教科書で教えている。それは、入試問題にまで及び、教員、学校関係者らが何ら疑問を抱かない。これは、日本の弱体化、消滅計画に他ならない。
阪神淡路大震災、東日本大震災でマスク、防護服が必須であると経験したにも関わらず、価格競争のみを前面に出して、なぜ、中国に生産を委託してしまったのか。一時期、アメリカのトランプ大統領の自国第一主義を世界の報道機関は批判した。しかし、新型コロナウィルスの発生により、世界中の国々が国境を封鎖し、出入国を厳格化した。この現実に、トランプ大統領を批判した評論家の謝罪コメントは目にしていない。いかに、情報収集、自主性に瑕疵があるかを露呈した出来事ではなかったろうか。
著者は、もう一つ、大きな問題提起をしている。それは、アメリカとの同盟関係も大事だが、自主独立の気概が日本に欠けていることである。実質的な防衛予算が必要であり、そこから初めて、国益にかなったインテリジェンスが生きてくる。政府任せ、アメリカ任せではない、日本国民がそれぞれ、独自の視点をもって意見、意思を持たなければならないと警告する。
世界は大きく動いている。保守自由主義を支持する方々は、インテリジェンス機関の重要性にも関心を向けて欲しい。
以上
『団塊ボーイの東京』(矢野寛治著、弦書房)
東京の武蔵野の一画に成蹊大学のキャンパスがある。著者の矢野寛治氏が通った大学だ。一度、作家の多田茂治氏と訪ねたことがある。『夢野久作と杉山一族』『夢野久作読本』という著作がある多田氏に連絡し、大学図書館で待ち合わせた。大学の創立記念事業として、夢野久作が腹違いの妹に送った書簡を翻刻し、その研究発表会があるということからだった。校舎は三菱財閥が関係した学園だけに、風雅を感じる。そこに宇宙船を想起させる図書館が出現した。豪華な空間に軽い嫉妬を覚えながら、久作の書簡をガラスケースから眺めた。
そのガラスケースの並びで目に留まったのが、有馬頼義の著作だった。映画「兵隊やくざ」の原作となる『貴三郎一代』の著者である。『遺書配達人』という名作は、渥美清主演の映画にもなったが、シリーズとなった勝新太郎の「兵隊やくざ」の方に世間の関心は集まる。少々、残念ではあるが、その有馬頼義が、なぜ、成蹊大学にと訝る。その答えは「有馬の殿さま」として本書の中にあった。1969年(昭和44)、当時、経済学部の学生であった矢野寛治氏だが、偶然、有馬の殿さまこと有馬頼義と野球部のグラウンドで遭遇した。なんとも、実にウラヤマシイ思い出である。
著者の東京での学生生活は、「個は孤」という団塊世代にしか経験できない時代だ。悲哀を込め、振り返りたくもない青春時代を、それこそ、フーテンの寅さんのセリフではないが、「恥ずかしき」日々の連続、悪戦苦闘が綴られている。その事々が、憧憬と哀れみがないまぜになり、やがて、共感となって沁み込んでくる。本書は、中洲次郎という矢野寛治氏のペンネームで「ぐらんざ」という雑誌に連載されたものだが、筆者自身、青春時代を描けと言われれば、やはりペンネームでしか書けない。しかし、ついに、矢野氏が本名で刊行したことに意義がある。
ノンフィクションとして記録される歴史も大事だが、文書化されず、口伝として、やがて消えていく「常民」の歴史は恣意的なものが加わっていない。それだけに、本書が内包する青春時代という歴史は貴重だ。日本の戦後史、誰もが頂点を目指した復興期の歴史と見ても良いだろう。全80話、250ページに及ぶエッセイは、まさに小宇宙。小説でしか書けない事も、年月を経ると「半生(反省)の記」として昇華する見本である。団塊の世代を自認される方々は、矢野寛治氏の青春時代に自身の青春をトレースしてみては良いのでは。
*作家の多田茂治氏は、令和二年五月三日病没された。享年九十二歳。合掌。
以上
『イスラム国と日本国』(三宅善信著 集広舎)令和2年6月16日
本書は、そんな日本の成りたちをイスラム国との歴史の比較から、現実を説いた内容である。全6章にわたって、国とは?という概念が語られるが、中でも秀逸なのが第6章の「二十一世紀における国家論」だ。日本から遠い中近東の国々ついて、テレビのニュースでしか知らないのが現状だ。日本人が関係した事件でも起きない限り、関心をもたない。日本経済に必須の石油資源の中近東でありながら、系統だって報じることができるメディアも少ない。
その根源の一つに、著者も問題提起しているが、イスラム教会による日本及び日本人に対する啓蒙、普及活動に積極的でないからだ。日本国民の1パーセントに満たない信者数でありながら、日本におけるキリスト教への理解は進んでいる。ゆえに、本書の第6章はイスラム国、イラン、イラク、シリアなどの地域紛争を解かりやすく解説していることに意味がある。
日本のように、郵便、新聞、テレビ、ラジオ、インターネットなどの情報機関が整備されていない国々では、SNSが重要な情報源となる。国境を有していれば、危機に際しての冷静な判断をくだす時間的余裕はない。一瞬の判断ミスが、自身や家族の生命を奪ってしまうからだ。目が覚めたら、他国の兵士が庭先に立っていた。などという経験を重ねてきた国々にとって情報と迅速な判断は肝要だからだ。
日本のマスコミは、日本が世界のグローバル・スタンダードに追いついていないと喝破する。このままであれば、日本は世界の孤児になると危機感を煽る。しかしながら、日本のマスコミはそのグローバル・スタンダードの真実を見極めていない。ゆえに、世界が、日本のグローバル・スタンダードに追いついていない事を、再認識させてくれる一書でもあった。果たして、日本のマスコミ、評論家が、本書を手にして、この真実に気づけるか否かはわからない。
蛇足ながら、大正14年(1925)1月、東京回教徒団が結成された。ロシアから追放され、日本に亡命してきた回教徒(イスラム教)の僧正たちが中心となったものだが、その集合写真中央には玄洋社の頭山満がいる。この一葉から、大東亜戦争前の日本の意識が広く世界に広がっていたことを感じとることができる。
以上
『占領と引揚げの肖像BEPPU』(下川正晴著、弦書房)令和2年6月14日
別府と聞いて、何を思い浮かべるだろうか。何といっても、まずは、「温泉」だろう。さほど、別府の至る所、湯煙がもうもうと立ち上っている。大分自動車道のパーキングエリア、現在の立命館アジア太平洋大学のあたりから見下ろす別府湾の風景は、あらゆる人を開放的にする。
本書は、その別府の歴史、特に戦後史に特化して書かれたものだ。しかし、ここで注意しなければならないのは、地方都市の戦後史として軽く見ると、とんでもない大ヤケドに見舞われる。そのことは、全8章の項目を追うだけで、従来の戦後史が粗雑であったかが浮かび上がる。それぞれを列挙すると、「戦後史へのアプローチ」「モダニズム都市別府」「占領都市BEPPU」「朝鮮戦争とBEPPU」「戦災孤児・混血児の別府」「煉獄の引揚者」「阿南綾の戦後」「新生の別府女性史」だが、別府をわざわざアルファベットのBEPPUと記さなければならない史実に、本書の秘密がある。
なかでも、第2章72ページには驚いた。昭和三年(一九二八)から三年間、アメリカ海軍の情報将校が、別府に滞在していたのだ。まだ、日米が太平洋を挟んで激闘を繰り広げる十三年も前の事である。エドウィン・T・レイトンという人物だが、なんと、あのニミッツの補佐官を務めるのである。戦意高揚の歌に登場する「さあ来い、ニミッツ、マッカーサー」と揶揄した敵将の補佐官である。
そして、第6章180ページには、戦後の別府市長を務める脇鉄一の事績が紹介される。熊本五高、東京帝大、朝鮮総督府を経た人だ。さらに、近現代史では無名に近い存在かもしれないが、杉目昇という満洲での諜報活動で欠くことのできない人物の名前までもが登場する。
そして、第7章は、最後まで本土決戦を主張して止まなかった陸軍大臣阿南惟機の妻・綾が主人公である。
戦前、さしたる産業に恵まれない大分県は、地域振興のため海軍基地の誘致を試みた。宇佐海軍航空隊、大分海軍航空隊のみならず、保養施設、療養施設としての別府までもがあったのだ。別府のことを「泉都」とも呼ぶが、「軍都」と呼んでもよいかもしれない。温泉の湯煙に隠れて、アメリカ海軍の情報将校までもが潜むのが別府だったのだ。
復員船の第一船「高砂丸」が入港したのが別府だが、そこから展開する別府の戦後史を一地方史として見てはいけない事実に驚愕するだろう。巻末には大分県、別府、大分の戦後の事件簿が掲載されている。これを追うだけでも、資料的価値の高いものであることが証明されるだろう。
ちなみに、別府の米軍基地の復元図がある。後世に歴史を遺す新しい試みとして評価したい。
以上
*『忘却の引揚史』(下川正晴著、弦書房)との併読をお勧めします。
『武家の女性』(山川菊栄著、岩波文庫)令和2年6月7日
著者の山川菊栄(1890~1980)は女性解放の論客であり、伴侶は社会主義者の山川均(1880~1958)である。その菊栄が水戸藩下級武士の娘である実母の青山千世の聞き書きをまとめた内容だが、物語風に綴られた話は、昔話のようであり、肩が凝らない。
この物語は15に分かれているが、中でも「子(ね)年のお騒ぎ」は必読の章である。いわゆる水戸藩における内訌(内紛)である。水戸藩といえば水戸光圀が始めた『大日本史』編纂が続けられていたが、それは、全国の諸藩の模範でもあった。いわゆる水戸学と呼ばれる日本の歴史、政治体制についての集大成であったが、それが逆に時代の変遷において藩内に齟齬をきたした。このことは山田風太郎の『魔群の通過』や吉村昭の『天狗争乱』に詳しいが、「お騒ぎ」の水面下で、動きのとれない女性、老人、子供の姿は哀れとしかいえない。
心痛むのは、天狗党で決起した者の家族が牢に投じられた場面だ。不衛生な獄中で亡くなる者、食を絶って自殺する女性たちがいたことである。武家の家に生まれたばかりに、わずか三歳の幼児といえども男子ということで斬首となった。水戸藩の平時と有事の落差が大きいだけに、悲惨さがより一層、如実に浮かび上がる。先述の山田や吉村の作品といえども、こればかりは太刀打ちできない。
明治維新の目的の一つに、封建的身分制度の打破があった。しかし、その全てが達成できたわけではない。その残滓が女性解放であり、その対応に著者の山川菊栄が行動した。遠い、幕末維新の話ではなく、現代においても男女共同参画が問題とされる。先駆者として山川菊栄を取り上げても良いのではと考える。
ちなみに、本書に中島歌子という女性が登場する。明治時代、文壇において樋口一葉、三宅花圃という女性たちの活躍は目覚ましいが、その樋口や三宅の和歌の師匠が中島である。「子年のお騒ぎ」で伴侶が処罰を受けたことから、累として獄窓にあった女性である。
尚、三宅花圃の伴侶はジャーナリストの三宅雪嶺だが、この雪嶺を岳父にもったのが朝日新聞記者から政界入りをした中野正剛(玄洋社員)である。
以上
『魔群の通過』山田風太郎 著、ちくま文庫 令和2年6月4日
本書は幕末の水戸藩を舞台にした天狗党の顛末を描いた物語である。この小説を読む前、吉村昭の『天狗争乱』を読了したが、同じ天狗党を扱った内容でありながら、読みやすさと印象は大きく異なる。
吉村昭の場合は膨大な文献資料から事件を忠実に描いている。山田風太郎の場合は事件の渦中から、少しばかり離れた位置に立って、物語風に描いている。人情の機微の絶妙さとしては、山田風太郎に軍配をあげたい。山田は資料を渉猟しながらも実際に天狗党たちが通過した断崖絶壁の道も歩いている。地の気、風の音、広大な風景は、やはり、現地を訪ねなければわからない。
武田耕雲斎、藤田小四郎を首領とする天狗党は、有無を言わせぬ武威によって恐れられた。その天狗党を迎え討ち、通過させた諸藩の中には、偽政者に都合のよい記録を遺している藩がある。このことを山田は見逃していない。文献資料に忠実に従う事も大切だが、その資料自体の信用度にまで踏み込まねば、実態はわからない。それを看破した山田の眼力に恐れ入った。
もともと、本書を手にしたのは玄洋社の杉山茂丸が遺した「過去帳(交友録)」に横浜富貴楼倉の名前があったからだ。杉山茂丸とは、玄洋社の総帥頭山満と半世紀に渡る盟友関係にあった人だ。その杉山の記録にあった倉の名前が「天下の糸平」こと田中平八の顕彰碑にあるという。碑が立つ東京都墨田区の木母寺を訪ねたが、顕彰碑に手跡を遺すのは、あの伊藤博文だった。倉の名前は、裏面の賛同者の一群のなかにあった。
田中は幕末から明治初期、横浜を中心に莫大な富を誇った生糸商人であり相場師である。水戸天狗党の決起にも参画したが、維新後は長州藩を後ろ盾に財を成した一人である。倉を介して、杉山茂丸も田中平八と親交があったのではと想像した。
山田はこの天狗党を描くことで主義主張、事件というよりも、人間というものの性を描きたかったのだろう。行間と行間、その後ろに垣間見える大きな問題提起に考え込んでしまった。読了後、小説とはなんぞや、しばし、再考したのだった。
蛇足ながら、明治42年(1909)、伊藤博文はハルビンで安重根に暗殺された。その伊藤の側にいて被弾したのが室田義文という水戸天狗党の人だった。もしかして、かつての恨みから室田を狙った銃弾が誤って伊藤に直撃したことから起きた暗殺事件だったのではと想像を巡らせた。さほど、骨肉相争った水戸藩だったのである。
以上
『天狗争乱』(吉村昭著、新潮文庫)令和2年6月1日
今から10年以上も前に読了した本書だが、読み返そうと思ったのは、権藤真卿こと古松簡二(1835~1882)の足跡を確認したかったからだ。古松簡二とは、明治四年に維新のやり直しを画策して捕縛された旧久留米藩(現在の福岡県久留米市)の人である。
古松は、福岡県八女郡溝口村(現在の筑後市溝口)の医師清水潜龍の次男として誕生した。才能を認められ、久留米藩の藩校明善堂の居留生となった。封建的身分制度が厳格な時代、一介の医師の息子が藩校に入ることができるのだから、どれほどの秀才であったかがうかがい知れる。以後、安井息軒の塾で学んだが、脱藩し、水戸天狗党の挙兵に身を投じた。
しかし、水戸藩の内訌(内紛)問題を優先する藤田小四郎(藤田東湖の子息)と意見を異にし、天狗党を離脱。その件を確認したく、本書の再読に取り掛かったのだった。「久留米藩を脱藩して天狗党にくわわっていた権堂(藤)真卿は・・・」という箇所がそれになる。
著者の吉村昭の関心もここで止まっているが、この権藤真卿こと古松簡二は、維新後、長州の木戸孝允、薩摩の大久保利通と大坂遷都問題で意見対立し帰郷。久留米藩の若き青年を訓育し、維新のやり直しを画策していた。そこに飛び込んできたのが、長州の大楽源太郎だった。大楽も長州では、木戸、山縣有朋らと奇兵隊の解散問題で対立し、反政府者として追われの身だった。そこで、旧知の仲間がいる久留米藩に逃げてきたのだった。
しかし、明治4年、古松らは反政府勢力として捕縛され、東京の獄に投じられた。獄中でも若者への教育、医師であったことから病者の治療にもあたった。劣悪な環境でも執筆活動に励んでいたが、コレラ患者の治療中、自身も罹患し獄中死した。
獄には、明治10年(1877)の西南戦争での賊軍兵士も投じられていたが、古松の教えを受けた者は多い。その一人に、福岡発祥の自由民権運動団体玄洋社の初代社長となった平岡浩太郎がいる。平岡は出獄に際し、古松の国学関連の著書を持ち出したという。
また、他の著書の多くは、鹿児島県出身者が持ち帰ったとも伝わる。
幕末史において、三條実美らが都落ちした文久3年(1863)の「八月十八日の政変」、元治元年(1864)の「禁門の変」は注目を集める。しかし、水戸天狗党の決起が東西挟み撃ちの義挙であったことは振り返られない。これは、後年、日本史を編纂した者の意図が働いたのかもしれないが、今では確認の術はない。ただ、残念としかいえない。
尚、本書にも平田篤胤の国学の影響を受けた人々が水戸天狗党に好意的であったと出ている。国学の観点から本書を読み解いても面白いのではと考える。
以上
『幕末の魁、維新の殿』(小野寺龍太著、弦書房)令和2年5月29日
本書は水戸藩を中心にした幕末維新史だが、読み進むうちに斎藤佐治右衛門という水戸藩士の名前に目がとまった。文久3年(1863)「八月十八日の政変」を経て三條実美公たちは太宰府天満宮延寿王院に移転してきたが、斎藤は藤岡彦次郎という変名で警護役浪士団の一員に加わっていた。その一団は土佐の土方久元、中岡慎太郎、久留米の真木外記などで編成されていたが、斎藤までもが落ちてきた真の意図はわからない。水戸藩を震源地とする一連の尊皇攘夷行動の連絡係として国元から派遣されたのかもしれない。
水戸藩といえば、水戸学の本家として全国の志士が遊学に訪れたところである。会沢正子斎の門を叩き、藤田東湖の知己を得る者が後を絶たず、ひとえに、名君徳川斉昭を支える英才に交わりたいとの思惑があったからである。さほど水戸藩は時代の魁であり、主要な政治事件の中心にいた。それにも拘わらず、維新後、「薩摩警部に水戸巡査」とのたとえ通り、新政府においては殿だった。
水戸藩が関わった事件としては万延元年(1860)三月の「桜田門外の変」、文久2年(1862)の「坂下門外の変」、元治元年(1864)の「天狗党騒乱」等が著名である。其々、単発の史実として語られることはあっても、水戸藩の一貫した幕末維新史としては扱われない。攘夷思想の対立が藩の権力闘争に発展し、収拾がつかなくなったからである。安政の大獄は全国の主要な人材を抹殺したが、水戸藩の政治闘争は親兄弟、門閥を問わず、皆殺しの様相を呈した。このことで、水戸藩は尊皇攘夷思想を語り継ぎ、次代につなぐ人材を失った。
思想に忠実であったことから同士討ちとなった水戸藩だが、その頃、太宰府で時勢を待った三條公たちは西洋列強の現実を直視していた。ひとつに長崎が近いという地理的要因があるが、日本を取り巻く情報を潤沢に入手できたことが大きかった。三年に及ぶ太宰府滞在は三條公を討幕維新へと向かわせたが、この動きを斎藤がどのように水戸へと伝えたのか、いささか気になるところである。
余談ながら、明治2年(1869)、安川敬一郎(旧福岡藩士、安川財閥創始者、玄洋社員)は京都に留学途上、乗り合わせた船内で斎藤佐治右衛門と出会う。そこで、今回の維新で活躍した西郷隆盛、大久保利通、坂本龍馬らの話を聞き、大いに驚愕したという。
この内容は、平成24年(2012)10月14日付西日本新聞に寄稿した書評に加筆したものです。
以上
『勝海舟強い生き方』(窪島一系著、中経文庫)令和2年5月22日
「読書百篇、意自ずと通ず」という言葉がある。一度読んで分からずとも、繰り返し、繰り返し読むうち、意味が次第に分かってくるという先人の教えだ。
本書は勝海舟の遺した言葉、事績から選びだした事象を75話にまとめ、10章に分類している。一日に一話ずつ読んでいけば、およそ二か月半で読了する。筆者も一日一話ずつ読み進んだ。
第一章の第一話は、勝海舟の剣の師である島田虎之助の勧めで禅の修行に打ち込んだ話が紹介されている。島田虎之助は剣豪として知られるが、海舟も剣に禅にと激しい修行に打ち込んだ。海舟は、維新という大変革の時を生き抜いたが、その底辺には剣と禅があった。
海舟の周辺には、実に多くの人々が関係する。人は、一時の事例から他者を評価するが、この海舟の交流関係を見ていくと、多面的に見なければ他者は評価できないと考えさせられる。それでいて、これは運、不運という言葉でしか片付けられない事故も垣間見える。
最終の第10章、第7話は、海舟の盟友というべき山岡鉄舟の見事な末期の姿が綴られている。現代、「なぜ、俺が、死ななければならないのだ」と不運を嘆く人がいるが、生まれたら死ぬ。ただ、それだけ。だから、しっかりと生きて行く。人の一生とは、ただ、それだけのこと。しかし、これが簡単なようで、もっとも難しい。
流行病で生命を落とすより、慢性疾患、自殺で亡くなる人の方が多い現実の日本を振り返れば、情報に振り回されるよりも、日々、しっかりと生き抜くことを考えるほうが、気が楽だ。そんな事々を悟らせてくれる書だった。
尚、本書にも記されているが、勝海舟と福岡藩主の黒田長溥の人間関係は、深い。
さらに、福岡発祥の自由民権運動団体である玄洋社の人々との関係も強い。
以上
『柳原白蓮』(井上洋子著、西日本新聞社)令和2年5月20日
太宰府天満宮参道の中間地点に、ひとつの鳥居が立っている。土産物店の「小野筑紫堂」の軒先にあるそれは、伊藤伝右衛門が寄進したものだ。伊藤は本書の主人公・柳原白蓮の元夫であり、「白蓮事件」として大正時代の一大スクープとして日本中を騒がせた渦中の人である。しかし、観光客の多くは、なんら関心を示すこと無く通り過ぎる。
さて、本書をどのように捉えるかは、性別、年齢、地域、知的関心によって幾通りにも解読が可能となる。女性解放史、階級闘争史、維新史、近代産業史、文学史などだが、アジア史も付け加えることができる。さほど、この柳原白蓮という女性の辿った道は複雑にして、怪奇であるということだ。
柳原白蓮は、明治18年(1885)、伯爵柳原前光を父として生まれた。伯爵家という家柄だけでなく、不躾な言葉で言えば、大正天皇のいとこにあたる。白蓮の叔母・柳原愛子は大正天皇の生母だからだ。
その白蓮が、九州は筑豊の炭鉱主である伊藤伝右衛門の後妻に入った。資産家で衆議院議員とはいえ、伊藤伝右衛門はまともな学校教育を受けたことが無い。いわゆる、労働者階級から裸一貫で成り上がった人だった。加えて、万延元年生まれの伝右衛門と白蓮。その年齢差は親子ほどの24歳違い。誰がどう見ても、不釣り合いな結婚であった。結婚生活が上手いくはずもなく、仮にいったとしたら、それは奇跡と呼べる。
白蓮は、ちぐはぐな生活のなかで、歌を詠む事に希望を抱いた。歌集を出し、寄稿も求められる。そんな白蓮を訪ねてきたのが、後に、出奔し、結婚することになる宮崎龍介だった。あの孫文、黄興という革命家たちを支援した宮崎滔天の長男である。
明治維新は、四民平等、一君万民という理想を掲げ、封建体制を破壊することで挙国一致体制を構築した。しかし、旧藩主、公卿の救済措置から生まれた華族制度が誕生し、新しい封建制度を生み出すことになった。その制度が生み出した事件が、白蓮事件である。華族制度は、次なる課題である男女平等の理想を積み残して始まったが、その制度破壊の先駆者が白蓮であったとすれば、彼女は革命家としても名を遺したことになる。
本書には内田良平、中野正剛、出口王仁三郎などが白蓮や龍介の周辺に登場する。龍介の父・宮崎滔天、玄洋社関連の文献が読み込まれていたならば、人間関係の濃密さがより一層浮かび上がったのではないだろうか。
蛇足ながら、太宰府天満宮本殿奥にある「お石茶屋」前には、白蓮の姪である徳子の元夫・吉井勇の歌碑がある。この吉井も白蓮の歌集編集に関わっている。学問の神様・太宰府天満宮は御祈願所だけではなく、不思議な人間模様も学べる場所だ。
以上
『海と神道譲位儀礼と大嘗祭』(神道国際学会、集広舎)令和2年5月18日
本書は第20回、第21回の国際神道セミナーでの基調講演、シンポジュウムの内容をまとめたものである。第20回のセミナーは2018年(平成30)3月16日、東京の学士会館で開かれ、第21回のセミナーは2019年(平成31)3月5日、東京の関西大学東京センターで開催された。
まず、第20回の基調講演は宮城学院女子大学・大内典教授の「龍神と音楽:エビス信仰との関連から」だった。ここでは、島根県松江市の美保神社に多くの楽器が奉納されていることが紹介された。楽器といっても多々あるが、太鼓、弦楽器などだが、なぜ、神社に楽器が多く遺されているのかという疑問から、エビス信仰を考えるというものだった。従来、神社の歴史といえば、古事記、日本書紀から捉えようとするが、楽器に着目するという発想が面白い。音楽文化学を研究されている方ならではの着想と思う。
さらに、金印で知られる志賀島の志賀海神社(福岡市東区)、世界遺産の宗像大社(福岡県宗像市)から、海と楽器との関りを述べた箇所は、なるほどと思えるものだった。志賀海神社では神功皇后と安曇磯良の物語が楽器(鳴物)と結び付くことから、神社拝殿の鈴、雅楽などを想起した。
次に、第21回の基調講演は皇學館大學の研究開発推進センター神道研究所助教の佐野真人氏の「大嘗祭における太上天皇の役割」としての話だった。ここでは、平成の時代の天皇が譲位され「上皇」と呼んでいるが、その元は「太上天皇(だじょうてんのう)」の短縮形であることを知った。
そして、この譲位というものについて、政教分離なのか、日本国憲法の観点からはどうなのかなど、様々な意見がパネラーから発信されたことは興味深い。特に、マールブルグ大学名誉教授のマイケル・パイ氏の発言は、政教分離を杓子定規に考える日本人にとって考えさせられるものだった。
巻末、神道国際学会三宅善信理事長の寄稿があるが、ここでも、日本民族は「海洋民族」であったと考えるほうが自然という説に、志賀海神社、宗像大社が基調講演で紹介されているだけに、なるほどと納得できる。
今から75年前、連合国軍総司令部の「神道指令」によって神社の在り方が大きく変化した。しかし、成熟社会を迎えた日本において原点回帰のように伊勢神宮に参拝する人が増える背景に何があるのか。安定の時代から内省の時代に移行したのではと考えるが、排除なのか、共生なのか、遠い、遠い先祖たちの営みから得られる事々は多いのではないだろうか。講演者、パネラーの発言から、種々、考えるヒントをいただいた一書である。
以上
『「明治十年丁丑公論」「痩我慢の説」』(福沢諭吉著、講談社学術文庫)令和2年5月12日
本書は「明治十年丁丑公論」「痩我慢の説」「旧藩情」の三部からなる、福沢諭吉の評論である。
まず、「明治十年丁丑公論」だが、この題名にある「丁丑(ていちゅう)」とは、十干十二支でいう十四番目の年のことを指す。元号とともに十干十二支を併記することで、年という時間経過を認識していた時代の名残だ。ゆえに、ここでは明治十年(一八七七)の西南戦争後の世評を述べている。
この論では、新聞紙上で西郷隆盛を批判することを、福沢が批判している。維新の功労者として西郷隆盛を評価したにも関わらず、掌を返すが如く、親の仇のように、西郷を叩き潰す。この様に、節度が無いと憤慨している。同時に、西郷が文武の武によって政府批判をしたことを福沢は咎めながら、西郷の尊皇精神は称賛するのである。
道を間違えた為政者を批判するのは当然として、しかし、西郷が武によって起った事を福沢は批判し、返す刀で西郷を追い込んだ政府に責任があると言い切っている。言論弾圧下の明治期、福沢はこの論を後世へと書き残したのだった。
次に、「痩我慢の説」だが、これは、幕臣から新政府の要職に就いた勝海舟、榎本武揚に送り付けた糾弾の説である。同時に、福沢は、この内容を木村芥舟など、ごくわずかな人に開示している。ここでいう木村芥舟とは、幕末、咸臨丸で太平洋を渡った際の責任者であり、この時、勝海舟は咸臨丸の艦長であり、福沢は、木村の随員という形だった。いわば、同じ艦に乗った仲でありながら、今は呉越同舟の関係ということだ。
武士の世界は「二君に仕えず」という掟にも似た規範があったが、勝海舟、榎本武揚は徳川幕府の禄を受け、新政府が樹立すると、その新政府の禄を受けた。二君に仕えたことが世の中のモラル崩壊につながるとして、福沢は両名を批判したのである。これに対し海舟は、「いささかも相違なく、自身の行動責任は自身が負う。この内容を公表されても構わない。」と返信し、榎本は多忙につき後日とその場を取り繕った。
この福沢の挑戦状ともいえる「痩我慢の説」を読みながら、福沢の半生記を述べた『福翁自伝』を思い出した。福沢は、「封建制度は親の仇」とまで言い切った。が、しかし、「痩我慢の説」とは矛盾しないだろうか。封建制度を批判しながら、武士の在り方を問題にしたからである。この件に関しては、今一度、多角的に福沢の環境、考えを検証しなければ分からない。
最後の「旧藩情」は、福沢が属した中津藩(現在の大分県)を事例に封建制度の矛盾を述べたものである。同じ武士でも上士、下士によって待遇が異なり、下士は下される禄だけでは食えず、内職が必須。具体的な数値を挙げて、その矛盾を開示している。本書全体を通読して、これは、維新の目的を考える材料と思った。
尚、本書や『福翁自伝』だけでは福沢の実態を知ることは難しい。博多・萬行寺の住職七里恒順と福沢と交流があった。七里の言行録などが参考になるのではと考える。
以上
『幕末』(村上一郎著 中央文庫)令和2年4月24日
本文庫は、明治維新150周年に合わせて再刊されたものだ。初出は1968年(昭和43)なので、明治維新100周年に出された。昭和49年(1974)には文庫本化された。西暦と和暦とが入り混じるが、これは、村上一郎自身が夫々の「あとがき」に記述したものに従っている。
内容は、一、大塩平八郎、二、橋本左内、三、藤田三代(幽谷、東湖、小四郎)、四、真木和泉守、五、三人の詩人(佐久良東雄、伴林光平、雲井竜雄)という内容になっている。吉田松陰については、別途、記述したので、あえて取り上げないと村上一郎は述べる。村上は吉田松陰に「先生」を付けて呼ぶほど、松陰に心酔している。
今回の文庫本で注目したいのは、村上一郎(1920~1975)が、国学的ナショナリズムの権化と呼ばれる文芸評論家・保田與重郎(1910~1981)との対談が収められていること。解説を渡辺京二氏(熊本在住の思想家)が行っていることである。渡辺氏の起用は、生前の村上一郎を知る人としてであると思える。
さて、本書では、唯一、真木和泉守に対する評価が厳しい。厳しいというより、「わたしは、真木和泉守という人は、本質においては狂夢家そのものであったと思う。」と村上は述べる。評するというより、批判の対象として見ている。この真木和泉守に対する酷評に、初出の文章を読んだ読者からの批評が集中したようで、「文庫本の再刊にあたって」の一文で「けっして、真木和泉守一人をおとしめて言うのではない。」と弁解がましい言葉を述べている。
さらに、本文庫の解説に渡辺京二氏が解説を寄せているが、氏は村上一郎との思いでのなかで、「僕は九州の人間は信用しません。」と村上から言い放たれた事を記している。筆者は、ここから、村上は東国(関東)出身者特有の九州人嫌いから、真木和泉守も酷評したのだと思っていた。しかし、それは的外れで、村上の海軍経理学校時代の戦友である小島直記は福岡県八女市の出身であり、村上に師事した岡田哲也氏(詩人)は鹿児島県出身である。これは、九州人というより、渡辺氏個人に対する村上の嫌味だったのではないかと考える。
そう考えた末、なぜ、村上が真木和泉守に対しての評価が厳しいのか。一つに、幕末において久留米水天宮の宮司の家に生まれながら、真木和泉守が漢学、仏教、蘭学と幅広い思想に触れたことが気に食わないのではないか。唯一、村上が真木和泉守を評価するのは、元治元年(1864)の「禁門の変」で事敗れて自刃したことである。もしかしたら、村上は、自由奔放に思想の海を泳いだ真木和泉守にあこがれ、その反発から評価が厳しかったのではと思った。
昭和45年、三島由紀夫が自決する。その5年後、村上は自らの愛刀で自決して果てた。すでに、この頃の村上は躁鬱との狭間にいたという。狂が狂の真木和泉守に憧憬していたのかとの疑念すら沸き上がった。
以上
『日本外務省はソ連の対米工作を知っていた』(江崎道朗著 育鵬社)令和2年4月18日
アメリカという国から、日本人は何を連想するだろうか。自由の国、アメリカン・ドリーム、世界を動かす金融の中心地。時に、移民や人種、宗教の相違から銃乱射での悲劇を早期させる。トランプ大統領のわがままな発言に反発するマスコミ。そんな事々が、がニュースとして日本に伝わる。そんなアメリカに、実は、共産党があると言ったら、日本人は、どんな反応を示すだろうか。一様に、「まさか・・・」「ウソだろう」という言葉が返ってくるのが大半だろう。さらに、この自由の国アメリカで共産党が本格的活動開始が、1933年(昭和8)年からと言ったら、信じられるだろうか。まずは、このアメリカに対する先入観を払拭してからでなければ、本書の問題提起を深く理解することは不可能だろう。
本書は外交官である若杉要が作成した『米国共産党調書』が基本になっている。駐米日本外務省職員が、アメリカ社会で暗躍する共産党の活動を逐一まとめた内容だ。まさか、主義主張の異なる旧ソ連の指令を受けたコミンテルン組織が自由の国アメリカで活動していたとは、信じがたい。しかし、この若杉要が作成した調書に添って、日米関係、日中関係のもつれを見ていくと、腑に落ちる点ばかりだ。いつしか、全十章、270ページ余りが付箋だらけになった。
本書は、アメリカ共産党の謀略と日米関係、日中関係の軋轢だけではなく、現代日本の保守政党である自民党に対する諫言も述べられている。戦後75年といいながら、いまだ、戦後の占領政策から脱却できない日本の原因が述べられている。その大きな要因は、インテリジェンスの重要性を与党が理解していないことにある。インテリジェンスといえば、戦前の陸軍憲兵隊、特高警察のような弾圧組織に結びつけるからではないか。さらには、その報告内容を理解できない為政者の存在が大きい。
日本人は世界に比して善良な国民と言われる。翻ってそれは、他者を簡単に信用し、騙されやすい。他国のインテリジェンス活動を容易にならしめる国民性と言っても良い。そのお人よしの日本人を逆手に、歴史伝統文化が捏造され、洗脳されてきたのが戦後の75年ではなかったか。今一度、本書に記載されている事々と、事件や戦乱を重ね合わせてみてはどうだろうか。ぞっとするのは、間違いない。
以上
『残心』(笹川陽平 幻冬舎)令和2年4月14日
令和という元号に、人々は自然災害の無い安寧を期待したことだろう。しかし、早々に、新型コロナウィルスが発生した。一九一八年(大正七)も、世界はスペイン風邪によって六億人が罹患し、二千万とも四千万ともいわれる人々が命を落としたという。振り返れば、人類は目に見えないウィルスとの戦いを繰り返してきたが、その過程で迷信、宗教、差別、偏見を生み出した。今回の新型コロナウィルスが世界を席巻する最中も、スペイン風邪と変わらぬ風評被害が発生したことは記憶に新しい。科学が発達したとはいえ、人間の本質には、なんら変化がない。
本書は、ハンセン病制圧の戦いの記録である。ハンセン病はかつて、不治の病、業の病として、罹患者は離島などに隔離された。撲滅より、隔離隠蔽したのが現実だった。今も、謝罪と賠償請求の裁判報道を目にするが、どこか遠い記憶の彼方のこととして見ていた。しかし、本書の54ページにあるように、「無理解、無関心は人を差別する歴史の一端」に加担していた事と認識させられた。加えて、本書を手にするまで、笹川良一がハンセン病制圧に強い使命感をもって取り組んでいたとは、まったく、知らなかった。当事者意識が、根本的に異なる事を知った瞬間だった。
日本人は阪神淡路大震災、中越地震、東日本大震災、熊本大分地震などを経験した。192ページに記されるように、この一連の災害で、行政サービスでは対応できない社会構造になったことを日本人は認識したはずだった。かつての社稷(共同体)を復活させればよいのだが、まだ、気づいている風は無い。しかし、その共同体意識を早くから世界に広げたのが笹川良一である。その特筆されるべきものが、ハンセン病制圧であった。
222ページの「かつての日本人がもっていた気概」を読みながら思い起こしたのは、杉山龍丸である。戦後、インドの要請に応じ、私財を投じて一万本の植林をした。砂漠を緑に変え、インドの人々の食糧自給を支援した。インドのラス・ビハリ・ボースを玄洋社の頭山満、内田良平らが庇護したが、ボースの逃走用の車を用意したのが杉山茂丸だった。その杉山茂丸の孫が杉山龍丸だ。インドでは「グリーン・ファーザー」と呼ばれる。今も、ミャンマーで和平交渉に奔走する井本勝幸、カンボジアで地雷撤去活動を進める大谷賢二、アフガニスタンで銃弾に倒れた中村哲も気概をもった日本人だが、全員が福岡県人であるのは玄洋社の影響なのだろうか。
全八章を読み通し、笹川良一、そして著者の崇高な使命に考えさせられる事々は多い。とても、同じことは自身にはできない。さすれば、気概をもった日本人として笹川良一と著者に拍手を贈りたい。
しかし、一つだけ私にできる事があるとすれば、笹川良一がハンセン病制圧に全身全霊をかけたこと、今も著者が継承していること。それを、日本と世界に伝える事だ。
以上